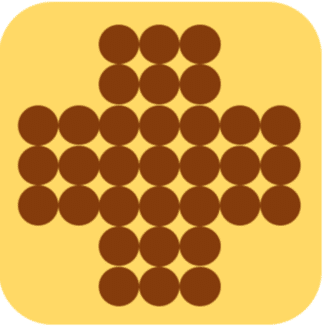「盤双六」について想う 巻之肆 (My thoughts on Backgammon 4)
タイトル画像はwikipedia「すごろく」から引用です。
昨日からの続きです。
そもそも、ラジくまるには、古文を読み込もうとする意志がないです。
そんなわけで、高橋さんのような研究家がいてくださると本当に助かります。ありがとうございます。
さて、平安時代に遊ばれていた盤双六のルールを、ぜひこの機会に読者のみなさんにご紹介したいと思います。
さりとて、ラジくまるが「私がご紹介します」などと、えらそうにルールを提示するのもおかしな話です。どうしたものか?
と、いうわけで、平安時代の「盤双六ルールの説明文章」は、高橋さんがご自分で執筆なさったurlリンクを紹介する手法で進めたいと思います。
1つめは本双六です。
現代のBackgammonと、ほとんど同じルールで遊ばれていたことが判明しています。もちろん、細かいルールが現代のBackgammonとは違っていた可能性があります。
しかし、その程度のことは、全てのゲームでよく見られることです。いわゆる「地方(ローカル)ルール」というヤツです。あんまり神経質に気にしすぎてはいけないことです。
https://www.asahi-net.or.jp/~rp9h-tkhs/dg_bansugo1.htm
2つめは「折葉」です。
おそらくは、本双六よりも短時間で終わるルールに変更して、1日に何度も何度も繰り返し遊びたかった人が考案したものだろうと思われます。
たぶん、せっかちな日本人が発明したゲームなんじゃないでしょうか。
Backgammon終盤の「上がり処理部分(ベアリングオフ)」だけにスポットライトを当てたような感じのゲームです。
https://www.asahi-net.or.jp/~rp9h-tkhs/dg_bansugo2.htm
3つめは「柳(積みかへ)」です。
対戦相手のコマを「ヒット」できません。お互いに対して優しいルール設定になっています。
ギスギスした人間関係になる心配がない、安心設計です。
ゲームにそういう「優しさ」を求めるのは、まさに日本人的だなあと思います。これも間違いなく日本人が考案したルールだと思います。
https://www.asahi-net.or.jp/~rp9h-tkhs/dg_bansugo3.htm
これ、実は1982年前後の読売新聞に、詳細ルールが掲載されたことがあります。その際にはこのゲームは「折葉、あるいは積みかえ」と呼ばれていたと書かれていました。
「なんだよ、名前が違うじゃん!」と2024年にラジくまるは憤りを感じたわけです。
しかし、高橋さんがお書きになった別の著作を読むと、「諸説あり」ということがわかります。
どうやら、ルールが友人から友人へ、親から子へと口伝伝承される途中でゲーム名が間違えて伝えられた事例もあったようだ、というのが真実みたいです。
*万一、掲載紙が朝日新聞だったらごめんなさい!この記事はちゃんと裏取りしないで書いちゃってます。
まだ明日に続きます。
いいなと思ったら応援しよう!