
前説用制作物&製作物(ほぼ月刊いきものニュース2019/1~2020/10)
私とふじのくに地球環境史ミュージアムの岸本年郎教授が知り合ったきっかけで、インタビューの場所にも使った小劇場・人宿町やどりぎ座で教授が酒を飲みながら生物トークをする企画「ほぼ月刊いきものニュース」が始まり、劇場の運営、支配人をしている劇団の先輩から「舞台美術作れるし生物好きだって言うならカマキリ先生みたいな仮装とか被り物作って」「ついでにイラスト付きの解説文章作って」「どうせなら毎回作って何の生き物かクイズ形式で前説のミニコーナーをやろう」と無茶ぶり依頼されて、前説をする支配人の先輩に仮装なんかを着けさせていた。
大体数日前か当日にどの題材にするか思い付きで決めて100均で数百円の材料を買い、文章30分、イラスト30分、仮装30分~数時間~たまに長いと数日、くらいで低予算・短納期(+クオリティ相応)で仕上げて作っていた。
【#ほぼ月刊いきものニュース 】
— 人宿町やどりぎ座 (@yadorigiza_2018) June 13, 2024
明日のテーマは
「生物多様性」
最後のいきものニュース、系統樹いっぱい出るとか出ないとか?
みなさま、やどりぎ座でお待ちしております! pic.twitter.com/vOfDjPe0L0
支配人と運営していたやどりぎ座の代表が亡くなり、7月で運営を終了、閉館することになり最終回となった。岸本教授のトーク・講演は今後も方々でやるだろうし、やどりぎ座も屋号は残して舞台関連の企画運営は続けるそうだが、一区切りなので今までの制作物&製作物を残っているだけ引っ張り出して紹介。
カイコ
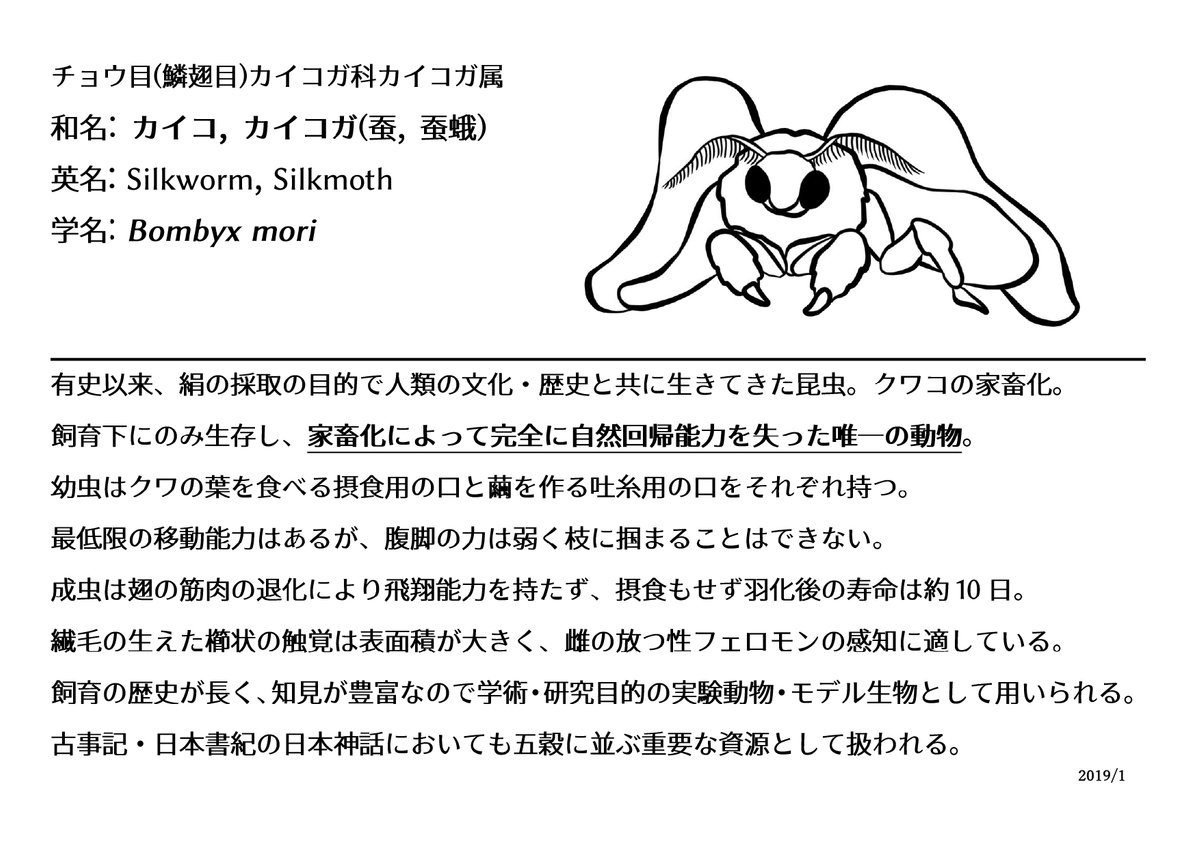
チョウ目(鱗翅目)カイコガ科カイコガ属
和名: カイコ, カイコガ(蚕, 蚕蛾)
英名: Silkworm, Silkmoth
学名: Bombyx mori
有史以来、絹の採取の目的で人類の文化・歴史と共に生きてきた昆虫。クワコの家畜化。飼育下にのみ生存し、家畜化によって完全に自然回帰能力を失った唯一の動物。
幼虫はクワの葉を食べる摂食用の口と繭を作る吐糸用の口をそれぞれ持つ。最低限の移動能力はあるが、腹脚の力は弱く枝に掴まることはできない。
成虫は翅の筋肉の退化により飛翔能力を持たず、摂食もせず羽化後の寿命は約10日。繊毛の生えた櫛状の触覚は表面積が大きく、雌の放つ性フェロモンの感知に適している。
飼育の歴史が長く、知見が豊富なので学術・研究目的の実験動物・モデル生物として用いられる。
古事記・日本書紀の日本神話においても五穀に並ぶ重要な資源として扱われる。
フェルトで触覚のカチューシャ。眼や翅のパーツを作ればよりそれらしくなったか。教授から「ポケモンのイーブイ?」と言われたが、それによって「イーブイは後肢の骨格により分類するなら食肉目」という知見を得る。

カモノハシ

カモノハシ目(単孔目)カモノハシ科カモノハシ属
和名: カモノハシ(鴨嘴)
英名: Platypus, Duck-billed platypus
学名: Ornithorhynchus anatinus
分布: オーストラリア東部・タスマニア
保全状況: 準絶滅危惧(NT)
原始的な哺乳類であり、生きている化石の一種で現生種は約250万年前から存在。嘴、水掻き、総排泄腔を持ち、卵生であるが処女膜を持つ。系統学上、鳥類とは全く別物である。
ゴム状の嘴は水中で獲物の生体電流を感知する感覚器官として機能している。雄の後肢にある蹴爪の毒腺から分泌される神経毒は小動物程度なら死に至らしめる。仔は授乳で育つが、乳首を持たず腹部の乳腺から母乳を分泌し、体毛に溜めて仔が舐め取る。
18世紀末にイギリス人に発見されて、その剥製標本がヨーロッパに持ち込まれた。しかし当初、学会ではビーバーとカモの剥製を組み合わせた模造品だとして疑われた。
100均でサンバイザーが4個100円で投げ売りされていたのでシンプルに被り物っぽく作る。

メンフクロウ

フクロウ目メンフクロウ科メンフクロウ属
和名: メンフクロウ(面梟)
英名: Barn owl
学名: Tyto alba
分布: アフリカ大陸・北アメリカ大陸カナダ以南
ユーラシア大陸南部~西部・オーストラリア大陸
保全状況(レッドリスト): 軽度懸念(LC)
英名は「納屋のフクロウ」を意味し、建物の隙間に入り込み巣を作る。農耕地では害獣となるネズミ等の小動物を捕食するため、ヒトと共生関係を築くことが多い。視力、聴力に優れ、風切羽の綿毛が音を吸収するので、ほぼ無音で飛行して獲物を狩る。他のフクロウの仲間に比べ、繁殖力が高く、世界中に広く分布している。
見た目や鳴き声から各地の民話伝承において知恵の象徴と同時に不吉な存在として扱われる。ウェストヴァージニア州で発見された宇宙人フラットウッズ・モンスターの正体とも言われる。
和紙を張り合わせたお面。かなり粗雑になってしまい、今思い出すと『変な家』みたいだった気がする。
カンザシフウチョウ

スズメ目フウチョウ科カンザシフウチョウ属
和名: カンザシフウチョウ(簪風鳥)
英名: Western parotia
学名: Parotia sefilata
分布: インドネシア
保全状況: 軽度懸念(LC)
約40種いる通称「極楽鳥(Bird-of-paradise)」で知られるフウチョウの1種。フウチョウがはじめてヨーロッパに輸入された際、交易用に足を切り落としていた。枝に止まることなく風に舞い続けると思われたため、極楽鳥、風鳥と呼ばれるようになった。
フウチョウは食料不足や天敵の危険が少ないことで求愛の為に各種独自の進化を遂げた。
本種は地味な茶褐色の雌に対し、雄は全身黒色で首の一部は玉虫の様な構造色に輝く羽根。黒色の羽毛は毛先が緻密に枝分かれして内部で反射を繰り返し減衰させて光を99%吸収する。
雄は周囲の葉や小石を取り除き、見晴らしをよくして頭上の雌に対し求愛ダンスを踊る。
ワイヤーで飾りの付いた帽子。質量があってガチャガチャし過ぎてパッと見は蜘蛛に見えたしそう言われた。
キヌガサタケ

スッポンタケ目スッポンタケ科キヌガサタケ属
和名: キヌガサタケ(衣笠茸)
英名: Long net stinkhorn, Crinoline stinkhorn, Veiled lady
学名: Phallus indusiatus
分布: 北アメリカ大陸・オーストラリア大陸・中国・日本
(ただし近縁種が多く曖昧)
竹林を中心に発生して腐敗した植物の基質に菌糸を張る腐生菌である。
殻皮に包まれたつぼみの様な状態から十分に成熟すると殻皮を割いて数時間で急激に伸長する。伸長が終わると、かさの下から折り畳まれていたレース状の菌網が広がる。その見た目から「キノコの女王」とも呼ばれるが、菌網が出ている状態は一日ももたない。
菌網や粘液から独特の異臭を放ち、ハエやナメクジ等を誘い、引き寄せる。胞子を風に飛ばして散布することよりも小動物を媒介にすることによって拡散させる。
粘液を落とせば中華料理等で食用として使われ、近年人工栽培もされている。
工作粘土とグルーガンで作った髪飾り。

ヒメアリクイ

アリクイ目(有毛目)ヒメアリクイ科ヒメアリクイ属
和名: ヒメアリクイ(姫蟻食)
英名: Silky anteater, Pygmy anteater
学名: Cyclopes didactylus
分布: メキシコ南部~南アメリカ大陸北西部
保全状況(レッドリスト): 軽度懸念(LC)
アリクイの仲間では最も小型で体長約20cm、尾はそれよりも長く発達している。爪と肉球、尾を使って樹上を移動して幹の裂け目からアリを舌で絡め取って捕食する。代謝が低いので体温も低く、胃の消化液も弱いが、食べたアリの蟻酸を消化に利用する。毎日棲み処となる木を移り、アリを全滅させないことで食糧不足になることを防いでいる。
夜行性で寝ている間は柔らかな体毛で丸まってパンノキの果実に擬態していると考えられる。
天敵に襲われると後肢で枝を掴み、背を伸ばし、前肢を上げて必死で威嚇する。アリクイの仲間は子が親の背中にしがみつき生活する。威嚇の仕方も親から学ぶ。
3時間程でかつフリーハンドで作ったフェルト製ぬいぐるみ。芯材で四肢尻尾にワイヤーが入っていて肩に乗せた。

メンダコ
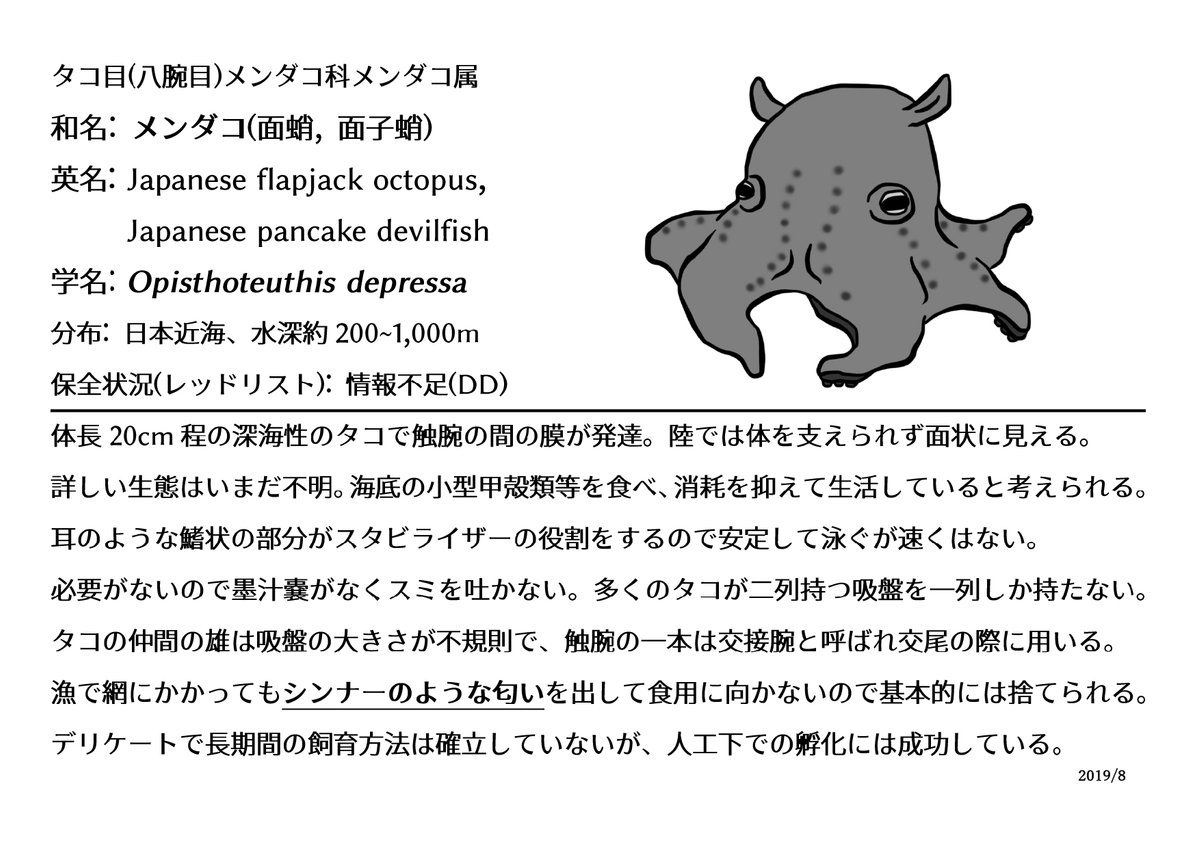
タコ目(八腕目)メンダコ科メンダコ属
和名: メンダコ(面蛸, 面子蛸)
英名: Japanese flapjack octopus, Japanese pancake devilfish
学名: Opisthoteuthis depressa
分布: 日本近海、水深約200~1,000m
保全状況(レッドリスト): 情報不足(DD)
体長20cm程の深海性のタコで触腕の間の膜が発達。陸では体を支えられず面状に見える。
詳しい生態はいまだ不明。海底の小型甲殻類等を食べ、消耗を抑えて生活していると考えられる。耳のような鰭状の部分がスタビライザーの役割をするので安定して泳ぐが速くはない。
必要がないので墨汁嚢がなくスミを吐かない。多くのタコが二列持つ吸盤を一列しか持たない。タコの仲間の雄は吸盤の大きさが不規則で、触腕の一本は交接腕と呼ばれ交尾の際に用いる。
漁で網にかかってもシンナーのような匂いを出して食用に向かないので基本的には捨てられる。デリケートで長期間の飼育方法は確立していないが、人工下での孵化には成功している。
「チューリップハットを作ってメンダコっぽくすればイイ感じになるんじゃね?」という発想で作り始めたが、検索したら『どうぶつの森』にまんまのがあったので、もういっそそれの再現ということにする。


ミツクリエナガチョウチンアンコウ

アンコウ目ミツクリエナガチョウチンアンコウ科ミツクリエナガチョウチンアンコウ属
和名: ミツクリエナガチョウチンアンコウ(箕作柄長提灯鮟鱇)
英名: Triplewart seadevil
学名: Cryptopsaras couesii
分布: 熱帯から亜熱帯、水深100~4,000m
保全状況(レッドリスト): 軽度懸念(LC)
魚類の中では2番目に長い和名を持つチョウチンアンコウの仲間で背中の3つ並んだ瘤が特徴。泳ぎが遅いので背鰭の一部が変形した誘引突起(イリシウム)で獲物を誘って捕食する。
雌は体長約40cmなのに対して、雄は数cmと極端に小さく矮雄と呼ばれる。雄は雌の体に噛み付くとそのまま皮膚や血管が癒着、同化して雌に寄生するかたちになる。寄生した雄は雌から栄養分を得て次第に生殖器以外の器官が退化し、雌の体の一部と化す。複数の雄が雌に寄生することもあり、遭遇の機会が少ない深海での生存戦略と考えられる。鮟鱇の七つ道具と呼ばれる可食部に白子、精巣が含まれないのはこのためである。
合皮で矮雄を複数作って口に仕込んだクリップで服に付ける。アイデアはいいがクオリティ微妙。大体自分の作るものは製作費、製作期間、技量的にそうなる。

ナミチスイコウモリ

コウモリ目(翼手目)チスイコウモリ科チスイコウモリ属
和名: ナミチスイコウモリ(並血吸蝙蝠)
英名: Common vampire bat
学名: Desmodus rotundus
分布: メキシコ~南アメリカ大陸中央部
保全状況(レッドリスト): 軽度懸念(LC)
鼻に熱を感知する器官が備わっており、主に寝ている家畜の傷から血液を摂食する。犬歯で皮膚を裂き、血液凝固を阻害する唾液と高速で動く舌で自らの体重の40%分も舐め取る。摂食後は飛ぶことが困難なので、コウモリの中では前肢親指と後肢が発達し、這って移動が可能。
代謝が早いので摂取後30分以内に排泄が可能だが、獲物にありつけなければ2日で餓死する。100~1,000匹単位の群れの仲間同士で血液を吐き戻して分け与える利他的行動が確認される。
コウモリは吸血鬼のモチーフだが、吸血コウモリは南米にのみ生息。ルーマニアにはいない。吸血鬼伝説の正体は狂犬病等の感染症でコウモリはその媒介であるためとする見解が多い。
ハロウィンシーズン。羽を模したカチューシャ。ちゃんと親指が長い。

ヒゲワシ

タカ目タカ科ヒゲワシ属
和名: ヒゲワシ(髭鷲)
英名: Lammergeier, Bearded vulture
学名: Gypaetus barbatus
分布: ユーラシア大陸南西部・アフリカ大陸北部
保全状況(レッドリスト): 準絶滅危惧(NT)
山岳地帯に生息し、大型猛禽類の中でも最大級で体長1m、翼長2~3mほどもある。和名・英名・学名の通り、咽頭部に生えた黒いアゴヒゲ状の羽毛が特徴。
腐肉食で動物の骨を丸呑みにして強い胃酸で溶かす。骨髄に含まれる高い栄養を摂取する。呑み込めない大きな骨やカメ等を掴んで飛び上がり、高所から落として割って中身を食べる。
その習性から『千夜一夜物語』に登場する怪鳥・ロック鳥(ルフ鳥)のモデルともされている。ギリシア悲劇の確立者・アイスキュロスの死因はヒゲワシの落としたカメとされる。
現在、日本で飼育されているヒゲワシは日本平動物園の老齢の一羽のみ。
イヤーマフにフェルトで目玉模様を付ける。

オオウミガラス

チドリ目ウミスズメ科オオウミガラス属
和名: オオウミガラス(大海烏)
英名: Great auk
学名: Pinguinus impennis
分布: カナダ東部~北欧の北大西洋~北極海
保全状況(レッドリスト): 絶滅(EX)
現在よく知られるペンギンの仲間が南半球で発見されるまで、ペンギンとはこの種を指した。ペンギンの語源は古代ケルト語の「白い頭」やラテン語の「脂肪」等、諸説ある。目の近くの白い模様と筋の入った嘴が特徴。ペンギンとは全くの別種だが生態はかなり近い。
数百万羽は生息していたが羽毛・肉・脂肪・卵を採るために各地で乱獲され急激に減少。ヒトへの警戒心が薄いので簡単に捕獲され、繁殖力が低くて年に1個しか卵を産まなかった。個体数減少後も希少価値が上がったことで乱獲が収まらず、また地殻変動でも繁殖地を追われた。
1844年、抱卵していた最後のつがいは発見後すぐに殺され、卵は割れて絶滅に至った。
白い模様と嘴の柄を白布で貼った黒ネクタイ。ふじのくに地球環境史ミュージアムの企画展とトークテーマが「絶滅」。
ハダカデバネズミ

ネズミ目(齧歯目)デバネズミ科ハダカデバネズミ属
和名: ハダカデバネズミ(裸出歯鼠)
英名: Naked mole-rat, Sand puppy
学名: Heterocephalus glaber
分布: アフリカ大陸東部ソマリア周辺、乾燥地帯の地中
保全状況(レッドリスト): 軽度懸念(LC)
和名・英名・学名共に毛のないことに由来するが、地中で役立つ感度の高い細かな毛を有する。
哺乳類では数少ない変温動物であり、かつアリやハチの様な真社会性を築きコロニーを作る。コロニーは数十匹、多いと300匹近くからなる。土を掘って巨大な巣を作り集団生活をする。繁殖と労働を完全に分業しており、繁殖を行うのは1匹の雌と1匹ないしは少数の雄のみ。繁殖雌のフェロモンで他個体の繁殖が抑えられる。密集して生活するのでフェロモンが作用する。労働個体の中には労働を独占するために他個体を妨害することもあり、不可解な点も多い。
環境から代謝を抑制することが可能で酸欠・老化・がんに対して耐性を持つので研究対象である。
ピンクのタオル地のヘアーキャップに目と歯を付ける。子年。
フェネック

ネコ目(食肉目)イヌ科キツネ属
和名: フェネック, フェネックギツネ
英名: Fennec, Fennec fox
学名: Vulpes zerda
分布: アフリカ大陸北部、サハラ砂漠
保全状況(レッドリスト): 軽度懸念(LC)
砂漠、乾燥地帯に生息し体長30~40cm、体重1~2kg程度でイヌ科の動物としては最小の種。
巣穴を掘り、家族で群れを作って生活。足裏にも生えた厚い体毛は昼夜の寒暖差に耐える。雑食性で時には有毒のサソリも食べ、水を飲まなくても食物から必要な水分をまかなえる。
耳が非常に大きく、外敵や獲物に対する集音以外に余分な熱を放散する器官として役立っている。低緯度の恒温動物が体は小さく、局部は大きくなる傾向になるベルクマン・アレンの法則の典型。
ペットとしても流通して人気も高いが、人馴れしにくく飼育にはかなりの手間がかかる。
サン=テグジュペリの『星の王子さま』に登場するキツネはフェネックであると考えられる。
付け耳。この時点で既に「簡単な仮装で再現できて面白く紹介できる生き物ってそんなにいなくね?」と思い始めている。よく続いたものである。
キリン
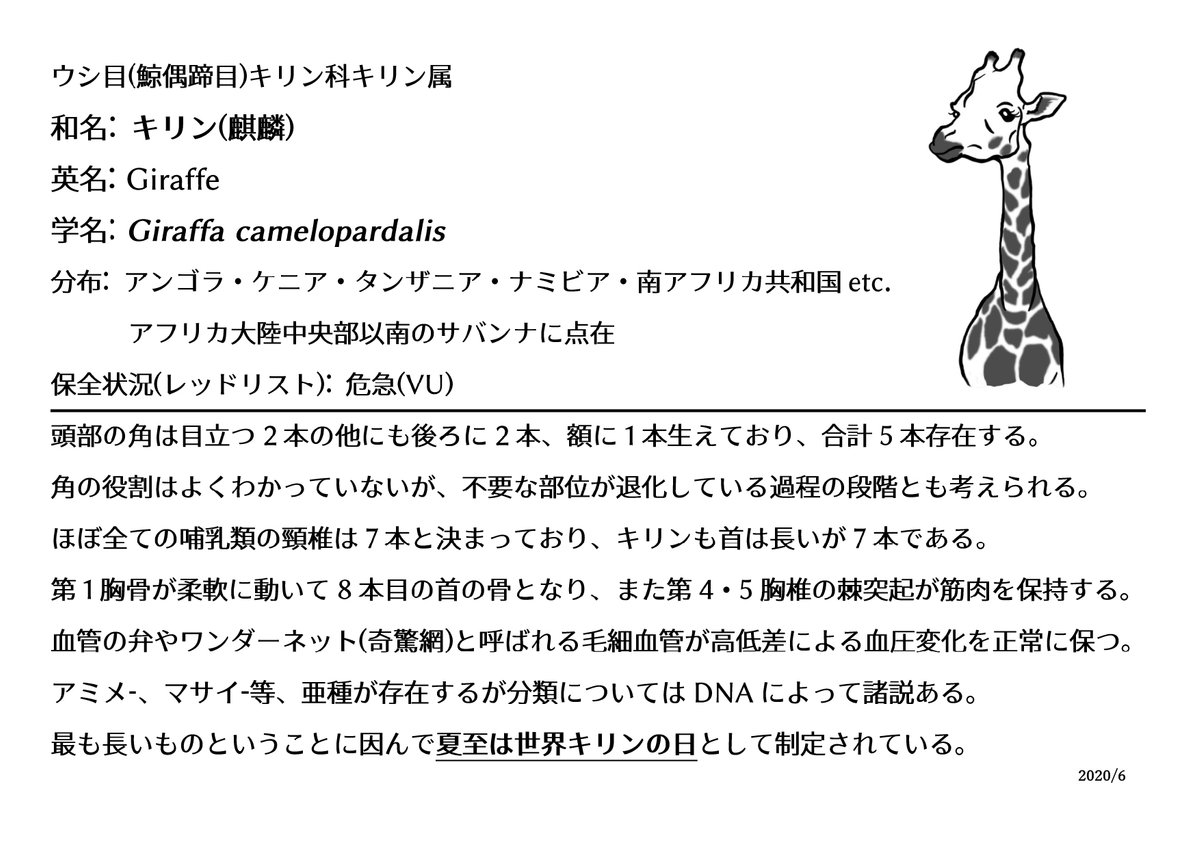
ウシ目(鯨偶蹄目)キリン科キリン属
和名: キリン(麒麟)
英名: Giraffe
学名: Giraffa camelopardalis
分布: アンゴラ・ケニア・タンザニア・ナミビア・南アフリカ共和国etc.
アフリカ大陸中央部以南のサバンナに点在
保全状況(レッドリスト): 危急(VU)
頭部の角は目立つ2本の他にも後ろに2本、額に1本生えており、合計5本存在する。角の役割はよくわかっていないが、不要な部位が退化している過程の段階とも考えられる。
ほぼ全ての哺乳類の頸椎は7本と決まっており、キリンも首は長いが7本である。第1胸骨が柔軟に動いて8本目の首の骨となり、また第4・5胸椎の棘突起が筋肉を保持する。血管の弁やワンダーネット(奇驚網)と呼ばれる毛細血管が高低差による血圧変化を正常に保つ。
アミメ-、マサイ-等、亜種が存在するが分類についてはDNAによって諸説ある。
最も長いものということに因んで夏至は世界キリンの日として制定されている。
耳と角の付いたカチューシャ+キリン柄に描いたスカーフ。夏至当日。

マレーバク

ウマ目(奇蹄目)バク科バク属
和名: マレーバク(馬来獏)
英名: Malayan tapir, Asian tapir, Piebald tapir
学名: Tapirus indicus
分布: インドネシア(スマトラ島)・マレーシア
保全状況(レッドリスト): 絶滅危惧(EN)
奇蹄目とは蹄の数が奇数であることによる。ウマは1、サイは3、バクは前肢が4で後肢が3。バクの中では最大の種で唯一アジアに生息。他の種は全て中南米に生息している。
身を守るため水中で生活することも多い。長い鼻は食物を掴み、水中での呼吸にも使う。
成獣は黒地に腹部が白く、一見派手だが夜間は輪郭が不鮮明になり目立たないと考えられる。生後数ヶ月の幼獣は黒地に白い縦縞、斑模様でイノシシのウリ坊の様に保護色になっている。
夢を食べる妖怪・獏がいるが、鼻は象、目は犀、尾は牛、肢は虎と特徴が似ている。動物のバクから獏が創作されたのか、妖怪の獏に似ているからバクと名付けられたのかは不明。
付け耳+白いタオルで包んだ腰サポーターを巻く。
ナミテントウ

コウチュウ目テントウムシ科ナミテントウ属
和名: ナミテントウ, テントウムシ(並天道, 天道虫)
英名: Asian lady beetle, Multicolored asian, Pumpkin lady beetle, Halloween lady beetle, Harlequin
学名: Harmonia axyridis
分布: ユーラシア大陸北東部・日本
保全状況(レッドリスト): 低危険種(LC)
ナナホシテントウと並んで日本で見られる一般的なテントウムシで翅の体色が多様である。個性的な模様から欧米では「かぼちゃ」「ハロウィン」「道化師」等の俗称で呼ばれる。
「天道虫」の名は光や重力に対する走性で太陽に向かって上に移動することから。天敵から擬死(死んだふり)や悪臭のする体液で身を守るので体色は警戒色であると考えられる。
肉食なので害虫を駆除する生物農薬として利用されるが外来種として生態系を侵す危険もある。そのため幼虫時に飛翔するための遺伝子の発現抑制や翅を接着剤で固定する等の処理を行う。
聖母や女神の化身とされるので古くから幸福や恋愛のシンボル、モチーフにされる。
黒い布マスクに赤い転写シートで丸模様を貼った。予想はしていたが「くまモン?」と言われる。複数パターン作れば良かった。

ロイコクロリディウム

有壁吸虫目ロイコクロリディウム科ロイコクロリディウム属
和名: ロイコクロリディウム, レウコクロリディウム
学名: Leucochloridium
サナダムシやプラナリアのような扁形動物でジストマ、二口虫の一種の寄生虫の総称。
寄生生物は繁殖するための終宿主の体内に入る目的で中間宿主に寄生することも多い。ロイコクロリディウムの終宿主は鳥。そのために中間宿主のカタツムリの目の触角に寄生する。触角は膨れて目立つ色で脈動。カタツムリは視界が遮られるのか明所に移動するようになる。結果として鳥に目立って捕食されやすくなるので、そのまま終宿主の体内に入ることになる。鳥の消化器官で繁殖し、卵は糞と一緒に排出され、カタツムリがそれを食べるサイクルである。
他にも宿主の生態や行動を何かしらの要因で制御・操作する寄生生物は様々に存在する。
頭に付けるフェルト製の触覚。スプリング状にしたワイヤーと綿を詰めてブヨブヨする。

タスマニアデビル

フクロネコ目フクロネコ科タスマニアデビル属
和名: タスマニアデビル
英名: Tasmanian devil
学名: Sarcophilus harrisii
分布: タスマニア、人為的にオーストラリア南部
保全状況(レッドリスト): 絶滅危惧(EN)
現生では最大の肉食有袋類であるが大きさは小型犬程度。主として腐肉食の雑食性である。デビルの名前は夜行性であり、威嚇時の恐ろし気な鳴き声や死骸を漁る習性から名付けられた。
顎の力が体の大きさに対して強く、犬歯は一生伸び続けるので死骸を解体するのに適している。食欲旺盛で一度の食事に体重の10~40%分を食い溜めする。脂肪は尻尾に蓄えられる。
巣穴を掘るため育児嚢は後ろ向きについている。繁殖期の雄は雌を巣穴に閉じ込めて監禁する。
デビル顔面腫瘍性疾患(DFTD)という固有の感染性の悪性腫瘍が存在し、絶滅が危ぶまれる。しかし抵抗力のある遺伝子を持つ個体が増えて急速に進化、適応しているとも考えられる。
オーストラリアに帰化のニュース+ハロウィンシーズン+感染症対策ということで付け耳+顔の模様のフェイスガード。
この後、情勢的に企画自体が一年程休止する。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
