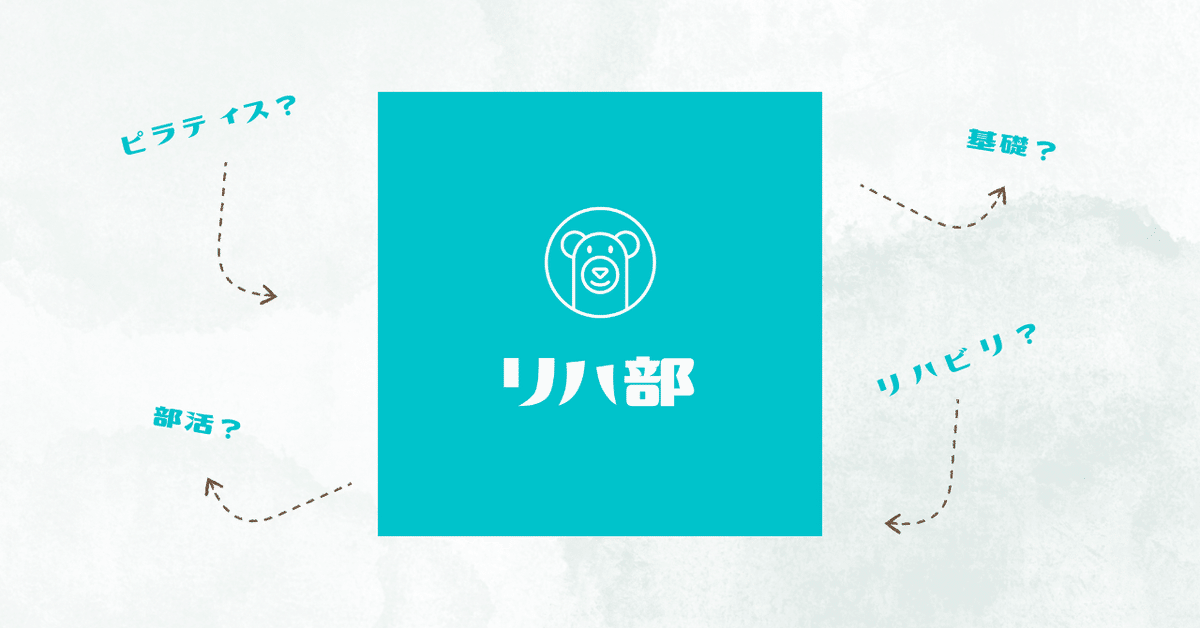
潜在学習
人は知らないうちに身体に学習させている能力があり、
きっかけがあると表に出てくる不思議な力
例えばラジオ体操の曲が流れたら
「ラジオ体操第一っ」とでも
耳にしたら
足を揃えてしまう
手を体側に構えてしまう
足首でリズムを取って出だしを待ってしまう
そういう学習能力のことで
氷山の一角の下の部分
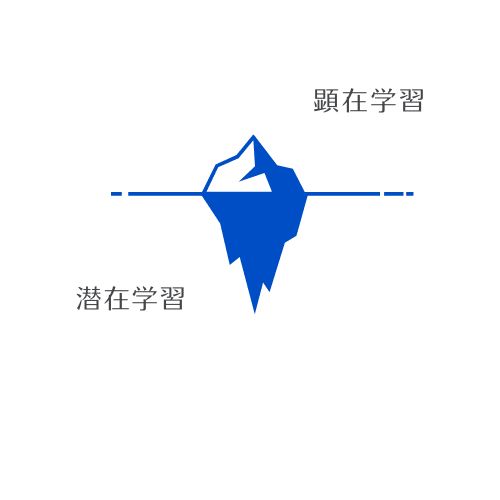
ピラティスはエクササイズ全体を知らなくても
一部分の動きが潜在的に
学習している動きかもしれないこともある
それを上手く引き出すことが
インストラクターの役目であって
持ってる可能性を引出すチャンスでもある
逆に、エクササイズの原則や型
「~したらこうなったよ」という結果の情報
動きの知識、関節や環境、道具の使い方の注意
とかそういう情報を与えるのは
顕在学習の方にいきる
つまりお客様が理解して
繰り返すことで上達していくことができる
ここまでは、結構達成している
インストラクターが多いのではないかしら
ここからが面白いところ。
情報の与え過ぎによる「上達の停滞」
結果の情報の与え過ぎは依存になり
動きの知識の与え過ぎは過剰修正を起こして
(もっとやれば上手くできる!って思っちゃう)
結果的に求めたい動きにならない
つまり、ある段階にきたら
インストラクターは顕在学習に生きる
情報を減らして
身につけた潜在学習を引き出す、気づかせる
情報に絞ることが必要になるんです
私たちインストラクターがどこに向かって
発信している情報なのか
それをたくさん提供するか
ちょっと引くか
そのさじ加減でもティーチングを楽しくなります
こちらの「リハ部」は
ちょっと専門的な事を学びたいな
マニアックな雑談したいな
人には言えないけど、こんな考え方ってあり?
をディスカッションできる部活です
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
