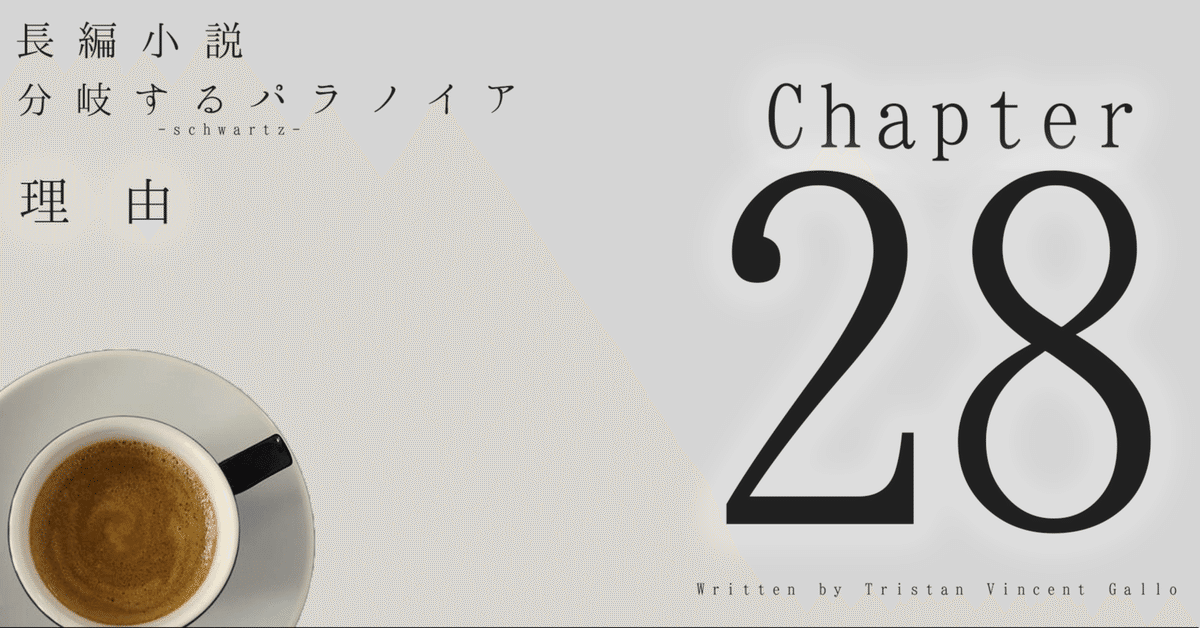
【長編小説】分岐するパラノイア-Schwartz-【C28】
<Chapter 28 理由>
竜姫との関係性にはおかしな点があることはわかった。
カフェの店主はその後も30分くらい、もっと短かったかもしれないが
タイムトラベルやパラレルワールドが関係しているという実例をいくつも紹介し、私を納得させようとした。
私が理解できなかったり、興味を示さなかったりで店主がやきもきしていることだけはしっかりと感じ取れた。
「はぁ。もう理解してもらえないみたいだなぁ。君はもしかしたら相当おもしろいことに巻き込まれているのかもしれないのに。」
店主はゆっくり立ち上がり、コーヒーサーバーに手を伸ばす。
「おかわりは?」
いつの間にか私のカップも店主のカップも空だった。
話の最中に手持ち無沙汰で仕方なく飲んでいたことを思い出した。
「あ、おねがいします。」
店主はサーバーから自分のカップと私のカップにコーヒーを注いだ。
「それで?」
店主はまた椅子にだらしなく座った。私が——え?、という顔をすると、
「それでその女の子、那実ちゃんのことはなにかわかったの?」
「あぁ、いや、まったく。」
そうなのだ。この物語の最終的な目標は那実の死の理由を探すことだった。———そうなのか?
「ねぇ、その子が死んじゃった理由を知ってさ、どうするの?」
店主の顔つきや店の中の雰囲気が変わった気がした。
今まで私の混乱具合をおもしろがっている雰囲気とはまるで違う。
薄暗く、どんよりと空気が重くなる。
ふと店の外に目をやると、向かいの店、床屋だろうか。
さっきまではその古めかしい時代の雰囲気や色褪せたポスターが懐かしく、
あったかいものに感じていたのに、今はそうではない。
店の外装は乱れていて、グレーみがかっている。
今でも営業しているのかわからないほど窓は曇り、中の闇を一層暗くしている。
懐かしいはずのポスターに映った女性の顔の笑顔が不気味に見える。
色褪せ、雨ざらしにされていたようでポスターの上の方から滴る水跡がまるで血の流れた後のように見える。
その血の跡に見えるシミは、不気味に笑う女性の目のあたりまできていて、
まるで目から出血しているようだった。
私は怖くなり、目をそらした。
ポスターが怖かったのではない。
この店主の言うように、私は別の世界にきたのかもしれないと可能性を感じたからだ。その瞬間に、全てが薄気味悪く、不気味に感じられた。
「その子が死んだ理由を知ったところで何も変わらないじゃん。」
店主はじっとこちらを見ている。私の目から目を逸らさない。
「ほんとに?」
「え?なにがですか?」
「ほんとに知りたい?その理由。」
「わかったところでどうにもできないのはわかってます。わかってるんですけど、そこに何か、ねじれを感じていて、何かはわかんないんですけど。」
「ねじれ?」
別にこの店主の言うことを真に受けるわけではないが、パラレルワールドの話はまったくもって関係がない話、空想上の、“架空”の、怪しさ満点の話だとは思えなかった。
事実私自身がはっきりと自覚している。
長谷部ケンという男がいる。
この男とは浅はかならぬ縁であった。
そしてこの男こそ、私の時系列に大きく関わっている人物でもある。
長谷部は私に成人のお祝いの言葉をかけてくれたたった一人の人物である。
それと同時に、私が成人する時、20歳の時には会ったことない赤の他人でもある。
私にははっきりと成人の日の記憶がある。
私と長谷部はいつもようにファミレスで長居をしていた。
私は成人式に出席しなかった。
会うべき人も会いたい人もいなかったからだ。
いつもどおり夕方まで家でDVDを見て過ごし、そのあと長谷部といつものファミレスへ行った。
そこでやはり同じように成人を迎えた集団が来店し、長谷部も私が成人の日に該当することを思い出したようで、「あ、おめでとうございます」ととってつけたかのようにお祝いの言葉をくれた。
しかし時系列では彼とは私が成人の日に該当する年には会うことができない。長谷部とは長谷部のバイト先で出会った。
私が成人の日にはまだそのバイトはしていなかった。
出会いようがないのだ。
さらに、私は長谷部とはかなり長い付き合いだと思っている。
それは1年や2年ではない。正月や夏を何回か繰り返した。
繰り返したと思っている。
その思い出ももちろんある。
だが、よく考えると長谷部とバイト先で出会ったのは彼が高校三年の夏である。それから長谷部は県外の専門学校へ進学する。
正味、半年なのだ。
私は長谷部と数回正月や夏を経験した記憶があるが、長谷部にはない。
その思い出の中に、長谷部と那実そして那実の友人である中村麻衣子と私の4人の思い出もある。
私はこれを「世界線の移動」として捉えている節があった。
長谷部が思うよりずっと前に私と出会っていて、那実や中村麻衣子とも面識がある世界線から長谷部が言う「半年の付き合い」という世界線に移動したと考えることがある。
「その長谷部くんとの思い出はちゃんとあるんだ。」
「はい。いろんなくだらないことをしました。若気の至り、ですね。」
「誰にでもあるよ、そんな時代は。」
店主の雰囲気は相変わらず重い。
「要するに、その“ねじれ”ってのはそれが原因ってこと?」
「わかりません。ただ、私の記憶がおかいしことのすべてに那実が関わっているんです。長谷部も私の記憶では那実とかなりいっしょに過ごしたはずなんです。」
「だから、その那実ちゃんが死んだ理由を知りたいってこと?」
「そう、ですね。結局は自分のことなのかもしれない。でも信じられないんです。」
店主はまだ私から目を逸らさない。
「那実が死んでしまった、いなくなったってことが信じられないんです。
あれだけ毎日のようにいっしょに過ごしていたのに、急に疎遠になって。
また急に連絡が来たりして、また難しいお願いをしてくるんじゃないかって思ってしまうんです。まだ未練があるとかそんなんじゃないんです。
ただ、なんていうんですかね、こういうの。」
この重い雰囲気に耐えられずに笑ってみることにした。
馬鹿のフリは上手い方だと思う。
「腕時計。」
店主はポツリとこぼした。
私はなんのことかわからなかった。
相変わらず店主の目は私の目に刺さっていた。
「腕時計、昔使っていた腕時計がさ、見当たらないんだよ。
どこを探しても。絶対に捨ててはいないし、なくしてもいない。
腕時計だけじゃない。
帽子や靴も。とても気に入っていたのに見当たらないんだ。
ただ使わなくなっただけかもしれない。
でもいつ使わなくなったのか、どこへやったのかわからない。
失くしたわけでも壊れたり捨てたりしたわけでもなく、
つい前日まで持っていたものをある日突然持たなくなった。
それをさも当たり前かのように、
何事もなかったかのように受け入れてしまっていた。
ずっとつけていた腕時計をしなくなったその日はどんな気持ちだったんだろう。」
「そうですね。」
私は淡々と話す店主の言葉の意味が痛いほどわかった。
そうですね、という回答は正しくないかもしれない。
あれだけ毎日ともに過ごした仲間たちはいったいどこへ行ったのだろう。
いつの間にか煙や湯気のように跡形もなく消えてしまった。
仲間なんてよべる関係ではないかもしれない。
でも私の周りにはもう存在しない。
彼らもこの社会のどこかで存在し、生きている。
私にはその存在のかけらさえ感じとることはできない。
今もどこかで元気にやっているだろうという想像、推測しかできない。
それは死んでしまった那実にも同じように思うのだ。
「あ、そうそう。そういえばね、メグちゃんがずっと気にしていたことあったなぁ。」
「気にしてたこと?」
「常連さんの中に忘れ物が激しい人がいるんだ。その人がケータイを忘れていってね。そのことをずっと気にしていたんだ。」
どこへやったかな、といいながらカウンターへ向かう店主の背中は見ず、
向かいの床屋の不気味に笑うポスターを見ていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
