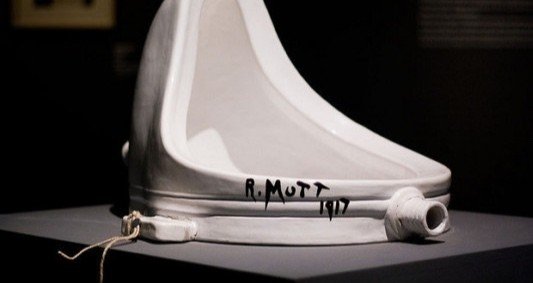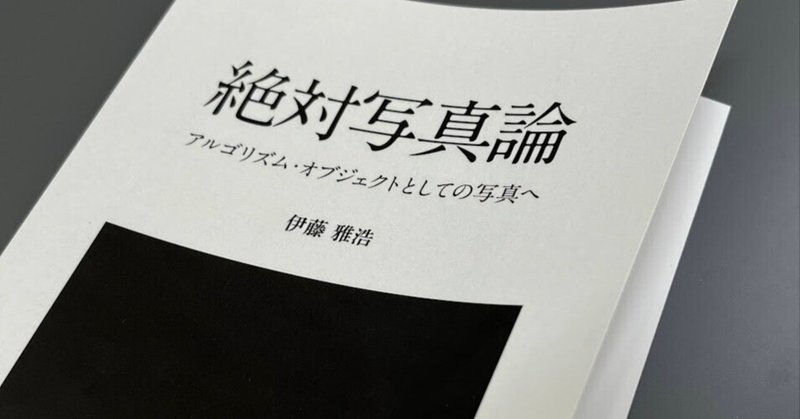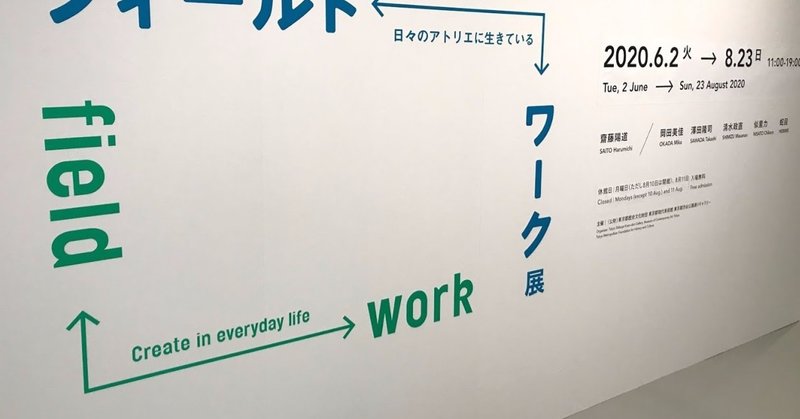#写真

小瀬村真美 『Classic – 絵画の輪郭/Outline of a Painting –』 @kenakian 鑑賞メモ
佐賀に硬派な現代アートギャラリーが開廊した。 佐賀駅からバスで20分ほどの立地、周辺は広大な駐車場を抱えるコンビニエンスストアとドラッグストアがある。夕方の時間帯になると高校生が自転車で下校していく。どこにでもあるような地方都市の郊外、そんな場所にkenakianがある。 二階建ての広大なスペースは、天井が高く、一階と二階とで趣が異なる。自然光の入る二階の展示室は、大きな窓が開口しており、展示室とその先の空間が接続しているかのような錯覚に陥る。一階は暗転させることも可能で

『分裂と融合 post / photography 2011-2021 3.11から10年目の、写真の今と未来展』@銀座奥野ビル 306号室 鑑賞メモ
3.11から10年。あの年に生まれた次女は今年の9月に10歳になる。父親が秋田出身、そのためか親族に東北出身者が多かったような印象がある。母親は東京出身というか、いくらか事情がある。 確かな話は確認のしようが無いけれど、母親の親世代、父が代官の家系で母が豪農の家系、明治に変わるかどうかの頃合いだったのか結婚が許されず、駆け落ちして東京にやってきた。 東京で始めた運送業の商売が軌道に乗り、成功したので親に許しをもらい、東京に呼び寄せた。運送業といっても、その当時は馬車であり

『Wolfgang Tillmans How does it feel?』@WAKO WORKS OF ART 六本木周辺の展覧会 鑑賞メモ
六本木のWAKO WORKS OF ARTで開催されているティルマンスの個展、6年ぶりの開催ということ。展示は完全予約制で、週末は早々に満席になってしまう。早めに予定を立てるようにするといいと思う。 様々な作品が展示されている。入り口の部屋には、ピン止めされた作品が、目線の高さで、白い壁を埋め尽くしている。様々な構図、写っているモデルやモノ、ある種、無造作に見える写真の提示。フレームの中にオーバーレイで表現されている。フレームの中にあるフレームは、フレームそのものを考えさせ