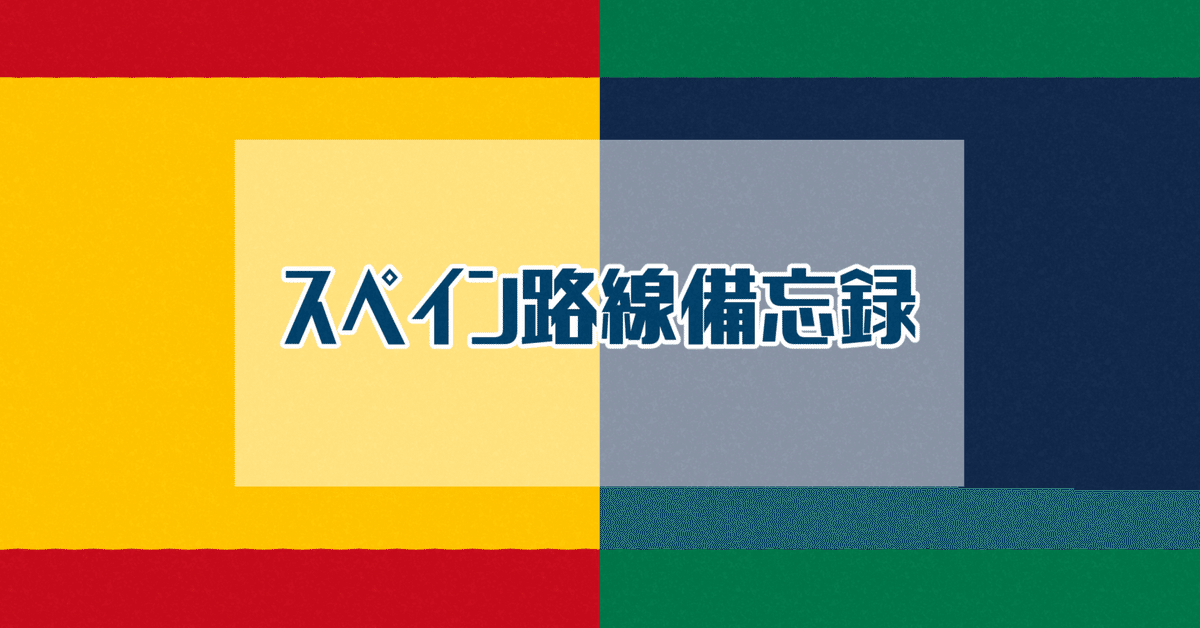
スペイン路線備忘録
まえがき
全国44位の人口約70万人という田舎にあり、最寄りの都会へアクセスするにも車やバスで海を渡らなくてはいけない。
かつて全国的な強豪高があったこともあり圧倒的に野球文化の根強い地域性。
スポーツ全般へのスポンサードに力を入れる地元発祥の製薬会社サッカー部から始まり現在まで多くの面で依存している。
良くも悪くも"相応"だった徳島ヴォルティスというクラブが、一人のスペイン人監督招聘から大きく変わり始めた。
国際空港のないこの町が、今や日本で最もスペインに近い場所かもしれない。
その過程を一人のサポーター目線で書き記していきたいと思う。
前日譚
2005年にJリーグへ参入した徳島ヴォルティスは初年度こそ12チーム中9位だったものの、そこから3年連続で最下位に低迷する。
2009年から親会社からの出資が増え順位を伸ばしていき、2011年には美濃部直彦監督のもとで4位と初めて昇格争いに加わる。
その後就任した小林伸二監督体制での2年目2013年には初のJ1昇格を達成した。
しかし初のJ1は最下位に終わり、獲得した勝ち点は僅か14。
降格した2015年もそのまま小林監督が続投するも14位と低迷した。
2016年はヘッドコーチだった長島裕明が監督に昇格し、選手の自主性を尊重したチーム作りを行うも昇格争いには加われず9位フィニッシュ。
これまではブロックを敷いて前線の個の能力を活かしたカウンターやセットプレーからの得点がベースで、持たされると手詰まりといったサッカーだった。
補強方針としてはJ1やJ2上位クラブで出場機会を失っている選手が中心で、経験値やネームバリューが優先されるような印象だった。
リカルド・ロドリゲス体制(1年目~)
1年目(2017年)
2016年11月29日、徳島ヴォルティスは2017シーズンよりリカルド・ロドリゲス氏が監督に就任すると発表した。

降格以降の閉塞感漂うクラブを変えてくれる期待感と、クラブ史上初の外国人監督でありタイやサウジアラビアといったよく分からない経歴という不安感が入り混じっていた記憶がある。
そんな半信半疑だった状態から大きな期待へと変えたのが、新体制発表でのプレゼンである。
詳しくは記事を読んで欲しいが、当時このように監督が長時間演説をするというのは前例がなく、その熱量に一抹の不安は大きな期待へと変わっていった。
2017年当時の日本ではポジショナルプレーはまだほとんど知られておらず、徳島のサポーターもポゼッションサッカーとの違いを説明できた人は全くと言っていいほど居なかった。
そんななか日本のクラブにいち早くポジショナルプレーを取り入れたのがリカルド監督と、同じ年東京ヴェルディの監督に就任したロティーナ監督だった。
ポジショナルプレーを理解している選手が誰一人いないチームで監督の考えを浸透させるのは容易ではなく、岩尾憲はリカルドの指導について「僕らが考えてプレーするのではなく、勝手にそういうポジションを取れるとか、癖になるところまで持っていく」と話している。
岩尾は「FWがボール来なくてずっとキレてる」であったり「チャーハンばっかり食べさせられてるイメージ」とも言っていたが、このように無意識レベルで適切なポジションが取れるまで繰り返すことで徳島にポジショナルプレーを浸透させていった。
その結果「開幕した頃には既に理解してやっている感じはありました」と語っており、実際サポーターは開幕戦で昨年までとは全く異なるサッカーを見せつけられた。
開幕戦となった東京ヴェルディ戦
選手たちはピッチの横幅をフルに使うこれまでの徳島では見たことのない立ち位置を取り、中央のカルリーニョスから高い位置を取った左SBの馬渡へダイナミックなロングフィードが何本も通る。
立ち位置と局面的数的優位で試合を支配し続け、観客が試合結果に関わらず見ていて面白いと感じるサッカーで勝ち切った。
結果的に2017年は7位フィニッシュ
システムは相手によって変える戦い方で4312がメインだった印象
昇格プレーオフにあと一歩届かなかったものの個人的には結果以上に強かった印象が残っている。
その要因としては
・リカルドが持ち込んだポジショナルプレーが衝撃的だったこと
・クラブ歴代最多得点である71得点を記録(2022年時点で最多)
・5点差で勝った試合が2回(5点差以上の勝利は2009年以来)
などが上げられる。
一方で印象の割に結果が伸びなかった要因としては、1年間を通して安定的な戦いが出来なかったことが大きい。
失点数自体はリーグで4番目に少なく、得失点+26はリーグ最多だったが、5試合勝ちなしが1回、6試合勝ちなしが1回と調子の浮き沈みが激しいシーズンとなった。
要因としては、攻撃的であるがゆえに少し噛み合わなくなるとバランスが狂いチーム全体として崩れてしまう。
4312というシステムは前へプレスに行くぶんには良いもののブロックを敷くのが難しいという欠点もあった。
リカルド・ロドリゲス監督のサッカーに大きな可能性を感じた一方、昇格や優勝を狙うには足りない部分も多く出た。
全く新しいプロジェクトをスタートさせた最初の1年としては非常に有意義な1年となり、リカルド監督も1年間を振り返り「全体的に非常にポジティブなシーズン」と語っている。
最初の1年で可能性を感じられたことは、スペイン路線を長く継続していくという判断に大きな意味をもたらしたのではないかと感じる。
難解なサッカーを1年目から成功といえる水準まで持っていく事ができた大きな要因の一つが岩尾憲の存在だろう。
いち早くリカルド監督のサッカーの理解者となり選手目線で他の選手たちに考えを共有できたことはチームの完成を大きく早めた。
もう一人は通訳の小幡直嗣氏。
スペインで指導者経験のある小幡さんが通訳に就任したことはスペイン人監督の意図を日本人に伝えるうえで大きな存在だった。
2017年のルーキーは小西雄大と川上エドオジョン智慧の高卒2人で、渡井理己と坪井清志郎の2018年加入も内定していた。
徳島ヴォルティスは2016年の時点で高卒選手は地元出身か韓国人のどちらかで、合わせても12年間で5人のみだった。(対して大卒は17人)
川上エドは地元出身以外で初の日本人高卒選手だった訳だが、徳島ヴォルティスの補強方針は小西と川上エドの2人が加入内定した2016年の時点で大きく転換していたといえる。
前年の大卒ルーキーだった井筒陸也も当時の徳島のチームスタイルとは合わないタイプの選手だった事を考えると2015年の段階でもしかしたら転換が始まっていたのかもしれない。
単に監督やサッカーが変わっただけでなく、補強方針やチーム作りからクラブの体質を大きく変えたことはその後の徳島ヴォルティスというクラブを語る上では避けられない部分である。
育成面でも改革が始まり、小西雄大がスペインのラージョ・バジェカーノBへ留学するなどこれまでになかった試みも行われた。
ピッチ上での変化、フロントの変化、スペイン路線始まりの年はこれまでの徳島に劇的な変化をもたらし、チームスタイルの確立に確かな光を感じる1年となった。
2年目(2018年)
昇格は逃したもののスペイン路線と監督のサッカーに手ごたえを感じたクラブはリカルド監督の続投を発表。
しかしリカルド・ロドリゲス体制2年目は苦難の年となる。
昨年J2日本人得点ランクトップの23得点を上げた渡大生とアシスト数チームトップの馬渡和彰がともにサンフレッチェ広島へ移籍。
FWに薗田卓馬や呉屋大翔、SBに大本祐槻を補強するも絶対的なエースとSBの穴は埋まらず、4度の連敗もあり前半戦終了時点で15位と低迷する。
補強がはまらなかったことに加え怪我人も重なり、SBが足りなくなったことで昨年戦っていた4バックが困難になった。
受難はさらに続き、夏のマーケットで大﨑玲央、山﨑凌吾、大本祐槻、島屋八徳の4人がJ1へ個人昇格。
その穴埋めとしてピーター・ウタカとダビド・バラルという2人外国籍ストライカーを獲得。
フィジカル的に優れたウタカと圧倒的な決定力を誇るバラルの加入で、チームはこれまでのアグレッシブにプレッシングをかける戦術から、ブロックを敷いてリスクを避ける戦い方に転換。
昨年から積み上げてきたスタイルを捨て結果にフォーカスする決断をした。
結果的にチームはホームゲーム8連勝というクラブ記録を塗り替えるなどもあり後半戦の半分が終わった時点で8位まで順位を伸ばす。
しかし研究されるとともに個人の能力に頼ったサッカーは限界を迎え、ラスト9戦を6敗3分0勝で終えた。
その中で光明と言っていいのはラスト2試合のドロー。
昇格の可能性がなくなったチームは本来のアグレッシブに相手を敵陣にを仕込み試合を支配するサッカーに回帰する。
一度スタイルを捨てたことで成熟度的には甘く2試合を無得点で終えたものの、昨年見せたような見ていて楽しいサッカーで相手を圧倒する試合が帰ってきた。
システムは3142が主で、昨年とは最終ラインの枚数が変わったが中盤3枚と2トップはこだわりのように感じられた。
この年を振り返って岩尾は「積み上げができているという感覚にならない。くじを引いているような感覚が強かった。」と語っている。
非常に苦しい1年となったが、15位で折り返した夏の段階、6連敗を喫した終盤戦の段階、監督を解任してもおかしくない状況で継続を決めたことはその後の結果に関わる非常に大きな判断だったと言える。
この年も夏に渡井理己がデンマークのヴェイレBKに留学を行った。
スペイン路線に活路を見出した徳島ヴォルティスはアカデミーもトップチームと同じサッカーで一貫した指導方針を打ち出し改革を始める。
2009年に廃止したジュニアチームを2018年から復活
夏には倉貫一毅氏がユース監督に就任した。
2017年に行われた2018年入団生を対象に行われたセレクションを最後に、公式HPでU-18セレクション実施のお知らせは発信されていない。
実際に行われていないのかは把握していないが、世界的に見ても優秀なアカデミー生を集める手段はセレクションではなくスカウトである。
コストはかかるもののメリットは大きいスカウトに2018年のタイミングで切り替えたのではないかと推測できる。
3年目(2019年)
ブレたスタイルを取り戻しに行くリカルド体制3年目
広瀬陸斗が横浜F・マリノスに移籍、昨年大量流出したぶん今年はレンタル組以外の主力流出が広瀬一人のみに抑えられた。
昨年の反省を基に、本来徳島ヴォルティスが目指すスタイルを実行できる選手補強を進める。
ここでひとつスペイン路線を継続してきた成果が表れた。
今まではいわゆる格下クラブからの補強が主だったが、この年は昇格のライバルチームから主力の引き抜きに成功する。
千葉から清武功暉、新潟から河田篤秀、横浜FCから野村直輝を獲得。
3名とも移籍の理由に徳島のサッカースタイルを挙げており、一貫したスタイルの継続がひとつ実を結んだ形となった。
新加入選手が多くなったこの年も出だしはつまづき、前半戦を終えて9位と昇格争いには加われない。
今季新たに就任したスペイン人のアベルヘッドコーチが6月末に家庭の事情により帰国。
そのまま契約解除となりジムナスティック・タラゴナ(スペイン3部)のコーチ就任が発表された。
スペインでのインタビューでアベルは、日本ではリカルドの戦術が最先端と言われていたが全く最先端ではなく時代遅れのものだった、と答えておりリカルドと考え方の相違があったのではないかと思われる。
確かに当時ポジショナルプレーがベースにあることは変わらなかったものの、リバプールを筆頭にフィジカルを活かした縦へスピードのあるスタイルが結果を残していたのでアベルの言っていることは確かに間違ってはいない。
しかし最先端かどうかよりも、同じ方向を向いて一貫したスタイルを積み重ねることの重要性を証明することになる。
後半戦は戦術の浸透、選手のコンディション向上、高卒2年目渡井理己の台頭などがあり、2度の4連勝を含む12戦負けなしなど巻き返していった。
昨年までの頑なだった中盤3枚2トップを崩し、この年は3421をメインシステムとした。
Love Vortisポーズの誕生、6度の逆転勝利(被先制時の勝率31.6%)など一体感の強いチームとなり最終的にシーズンを4位でフィニッシュ。
昇格プレーオフを勝ち上がり、湘南ベルマーレとの入れ替え戦はドロー。
レギュレーションにより昇格は逃したがJ1まであと一歩のところまで迫った。
観客にも徳島ヴォルティスが目指すサッカーが浸透し始め、バックパスで相手を引き付ける、最終ラインで相手を1枚剥がしてドリブルで運ぶといったプレーにもスタジアムで拍手が起こるようになった。
この年も藤原志龍がポルトガルのポルティモネンセへ、久米航太郎がオランダのローダJCへ留学が行われた。
ユースも改革の結果が出始め、Jユースカップでは川崎フロンターレU-18を下すなど史上最高の3回戦まで勝ち進んだ。
4年目(2020年)
積み重ねたものがついに実るリカルド体制4年目。
正守護神の梶川裕嗣、ビルドアップを身に着け中心選手となった内田裕斗、サイドの崩しを担った杉本竜士、攻撃のキーマンだった野村直輝がそれぞれJ1へ移籍。
その穴埋めに上福元直人、西谷和希、垣田裕暉などの獲得に成功。
ここ2年つまずき続けた開幕戦に快勝するも、新型コロナウイルスの蔓延によりリーグ戦が約4ヶ月中断。
再開後は昨年の3421や433など複数のシステムを使うも最終的に4231に落ち着く。
例年通り後半戦から調子を上げ第30節から首位を守り、初のJ2リーグ優勝とJ1自動昇格を果たす。
リカルド・ロドリゲス体制4年目にして最高の結果を手にし、集大成と言える年になった。
この年の大きな出来事は、昨年FWとして獲得した岸本武流をサイドバックにコンバートし大成功したことだ。
持ち前のスピードとガッツを活かし、そこにビルドアップを仕込むことで非常に質の高いSBへ生まれ変わった。
昨年の内田裕斗も元々縦に仕掛けるプレーが特徴のSBだったが、伸び悩んでいたところにビルドアップを仕込むことで3CBの左として絶対的な主力に成長した。
リカルド監督の元で多くの選手がJ1へ個人昇格していったが、特にサイドバックの育成には長けていた印象がある。
リカルド・ロドリゲス体制総括
スペイン路線を始めるにあたり、最初の監督がリカルドだったことは徳島にとって非常に幸運だったのではないだろうか。
日本に来る前から独自に分析を行うなど日本で仕事をすることへの意欲が高く、情熱的な人間性は戦術以前に選手にもサポーターにも親しまれた。
リカルドが自身のサッカーを表現するにあたり、高い戦術理解度とキャプテンシーを兼ね備えた岩尾憲の存在も非常に大きかった。
1年目から渡や馬渡などクオリティの高い選手を揃えられ、良い印象を残せたことが後に繋がったのではないかと感じる。
リカルド監督は配置で優位性を取ることで選手のウィークを隠しストロングを活かすことが上手かった。
一言で言えば、能力以上に選手が上手く見える。
選手をコンバートしたり原理原則を教え込むことで、他のクラブで伸び悩んでいた選手を生まれ変わらせた例はいくつもあった。
しかしそれにより実際の能力と評価が乖離し、個人昇格した先のクラブで個人の能力に頼るタイプの戦術の中に入れられると活躍できないという例も多くあった。
4年間で11人(レンタル選手除く)の選手がJ1へ個人昇格していったが、主力として活躍したと言えるのは大﨑玲央と山﨑凌吾、広瀬陸斗の3人のみである。
4年間でJ2優勝という素晴らしい結果だけでなく、徳島のスタイルを作り、徳島へ行けば成長できるというブランドイメージも構築した。
J2を優勝したチームでJ1を戦えなかったことは残念だったが、成功も失敗も全部含めてとても色濃く充実した4年間だったのではないだろうか。
ダニエル・ポヤトス体制(5年目~)
1年目(2021年)

2度目のJ1に挑むこの年、昨年まで指揮したリカルド・ロドリゲス監督が浦和の監督に就任し、新たにダニエル・ポヤトス監督を招聘した。
ポヤトス氏はレアルマドリードの下部組織で監督歴があり、徳島の前はギリシャのパナシナイコスで初のトップチームを指揮していた。
コーチにはバルセロナのアカデミーで指揮経験のあるマルセル氏を相棒として連れてきた。
通訳にはリカルドと共に浦和へ行った小幡氏の代わりに、ポヤトス監督と知り合いだった志水和司氏と、岡井孝憲氏。
2人ともスペインでの指導者経験を持っている。
新型コロナウイルスによる新規外国人入国制限の影響でポヤトス監督はキャンプに参加できず、リモートで指揮する状況が続く。
シーズンが始まってもポヤトスやマルセル、新たに獲得したブラジル人のカカなどが入国できず、ポヤトス監督の初指揮となったのはリーグ11試合目の鹿島戦からとなった。
スペイン路線を継続させ、ゲームを支配し攻撃的なサッカーというコンセプトは変わらなかったものの、リカルド監督との方法論の違いに苦戦する。
さらにはコロナによる過密日程でポヤトス監督は初指揮の試合から連戦が続き戦術を落とし込むのも難しさがあった。
リカルドが流動的に選手を動かすのに対し、ポヤトスは最初の立ち位置からあまり動かさずビルドアップをする。
具体的にはリカルド時代はアンカーの選手が最終ラインに落ちてSBが高い位置を取るというやり方がよく見られたが、ポヤトスはアンカーを落とさずボールを速く動かすことで相手のプレスを剥がそうとする。
このやり方は選手個々に高い技術が求められるが、ポジションを動かさないぶん守備時のリスクが減り安定した戦いが期待できる。
ポヤトス指揮開始後しばらくは今までのやり方との違いに選手たちは戸惑い、初めてJ1でプレーする選手が多いことも相まってビルドアップのミスから失点という場面がほぼ毎試合のように繰り返された。
その結果ポヤトス就任後リーグ戦4連敗を喫することになる。
ポヤトス監督は、自分の教えることはあくまで選択肢の一つで、選手たちが試合の中で適切な選択肢を選んで欲しいという意図だった。
終盤戦になり選手たちも監督の意図を理解し始め、昨年のようにアンカーが最終ラインに落ちる形も臨機応変に取り入れることで成績は上向き始めた。
様々なシステムを試したが最終的には藤田譲瑠チマと鈴木徳真のインテンシティを活かす433で、宮代を右WGに置き得点力を担保し右SBの岸本の上がりを活かす。
守備は両WGが外を切りながらプレスに行き強度の高いインテリオールのところで奪うやり方。
ラスト10試合は4勝1分5敗と、序盤からこのペースで試合が出来ていれば十分残留できる結果を出せる水準までチームを持っていく事に成功したが、最終的に一歩届かず1年でのJ2降格となってしまった。
この年の夏に高卒ルーキーだった鈴木輪太朗イブラヒームがスペイン1部バレンシアにレンタル移籍(所属は下部チーム)
新クラブハウス完成
食堂ができトレーニングルームが拡張
ジュニアユースがU-15全日本サッカー選手権で史上最高位のベスト8進出
2018年に再始動したジュニアチームの1期生がこの年6年生となり、JA全農チビリンピック四国で初優勝
・後日談
浦和の監督に就任したリカルドは昨年10位だったクラブを6位まで押し上げ、天皇杯優勝とタイトルももたらした。
2年目(2022年)
再びJ2を戦うこととなった2022シーズン。
ポヤトス監督続投とはなったものの災難の年は続く
昨年スタメンだった選手のうち9人もの選手がJ1のクラブに移籍
特に6年間絶対的な心臓としてチームの象徴的選手だった岩尾憲を始めボランチの選手は鈴木徳真、小西雄大、藤田譲瑠チマの主力4人が全員移籍。
チームは0から作り直しとなってしまった。
白井英治や児玉駿斗などなんとか人をかき集めるも、人数を揃えるだけで精一杯といったオフシーズンとなった。
さらには依然として続くコロナウイルスの影響で入国後の隔離期間が2週間あり、W杯の影響で開幕が例年より早いことも重なって、年明け後すぐに入国したとしても外国人監督や選手スタッフがキャンプまでに合流できず、全員そろったのは宮崎キャンプからとなった。
選手の多数が入れ替わりどれだけまともなサッカーが出来るのか心配されたが、開幕戦は想像以上に形になっていた。
昨年までとシステムは同じ433だが、昨年の右WGにストライカーを置く形ではなく両WGにドリブラーを置き、守備時も433で守る方法がベースとなった。
しかしボールを支配するところまでは出来たものの得点を奪う部分までは完成しきっておらず開幕後10試合は1勝9分1敗という珍奇な結果を残す。
その後はドローをベースにたまに勝ったり負けたりをふらふらしながら、前半戦終了時点で16位に低迷。
さらに夏には攻撃の中心だった渡井理己がポルトガル1部ボアヴィスタFCへ期限付き移籍
ここで監督を交代したり2018年みたいなスタイルを捨てて補強することはなく、夏の補強は杉本太郎の復帰のみで我慢強くチームを見守った。
守備時を442に変更することで安定性が生まれてからチームは調子を上げ、19戦無敗というクラブ新記録を樹立し最終節を前に昇格プレーオフ圏内へ浮上する。
しかし最終節に敗れプレーオフ圏外へ転落し、1年でのJ1復帰はならなかった。
2022の詳細な守備戦術についてはこちら↓
これまでJ1へ移籍して行く選手は他のクラブから獲得してきた選手が多かったが、渡井理己や鈴木徳真など生え抜き選手がステップアップし始めたのは育成の成果が出始めたと言えるのではないだろうか。
様々な不運や災難が重なったダニエル・ポヤトス体制は、その真価を見ることなく2年で終了となってしまった。
もう1年、コロナの大きな影響も受けず、選手も戦術も積み上げられたポヤトスのチームを見て見たかったがそれが叶うことはなかった。
昨年のワディに続き高卒ルーキー勝島新之助が加入後すぐにスペインのジローナBへ期限付き移籍
アカデミーダイレクターに高知ユナイテッドをJFLに昇格させた大谷武文氏が就任
ユースコーチにスペインで指導歴のある嶋田将利氏招聘
「POCARI SWEAT × TOKUSHIMA VORTIS Football Dream Project」始動
2500人から選ばれたカンボジアの中学生2人がJr.ユースに練習参加
高本スカウトのインタビュー↓
その他2022シーズンに書いた記事↓
アカデミー・育成の重要性について書いた記事↓
・後日談
浦和を率いて2年目となったリカルドは、徳島から岩尾憲と前迫コーチを呼び寄せた。
開幕前のスーパーカップで昨年のJリーグ王者川崎フロンターレに勝利し早くも2つ目のタイトルを手にした。
しかしリーグ戦では思うような成績が残せず前半戦終了時点で13位と低迷。
ACLでは躍進し決勝戦まで駒を進めるも最終的にリーグ戦9位という結果が理由なのか翌年のACL決勝を戦う前に2022シーズン終了後解任となった。
ダニエル・ポヤトス体制総括
ポヤトス体制を一言で表すと「不運」や「不完全燃焼」という言葉が思い浮かぶ。
リカルドとは違うアプローチでチーム作りを試みたものの、コロナで来日が遅れ、ただでさえ戦力的に厳しいJ1でいきなり連戦真っただ中に指揮を開始することになった。
2年目もコロナの影響は続いたうえ大量に主力を抜かれ積み上げができず、2年ともチームが出来上がってきた頃には少し間に合わず求める結果には届かなかった。
来年こそはポヤトスの真価を発揮できる年になるはずだったのに、このタイミングでガンバ大阪へ移籍。
リカルド時代の課題であった戦術に関わらず発揮できる個の能力の育成という点に、配置を動かさず個人が必要な能力を満たせば戦術が機能するというアプローチはどういう結果をもたらすのか興味深かったが、答えが出るはずだった3年目は幻となった。
不運と不完全燃焼が重なり、ポヤトス体制の2年間を評価することは非常に難しくなってしまった。
しかし1年目も2年目も終盤チームが出来上がっていくに連れて勝ち点が伸びていったのを見れば、1年目降格、2年目昇格逸といった結果をそのままポヤトス体制の評価としてしまうのは正確ではないと感じる。
2年間で8人(レンタル選手除く)の選手がJ1クラブへ移籍して行ったが、半数以上の5人は主力として試合に出場している。
単純に徳島へ加入する選手の質が上がったというのもあるため一概には言えないが、リカルド体制時よりもレベルの高い選手を送り出したと言える。
ポヤトス体制で一定の成果が見られたことは、上手くいったリカルド監督に依存したチーム作りではないことを証明できたといえる。
2人連続で監督が上位クラブへ引き抜かれた事も監督選考としてはポジティブな結果で、監督をサポートできるクラブの体制づくりも評価できる。
ベニャート・ラバイン体制(7年目~)
1年目(2023年)
契約延長を打診していたもののダニエル・ポヤトスがガンバ大阪の監督就任に伴い退任。
後任にレアル・ソシエダのアナリストを務めていたベニャート・ラバイン氏(トップチーム指揮経験なし)を招聘。

2022年12月にレアル・ソシエダとの育成業務提携を締結。
育成業務提携の一環として西坂斗和とアカデミー4選手コーチ2人がレアル・ソシエダに練習参加。
シーズン終了後には玄理吾もソシエダBに練習参加。
昨年オフとは打って変わり監督が変わった以外に大きな選手の流出もなく、柿谷曜一朗12年ぶりの復帰などポジティブな話題の多いオフとなった。
2018年〜2019年に選手として在席したシシーニョがアシスタントコーチに就任
フィジカルコーチにはスペイン人のアイトールを招聘。
通訳にはポヤトスとともにガンバ大阪へ行った志水氏と岡井氏の代わりにスペインでプレー経験があり2人のスペイン人監督の下で通訳を歴任してきた小澤哲也氏、スペインで指導歴がありUEFA A ライセンスを持つ布目浩樹氏が就任した。
キャンプ初日(始動日)から強度の高いトレーニングを行い選手たちを驚かせ、ソシエダと同じメニューであることも話題になった。
オフにトピックスが多かったこともあり例年以上の期待と注目を集めていたのとは裏腹に、厳しいシーズンを強いられることとなった。
序盤は4312とたまに433の併用
433も両WGを絞らせ、最初から幅を取るような立ち位置にはせず中央密集でこじ開けていくやり方で、昨年とは大きく異なっていた。
キャンプから試みていた縦への速さと中央のカオスという狙いは感じるものの、主導権を握ったり試合をコントロールする部分は失われ、意図的で効果的なカオスではなく、本当にただぐちゃぐちゃの混沌だけが残った様な内容は試合を追うごとに悪化。
WGがいない分SBには攻撃時に張った位置から仕掛けられる突破力、守備時にはサイドで数的不利が起きやすい配置のため個で負けない守備力が求められた。
カウンター時後ろに人数が少ないためCBの負担も大きく、中央に密集するため中盤の受けるプレッシャーも大きい、CFが中央から外のスペースへ走ったタイミングでピンポイントにフィードする必要があるため出し手も受け手も高い技術を要する。
全体的に相当高い個の能力を求められる戦術だった。
エウシーニョやケサダが怪我でほとんど試合に絡めなかったことも影響し、試合終盤に西谷や杉森をSBにするリスク度外視策でようやくチャンスを作れるといった具合には機能不全、戦術と要する能力とのギャップが顕在化していた。
勝てない試合が続くと消極的なプレーや迷走とも取れる采配が目立ち始め悪循環を生む。
開幕から10試合未勝利を受けクラブが声明を発表した後3142へと変更。
SB不足で3CBへの変更を余儀なくされた。
532で守ることで安定感が増し12試合目にしてようやく初勝利、そこから調子を上向きにしたものの森海渡のゴラッソでギリギリ勝ち切るような試合が多かった。
シーズン折り返し頃に出たスペイン紙によるラバインのインタビュー記事↓
3142が徐々に対策され始めると再び白星から遠ざかる。
3142で裏を気にして守ると配置上プレッシングをかけにくいためショートカウンターの回数が少なくなる割に、ビルドアップではJリーグで最も多い4231のプレスと完全に噛み合ってしまい前進に苦戦し、森海渡のゴラッソ以外に得点の道筋が見えなくなった。
後半戦スタートから8試合勝ちなしとなり、エウシーニョの復帰もあり4バックへ回帰し4231へシステム変更。
プレスをかけやすくなったことでショートカウンターからの得点が増加。
4231を採用してから3試合で7得点を上げるも、2点差を追いつかれたり、1人少ない相手に勝ち越されるなど不安定な戦いは拭えなかった。
後半戦11試合目でようやく勝利を挙げるも、その試合の2日後にラバイン監督の解任が発表された。
例年の課題であるゴール前での質と、速攻というオプション構築に挑んだ補強を敢行したシーズンだったものの、チームとしての基盤が耐えられずどちらも失敗に終わった。
後任には吉田達磨監督が就任。
保持するという部分は変えず守備を整備することで安定感をもたらした。
結果的に2試合を残して残留を決める。
詳細なシーズンレビューはこちらを参照↓
・その他トピックス
戦術カメラの映像を公開するTHE ANALYSISが開始
2023シーズンよりエンブレムがリニューアルされると発表
2022年12月に徳島県とドイツのニーダーザクセン州が姉妹都市であるという縁でクラブ取締役でもある副知事がドイツ2部ハノーファーへ訪問
それをきっかけに5月アカデミースタッフを現地へ派遣
11月にはハノーファースタッフが来日
Fußballschulleiter Arne #Kübeck und #96U17 Torwarttrainer Roland #Rasch sind in Japan 🇯🇵 bei @vortis_pr angekommen. Weitere Bilder folgen in den nächsten Tagen 📸
— 96-Akademie (@96Akademie) November 3, 2023
Alle Informationen zu der Japanreise findet ihr auf unserer Website#96Akademie #H96 #NiemalsAllein
⚫️⚪️💚 pic.twitter.com/T0iKAWK4id
ハノーファー96🇩🇪スタッフが徳島を訪問🙌
— 徳島ヴォルティス 公式 (@vortis_pr) November 5, 2023
徳島県が友好交流提携を結ぶニーダーザクセン州のクラブ、ハノーファー96からスタッフが11/3(金)から11/8(水)までヴォルティスと交流⚽️
その様子は後日、改めてお伝えします✨
Willkommen in Tokushima🔵🟢@Hannover96 @96Akademie #vortis pic.twitter.com/ULBiWN92IT
昨日、ハノーファー96のアカデミースタッフが、徳島ヴォルティスのスタッフとともに、徳島県・後藤田知事を表敬訪問しました🇩🇪
— 徳島ヴォルティス 公式 (@vortis_pr) November 7, 2023
交流の内容の報告などをおこないました🤝@Hannover96 @96Akademie #vortis pic.twitter.com/Cr4d55MOdO
徳島を訪問していたハノーファー96スタッフが、ヴォルティスとの交流を終え、昨日、徳島を出発しました🇩🇪
— 徳島ヴォルティス 公式 (@vortis_pr) November 9, 2023
徳島滞在中はクラブに関する様々な面での情報交換を行いました。訪問、ありがとうございました🤝
Vielen Dank für euren Besuch!Mach’s gut!👍@Hannover96 @96Akademie #vortis pic.twitter.com/wdDlH6iUWB
「POCARI SWEAT × TOKUSHIMA VORTIS Football Dream Project」
第2弾としてインドネシアリーグ1部RANSヌサンタラFCの選手が練習参加
オーナーのラフィ・アフマッド氏も来日し経営面での意見交換
第3弾としてU-14がカンボジア遠征
岡田強化本部長がカンボジアのペルシジャ・ジャカルタに訪問したことがジャカルタ側のインスタグラムで判明したが徳島側からの発信はなく詳細不明
クラブ設立記念日当日の試合にて出張FOOT×BRAIN第一弾として勝村政信さんが来場し収録やトークショーなどが行われる
新企画 #出張FOOTBRAIN 🗾
— FOOTxBRAIN (@foot_brain) September 29, 2023
今年5月放送の #Jリーグ勝手に向上委員会 で@gaku_mc さんが提案してくれたコラボ企画が実現✨
第1弾は #徳島 へ⚽️
いつもより30分遅い放送ですがお見逃しなく👀#FOOTBRAIN × #徳島ヴォルティス
テレビ東京 9月30日(土)24:55~
BSテレ東 10月8日(日)26:10~ pic.twitter.com/n7DIbbfcKC
勝村政信さんが行く✈️#出張FOOTBRAIN in 徳島✨
— FOOTxBRAIN (@foot_brain) September 30, 2023
スタジアムでサポーターの皆さんと触れ合い、トークショー、故・大杉漣さんと徳島の絆、柿谷曜一朗選手インタビューなど盛りだくさんでお届けします⚽️#FOOTBRAIN × #徳島ヴォルティス
テレビ東京 9月30日(土)24:55~
BSテレ東 10月8日(日)26:10~ pic.twitter.com/JT4BRRVFQZ
サッカー向け認知診断テスト「NeurOlympics」をアジアのクラブとして初の契約締結
中野桂太がスペイン4部のCFバダロナフューチャーへ練習参加
ユースがプリンスリーグ四国優勝
その他2023年に書いた記事↓
・後日談
ダニエル・ポヤトスがガンバ大阪の監督に就任
コーチのマルセル、通訳の志水和司、岡井孝憲も共にG大阪へ
1年目のシーズンは16位フィニッシュで降格争い
浦和を解任となったリカルドはJクラブからのオファーを断り欧州に戻る
スコットランドリーグ1部のアバディーンの監督候補に浮上と現地紙が報道
それに伴いスコットランド紙が岡田さんにインタビュー
リカルドの通訳だった小幡直嗣は鹿児島ユナイテッドのコーチに就任し、クラブはJ2昇格
岩尾憲がACLを優勝しアジア王者に
ベニャート・ラバイン体制総括
ラバイン体制の1シーズンは何もかもが上手くいかなかったと言える。
スペイン路線になってからここまでことごとく裏目に出たシーズンはなかった。
ラバインの所望する、縦に速く中央にカオスを作って崩すスペインサッカーにおいて応用と言えるスタイルは現在の徳島ヴォルティスというクラブの土台では支えきれないものだった。
毎年選手が入れ替わりスペイン流の基礎が身に付いていない選手も多い中、応用を導入したことでチームは完全に混乱した。
それを抜きにしてもこのサッカーは選手にかなりの質が求められ、現状徳島の規模では再現できる道筋を見つけられなかった。
ラバイン氏においてもアナリストやコーチのキャリアが長く、トップチームの監督歴がないのはまだしも監督としてのキャリア自体2年間のみで、最後に監督業を行ったのは8年前だった。
監督としての経験値の浅さが露呈し、技量面でも厳しかったと言わざるを得ない。
簡易版スタイル変遷
リカルド・ロドリゲス
ポジションを流動的に動かし、相手の配置を見て自分たちの配置を変える
攻撃的な反面リスクは高いので安定性に欠ける
自陣に相手を引き出すビルドアップで擬似カウンター
ダニエル・ポヤトス
最初の立ち位置からポジションはあまり動かさない
リスク管理には優れるため安定するが、個で優位性を作れないと攻撃が停滞する
相手を敵陣に押し込んで遅攻がメイン
ベニャート・ラバイン
目指したスタイルは縦に速く中央密集でカオスを作りコンビネーションで崩す形
ハイリスクで全ポジションに高い能力の選手が求められる
選手にスペインサッカーの基礎が染みついたうえでの応用型
あとがき
2024シーズンは2023年途中から就任した吉田達磨監督が続投するも、成績不振とサポーターからの支持が得られず7試合で途中解任。
その責任を取る形でここまで徳島ヴォルティスのスペイン路線を担ってきた岡田明彦強化本部長も辞任した。
岡田強化本部長の辞任を一つの区切りとして、この記事はここで更新を終えたいと思う。
もう少し長く続けられると願っていたが仕方ない。
この記事を書いている時点で今後の徳島ヴォルティスがどういった方向性で進んでいくのかは分からない。
それでもクラブは間違いなく続いていくことに変わりはない。
筆者がこれまで通りクラブを見続けていくことも変わらない。
徳島ヴォルティスがより良い場所へたどり着けることを祈っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
