
ドメインとは「アパートの住所」!? SEOとの関係は?
こんにちは、Webディレクターの伊藤です。
皆さんは毎日、どれくらいの数のWebサイトをご覧になっていますか?
そのサイトの一つ一つに必ずあるもの。それが「ドメイン」です。
ドメインとウェブサイトの表示の仕組みについては下記の過去記事をご参照いただくとして、今回はそのドメインの重要性についてお話ししてみます。
ドメインって何?URLとは違うの?

過去記事でも説明していますが、ドメインとは、インターネット上の住所のことで、Webサイトがどこに存在するかを示しています。ドメインと混同されがちな「URL」はインターネット上のファイルを示すものです。
✙
Webサイトを閲覧するとき、ChromeやSafariなどのWebブラウザは
「URL」でどのファイルやデータを表示したいのかを判別し、
「ドメイン」でそのファイルやデータがどこにあるのかを判別します。
「『プラスジャム』のホームページを見たい」を、
「『プラスジャム』というアパートに行きたい」に置き換えた場合、
『プラスジャム』というアパートの名前が『URL』、
アパートの住所が『ドメイン』と考えるとわかりやすいかもしれません。
ドメインの種類

独自ドメインと共有ドメイン
ドメインには、ユーザーが独自に、任意の文字列で取得できる「独自ドメイン」と、ブログサービスなどが提供するドメインを複数ユーザで使用する「共有ドメイン」があります。
Webサイト黎明期はこの共有ドメインが主流で、ジオシティーズなどの無料で使えるスペースにWebサイトを公開していて、当時のWebサイトのドメインは「****.syuriken.jp」「****.jcom.home.ne.jp」のようなものが多かったですね。
✙
現在は企業や商品・サービスのWebサイトにこうした共有ドメインが使用されていることは稀ですが、共有ドメインの場合、母体のサービスがサービスを停止するとそのドメイン・URLでWebサイトが表示できなくなる、SEO対策ができないなどのリスクがあるため、万一自社のサイトが共有ドメインだという場合は、独自ドメインへの切り替えをお勧めします。
「co.jp」「com」「net」などの違いは?
ドメインの末尾を見ると、「.co.jp」「.com」「.net」などなど様々な表記を見かけますが、実はこれにもちゃんと意味があります。
①分野別ドメイン

.comや.netなどの分野別ドメインにはこのように意味が込められており、ドメインを見ただけでもどんな分野のサイトなのかを類推できるようになっています。
②国別ドメイン

.jp以外はあまり見慣れないかもしれませんが、どこの国のサイトなのかを判別できます。(略し方によっては調べないとわかりませんが…)最近は「国」だけではなく「.tokyo」のようなエリア別ドメインも生まれてきています。
③属性型jpドメイン

①のような分野別を示す文字列と、jpドメインを掛け合わせたのが属性型jpドメインです。日本のサイトなのだということと、それがどのような分野のサイトなのかがわかるようになっていますね。ちなみに.co.jpドメインは1法人につき1つしか取得できませんのでご注意ください。
✙
このように、「.com」や「.jp」にも「意味」があるのですから、「.com」の前の文字列も、そのサイトを表現する言葉であることが望ましいですよね。
SEOの面から見ても、認知度の高いブランド名の入ったドメインや、検索キーワードとの関連性が高いドメインは上位表示がされやすくなります。例えば価格ドットコムなどは、ブランド名とドメインが同一で、尚且つ価格を比較するサイトであることから「価格」という検索ワードと相性が良いと考えられるので、ドメイン名はブランド名やサイトの内容としっかり関連づけることが重要です。
ドメイン変更のリスクと対策

さて本題です。このドメインを変更(「移管」とも言います)することには、どのようなリスクやデメリットがあるのでしょうか?
ユーザーに与える影響が大きい
まず一つ目は、ユーザーに対する影響です。これまでサイトに訪れていたユーザーは、ブックマークやお気に入り登録をしています。ドメインが変わればURLも変わるのですから、ブックマークからのアクセスはできなくなります。
前述のアパートの例で考えると、アパートそのものが別の場所に移築されてしまうわけですから、「行ってみたらアパートがない!」という事態。当然混乱しますよね。
旧ドメインと新ドメインを並行して利用できる期間があれば、リダイレクト(特定のURLにアクセスしたユーザを指定のURLに自動で遷移させる仕組み)での対応も可能ですが、ユーザーがブックマークをし直すという手間はかかります。
メールアドレスも変わってしまう場合がある
Webサイト同様、メールアドレスにもドメインがあります。@以降の文字列がメールアドレスにおけるドメイン部分ですが、これは自社サイトのドメインと同じドメインを利用していることが少なくありません。
旧ドメインはメール利用のために残しておく、ということであれば問題ありませんが、破棄してしまう場合は取引先や協力会社など多くの方にメールアドレスの変更を周知し、対応して頂く必要が出てしまいます。
SEOにも影響する
ドメインは実はSEOにも関わっており、その一つがドメインエイジ=ドメインの使用年数です。(厳密にはGoogleなどの検索エンジンに認識されてからの経過年数)
ドメインエイジが長ければSEO上の評価が高くなる、というわけではなく、サイトが長期間にわたって安定的に運営・更新されており、過去にペナルティもないという「実績」が評価を高めると言われています。
既存のサイトのドメインを停止すると、「ドメイン」に紐づいているその「実績」も失われ、SEOにも影響します。
Googleなどからサイトに対してペナルティが発されている、ドメインを変更してサイトを再構築しなければ問題点を改善できない、といった致命的な事態でない限り、ドメインの変更には慎重を期すべきと考えられます。
きちんと対策すれば変更(移管)しても問題ない
「致命的な事態でない限り、ドメインの変更には慎重を期すべき」とお話ししましたが、その「致命的な事態」とはどんな状況でしょうか?
例えば、過去に行ったSEO施策(例:悪質な被リンクを量産した)等により、Googleからサイトに対するペナルティが発せられることがあります。
指摘されているところを改善できればペナルティは解除されますが、対応が困難な場合はドメインの変更を行うことで対策が可能です。
ではどのような対策が必要なのでしょうか。
【具体的な対策例】
・適切なリダイレクト設定を行い、新ドメインのサイトへ遷移させる
・ミラーサイトにならないよう旧サイトの全コンテンツを閉鎖する
・no indexの解除、サイトマップ送信等、移管後のインデックス対応を行う
・Google Analytics、Search Consoleなど解析ツールの設定変更を忘れない
・新サイトの内部リンクが旧サイトのままになっていないかチェックする
・必要な被リンクがある場合は更新を依頼する
・新旧ドメインの移行期間を設け、サイト・メール利用者の混乱を抑える
このように、ただ新たなドメインを取得してサイトデータをお引越しするだけでなく、様々な対策を行えば、ドメインの移管は可能です。
まとめ
さて、ドメインとは何か?何を意味しているのか?どんな役割があるのか?についてお話ししてきました。
今後色々なWebサイトをご覧になるときに、「あっこのサイトは大学のサイトだからac.jpなんだな」など思い出して頂けたら嬉しいです。
と同時に、自社のサイトのドメインはどうなのか?見直していただくきっかけにもなればと思います。
✙
プラスジャムではWebサイト制作の際、ドメインに関するご相談(どんなドメインがいいか、事業領域ごとに別ドメインにしたほうがいいかなど)や独自ドメイン取得のサポートなども承っております。新たにサイトを立ち上げたいがどこから始めたらいいかわからない、などお困りの事業者様は、ぜひお気軽にご相談ください!
✙
プラスジャムはWeb制作会社です。
ウェブサイト制作、システム開発、Webマーケティングなど、さまざまな課題解決やアイデアを具現化するWebソリューションを提案・提供しています。
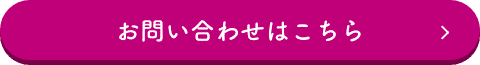
noteでプラスジャムを見つけてくださった方は、お時間あればコーポレートサイトや他の記事もご覧いただければ幸いです。
\コーポレートサイトはこちら/
\関連記事はこちら/
[今回の記事担当] ディレクター 伊藤
2024年入社。総合広告代理店出身のWEBディレクターです。
WEB以外のお話も投稿できたらと思ってます。
