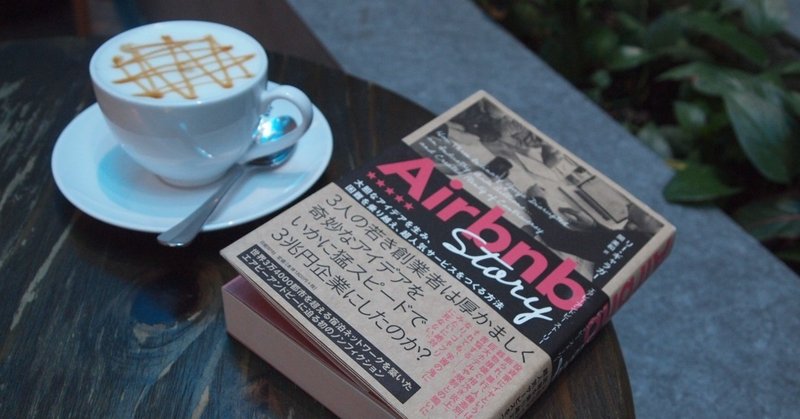
「雑音に惑わされるな」【本:Airbnb Story】
「雑音に惑わされるな」とは、Airbnbの共同創業者兼CEOであるブライアン・チェスキーがウォレン・バフェットにアドバイスを求めた際に言われた言葉だ。
「雑音」とは、私たちの日常に蔓延っているものである。それは、自分で選んでいる環境や情報や人々から影響されるもので、私たちの人生はトレードオフの繰り返しだ。この「雑音に惑わされるな」という言葉の重みと必要性を痛感していて、それがまたAirbnbの世界観を常に前へ推し進めている言葉だと思っている。
この世界に、「この会社は私の生き方そのものです」と言い切れる会社は、どれほどあるのだろう。私自身がAirbnbとの関わりの中で見出した世界観や自分の良さを引き立たせてくれている環境や出会った人々は間違いなく「私の生き方そのもの」だと思っている。そして、きっと世界中に「こんな世界があったのか」と驚きながら、同時に「そうだこれが自分たちが欲しかった世界だ」と、この時代のこの世界を生きている人々がたくさんいる。
「Airbnbとは?」という人々には、インターネットで山ほどある情報を調べてほしい。私にとって、人生そのものになったものに関して、「What is Airbnb?」を答えている時間とエネルギーは無い。
数年前に購入していて、わざわざベトナムまで持ってきた数冊の本の中に、この『Airbnb Story 大胆なアイデアを生み、困難を乗り越え、超人気サービスをつくる方法』がある。350ページにも及ぶ分厚い本。
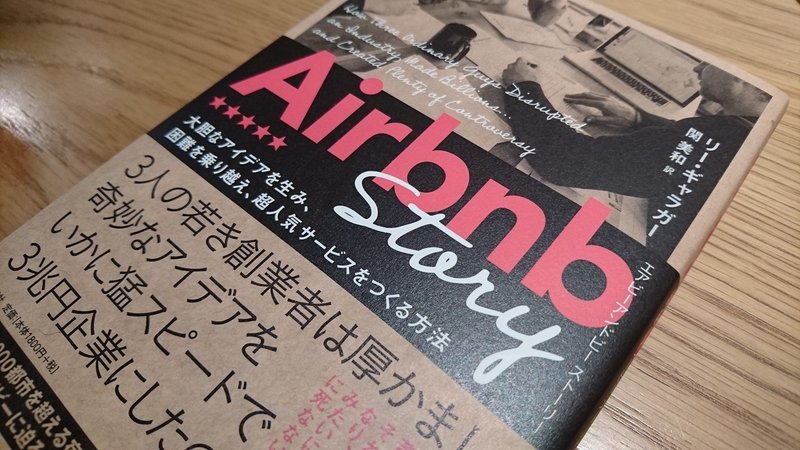
改めて「世界中を居場所にする」という世界を巻き込んだプロジェクトは、壮大なものなのだが、雑音に惑わされそうになりながらも信念に向かって突き進んでいる人々の旅路だし、これからも長く続くプロジェクトになる過程に過ぎないのだ。
本の中にあった「台所の国連」とはうまい言い方で、私自身も本物の国連に憧れたときから、より身近な国連が本当は必要なのではと感じ始めるまで、そしてこれからも、この世界観を共にしたいと思っている。
ちなみに、日本語訳の『超人気サービスをつくる方法』という言い方はあまり好きではない。なぜ、日本語にすると、「サービス」や「方法」という安っぽいビジネスチックな印象になってしまうのだろう。
ーーーーーーーーーーーー以下、本からの引用-------------
・ホームアウェイドットコム、VRBO、カウチサーフィン、ベッド&ブレックファストドットコム
・特にミレニアル世代(1980年代から2000年代初頭に生まれた若者)が手ごろで大胆な新しい旅の方法に惹かれた。地元の人の家に泊まり、同じような感性の仲間と知り合える
・ミレニアル世代:画一的なブランドに不満を持ち、冒険心が旺盛で、デジタルだけの繋がりに慣れている→オンラインでつながった誰かの家に泊まることにそれほど違和感がない
・「世界中を居場所にする」
・Airbnbの体験は、わたしたちが失った何かを埋めてくれる。身の回りのスペースに対するわたしたちの見方を変えた。
・想像力を刺激、赤の他人の親切心の上に成り立つ
・共有経済の大きな特徴は、アイデア自体は目新しくないこと
・バックエンドのインフラはシリコンバレーで最も洗練されている。信頼を強化するためのツール。(相互レビューシステムや身元確認制度)
・創業者にまったく事業経験が無かった
・自身のミッションを保ちながら拡大を続け、その間で繊細なバランスを保つこと。投資家を選び、長期的な目標を共有できる人たちを選んできた。
・子供たちが情熱と趣味を自由に追いかけられるように
・RIDSは「世界を変える」という理想に満ちた、有名な芸術教育の機関。世界中のどんな問題も創造的なデザインで解決できる、と教わる。
・サンフランシスコ:エネルギー、創造性、起業家のオーラ
・使い勝手の良い決済システムの必要性
・最初は何でもタダでシェアできる世界を無邪気に描いていた
・「地元に密着した旅行体験を」
・Yコンビネーターのグレアム:「『なんとなく好きになってくれる』100万人より、『熱烈に愛してくれる』100人」
・最初の頃は、家を一軒一軒訪問してサイトに登録してもらい、ミートアップを組織し、誰にでも近寄って自分たちのサービスを紹介し、アパートを使って小遣い稼ぎができると説明していた
・一番熱心な人間が、誰よりも成功する
・ホストとゲストのコミュ二ティをつくるという哲学。信頼の問題に応えるようなソーシャルな仕組みをデザインしたことも素晴らしい
・原始的なやり方に戻る
・わからないことがあれば、進んでそれを探り、自分のものにした
・3人は、企業文化を真似したい会社のリストをつくった:スターバックス、アップル、ナイキ、ザッポスなど
・強烈な使命と、はっきりした「価値観(コア・バリュー)」。それが企業内部での行動を導き、顧客や株主やその他のステークホルダーとの関係を導く基本的な原則になる。
・グロースハック
・供給確保が難しいビジネス。ホストの側は当然伸ばすのが難しい。
・ネットワーク効果はグローバル:旅行という活動そのものと、それによるグローバルなネッツとワーク効果の産物。効率の良さと成長性(拡大にお金がかからない)
・プロダクト:テクノロジーの世界ではアイデア以外の全てのもの。実際のウェブサイトやアプリ、その外見。仕組み、それを使ってできること。それを動かすエンジニアリング。ユーザーがそれをどう使い、どう接するか。(ユーザー・エクスピリエンス)
・なめらかに動くこと。簡単に使えること。掲載物件が美しく見えること。必ず3クリック以内で予約が完了すること。
・決済システム。顧客サービスプラットフォーム、つまりフロントデスク。そして、その人に最適な物件を目の前に持ってくるのは「検索」システムは当時も今も複雑。(双方向の超個人的な相性の問題)検索とマッチングの技術。
・初期の検索機能はかなり単純で、決まった地域の中で、旅行者数、日程、アメニティなどの基本的な条件に合う中で最良の物件が示されていた。しかし、その後アルゴリズムが進化し、部屋のクオリティ、ホストの行動パターン、予約の好みといった要素も組み入れられるようになった。たとえば、ホストの過去の行動パターンから、数か月先の予約を好むホストか、ぎりぎりの予約でも気にしないホストかがわかる。すると、ぎりぎりに予約をする旅行者と、その手の予約を喜んで受け入れるタイプのホストを結ぶように努める。そうすれば、予約しようとして断られる旅行者が減る。
・最大の挑戦は成長を生み出すことではなく、成長に追いつくこと
・リンクトインの創業者:リード・ホフマン
・イェルプの創業者でAirbnbの初期のエンジェル投資家:ジェレミー・ストップマン
・3人の厚かましさと押しの強さ
・ヨーロッパ市場を早く取り込むべきなのはわかっていた。世界中で利用できなければ、特にヨーロッパで使えないようでは、旅行会社とは呼べない。
(チェスキー:「そんなの、電波のない携帯と同じ。存在意義がない。」)
・アドバイザー:マーク・ザッカーバーグ、アンドリュー・メイソン、ポール・グレアム、リード・ホフマン
・「自分に賭けた」瞬間
・Airbnbの創業者は伝道師で、ウィムドゥの創業者はカネで動く傭兵。たいていは伝道師が勝つ。
・この会社がコミュニティの中に植え付けようとしている価値観を体現するお手本のような存在
・自分の優先順位が昔と逆転していた。自分たちの価値に添って経営すべき。コンセンサスで決定するな。危機の時、コンセンサスで決めると、中途半端な決定になる。
・コミュニケーションのプロが必要。民主党広報のベテランで、イーベイとヤフーで働いていたキム・ルベイは危機、消費者、政府の経験がある
・「(起業は)崖から飛び降りて、落ちながら飛行機を組み立てるようなもの」
・企業からムーブメントへ
・Airbnbの3つの段階:初期のカウチサーフィン的な段階。次はイグルーやお城が話題になった段階。最後はグィネス・パルトロワの段階。すべての人が何かを見つけられるほどプラットフォームが拡充した。
・(画一的なホテルの部屋ではなく)世界にひとつしかないもの
・2014年7月、本社で大きなローンチイベント。新しいブランドを発表し、携帯アプリとウェブサイトのデザインを一新。昔々、都市は村だった。しかし、大量生産と工業化の波が押し寄せるにつれ、人間の感情は「大量生産された個性のない旅の経験」に置き換えられ、その過程で「人はお互いを信頼することをやめてしまった」。Airbnbは、旅行よりはるかに大きななにかを体現している。それはコミュニティと人間関係を象徴する存在であり、その目的は、テクノロジーを使って人々をひとつにすることだ。
・「居場所を求める人間の普遍的な欲求」を満たす場所になる
・いつも目新しく慣れない環境に自分を置くことで「探検者」の気持ちを保っている。「よく知っている場所ほど、いろいろなことに気づかない。」
・ヒップスターノマド:マイケルとデビー・キャンベルの夫妻は4年間、56か国をほぼAirbnbだけで暮らしている。この生活を決断する前に数か月かけてすべて計画し、お金の計算をすると、コストを抑えればシアトルに住むのと同じ費用でAirbnbに「暮らせる」ことがわかった。
・「死ぬまで学びつづけたいし、健康で、好奇心も旺盛です」
・キャンベル夫妻の息子とその家族もまた、1年の休みをとり、ふたりの息子に学校を1年間休学させて、世界中を旅して回ることにした
・「高度に企業化されていた『おもてなし』を、どう人々の手に戻したらいいか?」という挑戦
・相互レビューシステム:見返りをもとにした生態系
・「人としてより良い存在になる」こと
・「なにをしたらいいのか、特別な体験とはなんなのか、誰もわかっていなかった。ゲストもホストも相手が気の狂った殺人者じゃないかと疑っていた」
・「ターゲット層を惹きつけるものならなんでも。私たちの生活もそれでよくなるから。」
・「世界中を居場所にする」実際には、どんな意味なのか?どう測るのか?どうしたら実現できるのか?
・「ウーバーはただの取引。エアビーアンドビーは人との触れ合い」
・広報と危機管理をどう行うか
・ブライアン・チェスキー「現実の人生が、僕らのプロダクト」「僕はより良い世界をつくる手助けをしているつもりだし、そういう世界の中で人間はよくなれると思いたい」
・安全を確保することは大きな挑戦。安全をデザインすること。「信頼性の高いコミュニティ」
・ニューヨーク大学のアルン・スンドララジャン教授「人はいつもトレードオフを選択しているし、共有経済では別のトレードオフを選択しはじめている」
・2011年、ハーバードビジネススクールのマイケル・ルカ准教授「イーベイやアマゾンやプライスラインといった匿名性の高いプラットフォームから、ユーザーの人格がより大きな役割を果たすような、急成長中の共有経済のプラットフォームへの変遷」に興味を持った
・人種差別は私たち全員の問題だ
・無意識の偏見を自覚させるためのホスト研修の実施と、クレーム処理と強化を助ける専門家チームの立ち上げを計画している
・「居場所づくり」の正反対はなにかといえば、差別だろう
・規制緩和、法律、条例違反、脱法ホテル、住宅価格の高騰
・「中流層の味方」Airbnbは観光業を活性化させる。特にこれまで観光客が足を運ばない地域にも、お金が落ちるようになる。これまで観光客の恩恵にあずかれなかった地域の中小企業にも助けになる。
・「人間らしい手づくり感のあるおもてなしをどうやったら拡大できるのか?」ひとつは家主とパートナーシップを築くこと
・「市と協力したければ、その地域を知っておくべきなんだ。そこに自分たちのほうから先に行って、地元の人たちを心から気遣えば、協力関係を築くことができる。」
・ホームアウェイの共同創業者カール・シェパード「このトレンドに乗らないのは『2015年の世界には参加しない』と言っているのと同じ。存在を否定するか、安全に使えるようにするか、どちらかだ。」
・価値が高く、金太郎あめのような観光業界にみんなが飽き飽きしていた。新しい価値観と行動力を持つミレニアル層にとって、ちょっと変わっていて、いいとこどりができて、独特で、本物らしい旅行の形は、ただの楽しみではなく生き方そのものになった。
・「これが世界の向かっている方向だ。受け入れるしかない。」
・「おもてなしに人間らしさを取り戻すこと」は自分らしさを取り戻すこと
・元ホテル業界のトップリーダーのひとりは、はじめはエアビーアンドビーや同種のサイトをまったく脅威だとは思わなかったと言っていた。だが振り返るとその理由がわかる。「40代の自分はそういうものに魅力を感じなっかったから。シーツはどうなんだ?マットレスは?鍵の受け渡しは?ってね。自分が年寄りだから、恐ろしかったんだな」若い世代は自分のような恐れや偏見なしに育ってきた。Airbnbのある世界しか知らない。「デジタルネイティブ」と同じで、彼らは「エアビーネイティブ」だ。若い人たちにとって、チェーンホテルに泊まるのは固定電話で話したり、銀行の支店に行ったり、オンエアの時間にテレビ番組を見たりするのと同じくらい、変なことなのだ。
・「情報源に行くこと」「正しい情報源を見つけられたら、早送りで学習できる」その道のプロに次ぎから次へと教えを乞う。「少なくとも自分より数年先を行っている人を選ぶのがコツ」「人脈があればもちろんいいけれど、本人に潜在的な能力がなければ役に立たない」
・学んだことを共有しなければ気が済まないのもチェスキーの特徴。バフェットと会ったあとに4000字のメールをスタッフに宛てて書くようなことも珍しくない
・チェスキーの原動力は、お金、権力、成功といったものではない。彼の先を読む能力、人間としての存在意義。「ブライアンは自分が信じることを人にやらせる力のあるリーダーだ。」
・「2020年までに、どれだけの多くの人が深く、意義のある、人生を変えるような経験ができるかを目標にしたい」
・Airbnbは「台所の国連」「赤の他人は未来の友達だと子供のころに教わった」
・ニューヨーク・タイムズ紙の有名コラムニスト「悲観主義者はだいたい正しい。だが世界を変えるのは楽観主義者だ。」
・ゲビアの強みは「少人数のチームの中で大胆で枠にはまらないアイデアを生み出すことで大組織の巨大な軍団を管理することではなかった」。前向きでやる気満々のリーダーだと見られていたが、完全主義者として知られ、周囲に怖がれていた。物事がうまくいかないときに素直に打ち明けにくい人物だと思われていた。
・「チームで起きていることを素直かつオープンに話せない雰囲気を僕がつくっていたとしたら、社内のほかの場所も同じようになっているということだ」「自分はアイデアを生み出すことには惹かれるものの、既存アイデアの運用にはあまり向いていない」
・「アイデアを生み出せる安全な場所をつくりたい」
・仲良しカルチャーのせいで対立を避ける雰囲気が生まれる課題
・Airbnbの短所としてよくあがるのは、新人管理職が経験不足で企業文化がすべてのチームに浸透していないという点。会社が大きくなると社員も増え、貧乏だった頃のAirbnbを知る初期の社員(先駆者タイプ)とMBAや大企業に惹かれるタイプが、自分のキャリアを築こうとやってくるようになった。
・文化を浸透させる助けになるのは、規模が大きくなるのに合わせて、社内の透明性をしっかり保つこと
・コアバリュー:おもてなしの心をもつこと、共感を持つこと、自分だけの道をつくり出すこと、伝統を破ること、企業使命をなによりも優先させること
・「誰の声に耳を傾けるか、どう勇気を持つかを決めるのは、結局自分なんだ」
・「親切なおもてなしを愛する初期のユーザーに合う体験を確実に届けるにはどうしたらいいだろう?また同時に、贅沢な体験を求めるユーザーにそれを届けるにはどうしたらいいだろう?また同時に、贅沢な体験を求めるユーザーにそれを届けるにはどうしたらいいだろう?そこが挑戦であり、チャンスでもある。」
・賛否両論を巻き起こすような破壊的なテクノロジー企業はこれまでにも多かった。だが、エアビーアンドビーほど規制当局と衝突し、古い業界から反発にあい、感情的な激しい闘いに巻き込まれた会社は最近ではほかにない。
・だが3人が感傷的になることはほとんどない。「そんな時間がどこにある?」(常に迅速で冷静な判断が必要)
・すべてくぐりぬけて先に進んでいくことが、大胆なアイデアと大きな変革につきものの挑戦なのだ
・アイデアはクレイジーでも、彼ら自身にクレイジーさはない。厚かましいけれど、攻撃的ではない。失敗したらすぐに反省するし、他人の失敗にも寛容だ。自分の弱みを認めて、それを埋めるべくすぐに専門家の助けを借りる柔軟性もある。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
私自身、社内(社員数も社内システムもオフィス数も環境も全て)が圧倒的スピードで変化していくのを体験しており、その度に世界中のメンバーたちの共通認識でもある「圧倒的なコアバリュー」の必然性を痛感していた。そしてAirbnbのメンバーとも共にコミュニティ構築に挑戦してきた。日本でも、サンフランシスコの本社でも、「築きたい世界観」に関しての対話だった。そう、それは「人々の信頼を構築する」というとてもシンプルで複雑なもの。
国が異なっても自分自身がずっと築きたいと思っているのは「物事がうまくいっていないときに、打ち明けられる環境」、つまりAirbnbでいう「居場所」なんだと思う。それは、葛藤や意見の食い違いが起こらない「仲良しグループ」ではないし、良い成果や部分を見せるだけの「美しい」環境でも無い。「物事がうまくいっていないときに、打ち明けられる環境をつくること」は、何も変化が著しいテクノロジー業界だけではなく、また「安全をデザインすること」は、現実社会のどこにいても必要な時代なのだ。

「カオス(無秩序)を楽しめる人。」私が、この企業の人々のキャラを紹介するとすれば、これに限る。そして、自分自身も、きっとこの部類なんだと自覚している。
ちなみに、写真は大好きなベトナムの路面店にて。Bún thịt xàoは、米麺と炒めた豚肉ともやし、ナッツにハーブを添えて。お好みでヌックマム(調味料)とチリを。
創造の場所であるカフェ代のサポートを頂けると嬉しいです! 旅先で出会った料理、カフェ、空間、建築、熱帯植物を紹介していきます。 感性=知識×経験 மிக்க நன்றி
