
日本的価値観と欧米思考の両立を【本:世界へ翔ぶ 国連機関を目指すあなたへ】
全く別の作業を行っていて、数年前に読んだ本のメモが見つかった。実はこの本以外にも100冊以上の本のメモが残っていて、いつか全てをnoteへ移したいものの、なんとか自分のモチベーションと優先順位とのバランスを続けるのみ。
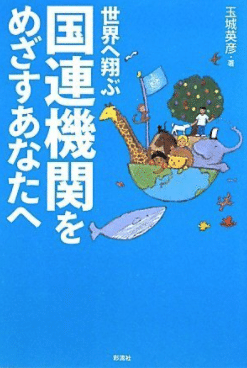
・大学院の教授としてWHOとの共同事業やJICA(国際協力機構)と連携した事業
・公衆衛生、人道支援、紛争解決、感染症、エイズ
・熱帯病(Neglected Tropical Diseases)東南アジア、アフリカ、南米
実行可能かつ持続可能
・WHOなどの国連機関は、おもに国の中央行政機関との堅い信頼関係において業務を進める
・中央省庁と連携し政策や方法、ガイドラインを末端にまで徹底させる
・スイス・ジュネーブ
・国連職員は契約職員
・次の契約に向けて、付加価値を付けた者のみが生き残れる
・役所からの出向
・プロパーとして空きポストに直接応募
・JPO ジュニアプロフェッショナルオフィサー
・AE アソシエイトエキスパート
・YPP 国連職員になるための競争試験
・日本的価値観と欧米思考はプラス:健康で、環境、食、文化などに対する適応力
・10年以上の国内外の専門的な経験&研究論文などがあればベター
・国連では、出身国のことなら何でも知っているとみなされる傾向があるので、知識を持って赴任されることを勧める
・職員の適正と国連における「健康」
・WHOの健康定義「健康とは、完全な肉体的、精神的および社会的福祉の状態であり、単に疫病または病弱の存在しないことではない」
・国連機関は研究機関ではなく行政的な仕事が多いので、研究能力よりは調整・管理能力、そして問題解決能力が有効。専門家よりも、ものごとを俯瞰し組織を動かせる行政能力の高い人が国連機関にはより向いていると思う。
・国連の専門機関へ就職する前にまず専門性を高めること。10年以上の経験は必要。
(欧米の友人たちが、卒業後の進路として普通に考えている発展途上国への旅行やインターン、そして国連機関でのポスト等、そういったのを周りで見てきて、日本だけではその経験は積めないと思った。日本は良くも悪くも、平和すぎて、実験というか貧困そのものの現場にいられる体験ができない為、東南アジアを選んだ)
・学生は、よく国連機関で働きたいという夢を見るが、だいたいは卒業後10年くらいはかかるため、その後状況が変わり、結局別の仕事につくことが多い
国連機関関連の人々や専門家の人々でよく言われているのは「魔の10年」という言葉。当然、人によっては「魔」なのか「過程」なのか捉え方は様々だけれど、とにかく国際機関での職は「不安定」だ。常に競争に晒されている。実現可能性を直視しながら、でも理想を追求し続けたい。
この頃から、ずっと言ってたな。英語、中国語、フランス語、ベトナム語、スペイン語等・・・5か国語は話せるようにしたいと。笑
創造の場所であるカフェ代のサポートを頂けると嬉しいです! 旅先で出会った料理、カフェ、空間、建築、熱帯植物を紹介していきます。 感性=知識×経験 மிக்க நன்றி
