
私が、建築をスキになった本10選
最初は、建築というよりも、欧州の図書館や美術館のデザインが好きで、そもそもデザインとは、なんて語れない自分に、本を読むこと、人と話すこと、実際の建築を見ること、ただその空間にいることの大切さを教えてくれたのは、紛れもなくただ旅行が好きな自分の好奇心だった。

小さな幸せを見つけ、毎日を楽しんで生きている人。
これだけで、人生の十分な功績だと、思いながら。それでも、移動を続ける。
進学よりも旅行をすることにお金をかけ、独学で建築家への道へと進んだ安藤忠雄氏も言うように、旅をすること、本を読むことは何にも代えられない自分の財産だ。そして、そのように旅をして、実際に足を運んで建築を語る人々の言葉は、とても温かくて人間味があった。そして、建築を通して、哲学、宗教、経済、社会、人類、道徳、心理・・・日本の花鳥風月や自然を、世界の人間の真理を、学んでいる気がする。(ずっと現在進行形)
ケルズの書
8世紀に制作された聖書の手写本。アイルランドの国宝になっていて、世界で最も美しい本とされる。アイルランドのダブリンを訪れた際、トリニティカレッジの図書館を訪れ、図書館の荘厳なる風景に圧巻されながら、そこでこのケルズの書と出会った。「建築」とは全く関係ないと言われるかもしれないけれど、デザインや感性といった点から、私自身は多くを学んでいる気がするし、今の自分の物の見方や風景の捉え方に繋がっている。

ミュシャ絵画集
パリの美術商、サミュエル・ビングの店の名前から一般化した美術運動アール・ヌーヴォー。フランス語で「新しい芸術」という意味で、花や植物などを有機的な曲線・モチーフを組み合わせた高い装飾性が特徴。ベル・エポックと呼ばれる、パリがもっとも華やかで繁栄していた時代にアール・ヌーヴォーが生まれ、その中でもひと際有名な芸術家がミュシャ。「スラヴ叙事詩」が有名。日本人藝術家の浅井忠は当時多くのポスターを日本に持ち帰り、ミュシャを紹介し、与謝野晶子の『みだれ髪』、『明星』などの表紙を描いた藤島武二の作品からはミュシャの影響が見られる。チェコのプラハにあるミュシャ美術館。この街は、その全てが美術館ではないか、と思うほど美しかった。

旅。建築の歩き方。
ある時、タイトルが気になって手にとった本。アイルランド作家のジェイムズ・ジョイス『ユリシーズ』ダブリンの街角の話や、「本などで知識や情報として得ているものと、実際に世界で起こっている状況や現象を結びつける。その架け橋となるのが旅。」という言葉。「現在の都市は情報に乗っ取られている」「どこでもいいから、日々の過ごし方に工夫が必要なところに行ってみたらいいんじゃないか」そんな言葉に惹かれて購入。実際にこの本のまとめnoteを書くに至る。

HOTEL INDOCHINA
数年前、ベトナムへ出発する日に成田空港で見つけた本。一瞬、「買おうかな」と思ったけれど、私の荷物の中には既に『地球の歩き方』と数冊のベトナム料理本が入っていて、立ち読みして終わった。・・・けれど、忘れられなさ過ぎて、1年ぶりぐらいに手に入れる。この本をきっかけにインドシナのホテル建築に興味を持ち始めた気がする。


ベトナム建築
https://forbesjapan.com/articles/detail/24542
アマン伝説 創業者エイドリアン・ゼッカとリゾート革命
そして、アマンリゾートとの出会い。ベトナムの南部、カントー市にあるアゼライリゾートとの出会い。東南アジアの南国リゾートの魅力や建築と自然との関わり。竹建築への興味。
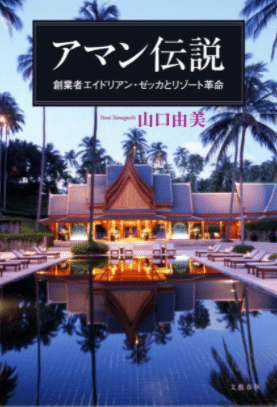
熱帯建築家 ジェフリー・バワの冒険
同時に、スリランカのジェフリー・バワ氏との出会い。熱帯建築家といわれるくらい、自然のなかにつくりだす建築空間。スリランカに興味を持ち、その後ちょうどスリランカの友人と出会う。

「組み立てる文化」の国
建築を学ぶというのは、この本に書かれている、その全ての環境を学ぶことになるのだと、後で知る。日本の建築にも興味を持つきっかけとなった本。
・学問・芸術・思想・文化は知的構築
・建築・機械・都市・文明は物的構築
・西洋文化における思想の正当性は宇宙からの整合性に裏打ちされているが、日本文化における思想の正当性は現実社会の構成原理によってのみ裏付けされているように見える
・石を積み上げて造る組積構法と、木を組み立てて造る軸組構法
・花鳥風月、源氏物語、寝殿造り、仏教建築、数奇屋、万葉仮名、雅、書院造り

Going Green with Vertical Landscapes
ベトナムの建築に興味を持ち、出会った日本の建築家の方々。その中でも、丹羽氏が出版されたこの本は、ドイツ、フランス、シンガポール、メキシコ、スペイン、ラトビア等の壁面緑化のケーススタディーが掲載されていた。壮大なスケールの建築と高層ビルと緑化の技術には驚くものの、やはりその土地の風土に合った緑化建築という点からは、東南アジア、特にインドシナ半島に勝る地域は無いのではないか、と思ってしまった本だった。

LIFE MEETS ART
世界のアーティスト250人の部屋
これもまた建築ではないけれど、世界のアーティストの部屋のデザインというのは、とても興味深いし、その人なりの感性やアートが垣間見れる空間がある。壁の色ひとつとっても、組み合わせも、全体のバランスも、こちらの感性も研ぎ澄まされる感覚。

建築家、走る
隈研吾氏の本は何冊か読んでいて、この本で語られていることと、他の本音で語られていることを頭の中で巡らせながら読み進めた。世界を駆け巡る。現場を大事にする。話し合う。世界の人々と交渉を続ける。「コンクリートに頼ってできた、重くて、エバった感じの建築が大嫌いだ」と一言。建築家の葛藤や本音が語られた。人生そのものが「走る」ことの繰り返しなのかもしれない。

隈研吾氏が以前言っていたが、建築を建てるという行為は「罪」である、ということを自覚する必要があると、なぜならば建築はその土地の社会的、生態的環境をも変えてしまいかねない、特に個人住宅の「罪」は大きいと言っていた。そうだとするならば、その土地の風土に適応した壁面緑化は、少しでも周りの環境を良くしようと、少なくとも人々にそのように訴えかけることができる、手段なのかもしれない。そして、何よりも熱帯気候の優位性(太陽の光、風、水、緑そしてベトナムの強いコミュニティ精神など)を最大限活用した建築は、本当はもっとシンプルで、質素で、人間に優しいのだと思う。
そんなことを考え、対話を繰り返しながら、建築というものは制約でもありながら、創造でもあるなと、その為には、その創造が生きる世界で、やっぱり自分を置くことが大事だな、そんなことを考えた。
創造の場所であるカフェ代のサポートを頂けると嬉しいです! 旅先で出会った料理、カフェ、空間、建築、熱帯植物を紹介していきます。 感性=知識×経験 மிக்க நன்றி
