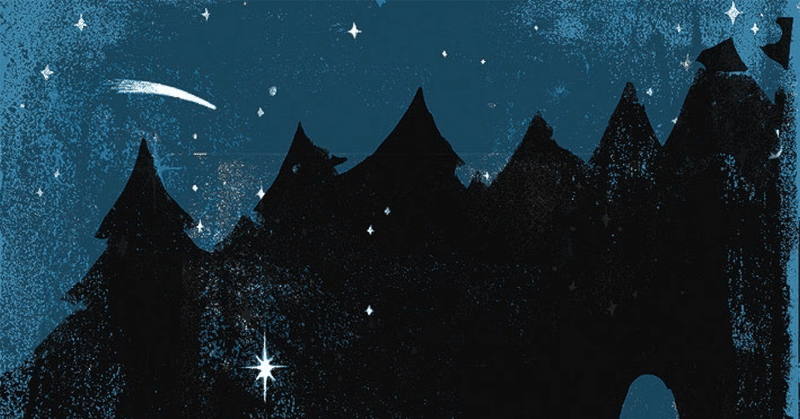
はぐれた星を抱き締めて
流星群がくるらしい。仕事の休憩中に、Twitterで噂を目にした。今晩だったら一緒に見に行けるなと思って、すぐにこっぺ(嫁さん)にラインを送る。
「流星群、今夜だって。いつものとこで見ようか?」
「わぁ、いいね。じゃぁ、サンドイッチでも買ってそこで食べる?」
「いいね。僕はつまみも買ってくよ。」
楽しみができた。今は曇ってるけど、天気予報だと夕方からずっと晴れだ。綺麗に見えるといいなとおもう。幸せな時間を思い浮かべながら、仕事にもどった。
*
二人の住むアパートは僕の母校に近い。山の上にあるその高校は街灯もほとんどなく、星を見るのにちょうどいい。夫婦の定番スポットだった。
22時。予報通り雲は少なく、そこには満天の星空があった。流れ星が見えるかは分からないけど、どっちだっていい。だってこんなに綺麗だから。心がすさんだらここに来ようって毎年思うのに、なんでか忘れちゃうんだよな。そして、また思い出すんだ。
駐車場に座り込んで、買ってきたサンドイッチや唐揚げをつまむ。ついでに黒ラベルをプシュッと開き、一口飲みこむ。
外でやる飲み食いというのは、どうしてこう気持ちがいいんだろう。
隣では、こっぺがアプリを使って流星群の見える方向を調べている。スマホを掲げて夜空を見上げる彼女は、どこかコミカルで可愛い。
「多分あっちに見えるとおもう」
そう言って指をさしてすぐ、ひとつの星が夜空を流れていった。僕たちは互いに「「見えたっ!!」」と叫んで顔を見合わせる。どちらも笑顔だ。この瞬間の、なんてキラキラしたことだろう。
二人は夜のなかにいた。流れ星が見えるたび「あ、きた」「おー」なんて、意味のない言葉を交わしながら。
ただ並んで座っていた。重ね合った手が暖まっては、黒ラベルの缶で冷える。
流星群。そんな言葉は大袈裟で、ポツリポツリと、思い出したように線を描いては消えていく光。
これが「群れ」だとしたら、距離が遠くて寂しいな。
なんとなく、そんな風に思ったりした。
次第に星の流れる感覚は延びていき、そろそろおしまいかなと立ち上がった頃、その星はやってきたんだ。
*
それは、先程までの駆け抜けるように消えるものと違って、ふわりと降ってくるような小さな光だった。不思議におもって眺めていると、どんどんとこちらへ近づいてくる。そしてとうとう、星はグランドへ落ちた。
駆けつけると、広い校庭の隅っこに大きめの穴が空いていた。見れば、その中心には何かが強く光っている。
「おぉ・・・星が降ってきた・・・。でも、えらいちっちゃいね。」
「欠片が降ってきたのかも。」
少しずつ光は弱っていき、やがて落ち着いた。うすぼんやりと発光しているそれは、体育座りをした男の子だった。ビックリするくらい白い肌と、白い髪をしていた。裸だった。
その子供はゆっくりと起き上がった。キョロキョロと不思議そうに周囲をうかがうと、僕たちを見つけ、無邪気な笑顔を浮かべた。まるで迷子が親を見つけたように。
だから、つい連れて帰ってしまった。
田舎の高校の片隅で、保護という名の誘拐が静かにおこなわれた。
*
そして、星の子との奇妙な生活がはじまった。彼は喋ることも声をだすこともしなかったが、表情はちゃんとあった。共に暮らすなかで、発光でも感情表現をしているのがわかった。嬉しいときはピカピカと激しく点滅するし、悲しいときや嫌なときは ピカ・・・ピカ・・・ とゆっくり瞬いた。それを理由にこっぺが「光太郎(ピカタロー)」と命名をしたのには、ちょっとあんまりだと思ったけど。結局僕もそれに慣れてしまったし、なにより本人が嬉しそうだったので、しょうがない。
光太郎は完全に夜型だった。日中はとにかく寝ていて、日が落ちると少しずつ活動をはじめる。その活動というのも、テレビを見たり僕たちのスマホをみたりするだけなのだけど。彼はとにかく、光るものが好きだった。
裸でいられるのも落ち着かないから、昼間、こっぺと子供服を買ったりもした。むず痒いような、喉にひっかかるような、複雑な気持ちが渦をまいていた。家で寝ている子供の服を選ぶデートなど、やれるとは思っていなかったから。でもそれは、確かに喜びだった。
3人でお風呂に入ったりもした。わざと電気を消して、光太郎の発光を楽しむ遊び。
「なんか、ラブホみたいだね。」
「そういうこと言わないの。」
ふたりが笑うと、光太郎もピカピカと点滅した。アパートの狭いお風呂のなかが、映画館のように照らされていた。
*
僕は夜更かしをよくするから、光太郎と過ごす時間はどうしても長くなる。隣に座る彼は、僕がnoteを書くのをみたり、流しっぱなしのアニメをみたりして過ごす。
あの日と同じ体育座りの光太郎。画面に流れる内容によって光る強さや速度がかわって面白い。僕が6本目のストロングゼロを取り出すと、いつも袖を引っ張って悲しそうにゆっくり点滅する。ひとつも声を出していないけど、僕は「うるせーよ」言って笑う。そしてやっぱり缶を開ける、どうしようもない光景。それが日常になりかけていた。
生活を重ねるほど、3人で外へ出たい気持ちが大きくなる。
でも、いくら田舎でも光っている子供は目立つし、警察に問いかけられても答えられることなどなにもない。この子は、誰の子でもないんだ。問題になる未来しか見えなかった。だから、ずっと気持ちに蓋をしてきた。光太郎が笑ってるなら、それでいいかと思っていた。
7本目は飲みすぎだったんだ。アルコールで加速していった欲をとうとう抑えきれなかった。深夜4時。僕は片付けもせずに寝ているこっぺを起こし「3人で散歩しよう!」と大声で言った。あとから聞くと、ものすごい笑顔だったらしい。こんな迷惑な提案に付き合うんだから、彼女も同じ気持ちだったんだろう。
*
外に出ると月がでていた。
誰もいない夜のなかを、3人で手を繋いで歩いた。僕と、光太郎と、こっぺ。防寒具やマスクで露出部分を限りなく減らした光太郎だったけど、少ない部分からしっかり光が漏れていた。ピカピカと激しく、強く点滅しているのがわかった。
僕はどうにも嬉しくって、終わってもないのに「また散歩しよう!」と何度も言っていた。そのたびにこっぺに怒られて、ハッとなって声をひそめた。それを見た光太郎が嬉しそうに笑って、また同じように光が漏れた。梅の花が照らされていた。
酩酊の記憶というのはピースの足りないパズルみたいなもの。だけど、覚えているすべてが変えがたい輝きをみせる。
あの夜の、手元に残った景色のすべてが、キラキラだった。
*
結局、3人で散歩をしたのはあれが最後だった。
僕はあの日以上に深酒をするタイミングがなかったし、光太郎が誘うことは当然のようになかった。こっぺは困った顔をしていたけど、言葉にはしなかった。
1週間ぶりの夜勤前、深夜3時を過ぎた頃だった。シンクには5本の空き缶が並び、いつものように冷蔵庫から新しいストロングゼロを取り出したその時、インターホンが鳴った。
非常識にも程がある時間だ。それなのに、苛立ちではなく不安が体を満たした。
一気に冷えた体をおそるおそる動かして、画面を覗く。そこには綺麗な女の人がいた。白髪で、ほんのり光っている。服は着ていた。
脳味噌からアルコールが1秒で蒸発した。母親だ。迎えに来たんだ。
少しだけ、でもとても長い間をおいて、通話ボタンを押す。伝わるかは分からないが「ちょっとだけ時間をください」と言った。僕の袖を引っ張っていた光太郎は、やっぱり画面を見ていた。
急いでこっぺを起こして、状況を説明する。すぐに察してくれた彼女も、眠気は吹き飛んだ様子だった。そして、あの夜のように3人で並び、扉を開けた。
その瞬間のあの子の表情を、僕は忘れないだろう。校庭で見た、あの笑顔に魔が差した自分が馬鹿馬鹿しくなるほどの、キラキラの笑顔だった。
心が波に飲み込まれる。僕たちは、結局子無しなのだ。仮初の親になれたとしても、この表情、この光は与えられない。
こっぺが涙をすする音で、光太郎が振り向いた。
あぁだめだ、そんな顔をさせてはいけない。彼は光ったり消えそうになったり、バグを起こしたようだった。今まで見たことのない感情の動きだった。
だめだよ、こっぺ。ちゃんとさよならしよう。
そう言おうと思ったけど、だめだった。目からは涙がぼろぼろと零れて、何も言葉にできやしなかった。口を開けば、嗚咽が溢れるだけとわかっていたから。
僕たちは手を繋いで、ただ我慢をしていた。弱さを、脆さを。
親でもないのに、この子に足枷を作ってはいけないなんて、勝手な思い上がりのもとに。
ーその強がりを簡単に崩壊させるのだから、この子もどうしようもないよね。実の親の前で僕たちを抱き寄せるなんて。
*
二人の泣き声や、光太郎の体温、その光の愛おしさ。忘れたほうが楽なのに、まだ、酒でもごまかせずにいる。
目の前の画面の明るさが、苦しい。
僕をサポートすると宝クジがあたります。あと運命の人に会えるし、さらに肌も綺麗になります。ここだけの話、ダイエット効果もあります。 100円で1キロ痩せます。あとは内緒です。
