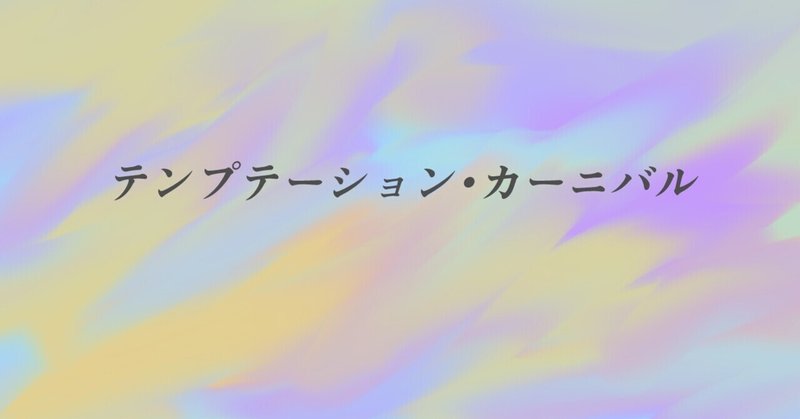
【短編小説】テンプテーション・カーニバル 後編:カーニバル_5
朱莉
子供が初めて寝返りをした時、命はほとんど勝手に、強く生きようとすることに衝撃を受けた。
同時に、なぜ私はそんな前進する力を持っていることを忘れてしまっていたのかを不思議に思った。
子供の成長を間近で見ると、自分が今生きていることの凄さを認識することが出来た。私の手を離れて寝返りをする赤ちゃんは凄い。この気持ちは、過去の赤ちゃんだった頃の私への言葉になった。
子供が成長する隣で、剛にも変化があった。
子供は新しいことを本能的に覚えていく。一方、剛は生活のため、自動車の整備の仕事を覚えていった。自分以外の人のための成長だった。
剛の成長は、出来なかったことが出来るようになるという単純なものではなく、自動車整備士としての強い自覚を持つことで促されるように見えた。近くに同業者が居なかった分、この地域一帯の住民に対する責任を感じていたんだと思う。
ルールを知り、最適な答えを出す。銀行員時代からそういう能力に長けていた剛は、お得意さん達と関わっていく中で、最適と思える答え以外を選べるようになっていた。曰く、深くルールを知ることでその柔軟性を生み出せるらしい。
私自身は、そんな二人の生活を支えることが生きがいになっている。
翌々年には次男が生まれ、慣れて少し乱暴になった子育てにも、新しい命は全く怯むことなく、またもその強さに感動し、繰り返される成長と挫折に追われる日々だった。
昔のことなんて思い出す暇もなく。
葉
俺は教師になるのを辞めた。つまり、俺は俺の人生より充との約束を守ったのだった。
充が凉夏から逃げたいと言ったあの日、終電に乗って凉夏の家につき、その頃には自分でもなんでこんなことをしているのか、よく分からなくなっていた。
とりあえず凉夏の家を観察してみるが、その日は窓の灯りがずっと点いていた。
「なあ、充。俺ってこれ、見てるだけでいいのか?」
朝日が昇ってから、俺は充に連絡をした。
「ああ。見てるだけでいい。ごめんな。環境は整えるから」
その日の夜、光は消えた。多分、寝たんだろうと思い、俺は近くの漫画喫茶に泊まって眠りについた。
しかし、凉夏かいつ起き出すのか分からないせいで、ほとんど眠ることができずに俺は日が昇る頃には凉夏の監視を始めていた。
朝は突き刺さるような冷たい風が吹き、たいして寝てないのに頭は冴えた。
坂道の上から庭を見下ろす。穏やかな景色だ。幸福の形がそのままそこにあるように見える。なのに、その家には、まだ若い女が一人、逃げた旦那を待っている。
家主が目覚めるまで、小鳥たちが我が物顔で庭を占領していた。近くには会社に向かう人が歩いている。当然だが、この街は充のことなんて知らないし、凉夏のことなんて知らない。
その日、凉夏は家を出てくることはなかった。
窓の光が消えてから満喫で短い休息をとり、また冷たい風で目を覚ます。
そして、俺は初めて凉夏を目にした。
穏やかな庭に、大きな白い布を持ってやってきた。何も知らない、無垢な女性がそこにいた。音楽が流れている。それは、充が演奏する少し簡略化された英雄ボロネーズだった。
その純白さになぜか俺は苛立った。
充はあんなに消耗していたのに。これは限りなく嫉妬に近い感情だった。
凉夏がこっちを見た気がした。目があった気がした。笑った気がした。俺はさりげなくその場を去った。少し離れたところから監視を続けた。
それから、毎日おんなじことが繰り返された。機械仕掛けの時計だ。俺もその一部となっていた。
一週間経った頃、俺は充から正式に社員として雇われることになった。充の特許の管理と昆虫の販売の手伝いという形で。
それと同時に週休二日になった。俺以外にもう一人、凉夏の監視で人を雇っていた。俺と同じように大学で知り合った林と言う男で、やけに体が大きかった。一度話したが、とんでもなく口下手な男だ。
驚いたことに、俺はこの男にも嫉妬していた。こんな大切な仕事を俺以外のやつが出来るなんて思わなかった。
そんな不満を持ちつつも、俺は監視を続けた。充との約束だから。
春がやってきた。今までとは全く違う春だ。新しい出会いもなく、別れもない春だった。
俺を取り巻く世界は、充と凉夏だけだ。妙だった。何十年もたったような気もするし、全てがついさっきの出来事のようにも思えた。
けど、それは俺が見ている小さな箱庭の中だけの話だと気がついている。世界はちゃんと動いているのだ。だから、今日の坂の上には見知らぬ人がいて、彼は高校の制服を着ていて、凉夏が庭から出てくるのをさりげなく見つめていた。
小太りで黒縁メガネを掛けていた。涼しいのに髪の毛は汗ばんでいる。どうやら、学年カラーを見るに、高校二年生だった。
彼に声をかける必要が出てきたのは半月ほど経った時だ。凉夏があの高校生の存在に気がついた時だ。
凉夏
充さんは私を大切にしてくれました。私も充さんを大切にしました。お互いが共通の悲しみを背負うことで私たちはよりお互いを思いやることが出来たんだと思います。
新しい子供を作る、という選択肢はあったのですが、充さんの性機能は停止していました。精神的なものが理由。つまり、彼も私と同じように、環境の変化によるストレスで機能が失われているのでした。
それでも、私は充さんと一緒にいられるだけで、それで良いと思いました。少し寂しい気分もありますけど、良いと思いました。
しかし、私たちは二人きりの世界にいるべきではなかったのかもしれません。そう思います。最悪の形で歯車が噛み合ってしまったのです。
元々、私自身に備わっていた無垢な感じ。それはいまだに失われることはありませんでした。そして、打算的に甘える行為も私の中では既に当然のことになっていました。私が持つ二つの才能のせいで、充さんが見る私と、私が知る私は解離していきました。
打算的な甘え。それは私が得意なことであり、才能でした。先天的に備わったものだと私は思っていたのですが、この頃になると、少し考え方が変わっていました。
好きこそ物の上手なれ。つまり、そう言うことなのです。この打算的な甘えには、私にとっての快楽があるのです。
人を騙し、私のためになってもらう。それが私の快楽だったのです。
私は、私の無垢な感じをなくしてしまうようなヘマはしません。そのためにはひたすら待つことが重要です。知性で目的を成すのではなく、偶然の巡り合わせを掴むんです。
充さんが子猫を拾ってきました。あれはお腹の中の子供がなくなってすぐのこと。結婚してから一ヶ月経った頃です。十月で、外は寒くなり始めていました。
捨て猫だったようです。その子猫を見る充さんは普段しない表情をしていました。なんというのでしょうか。もし、子供が生まれていたら、こんな表情で自分の子供を見つめたのかもしれません。
私も同じようにその子猫を見ました。とても怯えているようでした。とりあえず少しだけ温めたミルクを哺乳瓶であげて、それを飲む様子をじっと見ていました。果たして、子猫は、なんの意味があるのか分からない動作を繰り返しています。
小さな命は、決して一人では生きていけません。何をするにも、大人の助けが必要なのです。完全に私に依存している存在。その存在が私にとってとても心地が良いものでした。それは私が生きる理由になるような気さえしました。
子猫には、ミツコという名前をつけました。これは、充さんの名前をもじったものです。
ミツコは二週間ほどで活発に動き回るようになりました。カリカリとキャットフードを食べます。猫じゃらしで遊べば、怖いくらい喜びます。
そして、その時は訪れました。珍しく、充さんが昆虫を育てている部屋のドアを閉め忘れたのです。いや、もしかすると、私がわざと開けておいたのを充さんが閉め忘れたということにしてしまっているのかもしれません。それは、既に思い出せないのです。
ミツコは、その怖いくらいの活発さで充さんの昆虫をいくつか狩りました。トイレから戻ってきた充さんは、とても怖い顔をしました。
しかし、充さんは巧みに自分の感情をコントロールしたのでしょう。口を開けたときにはいつも通りの優しい表情になっていました。しかし、言葉はいつもよりも怒っています。
怒りの矛先は、当然、ミツコのはずなのですが、ミツコはまだ子猫で、つまり監督責任として、私が怒られたのです。本当に、わずかにですが、それは初めてのことでした。
私は傷つきませんでした。そして気がつきました。チャンスが降ってきた。そう思ったのです。
その日の深夜、私はミツコが呼吸出来ないように濡れた布で口と鼻を封して殺しました。庭に埋めました。
鳥居ぴぴき 1994年5月17日生まれ 思いつきで、文章書いてます。
