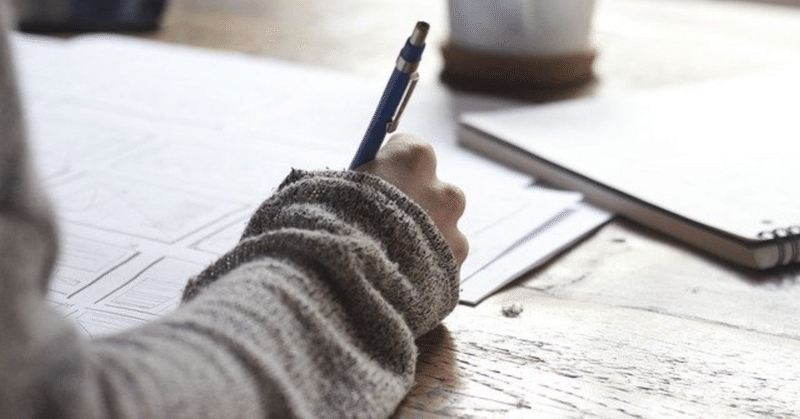
教員の兼業・副業
働くことについて今考えていることを記します。
何書いてたんだか、と後に感じて自己更新していけるように。
結論は、教員の兼業・副業を促進するべきで、自分も取り組みたい、ということです。
上越市について
私の生活する新潟県上越市は県下3番目の人口(約18.5万人)を擁する地方都市です。平成の合併で周辺の13町村と合併したこともあり、海あり山あり、宅地あり中山間地域ありのバラエティに富んだまちです。
全国的な潮流に乗り、少子高齢化が進んでいます。
年齢別で見ると団塊の世代の75歳前後が最も人口の多い部分になっています。(年齢別人口集計表, 上越市, 2023, https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/shiminka/jinko.html)
そして、18歳になるあたりで人口流出があることも見て取れます。
進学や就職で上越を離れる人が流入数より多いということでしょう。
今後の地元の未来を考えると、若い力が地域を盛り立てていくことが不可欠です。(もちろん私たちも頑張りますが。もう若者ではないのか…。)
子どもたちは
中学に勤めていて、子どもたちによく聞きました。
「将来どこに住もうと思っている?」
返ってくる言葉の過半数は地元に残ることにこだわらないというものでした。
その理由を聞くと大抵次の2パターンでした。
①地元には何もないから
②働く場所が地元にないから
①地元には何もないから
地元には首都圏のような魅力的な商業施設がない、アミューズメント施設がない、そういった意味合いで「何もない」と言う人が多いのだろうと感じます。
ECサイトでワンクリックした商品が翌日に届いたり、数百キロ離れた音楽イベントが自宅で視聴できたりしても、キラキラしたまちに憧憬を覚える人は多いようです。
まあ確かに、その点では劣ります。しかし、地元から出て行って失うものに対してはあまりに無自覚です。それは、地元の仲間とのリアルな繋がりです。
この辺りを十分に伝えきれない教育しかできていないことに歯痒さを覚えます。
いくらいいサービスや商品があってもそれを共有できる人がいてこそという感覚は、まちを出ていくまでの社会で子どもたちが経験していくべきことだと思います。
大半の子どもたちは現状、学校で過ごす時間が長いので学校でこれらを感じられるかどうかは大きな点かと考えています。そして地元に残ることの利点を感情ではなく理論的に伝える必要もあるでしょう。
②働く場所が地元にないから
大学や専門学校等進学を期に上京した若者が戻ってこない理由によく挙げるのがこれです。地元に雇用先がない。大都市には絶対的に雇用先が多いです。地方都市は、人口減少している限り、労働人口も減少するし、雇用先も減るばかりでしょう。こうなると止まりません。
テレワークが浸透し始め、コワーキングスペースもできましたが、主たる勤務形態は現状、対面が多いでしょう。
地方都市には雇用先の創出が必要でしょう。
さらに言えば、新たな雇用先を創出するような人材を学校教育の中で見出し(育てるというのも烏滸がましい気がします)、雇用する側を増やしていくことも求められるはずです。
なぜ教員の兼業・副業か
ビジネスを知らない人間の素人考えかもしれませんがご容赦ください。
職を賭して起業するとなるとかなりのリスクを抱えます。世帯持ちであれば尚更です。
その点で言うと、子どもたちは、家族と共に過ごしている限りは衣食住が担保されている割合が高く、社会人になってからよりも相対的にリスクが低いと考えることもできるでしょう。
もちろん、全員がやるべきことではないとは思いますが、もっとビジネスにトライする中高生が出てきていいと思うのです。
そして、それが未来の地方の雇用を支える一つの形になると考えています。
その考えに立ったとき、公務員として勤めているだけの教員がこのことを説いても一切子どもには説得力をもたないと思います。
「え、だって、先生は公務員だし自分でやってないじゃん」
もちろん外部講師として起業家や経営者を招聘することも考えられますが、最も長い時間近くにいる大人の教師が、そういったチャレンジをしているのは一つのロールモデルになると思うのです。
スケールが大きくなっていきましたが、教師の兼業・副業が子どもたち、ひいては地方都市の未来に影響をしていくものと私は考えています。
ちなみに教育公務員特例法で、教員の兼業・副業は許可されている形になっています。ここについての理解も広まっていくと良いと考えます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
