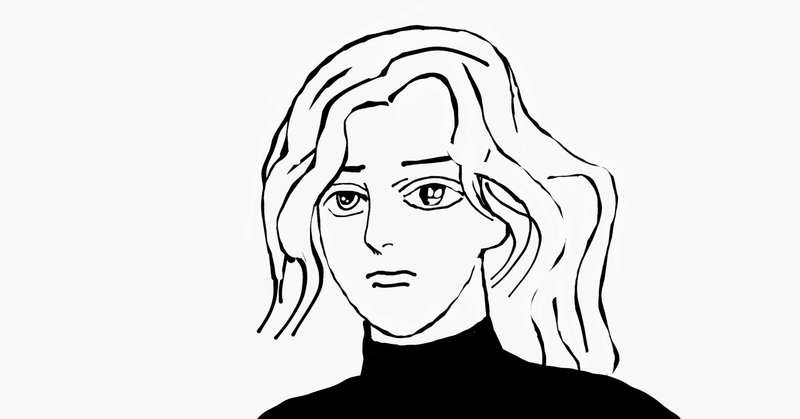
人生という名の鉱脈探し
鉱脈というのは、実際に掘ってみないと分からない。
もちろん、「ここらへんに豊富なお宝が埋まっている」という信念をもって掘り始めるのだが、何年掘っても何も出てくる気配さえなければ、その信念は揺らぐ。
10年掘って何も出て来なければ、あきらめて別のところを探したほうがよいというのが常識的な判断だろう。
しかし、他人から「別のところを探したら?」と言われても、なかなかその場から動けない者も多い。
「その場から動けない者」には、大別すると次の2つのタイプがある。
ひとつは、「絶対にここにお宝が埋まっている!」という固い信念を持っていて、その信念が信仰の域にまで達しているタイプ。宝が出て来ようが、出て来なかろうが、一生掘りつづけるだろう。
もうひとつは、他人に言われるまでもなく、この場所には宝物など何もないと、心の底では解っているが、これまでに費やした月日を思うと諦めきれずに同じ場所を掘りつづけるタイプ。掘りつづけるほど、なおさら撤退することが難しくなる。
人生というのは「鉱脈探し」に似ている。
掘りたいと思った場所を掘って、あっけなく鉱脈を見つける人。
ここには鉱脈はないと見切りを付けて、新たな鉱脈を探しに行く人。
そもそも新たな鉱脈を探すのではなく、既存の鉱脈を他人と共に掘る人。
なにかお宝を見つけた人を成功者と呼び、見つけられなかった人を敗北者と呼ぶ。偶然というものに大きく左右されるにもかかわらず。
成功者には、すべて自分の努力の成果だと思い込む傲慢さがある。
敗北者には、すべて自分の才能がなかった結果だと思い込む卑屈さがある。
成功者は「努力」を強調して、「運の良さ」を忘れている。
敗北者は「運の悪さ」を強調して、「努力不足」には触れたがらない。
どっちもどっちである。
どちらの道を歩むにしても、永続する鉱脈などはない。いずれは枯渇する。成功といっても、せいぜい生きている間の話。失敗といっても、せいぜい生きている間の話。いずれにしても、人生の最後に待っているのは「死」のみである。
どうせ死んでしまうという事実は、人間にとって、残酷な運命かもしれないが、最終的には、すべての人を平等にする。
一生懸命に生きても、不真面目に生きても、結果は同じ。死後の名声を気にしたって、自分が死んだあとには、世界そのものが無になる。
死んだ後も世界がつづくと思うのは、錯覚である。他人の死後も続いている世界を見て、自分の死後も世界はつづくであろうと類推しているに過ぎない。
他人の死と自分自身の死との間には、相容れない大きな溝がある。
そう思うと、どこかホッと一安心できる気持ちにもなる。結局、みんな同じじゃないかと。
死というものの意味を深く考えることなく、carpe diem (「今を楽しめ!」)という言葉を呪文のように唱えて生きている者は、自らの死という大問題を隠蔽して生きている。パスカルの言うように、死という崖の前に遮蔽物を置き、全力で崖に向かって疾走しながら、いずれ崖の下に落ちていくことを忘れるために。
人生なんて、気晴らしに見るせいぜい100年にも満たないドラマのようなものだ。満足できればそれも良し。不満足でも徒労の意味くらいは知ることができる。それ以上の意味なんてあるのだろうか?

#エッセイ #鉱脈探し
#妄想哲学者 #哲学 #note
#成功 #失敗 #山根あきら
#人生 #妄想哲学
#創作大賞2023
記事を読んで頂き、ありがとうございます。お気持ちにお応えられるように、つとめて参ります。今後ともよろしくお願いいたします
