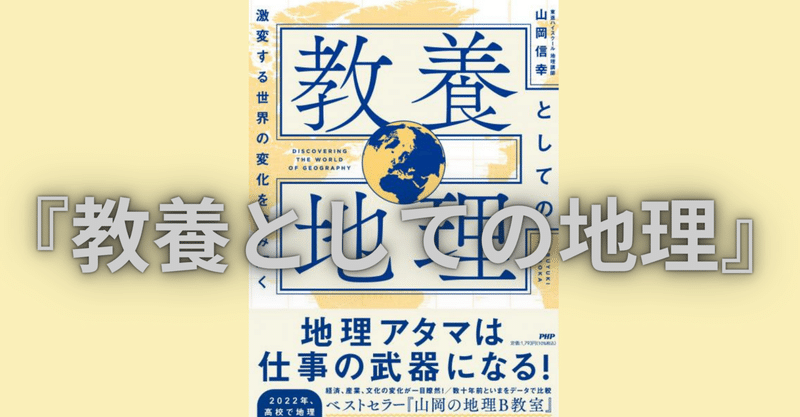
『教養としての地理』誕生秘話
6月19日に発売された山岡信幸著『教養としての地理』。「地理的思考で概観すると、世界の今とこれからが読み解ける」と評判で、即重版に。担当編集者が発刊経緯を語ります。
このところビジネスパーソンの関心の高い「大人の教養」と旬のテーマを合体して、何か本をつくりたいと前々から思っていました。そんなとき、弊社の営業責任者から「友人で面白い著者がいるんだけど、会ってみない?」と声をかけてもらったのが、最初のきっかけでした。
著者の山岡信幸先生にも、「過去数十年と現在とでは地理のデータが異なってきているので、それらをまとめる本をつくりたい」とおっしゃっていただきました。そこから、少しずつ原稿を上げてもらい、でき上がったのが本書です。
2022年度から、高校で地理が必修化されます。
大学入試センター試験に代わって、2021年度から始まった「共通テスト」の地理では、かつて「名物地理」と揶揄(やゆ)された、特産物や地名を羅列して暗記させるような内容は完全に姿を消しました。
そしていまでは、基本的な知識を活用して問題中に与えられたデータをどう読み取るか、といった設問が並んでいます。ご年配の読者には、「これが地理か」と隔世の感を与えるような問題も含まれます。これは大袈裟(おおげさ)ではなく、地理の「理=ことわり(ものの道理)」の部分が重視されているからです。
考えてみれば、山脈名や都市名、用語の意味、統計データなどは知らなくても、忘れていても、インターネットで検索すればすぐに出てきます。それらの知識や情報を組み合わせ、結びつけ、考察する能力を育てることに重心が移ってきたのは、当然のことだともいえます。
交通機関や情報通信技術の発達によって変化のスピードが加速する現代は、COVID-19(新型コロナウイルス)のような感染症、アメリカ合衆国と中国という2大国による熾烈(しれつ)な主導権争い、SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)に掲げられた「貧困をなくす」「ジェンダー平等」「安全な水とトイレ」「気候変動への具体的対策」といった17の到達目標をはじめとするグローバルな課題から、世界中の誰も逃れられない時代になりました。過去から誠実に学び、現在を的確に捉え、未来をソウゾウ(想像/創造)するために、「地理」という視点はきっとみなさんの役に立つはずです。
地形や気候のメカニズム、国際ニュースの背景、産業の盛衰、民族と文化のバラエティ……これらを探り、知る面白さや楽しさは、海外への出張や旅行、国際取引や人的交流など、社会人としての経験を重ねたからこそ、深く理解できるものかもしれません。
本書では、東進ハイスクールで30年以上地理講師として活躍し、地理を学んだ読者ならほぼ目にしたことのある『山岡の地理B』の著者が、最新の世界情勢、地理の話題を、多くの図版を用いながらやさしくお伝えする一冊です。
第一制作部人生教養課 木南勇二

