
サーチファンドにとって良い企業とは(その2)_サーチファンド活動日誌⑦
はじめに
2021年5月に脱サラして事業承継先の探索活動(以下、サーチ活動)をはじめました。この連載では「サーチファンドって何?」という方や、これから始めようと検討している方向けに、サーチャーの実際の活動について分かりやすくお届けしたいと思います。
企業戦略のチェックサイクル5つ
事業承継候補リスト(ショートリスト)にある企業から1つ1つを検討していって1社に絞るプロセスです。

ここで使うフレームは元ミスミ社長の三枝匡さんの著作「経営パワーの危機」に出てくる企業のチェック・サイクル(市場→戦略→組織→損益→資金)です。先回では市場→戦略→組織の3つをみてみました。今回で残りの損益→資金をみてみます。

チェックポイント④:損益
5つの中で最も定量的な情報が取れるはずのところです、もちろん信頼できる財務諸表がしっかり開示頂ければ、ですが。
アクセラレータからのサポートを受けているサーチャーの場合、時に㈱サーチファンド・ジャパンのような事業承継の候補先をある程度紹介して貰えるのようなケースは、こうした財務情報にアクセスできるスピードが伝統的なサーチファンドと決定的に異なります。
では具体的にどんな損益(≒売上と利益率)の企業をサーチ対象とするのかですが、サーチャーによってかなりバラバラな印象です。私が知る日本や海外のサーチャーには限りがありますので、ここではダイヤモンド・ハーバード・ビジネス・レビュー誌2018年5月号の「買収型起業に成功する法」から抜粋してみます。
調査の第一歩は、買収先候補を集めてふるいにかけることだ。ターゲットとして推奨したいのは年間500万〜1500万ドル(5.5億円~16.5億円)を売り上げ、75万〜300万ドル(8250万円~3.3億円)のキャッシュフローを生み出している企業である。 ※1㌦=110円換算
これをみると売上の下限が5.5億円、キャッシュフローの下限(ここではEBITDAとします)が8250万円(マージン15%)、ということになりますが、これら米国中心のケースは日本と比較するとやや規模が大きいように思いますが、およその売上・損益レベルはご理解いただけると思います。
EBITAマージン15%というのは中々の高い収益レベルですが、この点は後で詳述します。
先回の投稿とも重複しますが、私が気になるのは粗利率(売上総利益率)です。製造業なら30~40%、卸売業なら20~30%、外食なら60~70%が相場です。競合企業より相対的に高い粗利率の場合、それは商品・サービス自体に競争力があることを意味し、逆に低い場合は劣っている可能性が高いと解釈します。
現状のPL構造はオーナー企業特有の「色」のようなものがあります。例えば商品販売リスクに備えた保険料の支払額が相場と比較して異様に高いケースはよくあります。業者の言い値で契約してから長年変更をしていないために高いままになっている、あるいは懇意にしている業者との契約だからオーナーが放置している場合です。同じようなケースとして、懇意にしているコンサルタントに毎月支払っているフィーが結構高いとか、
更には、会社の土地建物がオーナー個人の所有物になっていて、会社が高い賃料を払い続けているケースも「あるある」です。会社は収益トントンなのに、オーナーに支払う家賃は長年高いままというケース。オーナー個人の財布と会社の財布が密接につながったこうした関係性は、サラリーパーソンである私の理解を超える状況にもときおり出くわします。
いわゆるこうした余分な(?)コスト、承継後には健全性を確保するために抑えるべきコストを差し引いて残った利益を、調整後営業利益(or 調整後EBITDA)と呼んでそれを企業の実力値として判断することが多いです。
で、この損益分析のチェックポイントは挙げるとキリがなく、また実際のところ私自身がすべてを把握していません。㈱サーチファンド・ジャパンのメンバーのアドバイスを仰ぐことが最も多いのがこの損益分析のステップです。

チェックポイント⑤:資金
最後にみるのが現預金です。企業再生ではここを一番最初にチェックするのが通例ですが、事業承継の場合、資金繰りが苦しい企業は検討リストから事前に除かれていることが多いのが実情です。
つまり、予めネガティブチェックを済ませており、そこを潜り抜けてきた企業のみを検討の俎上にあげるということです。例えば過剰債務の企業、つまり長期借入金がキャッシュフローに比べて不釣り合いに大きいとか、あるいは事業が20年とか30年と長く続いている割には利益剰余金が小さく、DEレシオが大きい企業などは、承継後の経営のリスクを鑑みて事前に除外する可能性が高いのです。
ここまで、最初のショートリストの絞り込みプロセスをどのような考え方や順番で行っていくのかを概観しました。実際にはこの5つのチェックポイントは行ったり来たり、一度はリストから除外した企業さんをもう一度検討したりすることも多く、この流れの順番通りに作業を行う訳では必ずしもないのですが、およその様子はお伝えできたかと思います。
ハーバードが考える「サーチファンドにとって良い企業」~恒久的な黒字企業~
これまで日本でサーチ活動を進める私のケースをご覧いただきましたが、ここからは、ハーバード・ビジネススクール(HBS)のサーチファンド講座の教授陣が書いた「HBR Guide to Buying a Small Business」という書籍を参照したいと思います。
上述したHBR論文「買収型起業に成功する法」と同じ2人の著者が書いた本で(この論文は「HBR Guide to Buying a Small Business」の要約版です)、主に米国を想定して書かれているのですが、日本で活動する私たちにも示唆が多いです。
詳しくみるのは同著の第10章 Enduringly Profitable Small Businesses(恒久的に黒字を出す中小企業) です。
著者のリチャード・ルバックとロイス ・ヨドコフは、"Enduringly Profitable Small Businesses(恒久的に黒字を出す中小企業)"こそ、サーチファンドが対象とすべき企業だと述べています。
このワードには3つの要素が含まれています。1つ目はsmallビジネスであることですが、Small and Mediumはサーチファンドの規模やサーチャーの属性(経営未経験)から考えると当然です。2つ目のProfitable(収益が出ていること)も言わずもがなでしょう。
大事なのは3つ目Enduringly(恒久的)であること。つまり、ちょっとやそっとのことでは赤字にならない強固な仕組みを備えている企業ということです。同書は恒久的に黒字を出し続ける企業は4つの条件を備えていると言います。

条件①スイッチングコストが高い企業
日本でもよく言われることですが、お客様が離反しにくい企業は収益が安定しています。
同書内ではその具体例として、披露宴などのパーティで使われる機材一式(テーブルや椅子のような大物から、皿・グラスといった割れ物まで)のレンタルを請け負うBe Our Guest(BOG)という名前の企業が取り上げらています(実在する企業のようです)。
一見すると、これらのレンタル商材はありふれたものばかりでBOG社には特に強みといったものは無さそうに見えるのですが、実はそうではないと言うのです。
あるイベント会社に「大事な1人娘のために披露宴を催して欲しい」という母親からの依頼が来ます。結婚披露宴の企画を請け負うこのイベント会社は、長年の付き合いでBOG社から機材一式をレンタルしてきましたが、今回は安いと評判の別業者に切り替えようと考えます。
切り替え準備を進めていざ発注しようとしたとき、ふと不安がよぎります。
いきなり仕入先を切り替えて、もし披露宴で何か問題が起きたらどうしよう。必要な機材が予定通りに来なかったとしたら、料金はどうなるのだろう? もしものことがあった時、被害にあった母親は、周囲の友人・知人らに「サイテーのイベント会社に娘の披露宴を台無しにされたわ!!」と触れて回るだろう。そんなことにでもなったら当社への打撃ははかりしれない。(前掲書より抜粋して意訳)
このイベント会社はそう考えた末に切り替え発注を思いとどまり、これまで通りBOG社から機材一式をレンタルすることにしたとのことです。
仕入原価(=BOG社に払うレンタル料)を抑えて一時的に利益率が良化しても、最初の取引でトラブればそれを遥かに上回る損失を被ることになる。つまり見た目以上にスイッチングコストが高かったということです。
このように、一見ありふれた商材・サービスでも時と場合によっては「かけがえない存在」に変貌するケースは少なくありません。
販売している商品・サービスだけをみて判断せず、取引の状況や立地、売り手と買い手との力関係をよく吟味し、見えにくいスイッチングコストの高さを正しく見積もることは日本のサーチファンドでも必要なスキルだと思います。

条件②:ガリバー不在の市場にいる企業
特に補足は不要にも思えますが、巨大な競合(ガリバー)とはどの程度の大きさの企業のことなのかについては考察が必要です。
サーチファンドが対象とする企業は業界の3位とか4位(あるいはもっと下位)で、市場内シェアも1%あるかないかくらいの企業であることも多いです。シェア1%の小さな企業からすると、例えばトップ企業がシェア5%だったとしても規模的には5倍の差、大人と赤ちゃんほどの違いがあります。
しかし、実際はシェア5%では圧倒的シェアNo.1とは言えません。ではどの程度のシェアが「ガリバー」なのか。私が参考にしているのはランチェスター戦略において、競争戦略を実行するうえでの目標や目安となる「3大目標数値」の内の2つです。(注1)
■シェア41.7%(相対的安定値): 3社以上の市場では圧倒的に優位な地位が確保でき、安定した事業を展開できる
■シェア26.1%(下限目標値): 競争から一歩抜け出した強者と認知され、一般に業界トップないし市場に影響力を有する地位を確立できる
この考え方から敷衍して、ざっくり25%がガリバーの下限とみます。これは下位プレーヤーよりも優位なポジションですが、しかし圧倒的ではない。
これが30%を超えると更にその力が強くなり、40%を超えれば完全にガリバーの誕生。業界の販売価格を事実上コントロールし、最安値で仕入れ、競争上のルールを自社優位に決めることが出来ます。
シェア40%を超えるガリバーと同じ土俵に立つ下位プレーヤーは、No.1プレーヤーの都合にモロに振り回されるばかりで、"投資前の段階で" 成長戦略を描くことはかなり難しいと言えます。
私の判断基準は、市場の1位プレーヤーがいて、そのシェアが25%までならOK、30%は黄色信号(慎重に判断)、40%は止めた方が良い、といったものです。もちろん投資先自身がガリバー企業であれば話は別ですが。
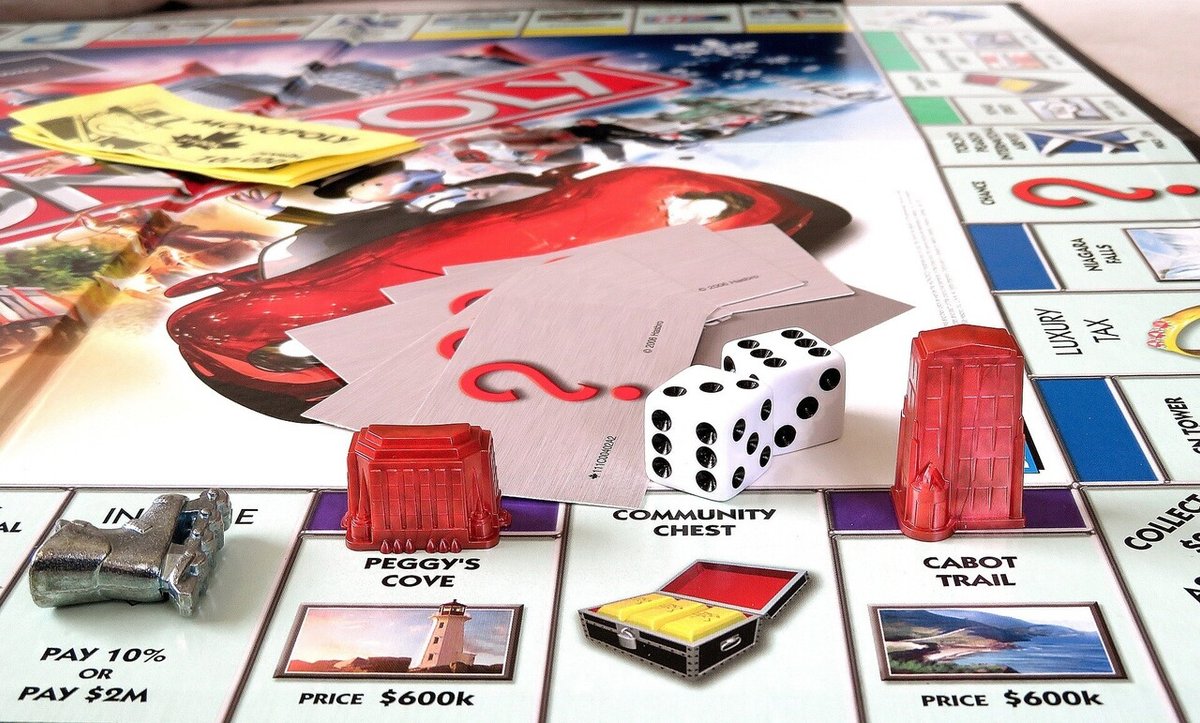
条件③:顧客にとっては "重要でない" 企業
妙な表現ですが、これは条件①スイッチングコストの高さの補足的条件と言えます。
仮に顧客の高いスイッチングコストに守られた企業だとしても、その顧客との取引高の金額自体が大きければ(顧客の原価・経費に占める構成比が高ければ)、離反は起きずとも早晩値下げ要求が来る可能性が残ります。
たとえ代替のきかない存在でも、図体が大き過ぎればコストダウン要求の目玉にされやすくなるということです(コストダウンとは、基本的に金額が大きい勘定科目や取引先から順番にやり玉に挙げます)。
逆に言えば、取引額が小さいほどやり玉に挙がりにくい、すなわち取引の継続性が高まることを意味します。顧客にとってはスイッチ(離反)を検討するほどの存在でもないということです。
条件④:顧客のオペレーションに "スペックイン" している企業
スペックインとは、私の前職㈱ミスミでよくつかわれていた和製英語です。HBSの資料ではこのワードを使ってはいないのですが、その意図を汲んだ私なりの表現です。
ミスミというのは、製造業者が製品をつくる際に使う部品を販売している会社です。顧客は最初からミスミ品を想定して製品図面をひきます。これが日々の当たり前の慣習となっており、私もミスミ時代に営業マンとしてお邪魔すると、製品設計者のデスクに分厚いミスミのカタログが当たり前のように置かれている光景を何度も目にしました。
つまり顧客現場の日常使い品になる訳ですから簡単には離反が起きません。仮にミスミが、③で言う取引額の大きな(憎々しい)相手だったとしても、縁を切れば困るのは顧客自身。ミスミの収益が安定していることは容易にご理解頂けるでしょう。
以上、HBSが考えるサーチファンドにとっての優良企業をみてみました。①~④すべての条件が当てはまる候補企業はなかなか見つからないでしょうが、「良い企業とは何か?」を考える上で示唆の多い分析だと思います。
まとめ
■チェックポイント④⑤:損益:狙う損益レベルはサーチャーによってバラバラ、HBSのエッセイでは売上:5.5億円~16.5億円、EBITDA:8250万円~3.3億円が目安とされている、資金については企業再生のようなケースを除いて大きな問題になることはまれ
■HBSの定義ではサーチファンドには恒久的な黒字企業=赤字転落の可能性が低い強固な仕組みを備えた企業が良いとされ、その条件は、条件①スイッチングコストが高い、条件②:ガリバー不在の市場にいる、条件③:顧客にとっては "重要でない"業、条件④:顧客のオペレーションに "スペックイン" している、という4つとされる
サーチ活動日誌目次
①サーチファンドとは何か
②いまの日本にサーチファンドが必要な理由
③私がサーチャーに挑戦するまでの経緯
④アクセラレータからの支援が仮決定する
⑤自分にあった業界を探す?
⑥サーチファンドにとって良い企業とは?(その1)
⑦サーチファンドにとって良い企業とは?(その2)
⑧事業仮説を練る
⑨オーナー社長と面談・交渉する
⑩市場分析/データ分析
⑪意向表明書を提出する
⑫デューデリジェンスを行う
⑬買収価額を算定する
⑭最後の交渉~譲渡契約締結
⑮経営に参画する~Day1を迎えるまで~
※目次は今後変更の可能性があります**************************************************
注1:ランチェスター戦略はコロンビア大学教授のバーナード・O・クープマンによって考案された文字通り戦争のための理論で、日本では1960年代に田岡信夫と斧田太公望がこれを企業の競争戦略に当てはめ、市場シェアの目標数値として導出した。その中で「26.1%」は下限目標値と呼ばれ、競争から一歩抜け出した強者になるハードルで、業界トップないし市場に影響力を有する地位を確立できるとされている
#サーチファンド #事業承継 #経営承継 #M &A #後継者不足 #searchfund #entrepreneurshipthroughacquisition #ETA
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
