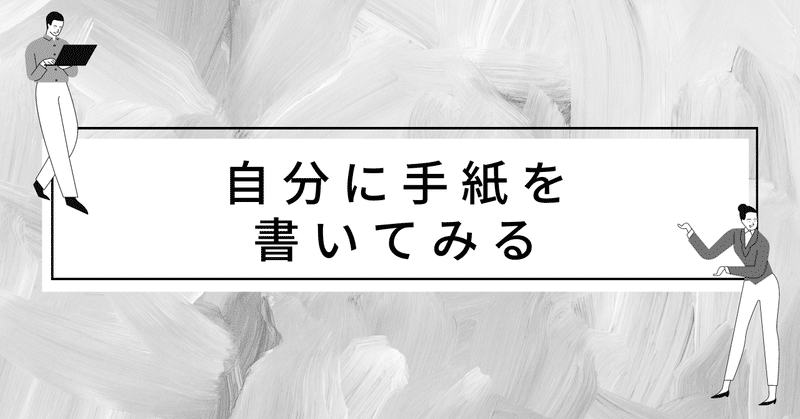
自分に手紙を書いてみる
今週から「人生を変えるSIY」というセッションに参加しています。
SIY(Search Inside Yourself)とは、Google社の20%ルールから生まれた、マインドフルネスに基づくカリキュラムです。
このプログラムでは、マインドフルネスから始まり 自己認識、自己管理、モチベーション、価値観、レジリエンス、コンパッション、共感、共感疲労、リーダーシップなど…このnoteでも過去に登場したような内容を、ワークを実践しながら学ぶことができます。
当初はGoogleの社員向けに展開されていましたが、社員の仕事におけるパフォーマンスや幸福度が上がったことで有名になり、5万人以上が受講するまでに広まった、世界的に著名なマインドフルネス・プログラムです。
2021年に受講したマインドフルネス講座の先生からご案内をいただき、一回あたり2.5時間×7回のオンラインセッションを受講中です。かねてより機会があれば参加したいと考えていたので、迷わず申し込みました。
このような専門的な講座をオンラインで気軽に受講できるようになったことは、コロナ禍がもたらした恩恵のひとつです。いやほんとありがたい。
情動的知能を育むトレーニング
SIYでは、脳神経科学で効果が認められているマインドフルネスを基盤に、「情動的知性」と呼ばれる「EQ(Emotional Quotient)」を、科学的アプローチで高めることができます。
EQとは、エール大学のピーター・サロベイ博士とニューハンプシャー大学のジョン・メイヤー博士が1989 年に初めて論文「Emotional Intelligence」で発表した概念です。「IQ」が学力や知能の指数であるのに対して、EQは「心の知能指数」というわけです。
SIYを創り上げたエンジニアのチャディー・メン・タンの書籍によると、EQは下記のように定義されています。
自分自身と他人の気持ちや情動をモニターし、見分け、その情報を使って自分の思考や行動を導く能力。
かつて、人間の行動に影響を与える感情は、生まれ持った性格や気質などの先天的な要素に起因するため、鍛えることができないという考え方が一般的でした。
しかし、EQ理論では感情を扱う知能(EQ)があり、後天的に開発することが可能であると提言されています。筋トレと一緒で、感情もトレーニングによって鍛えることができるのです。
EQを構成する5つの領域
「ニューヨーク・タイムズ」紙で行動心理学について執筆してきたジャーナリストのダニエル・ゴールドマンは、自信の著書のなかでEQを5つの領域に分類しています。
1.自己認識
自分の内面の状態、好み、資質、直感を知ること
2.自己統制
自分の内面の状態、衝動、資質を管理すること
3.モチベーション
目標達成をもたらしたり助けたりする情動的な傾向
4.共感
他人の気持ち、欲求、関心を認識すること
5.社会的技能
他人から望ましい反応を引き出すのに熟達していること
これを書いている現在、カリキュラムは2番目の自己統制あたりまで進んでいます。様々なワークを実践してきたなかで、今回特に面白いなと感じたのはジャーナリングです。
もやもやを言語化するジャーナリング
ジャーナリング(journaling)とは、自分に向けて思いつくままに文章を書くことで、自己発見を促すトレーニングです。
やり方は単純です。紙とペンを用意して、テーマをひとつ決めて、制限時間を設けて、頭に浮かんだ言葉をつらつらと書いていくだけです。テーマとは無関係のことでも、頭に浮かんだことならなにを書いても構いません。
書いた内容はほかの誰かに見せる必要はないので、字が汚くても誤字脱字が多くても気にする必要はありません。たったひとつの約束事は、決して書くのをやめないということです。たとえ何も思い浮かばくなっても、とにかく手を止めないことがポイントです。
自分の内面にありながら、もやもやとして明瞭でないものを言語化することによって、自分を客観視することができるだけでなく、新たな気づきや発見を得ることができます。自分が発した言葉を自分で読むことによって、自分の潜在的な考えに気づくオートクラインですね。
ジャーナリングは「書く瞑想」とも呼ばれ、メンタルヘルスやマインドフルネスの手法の一つとしても注目されています。
ジャーナリング自体は過去にもやったことがありましたが、正直なところそんなに面白いと思ったことがありませんでした。大きなストレスを抱えているわけではない(と思っている)し、押し殺している感情があるわけでもない(と思っている)ので、取り立てて書くこともないといった感じでした。
ところが、今回は面白いように筆が進んで、自分が自分に対して考えていることが明確になり、とても頭がすっきりしました。
これはおそらく、このnoteを続けていることでアウトプット力があがってきたおかげではないかと思います。書けるとジャーナリングがぐっと楽しくなってきたので、これからも色々なテーマで実践していきたいです。
出してしまえば楽になる
自分のなかの悩みや迷いというものは、意外と曖昧模糊として掴みどころがなかったりするものです。あるいは、複数の問題が絡み合っていて、全体像が把握しづらかったりもします。
言葉を使ってかたちを与えることによって、自分自身の内面にあるものが明確になり、それをどう扱うかが考えやすくなります。
話し相手がいる場合は対話によってオートクラインを誘発することができますが、一人のときはジャーナリングが有効です。もやもやしている人は試してみてください。
では。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
