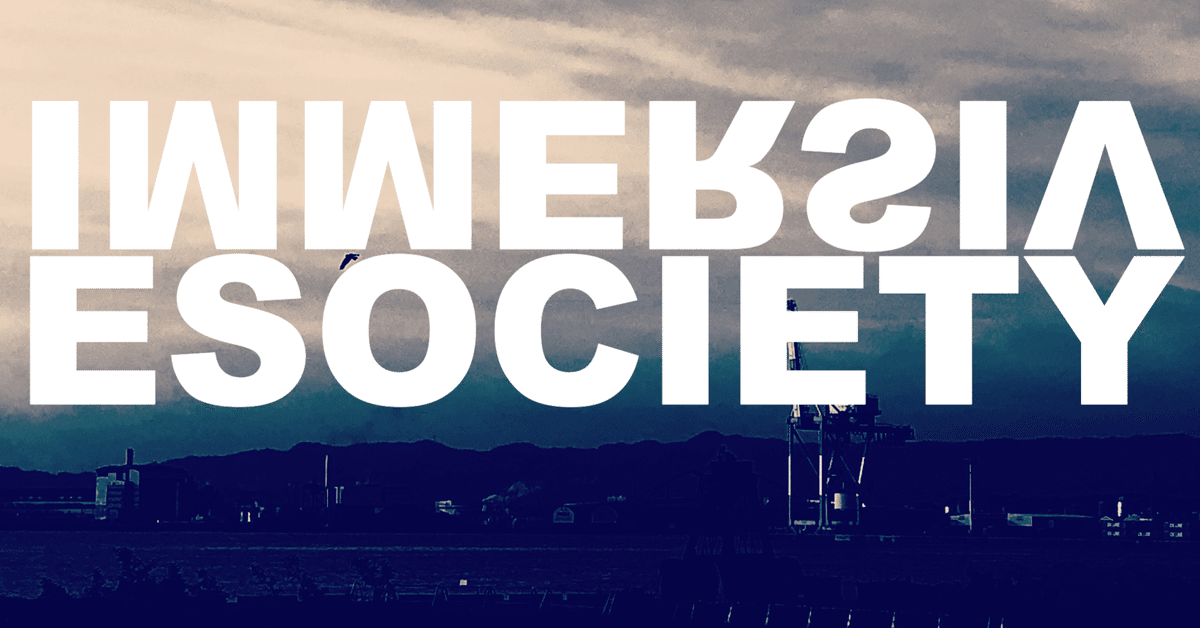
ピカソの「キュビズム」 - 生みの親かも知れない葛飾北斎は、それを嫌う。
キュビスムは、ピカソのゲルニカに代表される絵画の表現手法で、4次元視点から見た立体を2次元へと押し込める。
- - - - -
キュビズムとは?
3次元の住民である我々が、「高さ」という概念も存在も持てない平べった位2次元の住民には絶対不可能な方法 =「たとえば、ねじったり、折り曲げたり」で、トランプの表裏を同時に見ることができるように、4次元の住民が、(ボクらには想像も付かない方法で)同時に見る「立体を構成するあらゆる面」を(擬似的に)キャンパス一面に並べるようなこと。
それは、3次元の自然摂理や物理法則からは崩壊のように映るだろう。たとえば、片目しか見えないはずの横顔に両目が描かれたりもする。
- - - - -
キュビズムは、本来、見えるはずのない、立体(3次元の現実)の裏側に隠された部分まで、強制的に、たとえ、醜くなったとしても、並列に同時に可視化することで、否応なしに、表裏一体を鑑賞(認識)させる。
ピカソは「平和の裏に潜む戦争の影」あるいは「戦争いう犠牲の上にある平和」というメッセージを、より的確に伝えるために「キュビスム」を選択したのかも知れない。
だって、ゲルニカは、万国博覧会のために描かれたのだ––––
平和のシンボルでもある「万博」の壁(1つの面)へ「戦争」を描くのに、これほど相応しい手法が他にあるだろうか?
一方、ピカソに大きな影響を与えた葛飾北斎(一説では、ピカソは、北斎の絵からキュビズムのインスピレーションを得たとも言われている)は––––
キュビズムが「擬似的に(透視図法で)立体を描くと制限されてしまう多様性を1つの面に内包した」のに対し、立体かつ他面には一切触れず、ダ・ヴィンチのスフマート(線を用いず、グラデーションを活用し、立体的に見せる絵画の手法)ですら嫌い––––
しごく平面的に描くことで、視点の多角化(観る側が自由に想像を膨らませる幅)を受け手に残した。
キュビズムが立体のあらゆる面を暴くのに対し、浮世絵は「立体化のエンパワーメント(鑑賞者側への権限委譲)」を行ったと考察する。
紙の上で平面的に在る北斎の絵が観る人の心に生む立体的な心象風景は「十人十色」––––つまり、民主的だ。
一方、すべてを並べて可視化するがゆえに唯一解的(絶対的)になりがちなキュビズムにおいて、観る側は、作者が確定させた世界観やメッセージを(的確に/確信的に)享受する(しかない)。
このように、ビジュアライズにおける西洋の意識は、「写実(平面に立体を表現する)」に重きを置くことが多い。
キュビズムにおけるデフォルメを伴った過多ともいえる情報(あらゆる面)の詰め込み(3次元の現実空間では同時に見ることのできない多面を4次元視点から2次元に集約するコト)も、物事の多面性をすべて内包するコトで「メッセージのリアリティ(写実 = 事実性)」を獲得している。
ゲルニカであれば「戦争の表裏」であり––––立体であれば「光の当たる面の裏側にある暗黒面」である––––それらは「影」という幻とは違う紛れも無い事実だ。
この考察において、北斎は、多次元を捨て、2次元を極めるコト(良い簡素化)で、このマガジンの主題の1つである「○○○○○」を意識したメタ・インタラクティヴなアートを目指しているようにも感じる。
作者が描かなかった裏側を、鑑賞者が想像によって補完し、頭の中で好き勝手に立体化するコトを、おおらかに許容してくれる。
だから、浮世絵は、ファンタジーなのだ。
それは、ディズニーのスフマート的な3DCGアニメーションと、線をきちんと描くジャパニメーションの差異にも表れている。
一見、独断的で、クリアに描かれているように感じるグラデーションの乏しいベタ塗りの線画の方が曖昧で豊かに感じる場合もある。
日本人は、そんな2次元の万能性を愛する民族なのだ。アニメや漫画は、キュビズムと反対側で、今なお北斎の意志を継ぎ、世界を席巻している。
全てを描かれないことが、
僕に、全てを感じさせる。
- - - - -
【 最高/最大/最新のテクノロジーは必ずしも体験の上質さとは比例しない 】
【 マ ガ ジ ン 】
(人間に限って)世界の半分以上は「想像による創造」で出来ている。

人が そう呼ばれる「幻」の「壁」を越えられないのは
物質的な高さではなく、精神的に没入する深さのせい
某レコード会社で音楽ディレクターとして働きながら、クリエティヴ・ディレクターとして、アート/広告/建築/人工知能/地域創生/ファッション/メタバースなど多種多様な業界と(運良く)仕事させてもらえたボクが、古くは『神話時代』から『ルネサンス』を経て『どこでもドアが普及した遠い未来』まで、史実とSF、考察と予測、観測と希望を交え、プロトタイピングしていく。
音楽業界を目指す人はもちろん、「DX」と「xR」の(良くも悪くもな)歴史(レファレンス)と未来(将来性)を知りたいあらゆる人向け。
本当のタイトルは––––
「本当の商品には付録を読み終わるまではできれば触れないで欲しくって、
付録の最後のページを先に読んで音楽を聴くのもできればやめて欲しい。
また、この商品に収録されている音楽は誰のどの曲なのか非公開だから、
音楽に関することをインターネット上で世界中に晒すなんてことは……」
【 自 己 紹 介 と 目 次 】
【 プ ロ ロ ー グ 】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
