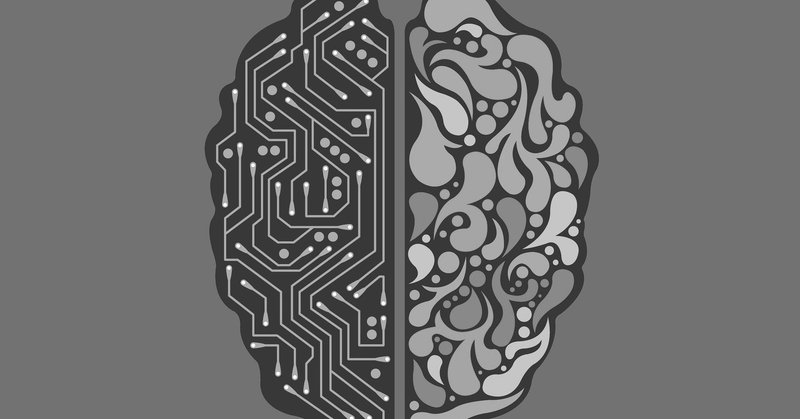
将棋とAIの「ケタ違い」な話──コミュニケーション考 (ⅰ)
「1000桁」をめぐる応酬
将棋ネット中継での視聴者コメントでよく使われるネタ表現に「1000桁」というものがある。
(ABEMAでは%表示が使われているので、ニコ生特有のネタかもしれない)
コンピュータの将棋ソフト(最近はAIと呼ばれることが増えたが)は、独自の形勢判断を数値化し、「評価値」などと呼ばれている。この数値が200〜300のうちは〈互角〉とみなされ、500ぐらいを超えてくるとすこし「指しやすい」などと解釈されるのがふつうだ。
この評価値が「1000」を超えると、(局面にもよるが)見た目にもはっきりと形勢が傾いてきているとみなされる。優劣の分かれめになる目安が、このキリのいい1000という数字。
この数値をみると、とたんに視聴者が騒ぎはじめる。そのおハヤシの定番が「1000桁」というやつだ。(「1000桁キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!」とかのコメントが、待ってましたとばかりに踊りだす)
もちろん、1000桁というのは算数的(?w)に間違いで、視聴者のなかにも「4桁だろ」とかチャカす輩もちょくちょく現れるのだが、「いや1000桁はネタだから。察しろ」といったタシナメの応酬がはじまるといった具合。
ほかに、評価値を年号や棋士人名に見立てたお決まり(定期)コメなども、これはこれでなかなかオモシロいので紹介した気持ちもあるが、話がだいぶそれるので別の機会にしたい。
いまやすっかり、ソフトの手が「正解」という感覚がプロ棋士のあいだでも定着しきって、観るほうもそれを前提にそれなりの楽しみかたをあみだしてきたのでこのようなネタもうまれるわけだが、棋力がAI>プロ棋士となったのもほんのここ数年の出来ごとだ。
コンピュータvs.トッププロの対局はチェスでの取り組みが先行して、ついで将棋も盛んになっていたが、盤面の広い囲碁では5〜6年前まで「あと10年はプロ棋士とわたりあえるソフトは実現しない」などと言われていたところへ彗星のごとくアルファ碁があらわれて、世界が一変してしまった。
アルファ碁がイ・セドルとの五番勝負を4-1で圧勝したのが2015年だった。
10の220乗?、360乗?!
ところで、みんなご存じ藤井聡太二冠の最近の大活躍で、ワイドショーとか地上波テレビ、新聞雑誌などでも将棋がふたたび世間的にも注目をも集めて「第二次藤井ブーム」みたいになっている。
世間の関心が棋士に向くと(将棋であれ囲碁であれ)、なんどでも不死鳥のごとく繰り返される質問が、「棋士は何手先まで読んでいるんですか?」というもの。
厳密なことをいうと、一手一手に複数の選択肢がある中からひとつにしぼりこんでいくことの繰り返しが「読み」なので、読みすすむにつれてどんどん枝葉がひろがっていく進化系統樹のようなものになる。これを全体の累積で読みの「手数」をカウントすれば膨大な数になるし、「何手先」という言葉の「先」に忠実に数えるなら〈何段階め〉まで見越しているかという意味になり、それほど大きな数にはならない。(テクニカルには読みの「深さ」と呼んだりする)
最近の中継ではAIの読みの手数が表示されることもあって、100億✕✕✕✕手などと出てきたり、藤井聡太二冠が最新ソフトに6億手まで読ませたときにはじめて最善手として割り出される手を指したと話題になったりもしたが、こうなってくると、もはやイメージもわかない読みの量だ。このようなときに出てくる数字は、先ほどのはなしでは累積の総手数ということになる。(そもそも一局の将棋の手数は120手ぐらいのもの、手数が長めの囲碁でも300手ほどがせいぜいなので、億などという数がでてくるはずもないw)
そもそも、ルール上で可能な指し手/打ち手の組み合わせを数え上げると、将棋の場合で「10の220乗」(!!意味不w)、囲碁となると「10の360乗」になる計算なのだそうだ。先ほどの「1000桁」まではおよばないもののw、「天文学的」という形容でもとうてい追いつかない数字で、もはや大きさのイメージすらわかないレベル。
囲碁の10^360にいたっては、なんでも「宇宙にある原子の総数よりおおい」(!!!!は?w)んだとか… なるほど千年、ぅん百年の歴史でもまったく同じ棋譜は存在しないというのも、そりゃそっか。
手の流れと点の読み
コンピュータの読みはイメージ的には「しらみつぶし」にちかい方法(厳密には正しくない表現なのだが)で膨大なシミュレーションから候補手を導きだすという感じで処理されている。
対して、棋士の思考は常人ばなれした経験と鍛錬をふまえて、もっとずっと絞り込まれた選択肢のなかから指し手(囲碁では打ち手)を決定する。
こうした棋士の思考は(素人のわたしには想像でしかとても語れないが)、その局面にいたるまでに指してきた「手の流れ」を重視し、これまでの手が生きるような選択を積みあげていくものだと説明されることもおおい。
また、「大局観」とよばれる俯瞰的な状況判断や「手筋」「筋」という手順の組み合わせの妙/技、「定跡/定石」などの歴史的な経験則も動員して、ある意味でストーリーを紡ぎ出すようにして手を読み、決断して対局をすすめていくようだ。
コンピュータ/AIはこうした対局の「流れ」は考えない。一手ごと、形勢の評価も指し手の読みもリセットし、まったくゼロから考え直して次の最善手を探索する。いわば「点の読み」。
それが不可解で意味不明な推奨手だと人間にはみえることもあれば、知らずしらずに思いこみが生じたり視野が狭まってしまう(見落としにつながる)といった罠をさけられる利点もある。
無尽蔵なコンピューティング・リソースが裏づける、このような“AI思考”が何百年にもわたる人間の匠(棋士)の叡智を結集した定跡/定石を、劇的に更新してきたのもたしかで、天才ひしめくプロ棋士の思考や思想を塗り替えもした。
AIが人間の仕事をうばうという警句も吐いて捨てるほど発せられてきたが、
コンピュータが天才たちの思考をも新次元へ連れていけるのだということを棋界のいきさつがみせてくれている。ぼくらのような凡人には驚異にも映るAIも、人間と共存することが可能だということを教えているかのようだ。
「棋は対話なり」と指し手の意図
ところで、近年の将棋ブームで「観る将」という人種がうまれている。棋士たちが対局するようすをながめるのがたのしい、すきだという人たちが大勢いるのだが、この人たちのおおくは自分では将棋が指せない/指さない。
棋士たちがAIによって開眼したのは、将棋や囲碁には「正解」(人間はこれまで到達できていないし、これから先も決して到達することはないかもしれないが)ともいうべき最善手とそれを導きだす法則(「棋理」とよばれる)があって、それに近づくためのヒントをAIから学んでいるのだといえる。
だが観る将たちは棋士たちとはちがう目で対局を観戦し、たのしんでいる。ルールですらわからずに観戦をたのしめるのだから、対局の内容そのものを評価しているわけではなく(すくなくとも第一義ではない)、もっとほかのものをみつめているはずだ。
それは、シンプルな「勝敗」という目的をめぐって、ものすごい才能同士が極限状態でシノギをけずる様子や経緯をみまもってドキドキしたり、超人的な思考や技術のすごさを体感したいとおもって観戦したり、もしくは異様なほど長時間なにも話さずひたすら読みふける、ふしぎな時間の流れと空間を単純にあじわったりしているのだろう。
AIに向けられた棋士の関心とはまたちがう眼差しで、対局という真剣勝負をみまもり、たのしんでいる。
「棋は対話なり」というこの世界のことばがある。
ながい対局時間のさいちゅう、基本的に棋士はことばを発することはない。「ボヤキ」ということは、おもに対局相手が離席しているときなどに時おりみられるが、それとて「三味線」ともいわれるブラフみたいなひとりごとが半ば習性みたいになっている人がいるぐらいで、本心の吐露なのかどうかはまったくアテにならない。
棋士はその指し手/打ち手のやり取りをつうじて「対話」をしているのだというのが、上にあげたことばの意味だ。
ある状況、ある局面で、どの着手を選ぶのかという選択そのものに、対局者の「読み筋」が込められている。まさに「手の流れ」「いきさつ」を複眼的にとらえつつ、ここからどの展開が本線となるか、どういう展開をめざしていくのかという意図をもとに、指し手/打ち手を決断している。
ここで、自身の意思を定めると同時に、相手がどう思考しているのかということも「読み」のなかに入ってくる。いうまでもなく、お互い自身の勝利をめざして読みあうのだから、はじめから利害、主張はガチで矛盾している。棋理にかなう「正解」手、最善手が、人と人の勝負においても最善かどうかはわからないところが醍醐味のひとつなのだ。
さらには、対局相手がどのような価値評価、形勢判断をする傾向(「棋風」とよばれる)があるか、という「人読み」の要素までが実戦では加味されている。
「棋は対話」の対話とは、沈黙のうちに指し手/打ち手のみを介して互いの思考を汲みあい、はずしあう駆け引きであり疎通なのだ。
対話と会話
〈対話〉はどこか文語的だ。似たようでいて、〈会話〉だと口語的なものを想起させる。すくなくともわたしにはそう映るが、みなさんはどうだろう。
これはなにもいわれのないことでもないと、おもっている。
想いおこしてみてほしいのだが、会話しているさなか、あなたがおもに相手と交わしているものはなんだろうか。また「対話」しているとかんじているときだったら、どうだろう。
かんたんにいってしまうなら、会話は感情のやりとりであり、それが対話であれば論理と思考、さきほどの話を持ちだせば「理(ことわり)」をめぐる見解の交換だとみることができるのではないだろうか。
感情の交歓である会話において〈世界の中心〉、その会話の〈芯〉はふたつ(3人以上の会話では人数分)あるだろう。話者の眼ざしは相手のこころへ向けられている。もちろん、会話をつうじて共感や交流をはかるものだが、おたがいの気持ちやこころに関心を寄せあうやりとりなのだから、どちらかが他方を組み伏せたり、いいくるめたりする類いのものでは当然ない。
〈あなた〉と〈わたし〉がそれぞれ独立してあってこその、会話なのだ。
対話のばあい、事情はすこしちがう。ディベートでもなければ、なにも相手をいい負かすのが対話ということではなく、相手の思考の独立性が必要ないということでもない(むしろ重要な)のだが、眼ざしの向く先が相手のなかというよりも、もっとほかのなにかをみつめていると感じないだろうか。
それは「真理」だったり「事実」だったり、対話者同士が共有する、しかも対話者自身のどちらでもない、もう少し客観性をおびたなにか。
さきほどの将棋の例でいえば、いま盤上にある局面、そしてつぎに指すべき最善手はいったいどれなのか?をひたすら読みふける。ひいては「棋理」を起点におたがいの思考はすすんでいるのだといえる。
「対話」というからには、もちろんそこでは相手の思考を推しはかる過程が起こっているが、棋理という〈芯〉を介した思考のやりとりがおこなわれていることがイメージできるだろう。会話のばあい、おたがいのこころという双軸でやりとりされているのとは、交感の構図はすこし異なる。
「棋は──会話ではなくやはり──対話なり」なのだ。
棋道におけるAIの意味
こうした視点に立つとき、棋道(将棋や囲碁)におけるAIの意味も、すこしちがって観えてくる。
かつて『ヒカルの碁』という囲碁漫画が人気を博した。このなかでは「神の一手」ということばが繰り返しつかわれ、囲碁の奥深さと棋理の存在を暗示し、象徴的な概念をつたえる印象的なキーワードとなっていた。
AIの候補手が「正解」とまでみなされ、その強さがどんな天才棋士をも凌駕することが前提となった現在では、このAIの候補手は人間よりも神の一手にちかい、棋理の光を映した「思考の道しるべ」として、棋士たちの「対話」と思考のありようをさまがわりさせたようにみえる。
もちろん、前段で述べたように棋士同士(人間)の対局において、理づめの〈正解〉が勝負での最善手となるかどうかはそのかぎりではない。対局相手の読みと思考、その「流れ」を観取して己の読みに組みいれる。相手の思考に呼応しつつ、それを上回る自身の「流れ」へとたえず描きなおしていく。
そのやりとりの積みあげこそが対局だ。AIなどなかったかつては茫洋とした抽象的な棋理を、観るともなく観つつ介在させることで「対話」をなりたたせてきただろう。AIの存在は、この〈芯〉となる棋理を抽象的理念や法則の次元から具体的な指し手/打ち手へと顕在化、可視化してみせたのだ。
この具現化された道しるべを、実戦で棋士が直接目にすることは、もちろんない。だがこの具体性が対局者間の対話を立体化し、次元を引き上げる働きをもたらしただろうことは想像される。
また、AIが人間とは違って「点の読み」をおこない、手の流れがもつ因果は読み取らないことが逆に固定観念をはずし視界をひろげることにつながってもいるだろう。
囲碁界往年の名棋士、藤沢秀行はかつて「囲碁(の棋理)を5%は理解できただろうか」と語った。あまたの戴冠をへて一時代を築き、67歳でタイトルの防衛をはたした大棋士が、である。
この途方もなく遠い漠然とした探求の道を、AIはほのかな光となり照らしている存在なのかもしれない。
「ヒカ碁」が流行った当時はそれが引き金となり、いまの囲碁界を牽引する棋士たちの輩出にもつながった。二度の七冠達成で注目をあつめた井山裕太もそのひとりだ。また、数年前はアルファ碁の鮮烈な登場で世界的にも耳目をあつめたものの、最近は盛りあがる将棋界を尻目にすこしさびしい状況にあるのは残念なことだ。
韓国や中国では、日本とは較ぶべくもない人気と地位を誇る囲碁への注目がまた高まってほしい。
AIとの幸福なかかわりは…
棋道は完全情報ゲームだ。人間的には無限にひとしい複雑性と多様性をもつからこそ道となり、おおくの人々を魅了するプロフェッショナリズムとしても成立している。とはいえ、だからこそ「棋理」も存在し、対局者のくだす決定もこれまでの経緯も、すべてが開示されているなかでの思考の勝負だ。究極的には必然性が支配する世界だといえる。
こうした世界のなかでAIは生身の達人、天才の技量を超え「理」の代弁者としての地歩を固めつつあるようにおもえる。
わたしたちにとってより身近な日常の実社会において、たとえばビジネスのなかでAIとのかかわりはどんな可能性をひらいてくれるだろうか。ときに、人間の立場をうばう驚異にみられることもあるAIだが、さまざまな領域での適用が競うようにチャレンジされ、効果的な活用が叶わなければ生き残りも厳しいとすらいわれる状況は現にきている。
ここで、わたしたちの生活や消費のじっさいは将棋や囲碁のような、「完全情報ゲーム」ではないことは念頭においておいて損はないはずだ。理づめで決まりきらない「会話」的世界にそれはあるという側面がある。
〈芯〉のみえない多軸的な世界で、理と感情が織り交ざる人びとの営為からAIは今後なにを読み解き、どんな光を照らしてくれるだろうか。
人はいきさつをだいじに動くもの。
いまはこの理解をあらためて強調しておきたい。将棋や囲碁において、AIがもたらしたものをみるなかから、コミュニケーションについて考えなおしてみることを今回は試みた。
対話と会話、理と感情、人間同士の交感がどんな特質をもっているか。
このことを、またちがった角度から問いかえす試みを、もうしばらく続けていきたい。
サポートはとてもありがたいです!できるかぎりみなさんの役に立ち、よろこんでもらえる発信をしていけるようがんばります。いただいたサポートは、そうした活動時間確保のためにあてさせていただきます。
