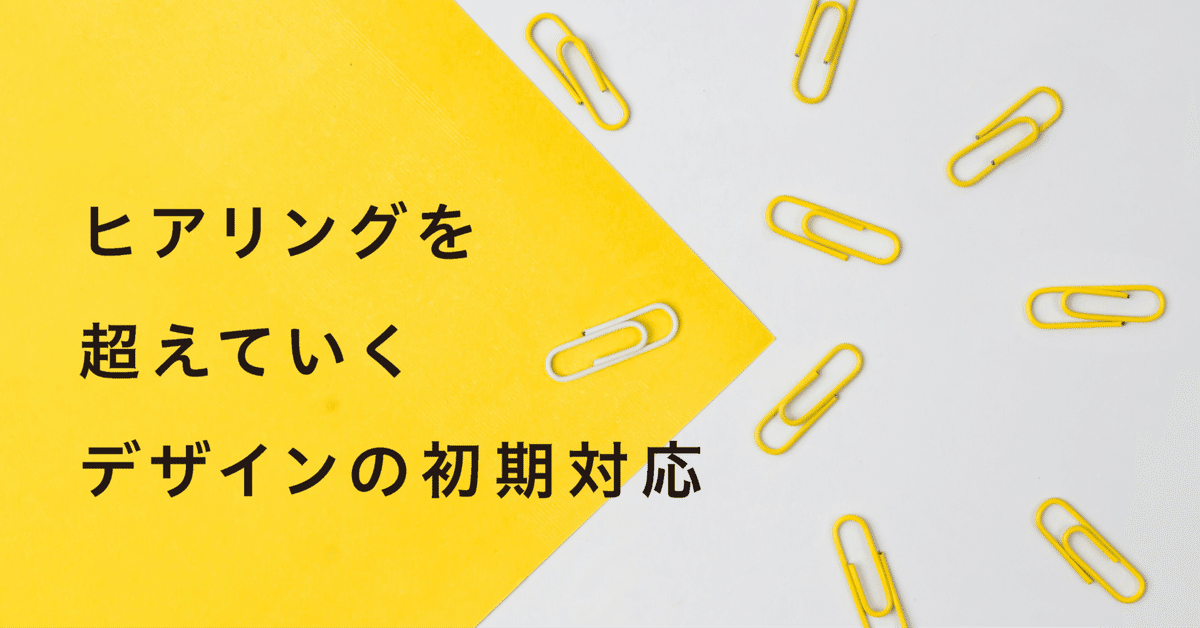
ヒアリングを超えていく、デザインの初期対応
ヒアリングに行くのではない。最初から価値を与えること。これは、プロジェクトの初期対応でデザイナーが取るべき基本的な態度です。
今回のテーマは、デザインの初期対応。その効果的な動き方を紹介します。
デザインプロジェクトのスタートは、他者から依頼を受ける場合と、デザイナー側から提案を始める場合の2つのパターンがありますが、今回はそのうちの「デザイナーが依頼を受けるパターン」について。
初期対応の時点で、デザインの成果の半分は決まってしまいます。それくらい重要なものですが、なせかデザインの世界ではあまり論点化されていません。自分の経験が何かの役に立てばとの期待を込めて。どうぞ。
ヒアリングじゃない。ディスカッションだ。
依頼や問い合わせを受けてデザイナーが初期対応すること。これをヒアリングと呼ぶこともありますが、それには注意が必要です。
最初に関係性が固定される
ヒアリングに行く。情報を聴きに行く。情報をもらう。このような意識で初期対応に臨んでしまうと、デザイナーと依頼者との関係は固定されてしまいます。
情報を与えデザインしてもらう者と、情報をもらいデザインを提供する者。「あなた」と「私」の関係の中で、情報提供とデザイン作業が往復される。依頼する者と請け負う者の構図がビシッと作られてしまいます。
デザインは協働作業です。「あなた」の視点と「私」の視点がぶつかるのではなく、ともに「私たち」の視点で成果に向かわなければなりません。
そのためには、ヒアリングではなくディスカッションとして初期対応に臨む必要があります。
医師やカウンセラーは、「ヒアリング=聴くこと」を通じて患者や依頼者と自らの間に適切な距離を保ちます。しっかりと線を引きます。自らを「相手の問題」に置きすぎると感情が引きずられ、多くの患者や依頼者に対応することができません。非対称な関係を保つことで、発言の有効性を維持することも重要です。「あなた」と「私」を区分することの合理性があります。
一方で、デザイナーの場合はもっと踏み込む方が成功する。依頼者とデザイナーの利害関係はありつつも、「私たち」の視点から同じ成果を協働するほうが成果に近づく。奇譚なく意見交換できる、お互いに動いてもらうことを促せる。一緒につくる。こういった「私たち」の空間を作り出すことが重要です。
信頼のスタートダッシュ
相手も忙しい。時間がない。そんななか相談してくれています。事前準備をして臨んでくれています。
1時間のミーティングならば、1時間なりの価値ある時間をデザイナーは提供する必要がある。相手が抱える問題や叶えたい成果に対して、ヒントとなる情報や、解決への手応え、なんとかなるという安心感。こういったものを1時間の初期対応に、ギュッと込めなければなりません。
ヒアリングはデザインの初期対応の一部ではありますが、全部ではありません。ヒアリングに徹してしまい、解決方法の議論を先送りにする。それでは、依頼する側は何も価値が得られない。デザイナーは依頼者から信頼される重要な機会を逃してしまいます。
デザイナーも初期対応の中でギブすることが必要です。デザインを協働するための信頼関係を、なるべく早く築くことが重要なのです。
依頼は正しいのか
企業の問題を解決するために課題設定すること。企業課題に正確にアプローチする依頼事項を整理すること。依頼者が立ち向かっているこれらの作業はとても難しいものです。
デザイナーの視点では、相手の依頼事項が間違っているわけではないが、完全に正しいとも言い切れない。こんな状況がほとんどだと思います。
企業活動に対して厳密な正しさを求めるのはナンセンスですが、デザインプロフェッショナルの視点からは、依頼事項を見るだけで、成果に向けた仕事の流れや、その成功確率をある範囲では想像できるはずです。
デザイナーにはクリティカルシンキングも必要です。依頼事項や相手の考えを批判的に捉えて、事象が起こっている背景を想像し、本質的な問題は何であって解決方法は何であるかを考え抜く。批判的とは言いますが、これはあくまで思考方法のこと。相手にとって批判的立場や態度を取るということではありません。
安易に持ち帰らない
その場で仮説として示す。持ち帰らずにその場で示す。唯々諾々と依頼をただ受け取るのではなく、依頼事項の有効性について、その場で生産的なディスカッションをする。価値ある対話の場にする。これが重要です。
初期対応の場がヒアリング中心になってしまい、仮説を示さず持ち帰ってしまう。それによって、デザイナーが後になって依頼事項を疑い、相手視点では想定外のソリューションを提案されることになる。そこから軌道修正が入る。これでは遅いです。
相手からしたら、初期対応の1時間の対話の中で、解決の幅であったり、方向修正の可能性であったりを想定に入れられた方が良いものです。依頼者の方の仕事の質もぐっと上がるはずです。
方向性を握って締める
デザイナーは、初期対応のミーティングのその中で、解決の仮説やプロジェクトの方向性を提案できると良いでしょう。
デザイナーは、初期対応のミーティングの後に、1週間ほど間を置いて詳細な提案をすることが多いもの。その詳細な提案をどういった方向性で行うのかを、初期対応の段階で相手に共有できることが最善です。
「それでは、このようにプロジェクトを進める方向で、後日、より詳しく提案しますね。念のため、メンバーの稼働だけ確認が必要ですので、持ち帰らせてください。」
初期対応の最後に、こんな形でミーティングを締められれば成功です。提案の方向性はその場で共通認識を得ておくのです。
プロジェクトのゴール設定。大まかなプロセスの流れ。リサーチすべき対象。ソリューションの仮説。アウトプットのスケッチ。自分が得意な領域をベースに、積極的にその場で仮説を示し、提案していく姿勢を持つ。
初期対応は、成果達成に向けた最初のディスカッション。この段階ですでにデザインプロセスは始まっています。
バッターボックスに立つ
このような積極的なアクションは、長年の経験がないとできないのではないかと思うかもしれません。もちろん経験や技術によって洗練されていくものではありますが、どんなに拙い仮説であっても議論を一歩前に進めることは可能です。
初期対応のミーティングの中で、仮説をぶつける経験を重ねないと技術は磨かれません。度胸も身につきません。漫然とヒアリングの経験を積み重ねていても、その場で仮説生成するスキルや瞬発力は向上しません。
事前リサーチで情報を増やす
初期対応の中でプロジェクトの方向性を示す。そのためには事前のリサーチも不可欠です。生産的なディスカッションをするには情報量が必要です。とくに経験の浅いデザイナーほど事前の調べに手間をかけるべきです。
初期対応のミーティングの前に、事前に依頼者から前提情報は伝えられるものと思います。それをもとに、こちらで調べられる情報は調べておく。こちらの手持ちの情報をなるべく増やしておく。
もし、事前リサーチのとっかかりが見えづらければ、相手に電話なりメールなりで簡単にヒアリングして、理解を深めておきましょう。
ディスカッション前に情報をなるべく多くして、相手と同じ視座でコミュニケーションできるようにする。ディスカッション前に情報を増やして、密度の濃い対話をする。
そして、その場では、プロジェクトの方向性の理解を得るためにスコープを絞るように意識していきます。初期対応の中でスコープを絞っていかないと、その後の詳細提案に無駄が生じます。ピントのずれた情報収集を繰り返して、状況にフィットをした的を射たシャープな提案ができなくなってしまいます。提案の質の面でも、デザイナーの作業効率の面でもマイナスは大きいものです。
事前リサーチすべき6つのレイヤー
では、事前リサーチはどのように行えば良いのでしょうか。
下の図は、事前リサーチで押さえておくべき情報をまとめたものです。

ポイントは依頼者を中心に、事業のレイヤー、部署のレイヤー、経営のレイヤー、業界のレイヤー、社会のレイヤーと区分して、多視点的に情報収集しておくことです。
たとえば、何かのサービスの課題解決をするような依頼だった場合。社会のレイヤーでは、そのサービスに影響を与えるような経済動向、法令改正、社会生活の変化、安全保障環境など。業界のレイヤーでは、業界全体の動向、業界に影響を与える技術トレンドなどです。
経営のレイヤーでは、ここ3年ほどの業績、中期経営計画などの方針や戦略、競合環境などを押さえます。部署のレイヤーでは、その部署が社内で果たす役割やミッション、成果指標などです。
事業のレイヤーは、その事業の直近の業績、競合サービスや代替品、その事業のユーザー状況などです。
最後に、依頼者個人の状況を理解することも必要です。依頼者のミッションやその達成の時間感覚、依頼者と社内決裁者の関係などです。デザイナーへの相談には、依頼者個人の悩みの要素も含まれるからです。
時間を決めてしっかりと
こういった多視点的な情報は、一般に公開されている情報から集めていきます。企業サイトやサービスサイト。企業や依頼者が登場するウェブコンテンツ。新聞記事。企業や経営者やサービスに関する著作。「業界地図」のような業界理解のための書籍、統計資料などです。
何から手を付ければよいかと迷うかもしれません。が、何が重要なのかも分からないことがほとんどであるため、まずは何も考えず片っ端に調べていけば問題ありません。調べるうちに「何を調べるべきか」もすぐに見えてきます。
事前リサーチはやろうと思えば無限にできてしまうので、時間を決めて行うのがおすすめです。私の場合は1時間です。ただ、この時間設定はデザイナーそれぞれの役割から最適な時間に幅があります。
私はデザインプロジェクトの責任者というよりは、その監督者として動くことの方が多いです。週に何回かデザインプロジェクトの初期対応に臨みますので、事前リサーチは短時間で終わらせる必要があります。また、私自身ではなく別のメンバーがリサーチして情報をまとめてくれることも多く、それを30分程度読み込むだけの場合もあります。初期対応に慣れていない場合や、その業界に不慣れな場合は数時間とってしっかり調べるのがおすすめです。
どこが要所なのかの勘所をつける
時間を決めて事前リサーチをすると言いましたが、先述した6つのレイヤーごとにまんべんなく情報を押さえることがポイントです(整理して情報収集するための自分用のリサーチテンプレートを作っておくこともおすすめ)。
なぜレイヤーごとに情報収集するのか。それは、なるべく視野を広くとった上で、デザインプロジェクトの要点がどこなのかをイメージする必要があるからです。要点というのは、プロジェクトが乗り越えなければいけない最大の障壁はどこなのか、強力な制約がどこにあるのか。逆に、成功要因となるレバレッジポイントがどこにありそうか、というような点です。
それが、ぼんやりとでも、ゆるい仮説であっても想定できるようになれば事前リサーチは終了です。
初期対応のディスカッションの場で、自分なりの想定と相手の発話内容にギャップがあれば、それをぶつけてみる。それだけでも十分に生産的なディスカッションは可能になります。
初期対応の場で瞬発力に自信がないデザイナーは、プロジェクトの要点だけでなく、ざっくりとしたデザインプロセスやゴール設定のレベルまで、方向性をシミュレーションしておくと良いでしょう。たとえ、そのシミュレーションが的外れであったとしても、自分自分のスキルアップには確実につながります。
自分の中の当事者性を引き上げる
ここまで、事前リサーチが初期対応での生産的なディスカッションに有効であることを紹介してきました。
それだけではありません。事前リサーチをすることで、デザイナー自身のそのプロジェクトへ向けた当事者性を引き上げられることも大切な効果です。
知らないことには関心を持ちようがない。依頼者や経営者の事業へ思いであったり、プロジェクトが接続する社会課題であったりを、知れば知るほど自分の当事者性が持ち上げられていく。プロジェクトを行う動機づけが強化されていく。そのための儀式としても事前リサーチは有益です。
デザインプロジェクトに前のめりであること。これも信頼獲得のキーになりますし、なによりも楽しく仕事ができる。「楽しい」は良いデザインに確実につながります。
ディスカッションの時間配分
事前リサーチを十分に済ませたとして、では、肝心な初期対応のディスカッションを具体的にどう進めたら良いのか。
ここでは、初期対応のミーティングが1時間だった場合を想定して書いていきます。時間配分はあくまで目安です。

1.自己紹介(5分)
まずは簡単な自己紹介です。自分の役割や所属部署のミッションを紹介します。合わせて相手の役割や部署のことについても確認をしておきましょう。
2.ヒアリング(15分)
相手から依頼内容を説明してもらいます。一旦はまずは話しきっていただき、疑問点などは手元にメモを取っておくとよいでしょう。
3.不明点の確認(10分)
事前リサーチの内容と照合しながら、不明点を質問していきます。事前リサーチをしていると、本質的に重要な要所部分にしぼって質問することができます。何を確認しておくべきなのかの勘所が磨かれ、筋の良い質問ができるようになります。
逆に、事前リサーチが不徹底の場合は、本質的ではない部分に時間を割いて質問してしまったり、最悪の場合は、ネットで調べれば分かる情報をわざわざ聞いてしまうことにもなります。時間がもったいないです。
デザイナーがどのような質問をするのか。これは、相手から見てデザイナーの力量を推し量る材料になります。事前に検索すれば出てくるような質問を繰り返していると、デザイン以前に、仕事のマナーとしても印象が良いものではありません。
不明点の確認はコンパクトに終わらせたいものです。この後のディスカッションに時間を使いたいからです。
4.プロジェクトの提案(10分)
事前リサーチで想定した要点と、ヒアリング内容を踏まえて、その場で考えうる解決策の仮説をぶつけてみます。プロジェクトプランの方向性や、アウトプットのイメージなどです。
オンラインであればmiroなどのオンラインボード、オフラインであればメモ用紙やホワイトボードなどを活用し、なるべく可視化しながら進めていきます。図示やスケッチを積極的に。可視化することで精度高く認識をあわせていくことができます。
5.こちらの提案を受けてのディスカッション(15分)
続いて、こちらの仮説提案を踏まえて、ディスカッションをします。
こちらの仮説が相手の視点で違和感があったとしても構いません。その違和感を起点にお互いの考えをすり合わせるきっかけになるからです。
理想的なのは、この対話の過程で、「私たち」の感覚と、コ・クリエーションの関係が立ち現れていることです。すでにデザインプロセスが回り始めている感覚。手応えを感じる瞬間です。
ディスカッションでは、最初は発散的に議論していきますが、ミーティングのクローズに向かい、徐々に方向性を絞っていくようにしていきます。
予算やスケジュールなどの制約部分もしっかり押さえます。時間と費用の制約の中で、現実的なプロジェクトを思考するためにも必要な確認です。
同時に「それが本当に制約なのか」も考えます。先述の6つのレイヤーで分析し、クリティカルシンキングを重ねた上で議論を重ねます。議論しながら、制約も含めて現実的なデザインプロジェクトの方向性をこちらから示し、違和感や問題がないかをその場で点検していきます。
期待値の確認も重要です。ざっくりいうと、相手がこちらに期待することの範囲と深さについてです。相手はこちらが何をできるかを完全に理解して依頼してきているわけではありません。ディスカッションの過程で、先方はこちらが何をどれくらい出来るかをだんだんと理解していきます。理解が進んだ段階で、あらためて確認するのが有意義でしょう。
6.詳細提案の方向性の確認(5分)
初期対応のミーティングを締める段階です。
多くの場合、この次は、日を改めてデザイナーが提案内容をまとめてプレゼンテーションする番です。その提案内容の方向性を概要レベルで説明し、違和感がないかをその場で確認します。その上で、ネクストアクションを決定しミーティングを締めます。
初期対応ミーティングの後に
デザイナーは持ち帰り検討し、アサインできる人員や工数を精査し、詳細な提案内容を詰めていきます。もし、その過程で疑問が出てきたら、メールや電話で相手に確認をします。ビジネスにとって重要なのは時間。時間が経過した後に方向違いの提案が出てくるよりかは、お互いに多少の手間があっても都度確認した方が、双方にとって幸せです。
詳細な提案をどうまとめていくか。この点に関してはまた別の記事を書いてみようと思います。
なぜこの記事を書いたか
この記事は、デザイン会社コンセントの社内研修の内容を要約したものです。デザインエージェンシーであるコンセントの環境に限定する部分は省略し、広く役立ちそうな内容に絞ってお伝えしました。
研修を実施したのは2016年です。サービスデザイン組織のメンバーに向けたものでした。そのころは初期対応をしっかりと行えるメンバーが非常に少なく、私と一部メンバーだけが属人的なスキルで乗り切っている状況でした。
暗黙知が暗黙知のままで閉じている。デザイン組織にとっても、個人のデザインキャリアにとっても、初期対応から提案の流れを磨き上げることは非常に重要です。にもかかわらず、その形式知化が進んでいなかったのです。
これはいかん。そう思い、自分のやり方や初期対応が上手なメンバーの動きを分析し、まとめたのがその研修であり、この記事です。
この記事の最初に、初期対応の時点でデザインの成果の半分は決まると述べました。これは事実です。初期対応がヒアリングだけになり、見当違いな提案をしてしまい、そもそもプロジェクトがスタートしなかったこと。初期対応でディスカッションが深まらず期待値にギャップが出てしまったこと。初期対応の段階で、悪い意味での「下請け」的な印象がつきすぎてしまい、健康的な交渉力や、健全な共創が叶わなかったこと。反省が多くあります。
この研修が功を奏したのかはわかりませんが、今のコンセントでは、多くの若手メンバーが初期対応できるようにまで成長できています。
多くのデザイナーの仕事の質が向上すればいいなと。偉そうに言ってしまい恐縮ですが、私なりにデザインによって社会を良くすることに貢献できたらと願い、この記事を締めます。
長文を読んでいただきありがとうございました。
Photo by Tamanna Rumee on Unsplash
※今回はデザイナーの初期対応について紹介しました。今回の記事の背景にあるのは、デザイナーが「仕事を待ってしまう」存在から脱して、主体的に事業や社会に貢献するように動くことの重要性です。その点については下記の2つの記事で掘り下げていますので、ぜひご覧ください。
