
◆読書日記.《三島由紀夫『金閣寺』》
※本稿は某SNSに2020年4月11~12日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
三島由紀夫『金閣寺』読了。ああ、面白かった。
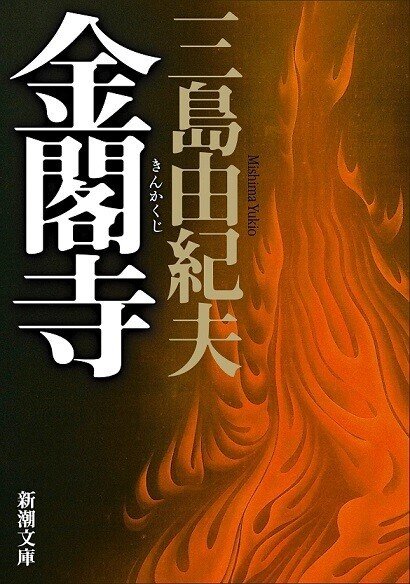
当初はもっとぱっぱと読み飛ばせるかと思っていたのだが、思った以上に文体が美しくてじっくりと味わいたくなり、その上頭でっかちな思想性が濃厚な感じも自分好みで、更には主人公の異常心理を最近ハマり始めたフロイト的な精神分析したくなって時間がかかってしまった(笑)。
しかし、さすがは三島由紀夫、当たり前だが改めて文章が巧え。
娯楽文学の姿勢が強い『命売ります』なんかはぱっぱと読めたし、20代前半の作品である『仮面の告白』もサラリと読めたが、本作は、読み飛ばせない。三島の中では最もぼくが好きなタイプの作品かもしれない。
しかも、本書が書かれたのが三島31歳の折との事。31歳でこの文章は凄いな。
『仮面の告白』の時は若干語彙の選び方に若さを感じたものだが、本作ではほぼ違和感が感じられないどっしりとした風格を備えている。
三島は本作の風格を醸成させるためにかなり鹿爪らしい語彙をしばしば入れ込んでいるようだ。これは既に本作ではかなり自家薬籠中の物としているようで、ある種の老練ささえ感じる。
改めて今回思ったのは、三島の文体は猫科の猛獣のようにしなやかで柔軟、そして力強いという事。グイグイと引っ張ってくるが、決してバランスを崩さない。体幹がしっかりしている文体なのだろう。
そしてやはりその理知的な文体はどの作品にも共通しているようだ。
特に、本作の主人公は驚くべき頭でっかちだし、重要な脇役である「柏木」も、独自の哲学を語る頭でっかちな人物だ。
こういう濃厚な思想性というのは、文体の風格も相まってぼくには特に好もしいものに思える。
あと、三島の文体はかなりセクシーなんじゃないかと思う事が多い。
実際に、男性に向けられる視線は時々粘っこくて情熱的になるのが「ああ、この人らしいなあ」と思う。
◆◆◆
本作は昭和25年7月1日に実際に起こった金閣寺の放火事件に取材し、その犯人が自分の金閣寺放火に至るまでの人生をふり返って告白している体で書かれた小説。
但し、主人公の名前と実際の放火事件の犯人の名前は一緒ではないし、その行いも微妙に差異がある。
実際の放火犯は、金閣を放火した後、カルモチンを飲んでから腹を切って自殺未遂となったが、本作の主人公は放火後も自殺しようとせず、持っていたカルモチンと小刀を谷底に投げ捨てて「生きようと私は思った」と告白する。
現実に起こった事件と本作の内容との、この微妙な差異は何なのだろうか?
三島は本作を実際に起こった事件に取材して、「外枠」については実際に起こった事をかなり細かくなぞって描いてはいるが、彼はこの事件の「真実」を推理したかったのではなく、あくまでこの事件の形式に仮託して自分の美学とテーマを追及したかったのではなかろうか。
そう思った理由の一つは、本作があまりに三島好みのテーマが詰まっているという事である。
というのも本作には、性的マイノリティである事の呪詛や自己へのコンプレックスの複雑な怨嗟が渦巻いており、その昇華としての「独自の美」への情熱的な傾倒が見え、それらが頑固な思想性へと収斂している、という特徴があるからだ。
◆◆◆
本書の重要なモチーフの一つは「エロス」ではないかと思っている。
これはフロイトの言う「エロス」だし、哲学家の竹田青嗣氏がよく主張している「エロス」の事だ。ニーチェだったら「力」というだろうが、本書は「美学」を扱っている点、フロイト的ではなかろうか。
本書の主人公はしばしば「美」について語り、しばしば己の「性」に関わる逸話を話し、己のコンプレックスを告白する。
ぼくは、これら「美」「性」「コンプレックス」をフロイト的「エロス」という欲動論によって解釈する事で、それら全てのヴェクトルが「金閣寺」へと向かう主人公の学僧の欲動として纏め上げられる事が出来ると思った。
まず、本作の主人公の欲動の性対象は、明らかに「金閣寺」に固着していると言えるだろう。
念のため、ここで言う「性対象」というのは「性欲を湧かせる対象」ではない。もっと大まかに「エロス」的なものだ。もっと言えば「他者へと向かおうとする欲望のヴェクトル」のようなもの。本来ならば、男の子の性対象はまず母に固着し、そこから各種の反抗期を経て他の異性に向かうという形で発展していく。
少年のエロスは父との同一化によって母へとむけられるが、彼は「父の真横で不倫していた母」という形式で、そのヴェクトルを拒絶される。
行き場を失った主人公の欲動は父へと逆戻りする。父への同一化によって主人公の欲動はどこへ向かうのか?
父は主人公が幼い頃からしばしば金閣寺の美しさについて語っていた。そこが手掛かりとなる。
主人公は、親友の鶴川から「君が金閣がとても好きなのは、あれを見ると、お父さんを思い出すからなのかい? たとえばお父さんが金閣がとても好きだった、というようなわけで」と尋ねた際「半分当たっている」と述懐している。
本来母へと向かう欲動の行き場を失った主人公のリビドーは、同一化する父を通して金閣寺へ流れたのではないか。
彼は、父以外に性対象を向かわせるべき相手がいなかった。
本来、少年が憧れるべき「美」の対象であり、大抵の少年のリビドーの対象となるべき美少女(=有為子)にも、本作の主人公は「何よ。吃りのくせに」と蔑まれて、拒絶をくらってしまう。同級生らにも吃り癖を馬鹿にされて孤立してしまう。母ですら、既に自分の万全の性対象から外されてしまった。
彼の欲動は行き場を失い、父への同一化の段階で固着し、そこから父の欲動を辿って「金閣寺」へ流れ込む。そこから先へは展開できない。だから主人公の欲動は「金閣寺」に頑固に固着してしまった。
というシナリオが、ぼくなりの「『金閣寺』の主人公の精神分析」だ。彼の欲動は母からも女性からも周囲の男連中からも拒絶され、同一化した父が亡くなった事で決定的に「金閣寺」に固着してしまう。
その後、彼が柏木と共に行った遊山の際「下宿の娘」と愛の営みをしようとする直前に「金閣寺」の幻想が彼を阻む。そして、かつて憧れた花のお師匠様が衣を剥ぎ、乳房を露わにした瞬間、乳房が金閣寺に変貌した。
ここでは彼の中で明らかに「性」=「美」=「金閣寺」となっている構図が読み取れる。
彼の吃り癖のコンプレックスによる社会からの疎外感が、余計に彼を「金閣寺」に固執させる。これが本作の深層心理的構図なのではなかろうか。
エロスの性対象が「金閣寺」に固着した彼の運命は、やがて金閣寺を炎上させる事となる。
女性との愛の営みが「金閣寺」への思いのあまり二度に渡ってみじめに挫折してしまった主人公は「ほとんど呪詛に近い調子」で、「いつかきっとお前を支配してやる。二度と私の邪魔をしに来ないように、いつかは必ずお前をわがものにしてやるぞ」と、金閣寺に向かって荒々しく呼びかけるのである。
「憎し恋し」なのであろう。彼はアイドルを付け狙うストーカーのように金閣寺への憎悪を露わにする。
金閣寺の老師への侮蔑、母への反発、そして、唯一の自分の親友だと思っていた人物が、自分とは全く関係のない理由で自殺し、自分が全く彼の心から隔離していた事に気づいた時、主人公は決定的に「美的なものはもう僕にとっては怨敵なんだ」と己の呪詛を明らかに宣言する。
かくて金閣炎上は確定した。
◆◆◆
本作は主人公と柏木との心理と思想の対比が実に面白く、その部分も本作の白眉だったと思える。
世間から蔑まれ、拒絶され、自己を正当化できないほどのコンプレックスを抱き孤立している者というのは、ある意味「自己が従属すべき世界を喪失している」と言える。
自分だけが、世間から外れ、仲間に入れてもらえず、世間に馴染めない。自分を優しく飽和してくれる世間から、自分が拒絶されている。
そんな「世界喪失」の体験は、自分を否応なく責め立てるのである。
笠井潔は『テロルの現象学』で、本作の主人公や柏木のような自己へのコンプレックスの複雑な怨嗟をこじらせている人物がテロリズムに傾倒していってしまう心理を「世界喪失の体験による観念的自己回復」として説明している。
本作で「柏木」は、主人公に対してこう述懐している。
「この世界を変貌させるものは認識だと。いいかね、他のものは何一つ世界を変えないのだ。認識だけが、世界を不変のまま、そのままの状態で、変貌させるんだ。認識の目から見れば、世界は永久に不変であり、そうして永久に変貌するんだ」――三島由紀夫『金閣寺』より
私たちを拒絶する世界は、確固として変わらない。だが、それを変化させる手段はあるのだ。
世界は変わらないまま、おのれの認識のみを変える。これが笠井潔の主張していた「観念的自己回復」であろう。
テロリスト的心理は「世界に馴染めない私は間違った人間だ」を裏返して「私を馴染めなくする世界のほうが間違っているのだ」にする。
これをフロイト的に説明するならば、他者に対して求めようとする欲動を拒絶される事で、そのベクトルは行き場を失い、欲動を自己へ撤収させてしまう。
つまりナルシシズム的な自己執着へと向かわせ、自分を愛し、守ろうとする欲動となる。
自己を守ろうとする自我は、自己を否定する他者や世界を否定する事となる。
本作の「柏木」の場合は、そのナルシシズム的な欲動の流れが、自分の劣等感の発信地である「足」に流れ、そこで固着する。
だから彼は、自分の「足」は人より劣っていて自分を貶めるものではなく、これこそが自分の個性であり自分にしかない特質であり、だからこそ他者はこの「足」を愛さねばならないと考えるようになる。
本作を読んでいると「柏木」は明らかに自分の「内翻足」をナルシシズムの欲動の流れる先にして、そこに己のリビドーが固着しているのが分かる。
彼は観念的に自分のコンプレックスを裏返したのだ。
どうあっても自分の「内翻足」は変わらない。であれば、「内翻足」に関するおのれの観念を変えれば救われる、と。そういう心理へと移行したのだ。
「己の内翻足は他者より劣っているのではない、己のこの内翻足こそが他者よりも優れた資質なのだ」と、――物理的には何一つ変わっていないのだが、彼は「観念的に自己回復」したのである。
だが、本書の主人公は、柏木のように認識を変える事はついぞできなかったのである。
「世界を変貌させるものは認識だ」と主張する柏木に「世界を変貌させるのは行為なんだ」と主人公は反論する。
己を拒絶した世界への呪詛は、かくして「具体的な行為」へと結実していくこととなる。主人公は、この「具体的な行為」によって、世界を変貌させることを望んだのである。
ぼくが思うに、本書に出て来る「柏木」は、半分三島自身の思想を仮託して造形されているのではないだろうか。
戦前戦直後の時代はまだ「ホモセクシュアル」に偏見の強い時代であった。
そういった時代にあって三島自身が性的マイノリティである自身の性癖や病弱な体質に対して強いコンプレックスを抱いていた。
そのコンプレックスはやがて三島の中でナルシシズムに逆転し、己の肉体を鍛え上げて自分の理想像に近づける事で、性的欲動を自身へ回収してしまった。
この辺のプロセスは「柏木」が、己のコンプレックスを裏返す事で、自身の欲動を「足」のほうへナルシスティックに回収してしまった心理との類似性を思わせる。
ぼくが思うに、本書の主人公の「動機」は、三島による「こうであったのではないか?」という推理ではなく、あくまで「こうであって欲しい」という願望だったのではないかとも思うのだ。
思えば、「儚く燃え落ちてしまう金閣寺」というのは、それだけで既に完璧に美しい事件である。三島好み、と言ってもいいだろう。
その美的犯罪を行った犯人の「動機」が、軽薄で、思い付きで、くだらないものであってほしくない。本作は、そういう三島の願いのようなものだったのではなかろうか。
思うに、しみじみ「美」というものは危険なものである。美は「善」でも「悪」でもない。そして、そのどちらでもあるのに、人を魅惑させる。
「美」と「倫理」は、関係ないのである。
例えば、20世紀初頭にイタリアを中心にして起こった美術運動である未来派は、「動き」や「機械」や「スピード」の「美」を評価しようという運動だったのだが、これらに深く関連するものとして「戦争」を称賛していた芸術運動でもあったことで有名だ。
つまり「戦争」も「美しい」のである。
だが、もはや現代の歴史を学んだ人間として「戦争は善だ」などと言う人間はほぼいないだろう。もっと分かり易く言えば、ジェット戦闘機はかっこいいし、戦車も文句なくかっこいい。だが、だからと言ってこれらが「倫理的に良い物だ」ということにはならない。
つまり、「美」は、それが例え「良い物」であっても「悪い物」であっても人びとを魅了してしまうのである。
だから「美」は危険なのだ。
本書の主人公も「美」に溺れ、「美」で挫折し、「美」を破壊する事で、自らも破滅する運命に至った。本書はそういった「危険な美の物語」としても優れたテーマを持っているとも思えるのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
