
◆読書日記.《カート・セリグマン『魔法―その歴史と正体』》
※本稿は某SNSに2020年12月4日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
カート・セリグマン『魔法―その歴史と正体』読了。
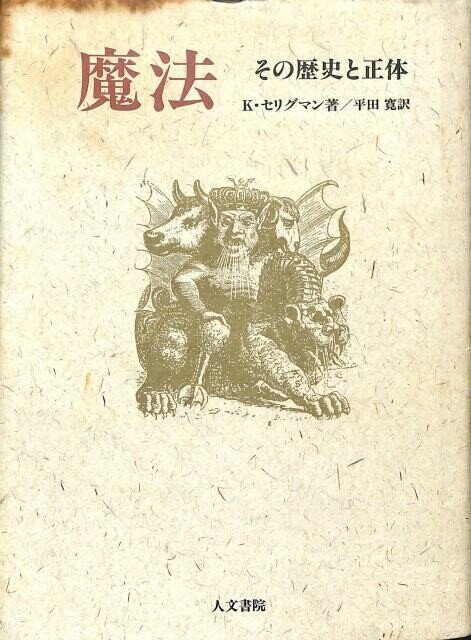
予想以上に読むのに時間かかってしまった! まずボリュームが予想以上にあるので物理的に長い!
二段組の上に450頁超の分量。ちょっと油断していたなぁ。あと、この著者の書き方も時間がかかっている原因のひとつになってるんだよなあ。
この本を読んでいてぼくが「魔術」や「呪術」のどこに興味を惹かれるのか薄っすら見えてきたようにも思える。
ぼくはそういった魔術を信じてしまう人のメンタリティであったりだとか、魔術や呪術の体系的な理屈のようなものに興味を惹かれているようなのである。
分野で言うと心理学や人類学だろうか。
最近はそういう観点からのオカルト分析に面白味を感じるようだ。
だからユングのオカルトの心理学というものにも興味を惹かれる。
という事で、本書もしばしばそういった興味を中心に読んでいるので、いちいち自分で定義づけや概要まとめなどをしなければ納得できない。だが、いちいちそういう事を読者の側でしなければならないくらい、本書の内容はけっこう散文的にできていると思う。
この人はたぶん、けっこうな説明下手なんじゃないだろうか。
歴史を説明するのに、「流れ」が全く見えてこない。文体自体は平明なのにもかかわらず、こまごまとした細事を並べていくので、そういった文脈や大意を把握するのに結構時間がかかってしまうのだ。
何というか、読む前にイメージしていた「入門書」や「解説書」といった感じの読み物ではなく、膨大な「魔術に関する膨大なエピソード集」といった感じ。
気が付くと、全く内容が頭に入ってない事に気付いて何ページも戻って読み直さなきゃならなかったりする。……と、なかなか一筋縄ではいかない読書になってしまった。
しかし、本書に書いてある事は間違いなくレア情報ばかりで、この内容はしっかりと血肉にしていきたいとは思うので、疎かにもできないんで、ここでしっかり本書の内容を総括しておこう。
※なお、以下の文章内における「魔術」「呪術」「魔法」の記述については、ほとんど意味の区別はしていませんので、ほとんど同内容の言葉だと捉えてください。
<古代ギリシア哲学者の魔術的世界観>
カート・セリグマンによれば、古代ギリシアの哲学者は全て呪術が実在している事を信じていたのだという。
ヘラクレイトスはおろかタレス、クセノフォン、ソクラテスに至るまで古代ギリシアの知識人は、魔術的世界観から逃れられなかったのである。
本書の中でセリグマンは「プラトンの世界は、呪術的なものである」と言っている。
「その世界は統一され、すべての事物が相互に関係づけられているからである。宇宙は、霊魂と精神とを賦与された一匹の動物である」
この「宇宙動物」には手も足も目も耳もなく、完全な形である「球形」をしていると考えられていた。
ぼくが昔読んだプラトンの主著『国家』でも、ラストが死後の世界について論じたオカルト論議で締めくくられていたのでちょっとびっくりしたのを覚えている。
そういった話もしていたためか、ギリシアの哲学者たちはオリエントの賢者らと同じように一般人からは呪術師のようなものだと信じられていたのだそうだ。
ソクラテスなどは、未来のことについて彼に告げてくれるダイモニオン(精霊)がついていると言われていたという。
ソクラテスの精霊については「返答が肯定か否定かによって、右向きか左向きのくしゃみで答えたという」や「ソクラテスのダイモニオン(精霊)はだれの目にも見えたと言っている」等とソクラテスの精霊についての論争は18世紀まで続いていたのだそうだ。
ネアズ『ソクラテスのダイモニオンまたは占いに関する小論(1782年)』には、ソクラテスは「ダイモニオン」という言葉を、単に自分の「未来予測の才能」を記述するために使っていた言葉だと結論付けているそうなのだが、ぼくもその辺りが正解ではないかと思う。
<古代エジプト呪術にみられるプロトコールと言葉の呪術性について>
本書によれば、エジプトで行われていた呪術で中心をなしていたのは、チベット密教と同じく「死」であったという。
死後、人間はどのような世界を見て、どのような体験をし、そしてその中で酷い結末を迎えないためにどういう行動をしなければならないのか。
それを教えるのが、エジプトのパピルスに刻まれた『死者の書』であった。エジプト神話では、冥府に赴いた死者はオシリスによって心臓を天秤にかけられ、永遠の生命を得るか、罪によって罰せられるか判定される。
エジプトの神官は、その時に行われる冥府の審判者らの判定の目を逃れる様々なノウハウをパピルスに刻み付けていたのだ。
――調査官にはこう答えるように。
「我は常に悪を避けたり。飢える者にはパンを、渇ける者には水を、裸の者には衣類を、座礁したる者には船を、与えたり。孤児には父親となり、やもめには夫となり、宿なしには家を与えたり」
このような"カンペ"を暗唱する事で、自分に有利な判決を得られると信じられていたそうだ。
エジプト『死者の書』には、「アニ」という名の書記生が死後、どのように冥府を旅し、偉大なるオシリスと一体となったかというサクセス・ストーリーが記載されているという。
金も資産も持って行けない冥府で力を持つのは、ある決まった「言葉」のようである。アニは言葉によって近づく悪霊を追い払っているのだ。
アニは冥府に流れる川に行き、渡し守に対して船に乗せてもらうように頼む際にも、ある決まったプロトコールを踏まねばならないらしい。
「おお、なんじ神秘の小舟の守護者よ、われ急げり、いざ、いざ。ここにきたりしは、わが父オシリスに会うためなり」と老年の渡し守に訴えかける。
すると小舟の胴体が「わが名を言え」と言ってくる。
「汝の名は闇なり」。次に帆柱が「わが名をいえ」と言う。
「汝の名は偉大なる女神をその行く先に導くのなり」
最後に帆が言う。
「わが名を言え」。
「汝の名は天の女神ヌイトなり」
――この一連のやりとりを完遂させる事で渡し守のサービスが受けられる。
この一連の流れは、ぼくにはしばしばWebサーヴィスを連想させられる。
ぼくらがWebアプリ等を利用する際、彼らはぼくらに「汝の名は?」と聞いてくる。
われわれはそこで予め決められたパスワードやユーザ名を示す等という一連のやりとりを完遂させる事によって、彼らのサーヴィスの恩恵に預かっているのである。
このように具体的な「言葉」が呪術的な力を持つ、というのは本邦の「言霊」信仰だけでなく世界でしばしば見られる事である。
エジプト人は生まれると名前を二つ与えられたという。「真実の名前とよい名前」だとか「大きい名前と小さい名前」だとかいうものだ。小さな名前は公にしても問題ないが自分の「真実の名前」を知られると、知られた相手によって自分が何かしらの影響を受けてしまう事を恐れたという。
『Fate/Stay Night』で言えば、サーヴァント名は明かしてもいいが、真名は明かしてはならない、というアレである。現代のSNSでも似たようなものだろう。
日本ではハンドル・ネームは公にしても問題ないが、本名を知られる事を恐れる人は多い。
確かに、言葉はある種の「力」を持つのは間違いのない事なのである。SNS上でも、悪辣な言葉を投げかける事で相手を自殺にまで追い込む事ができる。これを称して「呪い」と言う。
「呪い」の反対は「祝い」である。
つまり、実際に「言葉」は人を殺しもすれば、幸せにする事もできる「具体的な力」を持っているのである。
<秘術も呪術も科学も哲学も……昔はみんな異端思想>
錬金術というのもある意味「秘術」的なものでもあったので、ハッキリと確立された技術体系とはいいがたいものがあったのではないかとも思う。
初期錬金術の主要な書の著者名を並べると、イシス、マリア、クレオパトラといった……つまり「ペンネーム」を使っていた人ばかりだったようだ。
錬金術というのは大っぴらに宣伝できるようなものではなく、特にキリスト教が国教として固まっていた頃のローマでは、しばしばこういった術者は迫害されていた。
迫害されていたからこそ、著作にはしばしばペンネームが使われ、その技術に関する書についても分かり易く平明に解説される事もなく、なるべく象徴や寓意を用いて「分かっている人」にしか意味が通じないような書かれ方がされていたという。
こういう伝わり方が錬金術をより一層「秘術」的なものにしていった、と。
錬金術の重要な象徴物にはしばしば「自分の尾っぽを噛むヘビ」――ウロボロスが登場する。
このヘビは、『創世期』でアダムとイヴをそそのかして禁断の知恵の木の実を食べさせたあのヘビと同一視されている。このヘビはグノーシス派の「拝蛇教」の崇拝する蛇とも似たような意味合いを持ったヘビなわけである。
つまり『創世期』的に考えてグノーシス派のヘビというのは人間に知恵を与える慈悲深い動物だったわけだが、それはキリスト教的には異端思想だった。
例えば、聖アウグスティヌスも「知識および科学として知られている、無益で好奇的な研究欲」という表現で、こういった自然の法則を研究する事を批判している。
「錬金術は、呪術その他の不正な技術とともに、神の秘密をもらした呪われた天使たちによって、人類にもたらされた。かれらは、この不謹慎のために罰せられたのだった。そして人間を創造主と対抗できるようにした禁断の知識には、呪いがかけられている(本文より)」というのが批判される理由だったようだ。
特に初期錬金術師たちは異教徒と同じような迫害を受けていたと言われている。
錬金術というのは科学/化学だけでなく思想・哲学、宗教、テクノロジー、呪術、魔術といった様々な要素が混沌とした未分化な状態のものだったので「異端」と思われたのも仕方ないことだったのかもしれない。
ガリレオが地動説を説いて宗教裁判にかけられたというのも、そういった「学問に対する胡散臭さ」という偏見が存在していたのかもしれない。
現在でこそ、錬金術は西洋の科学技術の前段階としての役割を持っていたという評価を得ているが、そういった科学的な考え方が受け入れられるまでには血を血で洗うような歴史を潜り抜けているのである。
<中世の魔女の正体に関して、そして、悪名高い魔女裁判に関して>
「魔女」というと西洋では18世紀辺りまで風の早さに乗って空を飛ぶことができると信じられていたそうだが、スーパーマンよろしく単身で飛んでいたわけではない。
一般に知られているのはホウキに乗って飛ぶ魔女の姿だが、他にも魔法をかけられた棒や杖、熊手、フォーク(藁を積む農機具)なんかにも乗っていた。
その他にも魔神論者のグアッツォは『悪行要論(1608年)』にて「翼のあるヤギ」に乗って飛ぶ魔女の姿を描いているという。
つまり魔女は器具だけでなく動物や怪物、悪魔のようなものにも乗って空を飛んでいたと言われていたのだそうだ。「ホウキ」というのは、かなり通俗化した魔女のイメージなのかもしれない。
魔女が空を飛ぶのは大抵が人知れず悪魔の宴会、黒ミサに出席するためだと考えられていた。
魔女の特徴は地方によってまちまちだが、だいたい一致しているのは空を飛ぶ前に魔女が「香油」を使うという事なのだそうだ。
深夜、決まった時間帯になると魔女は、悪魔が呼んでいると感じて暖炉のある部屋へ引き籠る。
そして魔女は人目につかない部屋の中で呪文を呟きながら全身に香油を擦り込み始める。
やがて彼女は暖炉から煙突を通って空へと飛びあがるのである。
毒性のある香油は脊柱に作用するそうで、そのために実際は空を飛んでいるのではなく、昏睡状態に入って悪魔の宴会に参加したという幻覚を見ているのだと思われる。
毒性のある香油の作用による高揚感で浮遊感を味わっている――それが「魔女は空を飛ぶ」という伝説の正体ではないかと思われるのである。
さて、広く知れ渡っている通り、西洋の中世暗黒時代には宗教裁判による魔女狩りが一種のトレンドとなっていた。これは魔女狩り自体が一種の産業化していたとも言える。
本書『魔法―その歴史と正体』によれば「この(魔女の)迫害を行うために、裁判官、獄吏、拷問吏、執行吏、指物師、書記その他の専門家を雇っていたので、裁判を廃止すれば、経済危機を引き起こしたであろう。自分の生計が迫害の仕事で維持されている事を知っている人々は、裁判の継続に関心を寄せていた」とある。
この時期の魔女狩り宗教裁判は「見せしめ」ではなく怖いもの見たさの「見世物」になってしまっていたという。
裁判は公開式で公共広場で行われ、役人や貴族が大勢集まって見物できる特別観覧席を設けていた。また食べ物を売る屋台や露店も出店しており、見物人はお土産やロザリオ、パンフなどを買う事ができたという。
こういうお祭り騒ぎの中で一日の内に数人の魔女が、時に百人以上の魔女が火あぶりにされたのだ。
これは厳粛な裁きではなく明らかな大衆娯楽であった。
教会が認可していない限り、民衆が主催の大衆娯楽は禁止されたが、この宗教裁判は当時の大衆にとって新たな娯楽を提供していたようである。
裁かれる「魔女/魔法使い」とされた人々は、古代宗教が神を葬送する儀式のように犠牲者を着飾らせたという。
例えば被疑者は厚紙の三重冠を被らされ、硫黄色のシャツを着、それらには悪魔や炎や燃える人の頭などが描かれていた。そこういった派手な格好で駕籠に入れられた被告は大衆の前で晒し者になったのである。
この「愉快な歓楽」を永久に続けて自分の家族を食わせていくために、拷問吏は永久に魔女を生産し続けるための各々様々なアイデアを取り入れていたそうだ。
拷問を受けるさい、魔女たちは共犯者の名前を告げるよう強制させられた。これによって一人の魔女から百も二百も裁判のタネが生み出されるようになったのである。
イエズス会士フリードリッヒ・フォン・シュペー(1591-1635)は次のように述べている。
「私は度々思うのだが、我々の誰もが魔法使いでないというただ一つの理由は、我々の誰もが拷問を受けなかったという事実による」
――拷問で厄介なのは拷問吏の望む答えは引き出せるが、ことの"真実"は永遠に引き出せないという点にある。
魔女発見人」という職業人は、一人の女性が有罪となる毎に20シリングの報酬を得ていたそうで、C・レストランジ・エヴァンの言によれば、さる魔女発見人は最終的に220名もの御婦人を火炙りに追い込んだと自白した後、絞首刑に処されたと言われている。
フィリップ・ファン・リムボルク(1633-1712)の『宗教裁判の歴史』には「人間の所信に関するこの奇怪な裁きは、知性を持たないで知的世界の支配権を握ろうとしている。それは、スペインを中世に固定しておくために、復活されるかもしれない」と予言し、事実それは復活した後にナポレオンが放棄するまで続いた。
西洋というのは科学についても戦争についても植民地競争にしても、良くも悪くも決定的な大破局に至るまで徹底的に突き詰めてそれを拡大していく傾向があるのかもしれない。
何しろ、この宗教裁判一つを取っても、少なくとも16世紀の初頭には「ヨーロッパの人口の半分が「異端」になった」というほどなのだから。
※以上に出てくる参考文献は全てカート・セリグマン『魔法―その歴史と正体』の孫引きにによります。
<民衆の貞操観念と魔術について>
本書によれば、古代宗教による儀式であった「豊穣を願う性的な儀式」といったものは中世ではキリスト教の神聖な法に基づいて厳しく処されたのだそうだ。
だが、そういった乱婚といったものについては、貴族や聖職者といった人たちと、農民たちとでは認識が違っていたらしい。
何しろ当時の農民は領主らから「嫉妬してはいけない」という風に教え込まれていたので、貴族が農民の妻や娘を欲しがれば、求められるまま拒む事ができなかった。
夜会に出席して乱交を行う農民たちというのは、互いに楽しみを分かち合い、何でも分かち与え合える良い仲間たちといった認識でいたようだ。
当時のキリスト教会システムというのはミシェル・フーコーが言う様に、告解によって民衆の「心」にまで監視網を広げ、感情までも監視下に置こうと欲していた。
そういった抑圧権力に対して農民の抑え込まれた不満が、土地に古くから根付いている古い風習と結びついたからこそのサバトや魔女の存在だったのだろう。
悪魔礼拝というのは、キリスト教の儀式と全く関係のない独自のものというわけではなく、それはしばしば「キリスト教儀式のパロディ」という形式を取った。
例えば参加者は司祭の尻に接吻をしたり、悪魔の指でもって新参者の眉の下に印をつける事でキリスト教の洗礼を無効化するという儀式を行っていた。
こういったサバトや悪魔の宴会でのキリスト教のパロディ的儀式というのが「教会権力への反発」からなるキリスト教を笑い飛ばす動機が隠されていたと考えるのは、さほど不自然な事はないだろう。
西洋では、農民は高圧的な権力を逃れて地元の伝統的な風習に自由や解放感を感じていたとも考えられるのである。
日本でも農村部では乱交や乱婚といった風習は明治あたりまで残っていたという証言がある。
これについては赤松啓介が『夜這いの民俗学・夜這いの性愛論』で詳しく論じているのでそちらをご参照願いたい。
「大和撫子の貞操観念」などというものは、あくまで「武家社会の倫理観」であって日本の伝統的な性意識ではないのである。
つまり、乱婚や乱交をふしだらだとする倫理観というのは、西洋でも日本でも、元々貴族や聖職者や武士など支配階級の理屈であって、一般社会の普遍的な感覚ではなかった、といった所だったのではなかろうか。
所詮「女性の貞操」などという性認識は、単に男権社会特有の女性の専有化システムが覇権をとったという文化の一形態でしかないのだろう。
<オカルティスト・ノストラダムスは当時の進歩的知識人だった>
本書には、魔術師や占星術師などオカルティストを紹介する章が設けられているのだが、この章の中にちょっと興味を引く人物の名前を見つけた。
ノストラダムス(ミシェル・ド・ノートル=ダム)である。彼は20世紀末には終末論者に利用されたが、西洋では昔ながらの予言者だった。
彼の名前がアグリッパやパラケルススの名前と共に載せられていると、何だか妙にしっくり馴染んでいるようで面白い。
西洋では既に紀元前の昔から中世辺りまで予言者と呼ばれる人物が存在していたのだ。
予言者はキリスト教が国教になってから迫害されてきたのだが、ただし「当たる予言者」については別もの、と考えられていた面もあり、実際にノストラダムスはフランス王妃カトリーヌ・ド・メディシス等の王族や貴族などからもてはやされていたとも言われている。
だが、ノストラダムスはオカルティストの面だけではなく、ちゃんと知識人として活躍していたのを見逃してはならない。
彼はモンペリエの大学で医学の勉強をしており、その在学中に各地のペスト撲滅を助けて成果を上げている。
フランス国王のシャルル9世からは「常任侍医兼顧問」に任命されるほどであったという。また化粧品や香料、ジャムを作る方法などについての本も出していて、それはしばしば重版されたともいう。
つまり、彼は医学だけでなく料理研究家でもあり、薬草や鉱物の知識に精通していた薬学者でもあった。
オカルティストというと非科学的な人物と思われがちだが、中世に限ってはそうとも言えないようなのだ。
例えば魔術研究はラテン語やギリシャ語、アラビア語等の本を読まねばならないために語学ができねばならなかった。
占星術師のベースとなる知識は天文学に繋がっていくし、錬金術は哲学、化学、神学などが教養として求められていた。
逆に、その頃は哲学者も一般的には予言者や占星術師と同じようなイカガワシイ連中だと見られる事もあった。
中世というのはそういったように科学と非科学とか混沌としていた時代だったのだろう。
<魔術理論のロジックにも類感呪術の法則が適用できる>
魔術の理論というものは学術的なロジックと決して無縁ではない。
ぼくが強く興味を惹かれる著作にアグリッパの『隠秘哲学』がある。
アグリッパはこの著作で魔術を哲学や物理学、数学、神学などの理屈と統合して整合性のある学問として体系化を試みている。
西洋の科学的な考え方というのは、神はこの世をちゃんと整合性のある法則によってかっちりと作り上げている、という見方がベースになっているようなのだ。
地上の運動法則を研究する物理学は地上的な知であり、天体の動きを計る形而上学的な学問である数学は天上の知、そして神学は原型的な知を司っていると考えられた。
「隠秘的=オカルティック」というのは、一般には知られていない「隠された法則」を利用しようとするからこそ隠秘的なのであって「非科学的」という意味ではない。
西洋中世では科学と非科学の境界が混とんとしていたために、両者を区別せずに一学問体系として体系化する思想が出てもおかしくはなかったのだ。
この隠秘的な法則には面白い事に、フレイザー卿が定義した呪術の「類似の法則」がアグリッパのロジックにも残っている部分が見られるのである。
「例えば、地上の火は天上の火を刺激し、目は目を治療し、不妊は不妊を作る。だから生贄の火は神聖な火または光に反応し、蛙の目は人間の盲目を治療しラバの尿は女性を不妊にする。類似した事物の間には一致があるように、敵対している事物の間には不一致がある。例えば、経験から分かるように、向日葵と太陽の間には一致があるが、ライオンと雄鶏の間には、ちょうどゾウとハツカネズミの間のように、敵対がある(本文より引用)」といった感じで類感呪術が生きている。
オカルティズムの万物照応的なロジックには、こういったような類似の法則のロジックが遠く影響を及ぼしているようなのだ。
占星術も似たようなロジックを持っていて、天体の動きは地上の動きと無関係ではないというのがこの占いの理屈なのだ。
そこには、天上というものは神のおわす座であるからして、地上にあるものは天上にあるものに従うというロジックが存在している。
だから「星の位置関係=星座の形」が地上的なものの形の象徴をなしているわけである。例えば「人馬宮は、この星座の効力を下方にもたらすから、人馬宮の護符を馬につけると馬の幸福が保証される。それは、馬と人馬宮は類似しているからである(本文より引用)」という。
このようにアグリッパの『隠秘哲学』には様々な事象を統一された学問として体系化しようという情熱が見られるのが面白いのだが、そこにオカルト的なロジックが組み込まれている所になお一層興味を惹かれるのである。
<『魔法―その歴史と正体』総評>
カート・セリグマン『魔法―その歴史と正体』読了。
主に西洋世界での魔法の歴史を紹介すると共に、その他錬金術、悪魔、魔女、カバラ、悪魔の儀式など、魔法に関わるトピックスを細々紹介していく事によって古代から続いてきた西洋の魔術的思考の正体を探っていく「魔法概論」であり「魔法史」でもある一冊。
著者のカート・セリグマンはオカルティストでもなければ人類学者でもない。
20世紀前半のシュルレアリストであり美術評論家であり、美術史家であった。つまり、著者は「魔法」については「、魔術的画像イメージ」の興味から入っていると思われる。
事実、本書には200点にも及ぶ図版が挿入されている。
"シュルレアリスムの法王"アンドレ・ブルトンにも「魔術」という見方でもって美術史を構築しなおす『魔術的芸術』という美術史書があるくらいだから、元々シュルレアリスムと魔術は縁薄い考え方ではないのだ。
また、シュルレアリスム的に言うならば、造形芸術は古代から魔術的思考でもって発生し発展してきたと言う見方も取れるのである。
「ものの形を写しとる」という事はフレイザー卿の言う所の類感呪術の発想と無関係ではないし、ラスコー壁画のように狩りの成功を祈願して獲物が狩られる様子を描いたと思われる絵画も残っている。古代人は多かれ少なかれ、このような呪術的思考を持っていたのだ。
このような呪術的思考というものは、長い期間人類と切っても切れない関係を保ってきた。
人間は全てを合理的に捉える事などできないし、非科学的な考えを捨て去る事も未だに出来ていないのである。
神の存在を信じる科学者というのは欧米には現在も沢山いるし、逆に科学もしばしば宗教に利用される。
西洋では中世から長い事呪術や占いを禁じ、魔術師や魔女を迫害してきたが、これは「非科学的」だから迫害したのではない。
「異教的」であり「異端」であり、「非キリスト教的」であるから迫害されていたのであり、魔法が否定されていたのは非科学的だと言う理由ではなかったのだ。
魔法はほぼ近代までは否定しきれずに生存していたと言えるだろう。
啓蒙主義時代が来てさえ、科学は超常現象の全てを非科学的なものと断ずる事はできなかった。
それは証明されていないだけで、正体を捉えれば実証する事の出来る未知の自然法則なのではないのか?――という可能性を最近まで否定しきれなかったのだ。
逆に、こういう事も言えるのかもしれない――人間は生まれながらに科学的思考を持っているわけではない、科学的思考は学ばなければ身につける事ができず、また科学的思考を学んで身につけるまでは、人は呪術的思考から逃れる事ができない――つまり、人間の原初的な思考は呪術的なのではなかろうかと。
本書にも次のように書かれている。
「心理学者ジャン・ピアジェによれば、どんな人間も六、七歳までは、太古の人びとや現代の未開人と同じような信仰と習慣を持つ呪術的な世界に生きているという」
あらゆる古代人が呪術的な思考や呪術的な世界に生きていたという事は人類学が証明している所ではなかろうか。
つまり、呪術的思考というものは太古の昔から現在に至るまで我々の原初の思考感覚を司っており、科学的思考はその圏内から脱するために「訓練」が必要なものであって、自然に身につくものではない。
考えれば科学的思考とは、呪術的思考と比べればその歴史は驚くほど短く、人類全体の歴史から比べれば、それはまだ始まったばかりとさえ言えないだろうか。
また、そんな科学的思考と呪術的思考というものは、まったく水と油という関係ではなかったという事が本書を読んでいると分かってくる。
科学的思考と呪術的思考は元々一緒のもので混沌としており、時代を経るごとに科学的思考が徐々に呪術的思考の圏内から分離していったという歴史があったと言えるだろう。
錬金術は様々な化学のためのノウハウを用意し、魔術は実証実験をするための刺激剤となった。
魔術を学ぶために、魔術師はあらゆる学問を渉猟し、中世では神学徒とは違ったスタンスの知識人であった。
因みに、本書の翻訳者である平田寛は西洋科学史が専門の学者であり、その分野の興味から本書を訳したと記している。
つまり、人間の歴史の中で魔法は広い意味で科学であったし、科学も広い意味で魔法であったという歴史があるのだ。
そう考えて行けば、本書のような「魔法の歴史」というものは実は「西洋"裏"科学史」でもあったという興味深い事実が浮かび上がってくる。
本書は、そういう見方も許容するだけの書き方をしているのである。
つまりカート・セリグマンは本書において魔法をオカルティスト的な「信じるスタンス」で書いているのではなく、一定の距離を置いてその細々としたエピソードを紹介しているのである。
それが、本書が長く読まれ続けている要因の一つなのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
