
◆読書日記.《フリードリヒ・ヴィルヘルム・ニーチェ『道徳の系譜学』――シリーズ"ニーチェ入門"16冊目》
※本稿は某SNSに2021年8月11日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
フリードリヒ・ヴィルヘルム・ニーチェ『道徳の系譜学』(光文社古典新訳文庫版)読了。
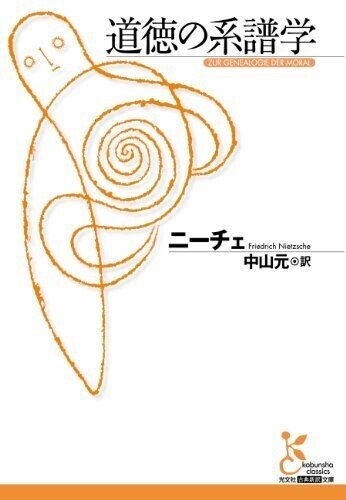
ニーチェにしては珍しい「論文形式」の著作。ニーチェの著書はほぼアフォリズム形式で書かれたものばかりで論文形式のものは本書と『悲劇の誕生』のたった2冊しか存在していない。
『悲劇の誕生』は処女出版だったという事もあるだろうが、本書はわりと晩年のほうの著作。
なぜその時期にわざわざ自分のスタイルを変更して論文形式にしたかと言うと……ニーチェが自ら主著と任じていた『ツァラトゥストラ』が、ほぼ周囲からの理解が得られず、そのある種「解説書」として書いたからだった。
『ツァラトゥストラ』は以前もレビューした通り、ゾロアスター教の教祖であるツァラトゥストラを主人公とした物語的な形式を採っており、その中に寓意、寓話、象徴詩、歌詞、説教劇等々の様々な要素を詰め込んだ、ニーチェの著作の中でも非常に特殊なスタイルで書かれた思想書であった。
ニーチェは自信を持っていた『ツァラトゥストラ』が空振りに終わったために、それと同じ内容の著作を、今度は得意のアフォリズム形式で書く事にした。
それが『ツァラトゥストラ』の次に出版した『善悪の彼岸』であった。更にそれでも理解が得られなかったために更に同内容を論文形式にしたのが本書だったのだ。
「ニーチェの解説書はニーチェを読むのが良い」と言われる理由の一端がここにある。
ニーチェは自分の主張を幾度も形を変えて表現していたのである。
◆◆◆
という事で本書の内容である。本書はニーチェが今まで主張してきた西洋の伝統的な考え方を転倒させるための内容を三つの論文に分けて論じている。
その本書の第一論文が『「善と悪」と「良いと悪い」』である。
これは日常的に使っている「良い」と「悪い」という考え方を、その起源までさかのぼって「西洋は今まで何をもってして"良い"とし、何をもってして"悪い"と判断をしてきたのか」という事を明らかにして、その「価値判断」の内容をはっきりさせる事で、その意味を鋭く問うている。
「起源を問う」という方法はいかにも元文献学者であったニーチェらしい方法で、本書を読むと、ニーチェの批判方法はどうやらこの方法論が土台になっていると思わせられる。
ニーチェはまず「良い(グート)」という言葉の語源が同じ概念に由来しており、それから様々に派生していると説明している。
本書には「――どの言語でも、身分の高さを示す「高貴な」とか「気高い」という語が根本的な概念であり、そこから「精神的に高貴」で「気高い」という意味で、「精神的に高潔な」とか「精神的に特権を持つ」という意味で、「良い」という語が必然的に生まれてきたのである(本書P.39より)」とある。
ニーチェが想定する「良い」の起源を象徴する人物とは、そういった「高潔な」人物であった。
これはどういう事かと言えば、古代において高潔な人物とされる人物は、約束を守り、責任を自らに負ってそれを果たす人物であったというのだ。
つまり、人間の道徳の始まりは「約束する事のできる動物(本書P.97より)」から始まったというのである。
それを果たせない人間、約束を守るだけの能力がなく、責任を果たす事ができない人間というのは、その当時では社会的な役割を負う事ができず、そのために社会的「善」ではなかった。
守り、戦い、責務を果たす人間こそが「高潔」なわけで、そのためにそれができない人間が「悪い」となった。
ニーチェが言うには、そのために「悪い」という概念は「卑俗な」「賤民的な」「下層の」という意味から始まったとしている。
つまり、善悪は社会的ポジションから始まった。
社会的責務を果たす人間が、それをできない人間を支配し、管理し、違反する者を処罰するという立場にあって「良い」人間とされたのだ。
これが第一論文で主張されている「良い」と「悪い」の概念の起源であった。
◆◆◆
この古代的な支配-被支配構造は、社会が発展するに従って様々な歪みが生じる事になってくる。その一つが財産の不平等である。
この辺りから本書の内容は第二論文『「罪」「疚しい良心」およびこれに関連したその他の問題』に移ってくる。
社会が発展するに従って、民衆の中にも富の格差が生まれてくる事となる。
この時、社会に発生してきた不平等が債権者と債務者という不平等で、債権者は債務者に対して<主人の権利>を行使する事ができた。
そこで「債務と抵当」という考え方が発生する事となる。
古代にあっては、返済ができない債務者に対して、債権者は「あらゆる種類の辱めや責め苦を加える事ができた(本書P.112より)」のだという。
例えば、シェイクスピアの『ヴェニスの商人』にあるように、債務者の負債に相当すると思われる量の「肉」を債務者から切り取る事ができたのだという(ちょうど先日見たアニメ『憂国のモリアーティ』18話にその逸話が出てきていた)。
約束を守れないほどの物覚えの"悪い"人間を、苦痛を与える事によって「矯正」したのだ。
人間の前史をつうじて、記憶術ほど恐ろしいもの、不気味なものはないのではないだろうか。「記憶に残るようにするためには、それを焼き付けるしかない。苦痛を与え続けるものだけが、記憶に残るのだ。(本書P.105より)
しかし、これらの処罰は、あくまで「罪」や「責任」という考え方からの理由で処罰されたのではなかったのである。
――むしろ現代でも親が〔怒りのために〕子供を罰するように、加害者がもたらした被害の大きさに対する怒りによって罰が加えられたのである。――しかしこの憤怒は、すべての損害にはそれを償う事のできる等価なものがあるはずであり、たとえば加害者に与える苦痛の大きさによって実際に埋め合わせる事ができるはずだという考え方のために制約され、加減されたのである。――損害と苦痛が等価であるという考え方はごく昔からある根深いものであり、おそらく今でも完全には根絶されえないものなのだが、この考え方はどこからのその力を手に入れたのだろうか? その秘密はすでにわたしが示唆してきた。それは債権者と債務者の契約関係からである。(本書P.110-111より)
ニーチェの考える「罪」や「疚しい心」の起源的なものというのは、この「債務と抵当」の関係から出てきたというのである。
「負い目(シュルト)」という道徳の主要概念の起源がこの「負債(シュルデン)」であった。
罪と罰の意識の元々の根本がこういった債務と抵当に関わる「報復」の感情にあったのである。
記憶が悪くて約束を守れず、また返済できる富も持たない「卑俗な」「賤民的な」「下層の」人間は「負い目(シュルト)」に苛まれる。
ニーチェが西洋の伝統的な道徳観念にある種のサディスティックな攻撃性を感じ取っていたのは、こういった(精神的にも、財務的にも)債務者である人間に対する「報復感情」が関係しているからなのである。
罪の重さに見合った「苦痛」や「苦悩」なんてものはない。「罪」は「苦悩」に翻訳する事はできないのである。
だが、それにもかかわらず――「苦悩はどうして「罪」を賠償するものとなりうるのだろうか?それは〔債務者に〕苦労を与える事で〔債権者は〕最高度の快感を得るからである(本書P.115より)」。
(ちなみに、現代日本でも刑法の「刑罰」を「罪に対する罰だ」という感覚で認識している人が良く見られ、重罪に対して厳罰化を声高に叫ぶ人たちがいるのも「刑罰」にこういったサディスティックな「快感」が伏在しているためであろう)
こういった債務や社会的責任といった領域の中に、ニーチェは「道徳」の起源を見るのである。
しかし、こういった恐怖と快感による社会発展は、奇妙な事に社会の成員の欲望をより抑圧する方向へと発展するのである。
社会の成員全員の欲望を叶えるようなシステムを作り上げるプロセスで、様々なルールや掟が作られて行き、それが逆説的に人間の欲望を抑え込んでしまうのである。
つまり、フロイト理論で言えば、人間の動物的な本能に「現実原則」がかけられる事で、根源的な欲望を抑えるようにコントロールされてしまうのである。抑え込まれた欲望は消滅したりはしない。他の噴出口を捜し、それがなければ遂に自分自身を責めるようになっていくわけである。
恨みつらみの内面化。
つまりはニーチェの言う「ルサンチマン」の発生であり、第二論文の言う所の「疚しい良心」もこのルサンチマンから発生するのである。
自らの欲望を最優先する事が「悪」となり、社会にとっての「善」が自分自身の欲望を攻撃する事となる。善と悪が転倒するわけである。
◆◆◆
ここから本書の内容は第三論文「禁欲の理想の意味するもの」に移行する。
「卑俗な」「賤民的な」「下層の」人間が、「高貴な」人間に抱くかもしれないある種の恨みつらみというものを自分自身に向けさせて、自分の欲望を抑え込む事を肯定するシステムが登場してくる。キリスト教とその使いの司牧者である。
既に社会の中に多くの「下層の」人間が存在するようになった時代、それらの人間たちが抱える欲求不満を自分自身へと向けさせる。
自分たちが不幸なのは直接的に自分たちに悪い事をする連中がいるからではないし、そういった人間たちに対して恨みつらみを向けるのは良くない事であるという考えを揺籃するのである。
やがて、弱い人々は自分たちを抑圧する勢力のイメージをキリスト教の「神」に結び付けていく事となる。
民衆は、不幸が襲い掛かるたびに自分が何かしら自分たちが神を裏切る行動をしたのではないかと自らの「良心」をチェックする。
司牧者は、そういった「罪」がないか民衆一人一人にチェックさせるために、自ら罪を告白させる。
キリスト教の司牧者たちは、そうやって民衆が自分の欲望を抑え込む事を「良い」事だとして肯定し「欲望を抑え込もうとする欲望」を教え込んでいくわけである。
弱い「下層の」人間たちは、強い者たちに抑圧されていたために、自分自身を肯定する方法を、他に知らなかったのである。
「禁欲的な理想」とは、このようにして出来上がっていく。
◆◆◆
――以上、ざっと見てきたように、ニーチェは西洋の様々な伝統的な価値観を批判するために、それぞれの概念が成立した時代まで遡って検討し、それが正当な概念だったのか?という事を西洋世界の人々に突き付けたわけである。
われわれがニーチェの著作を読んで「良心」や「道徳」を批判する言説に違和感を抱く事はしばしば起こりえる事ではあるが、それはニーチェがあくまで上述のように「諸々の西洋の伝統的な概念」を批判したからであり、その批判の根拠となるものはあくまで西洋の根っこにある古代ギリシア由来の概念だからなのである。
キリスト教の道徳を何故ニーチェは家畜道徳、奴隷道徳、卑俗な道徳であるかと考えた理由が、この論文には明確に記してある。
ニーチェはこれを「論理」ではなく、『ツァラトゥストラ』によってあくまでメタファーを用いて説明しようとしたのだ。
それはなぜかと言えば、ニーチェが行いたかったのは「説得」ではなくて、「意識変革」だったからだと言えるだろう。
おそらくニーチェは、西洋が長年かけて社会的に人々の意識に浸透させてきた「道徳」や「良心」といった基本的な概念を転倒させるには、もはや「頭で理解した」というレベルでは無理だと考えたのだ。
だからこそ「気づき」を促すメタファーであり、常識を脱臼させる「笑い」であり、「感性」に働きかける詩編の効果と言うものに期待したのである。
しかし、そういったニーチェの『ツァラトゥストラ』にかける望みは潰えた。
ニーチェは、自分の思想が皆に受け入れられるには次世紀を待たねばならないと言い、19世紀最後の年にこの世を去った。
――ニーチェの思想が後年、ハイデガー、フーコー、バタイユ、ローティ、はたまた三島由紀夫などと言った「20世紀」の様々な思想家に大きな影響を与えたのは周知のとおりである。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
