
私の発言 小舘 香椎子氏 光の幅広い応用の可能性を信じ,研究を通じた人材育成と成果の社会貢献(女子大発ベンチャービジネス)で次世代にバトンを渡す
日本女子大学 小舘 香椎子

東大で光に出会ったことが人生のターニングポイント
聞き手:まず,光学分野に興味を持ったきっかけについてお話しいただけますでしょうか。
小舘:私は中野区立桃園第三小学校で,戦後の民主教育を志向する教育熱心で人間味あふれる先生方から初等教育を受け,2年生の担任として平塚とし子先生(元中野区教育委員長)の明快な授業と強烈なリーダーシップに女性教師へのあこがれを抱きました。自然科学への関心も,4年生から始まった,専科の教師の工夫された教材による実験授業と東京都の理科指定校として,月1回の実験授業への参加の機会を得たことによって増しました。そして,受験・進学した日本女子大附属中学校,高等学校でも,女子のみでのびのびとかつ切磋琢磨しながら過ごした環境と理科好きが集まった科学クラブや原子力発電の原理などに関する自由研究で,自然科学,特に物理学への興味がさらに高められました。迷わずに進学した日本女子大学家政学部の理学科(物理専攻)には,わずか6名の同級生しかいませんでしたが,3年生の文化祭で,秋葉原での電子部品の買い出しから導波管の作製,伝送の実証実験まで,理論を学び,実現することができ,物づくりの楽しさを知りました。
卒業後,大学に残るようにと指導教授から誘いを受けましたが,なぜか助手の増員が見送られて結局,附属高校で物理の専任教諭として着任することになりました。高校教諭としての3年間は,とにかく全力投球で,女子が苦手な教科をわかりやすく楽しめる授業をと,それまで行われていなかった実験授業を取り入れるなどして心がけました。幸いにも,その年には,附属では初めてとなる10名を超える優秀な生徒たちが物理分野への進学を決め,その後の教師生活にいくばくかの自信となりました。3年間の高校教員生活の後に,今度こそ増員は確実ということで,退職願を出し,後任も決まった頃に約束されていた大学助手のポストがまたも流れてしまいました。まさに,働く場所を失ったのですが,幸い,心配してくださった女子大の先生の紹介で,東京大学工学部電子工学科の臨時雇用者として週3日の採用が内定しました。3月に入った頃,電子工学科で専任助手のポストが空き,至急後任を決めないとポストを没収されるので,助手採用の条件(教員経験者)を満たしているから,是非,専任助手の就任を引き受けてください,との夢のような連絡が主任教授からありました。振り返ると,これが,「研究者への道」に繋がる私の人生のターニングポイントでした。
そうして,幸いにもデバイス系の神山雅英先生の研究室に配属され,そこで初めて生涯の師と研究テーマとなる「光」に出会いました。神山先生は,理化学研究所で,原子分子の分光学の先端的研究を手掛けられ,電子工学科へ移られてからは,量子エレクトロニクスの研究に取り組んでおられました。この分野では,理学部の霜田光一研究室,生産技術研究所の斉藤成文研究室がすでにレーザー研究を始めていらしたのですが,神山研究室では,物理的手法を用いつつ,電子工学への適用を図ることを目指して,活発な研究が個性豊かな助手・大学院生達により行われていました。
私にとって特に幸運だったのは,この神山研究室で,その後,光量子エレクトロニクスの分野をリードする非常に優秀な若い研究者達との出会いに恵まれたことでした。神谷武志先生(東京大学名誉教授)は助教授として,伊澤達夫先生(千歳科学技術大学理事長),故 武藤準一郎先生(慶應義塾大学名誉教授),森川滝太郎先生(東洋大学名誉教授),故 氏原紀公雄先生(電気通信大学名誉教授),木村忠正先生(電気通信大学名誉教授)といった後の研究者が大学院生として机を並べ,助手の小林重昭氏らとルビーレーザー,ヘリウムネオンレーザー,アルゴンレーザー,炭酸ガスレーザー,半導体レーザーなどを手掛け,応用研究への模索が始まっていました。
それまで,光学を含めて,物理学の基礎も十分に学んで来ていなかった私は,キッテルの固体物理の英文購読の自主ゼミへの参加から,青木先生の電子物性論,小瀬先生の応用光学特論,小穴先生のレンズ設計論などの講義まで,院生の方々とともに参加しました。さらに,工作室で旋盤によるミラーホルダーなどの「装置作り」や,数値解析のためのプログラミングの習得など,研究創成の基礎をしっかりと学んだ中身の濃い貴重な5年間となりました。実際の研究ですが,神山研究室では,当時,レーザー応用研究も対象とされており,私は,その1つとしてレーザー光できれいな回折・干渉実験ができることから,X線回折を解明する2次元格子モデルを用いた光シミュレーションの実験からスタートし,X線回折像と対比しながら結晶構造の解析に適用しました。それが「一枚の写真」のコーナー(O plusE 1994年1月号)にも掲載していただいた「2次元格子模型のレーザー光による回折」です。
そして,この研究は「テーマとしてそう古くもなく応用分野もあり,競争相手がそう多くないという点で,子育て中の小舘さんに適している」と神山先生が勧めてくださった回折格子を用いた光計測の研究へと繋がることになりました。2枚の透過型回折格子を傾けて重ねるとできる粗い縞はモアレ縞としてよく知られていますが,周期格子の自己結像作用であるフーリエ・イメージ効果を取り入れ,フレネル領域で2枚の回折格子を横にずらすと周期的に透過光が点滅すること,また,そのコントラストは2枚の格子のギャップによって変化するという現象を見出して,精密変位計測器への適用の検討を行いました。さらに,独学でFORTRAN言語を学習し,数値計算によりコントラストを決める要因であるコヒーレンスを考慮した理論式を導きました。このテーマは,物理工学科から赴任された神谷武志先生に興味を持っていただき,私が日本女子大に教員として戻った後も継続して,ご指導いただきながら,長期に渡って携わることとなりました。結果的には,1970年代のマイクロオプティクスの黎明期から,回折光学素子の応用を目指した基礎研究に関わってきたことになります。また,回折格子をテーマとする科研費の総合研究や光エレクトロニクスの特定研究に参加をさせていただく機会も得て,まとまった額の研究費と活力ある研究の手法を学ぶことができました。こうしてみると,大変長いつながりではありますが,私の光との出会いは,たまたま東大の電子工学科の専任助手のポストが空くというチャンスを得て,先端的なレーザー研究をやっている研究室に配属されたときになるのです。
聞き手:運命的な,導かれるままに歩んでいたら「光に出会った」という感じですね。
小舘:そうですね。それに,神山先生のご指導は,こういうことをやらなければ駄目だという枠組みが全然ありませんでした。「自由な発想で大いにやりなさい」と,非常に個を尊重してくださいました。同時に,独自性のある研究を築いて,仲間として認めてもらうための覚悟と努力が必要とされていると感じました。一方,給与をもらっている助手の立場の私が,月謝を払っている院生の方たちに教えてもらえる環境にいることへの感謝が,前向きになれた1つの要因でもあり,なににも増して,研究室での「光の研究」は,際限のない興味の宝庫で,楽しい時間でした。そして,1970年,30歳のときに,ようやく初めての論文がJJAPに採択され,研究者としては非常に遅いスタートだったと言えると思います。
この後,この2重回折法の精度向上のために,設計,作製を行い,それらを用いた精密変位計測実験と数値解析など,当時の作製技術の向上による微細化などを含めたテーマを深く追求し,1981年に自分の予想より早い段階で博士論文をまとめることができました。博士号を取ってやっと一人前という世界ですから,その年も大きな区切り,新たなスタートとなりました。
回折光学素子は,半導体レーザーの実用化に伴い,デバイス作製技術の高性能化と大型コンピュータの出現による設計技術の高度化などと相まって,小型デバイスとしての応用分野が広まり,新しいアイデアによる設計・作製・システム応用があり,競争の多い興味深い分野となっていきました。神山先生に勧めていただいた時には想定されていなかった展開でした。ただ,おかげさまで,研究テーマに困るようなことはまったくなく,光相関法によるパターン認識,アレイ導波路型回折格子を用いた分光センサー,すばる望遠鏡用分散素子グリズムの開発,ホログラフィック光メモリ,厳密結合理論による微細回折格子の解析などの研究開発を研究室の学生たちと展開することができました。まさに,神山先生から教えていただいた「流行を追うのではなく,自分で考え,実行することが道を拓く」,その言葉通り,回折光学素子の研究を自分なりに全うすることができたと,感謝の気持ちを込めて,書籍にもまとめました(写真参照)。
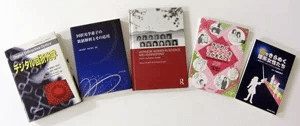
研究も子育ても両方継続していたら,ロールモデルに
聞き手:小舘先生は研究をしながら,育児も同時にしていらっしゃったのですよね。

小舘:私は神山研究室に助手として採用された年に結婚し,3人の子どものうち,長女,長男の2人は東大時代に出産しました。第2子の出産時には,神山先生に退職の相談をしました。すると「公務員の規定なのだから気にしないで休みなさい。子育てに協力してくれる環境にいるのに続けられないことはないでしょう。絶対無理と感じたときに考えなさい」と逆に励まされました。当時は実家に同居し,昼間は母に育児を頼んでいましたが,小児ぜんそくの長女の通院や家事,育児と自分の時間とのバランス作りなど,仕事をもつ女性なら誰でもぶつかる悩みを抱えていました。神山先生に背中を押されて初めて,この恵まれた環境を活かしていこうと決意したところがあったと思います。先生は,50年前の当時,極めて先進的な素晴らしい男性指導者,メンターだったと思います。光と出会って,研究室の指導者と若い研究者に囲まれて,自分の光の研究が,ゆっくりではあるものの,仲間に入れていただきながら,少しずつステップアップを図ることができたのです。
ですから,その後,母校に戻って自分の研究室をもった後も,似たような環境作り,つまり,学生たちが研究を楽しく続けていけるような環境を,ということは常に心がけていました。そのことも影響しているのかと思いますが,研究室の卒業生たちは非常に仲が良くて,何かといっては卒業後の今でも集まっています。それに,結婚して子育てをしていても,ほとんどの方が仕事を辞めていませんね。「先生が子育ても仕事も両方やっていたのだから,私たちもできる」と思うようです。意識して,というほどではなかったのですが,気が付いたらロールモデルにもなっていたのかもしれません。
聞き手:お集まりになると,お子さんの話でも盛り上がりそうですね。
小舘:最近では,子連れの集まりも多く(次頁写真参照),外で会う際には,会場の中に子供たちの遊び場も用意してもらっています。子育ての悩み,ワーク・ライフ・バランスのとり方,職場の課題などを話して,集まるたびにすごく元気が出たと言って帰っていきます。光関連分野から離れた職場の人たちでも,光をベースにして,学部・修士時代などに一緒にみんなで連携しながら研究をやった,ということが現在のすごいパワーになっているようです。
その意味でも光ってすごいですよね。やっぱり光の持つ明るさも影響していると思いますし,目に見えるものだから,ビジュアルに訴えるし,パワーになるようです。人や社会というものは移ろいもあり,とらえどころがないものだけれど,光も含めた自然現象や生物や物質は違うでしょう。サイエンスはほとんどの成果の追試ができて,立証が可能ですから,これほど確たるものはありません。それに,領域はキリがないくらいに幅広くて,探求したいことはたくさん出てきます。
私が1つ誇りに感じているのは,130人を超える理系女性が,小舘研究室から卒業していったということです。家政学部には博士課程がなかったので,1992年に理学部ができて,小舘研究室から博士号をとって巣立ったのは4名だけですが,それ以前から,東工大,早稲田大,豊田工大などの大学院に進んだ卒業生が,10人ほど学位をとっています。ですから,全部で14名,修士の学位は30名,これだけの人数の光分野の女性研究者を育成できたということは,光に出会ったからこそでしょう。アカデミアでは,2名が教授,3名が准教授となっています。
人間関係が難しくても,光の研究に集中できる環境と温かいサポートが救いとなった

聞き手:東大での5年間の研究を含め,研究されていく中でご苦労されたエピソードなどございましたらお話しいただけますでしょうか。周りの方にご相談なさって,すぐに解決できてしまったのでしょうか。
小舘:いやいや,そんなことはないです。非常に順調にきたような感じをお持ちかもしれないのですが,5年間東大に行って勉強して,東大紛争もあったので,研究に対する考え方や姿勢,研究の社会貢献のあり方や価値観など,生き方も含めて議論しながら,女子大にいた時よりも明確なビジョンを持つことができたと思います。ただ,母校に戻った後は,とても大変な経験もしました。日本女子大は非常に歴史のある大学ですから,上下関係にも厳しく,何かにつけて生意気になって戻ってきた,と思われたようです。
特に,昇任人事において,そのことが顕著に現れました。母体となっている「物理」では,相変わらずの年功序列型の人事体制であるのに対して,ポスト拡大の駒として所属させられた「一般教育」教授会は,業績主体の人事体制でしたので,この間に齟齬が生まれたようです。一般教育の先生方は,「小舘さんはこんなに論文があるのだから,早く助教授に昇任したほうがいい」と推してくださったのですが,物理では,「まだ先輩が助教授に上がれていないのに,あなたを先に上げるわけにはいかない」と言われました。それでも出した昇任自体は,全学教授会でも認められたのですが,今度は…今でいうパワハラですね。その後7年間は,物理の卒論の担当からはずされてしまったのです。
とにかく,研究や教育の前に,こうした独特の「人間関係」に悩まされました。でも,「暗幕の中の定盤とレーザー光」の物で形づくる空間が大きな救いとなりました。難しく考えることはやめ,研究を第一に頑張るのみと決めた時には,「一般教育」所属の先生方を始め,数学など学問・研究に理解のある先生方の存在をより強く認識して,落ち着いて自分の研究成果を上げる環境を得ることができました。また,引き続き共同研究を進めてくださった東大の神谷先生は,回折光学素子に関心がある中国人留学生2人も一緒に研究をやったらいいよ,とご紹介下さいました。卒業生も研究生として戻ってきてくれて,一緒に実験データを上げたりするような時代もあったのです。そして,東大や企業の研究所などと共同研究をすることで,寸断することなく,研究を続け,成果を上げることができました。こういう事実を知っている方は非常に少ないと思います。
それから7年後には,卒論生が戻ってきて2年目頃に,ぜひ光をやりたい,ホログラフィーは面白いし,光の研究を卒論からこの研究室でやりたいと,学生たちが集まりだして,ようやく日本女子大で光の拠点をつくるような環境が見え始めてきました。そうして,1992年に向けて理学部を設立するための委員に推薦されました。東大で学位も取り,研究業績も充分でしたから,物理分野の存続を託されるように「小舘さん頑張ってね」と急に周りも変わってきました。ある種の時代の流れ,タイミングもあったでしょうか。
光のバトンをリレーする女性研究者の育成
聞き手:女性研究者の育成については,どのように推進なさいましたか?
小舘:私が教授に昇格したときに神山先生は,「これからは女性研究者育成を頑張ってほしい」とおっしゃいました。辞めないで継続しなさいと励ましてくださった先生から,今度はあなたが次世代を育てる番だと,はなむけの言葉をくださり,とてもありがたく受け止めました。そして,先ほど述べた通り,退職までに小舘研究室から光のバトンを受け取れるドクターたちを14人出すことができました。
勤務する大学以外でも,女性研究者の啓発と育成を図るような会を作りたいと考えていたところ,一岡芳樹先生(大阪大学名誉教授)に背中を押していただき,1993年にコンテンポラリー・オプティクス研究グループを日本光学会の中にスタートさせたことも大きな意味があったと思います。
そして,その会をベースにして,応用物理学会が2001年に女性研究者ネットワーク準備委員会を設立し,さらに,2002年に大規模学会として初めて男女共同参画委員会が理事会の承認を得て発足しました。ですから,男女共同参画の活動の初めの一歩として,実は日本光学会が非常に大きな役割を果たしているのです。
私は,応物の初代委員長として,副委員長の遠山嘉一さん,事務局次長の伊藤香代子さとともに,理工系分野を横断する男女共同参画学協会連絡会の設立に貢献しました。設立後は,応物学会が初代の事務局を担当しましたので,その委員長として,20,000人から回答を得た大規模なアンケート調査を実施し,理系女性の研究環境や男女共同参画に対する実態を明らかにするとともに,さまざまな施策へ繋がる端緒を切り拓いていきました。この活動が,2006年からの文部科学省の女性研究者支援事業の開始にも繋がっています。政府のこの支援事業は,内容や焦点に変更はありましたが,現在も継続されています。また,初年度に採択された日本女子大学の「女性研究者マルチキャリアパス支援モデル事業」のプロジェクトリーダーを務め,2011年からは電気通信大学で特任教授として,女性研究者支援事業コーデネータを務めています。なお,2008年からの6年間は,当時の故 北澤宏一理事長の要請を受けて,JST(科学技術振興機構)の男女共同参画主監として,女性研究者を取り巻く課題解決やすそ野の拡大に向けて,ロールモデル集の発行などの活動を展開しました。
また,退職時の基金などをもとにして,女性としては初めて副会長を務めた応用物理学会に賞(女性研研究者業績・人材育成賞(小舘賞))も創設(2009年)しました。学会活動を通じて顕著な研究業績を上げた女性研究者・技術者,そして,女性研究者の人材育成に貢献することで科学技術の発展に寄与した男性も含んだ上司が対象です。学会は,大学だけではなく,企業もつなぐリサーチ・コミュニティが集う場所ですので,そこで女性研究者をサポートする制度作りをしていくことはとても大切だと思っています。
このように,研究生活の終盤には,女性研究者支援を中心とする人材育成が活動の柱の1つとなっていました。現在,浜松ホトニクス(株)の社外取締役もやらせていただいているのですが,浜ホトでも,女性同士のネットワークをしっかり作ろうということで,女子会を立ち上げて,これまでも数回実施しています。やはり,卒業生の会とも共通するのですが,こういうネットワークは大切ですね。欠席者も少なく,「次回が楽しみ」という方が多いようです。
大学の研究成果をもとに,社会貢献を(大学発ベンチャーを起業)

小舘:私は,いま株式会社Photonic System Solutions(PSS),電通大学認定ベンチャーの会長を務めています(20016年まで代表取締役)。そこにつながる研究の基盤は,女子大在籍時に始めた光相関システムの研究でした。最初はJTC(Joint Transform Correlation)という光相関システムを組んで顔認証の研究を始めました。その後,新たな光相関アルゴリズムの研究とホログラフィック大容量ディスクを融合させ,NEDOなどの支援を受け,日本で初めて自動・小型光相関コンピュータ(FARCO)を構築しました。現在も,渡邊研究室(電通大)では,実用機の実現に向けての開発を進めています。
インターネットの普及と共に,WEB上で配信される画像や動画,音楽ファイル,音声データなどのデジタルコンテンツの需要が増大しています。特に,動画共有サイトの利用は人気の広がりを見せている一方で,違法アップロード・ダウンロードによる著作権侵害が大きな問題にもなっています。本来は,これらの認証には,FARCOを適用するのが,大容量・超高速の特徴を発揮できるので望ましいのですが,残念ながら実運用化にはもう少し時間がかかります。そこで,PSSでは,光相関演算システムFARCOの画像識別アルゴリズムの部分を応用し,検索対象となる登録動画からWEB上の動画を自動検索するソフトウェア「自動動画識別による著作権管理システム(FReCs:Fast Recognition Correlation System)」を開発しました。このシステムは,長時間大容量動画に対応でき,例えば,30分アニメ番組で1本約0.7秒,52本で約1.6秒と高速照合が可能となっています。
PSSでは,2008年度に経済産業省による「自動動画識別技術を用いた海賊版実態調査研究」を受託し,FReCsを用いて海賊版動画の実態をWEBサイト名とともに具体的な 数値として示しました。また,設立から現在までに,経済産業省や総務省などの国のプロジェクトに加えて,TV局など延べ50社を超える事業者にサービスを実施しています。
このPSSの設立により,研究成果の特許を維持し,これまでの光の研究成果を社会還元することができました。資本金860万円の小さなベンチャーですが,この9月で第12期になり,昨年は,10周年を関係者と共に祝うこともできました。女子大からスタートした小規模ベンチャーで,10年間継続できたことは,素晴らしいことで,関係各位のご支援に改めて感謝したいと思っています。今後も地道な活動の積み重ねで,より社会貢献ができる課題に取り組みたいと考えています。
そんなわけで,私が現在力を入れているのは,人材育成と研究の発展形としてのベンチャーを通じた研究成果の社会還元といえるかと思います。
いたるところにある光を自分の興味につないでいくのが大事
聞き手:女性研究者に向けてメッセージをお願いします。
小舘:「きらめくチャンスをつかまえて!」という本を次男との共著で出版しています(前述の写真,右から2番目参照)。和書の前に,イギリスのRoutledge社から洋書を出したのですが,この執筆作業は,ロンドン大でPhDを取って,現在はアイルランドのダブリンで国立大学の教員をしている次男と,専門分野を越えて,協力して行いました。彼は小さい頃,女子大の研究室にもしばしば,連れていっていたので,「僕は半分ぐらい女子大で育ったかな」と言っています。現在,専門は比較社会政策という分野ですので,日本の女性になぜ研究者が非常に少ないのか,特に理工系分野が世界的にも際立って少ないことに関心を持ち,私とディスカッションをしながら,執筆しました。女性の理工系研究者の歴史から,日本の政策転換に至った背景や政策のこれまでの効果,我々が行ったアンケート調査結果などをまとめたものです。和書の方は,洋書の翻訳というよりも,女子高生やそういった年ごろのお子さんをお持ちのご両親にも読んでいただければ,ということで新たに書いたものになりましたが,小舘研究室の卒業生や学会関係者にも,キャリアパスを書いていただくなどご協力いただきました。
メッセージを,ということですが,女性は粘り強く,仕事が丁寧です。そういうところは理工系に不向きどころか,むしろ向いていると思います。それに,あきらめなければ未来は開けます。興味をもち,楽しみながら自己研鑽を継続し,前向きに進んでいってください。そして,ゆっくりとした歩みでいいから継続をしてください。研究のなかで「己の場」を創る努力と同時に,連携する大事な機会を得るために,仲間を大事に励まし合いながら,共に生きる環境を創る努力をすることが大事だと思います。今をつかんで明日につなげていってほしい,リレーをしていってほしいと思っています。
電通大の渡邊研究室からは,すでに今年3月に博士号を取得し,公立大の助教になった卒業生が生まれました。つまり,早いもので,私から見て3代目がもう育っているのです。「光」というテーマは研究対象がつきないところが本当に魅力です。
女性研究者に対しても,今がチャンスであると感じています。日本では,専門性をもち働く女性や理工系に進む女性の割合は,世界的にみてもまだまだ少ない状況です。少子高齢化もあるので,大学を含む教育界,学会,産業界,さらに政府と,理工系女性の支援体制を築く努力が推進されています。それでも,女性の研究者はまだ全体の15.7%で,先進国の中では最低レベルです。ただし,トレンドを見ると,日本の女性研究者数(実数)の推移は増加を続けていて,平成29年3月31日現在,14万4,100人で,過去最多を更新しています。研究者に占める女性の割合を2020年に20%とすることが目標なので,達成できるように様々な取り組みが進んでいけば,と願っています。もちろん,数が増えればいいというだけではなく,(研究やリーダーシップ,個人個人が能力を発揮できたり,満足できるという生活の)質もとても大切です。
そこで,男性の皆様には,女性研究者の育成と環境構築のために男性研究者にかけるのと同じ程度の支援やサポートをお願いしたいと思います。次世代を担う若者を育成する新しいイノベーション構築の場を作って,きらめく人材の宝庫を次の代へとつなげていくことがとても大切です。私自身も神山先生のような師に出会うことができましたが,本人だけではなくて,周りの支援が欠かせません。特に子育てをしているときなどは,理解や具体的なサポートもですが,精神的なサポートも必要です。今すでに指導的立場にある女性研究者たちともぜひ連携しながら,未来の研究者育成にご尽力いただきたいと思います。
(OplusE 2018年9・10月号掲載。肩書などは掲載当時の情報です)
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
