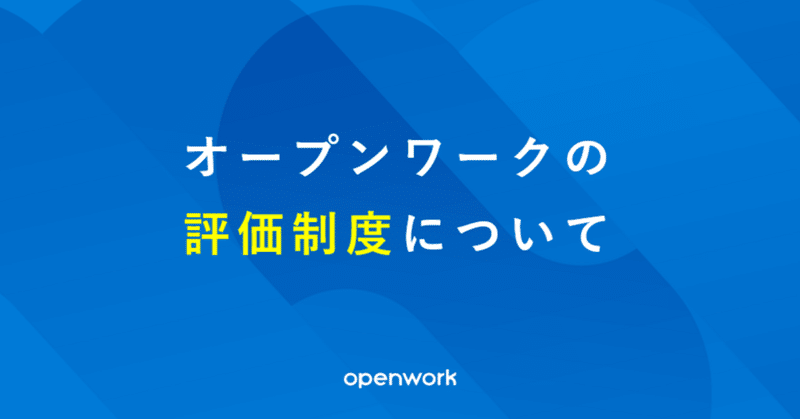
オープンワークの評価制度について
こんにちは!オープンワーク人事兼note 編集部の松元です。
今回は、オープンワークの評価制度についてご説明いたします。
選考でもよく質問を頂くこともあり、どんな流れでどんな意図を持って、評価制度を運用しているのか少しでも参考になればと思います。
オープンワークの人事制度について
オープンワークの人事制度は、行動指針を定めた「Action style」の体現を最大化できるような制度設計を行っています。
また、人事制度に基づく等級制度・評価制度・報酬制度の仕組みが確認できるハンドブックを社内に公開しています。
人事制度の全体像は下記の通りです。

今回は人事制度の中でも評価制度に焦点を当てて、ご紹介します。
評価制度の全体像
オープンワークの評価制度には大きく2つの目的があります。
①評価に応じて、報酬へ反映させること
②評価基準を明確に設定し、個々人へのフィードバックを通じて成長を引き出すこと
評価サイクルは3カ月で設計しています。フィードバックサイクルを高速で回すことにより、個人の成長を最大化することを目的にしています。
全体像はこちら。

期初に行うのは目標設定面談です。
評価ではいかに納得感を持てるかが大切だと考えています。そのため、まずは自身で目標を設定する運用となっています。そのうえで「等級スキルに見合った目標を設定ができているか」「成長を促す目標となっているか」といった観点で上長とすり合わせる運用となっています。
その後、期中に上長と1on1を通じて目標の進捗確認・軌道修正を実施。
期末時には、「評価面談」を行います。まずメンバー自身が自己評価を行い、上長に目標達成度合いをプレゼンします。その上で上長が一次評価を付けて、各部署の役職者が集まる評価会議の場で最終的な評価が決まり、最終評価を伝える「フィードバック面談」を実施しています。
このサイクルが、オープンワークの評価の一連の流れとなっています。
何を評価しているのか
次に、何を評価しているのか簡単に紹介します。
オープンワークは「成果」と「行動」、2つの項目で目標を立て、評価をつけています。

「成果」に対しては、MBO方式(組織とグループや個人の目標を関連付け、方向性をそろえるための目標設定方式)を採用し、全社のミッションや事業計画からブレイクダウンした目標を個別に設定して、評価を行っています。
「行動」については、自身の該当する等級定義に照らし合わせて目標を設定します。なお、等級定義は全10段階で設定しています。

評価は「成果」目標と「行動」目標を50%ずつ、それぞれ5段階でつけます。コミュニケーション頻度を高め、お互いの状況を把握できている状態を実現するため、目標の達成度を細かく反映できる設計としています。最終的に、各5段階の数値を足した数値が四半期の評価点になります。
報酬への反映について
こうして決定した個人評価を踏まえ、半年に一度、報酬に反映させています。
報酬の変動には3パターンあります。
①昇格:等級が上がる際に、月額報酬が上昇します。大きく月額報酬が上昇するのはこのパターンになりす。
②賞与:全社業績に加えて、個人評価に紐づいて、賞与が上昇します。
③昇給:等級が上がらない場合においても、個人評価に紐づいて昇給金額が決まっており、月額報酬が上昇します。

おわりに
最後までお読みいただきありがとうございました。
評価制度には完成がないと考えており、これからも制度を運用していく中でより良い形を模索していきたいと思います。
こちらの記事で少しでもオープンワークの評価制度についてイメージが沸いたら嬉しく思います。
