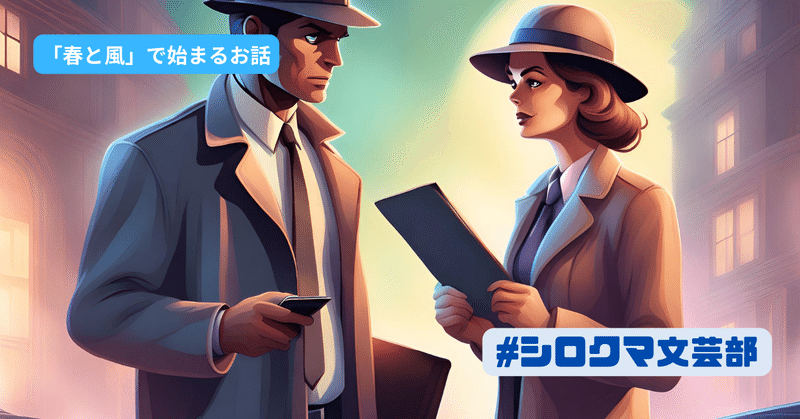
【短編】 見えてきた事実 #シロクマ文芸部
今回も前回の続きの短編に仕立てました。まだまだ終わりそうにありません。。。
春と風は切っても切れない縁がある。春一番が吹くと一気に暖かい空気が流れ込んでくるのだ。すでに今年も春一番が吹き荒れて、途端に暖かくなってきた。世の中は暖かい日差しを受け、コートを脱ぎ捨て春らしい明るい服装に変わろうとしていた。カップルが恋を語る季節に入ったのだ。
けれども世の中の暖かさとは裏腹に、青木真美はやるせない日々を送っていた。エーケーデザインを不本意ながら追い出された後、ドレスデザインの世界に戻れずにいたのだ。小早川日向が逮捕された後、エーケーデザインは窮地に陥ったようで、再三に渡り青木へ戻ってくれるように懇願していたようだった。しかし、信じていた人たちに見事に裏切られた真美は戻る気にはなれなかった。守と最後に約束したことは気になってはいたが、真美の心を奮い立たせることはなかった。結局エーケーデザインは、残留役員の中から代表が選出され表向きは体面を保ってはいたが、仕事の量は激減していった。
やはりトップデザイナーが存在していてこそのデザイン会社なのだ。次第に残った社員やパートも離れて行き、頭を抱えるばかりの経営陣に対し決定打になったのは、ロスのマークの会社からの発注が止まったことだった。マークは赤坂守の死を憂いていたが、青木真美が代表になるのなら信頼できると考え、取引を続行していたのだが、その青木が追い出されたと知り、会社内の確執を悟った。そして、発注を控えるようになっていき、さらに小早川日向が逮捕されたという情報が伝わると、完全に取引を停止することを決定したのだった。マークやジョンにしてみれば辛い決断だったのだろう。その後、青木真美と連絡をとることを継続して試みていたことがそれを物語っている。真美は再三にわたる電話やメールを受け取ってはいたが、守が創った会社を引き継いだ後を守りきれなかったことが申し訳なくて返信できずにいたのだった。
獄中の日向に会いに行った時は、精一杯の見栄をはり、思いの丈を日向にぶつけて帰ってきたのだが、全然スッキリとした気持ちにはならなかった。余計に気になり始めてしまったのだ。もしかしたら真美自身の日向に対する接し方が悪かったんじゃないかと悩んでしまうほどだった。真美は返信はできないものの、かろうじてジョンからのメールに支えられているところもあった。
『真美、もう守がいなくなって随分月日が流れたね。でも真美のデザインは順調にスキルを伸ばし、今では守に引けを取らないどころか、追い越しているといってもいいくらいだと思っているよ。日本ではいろんなことが起きているみたいだけど、もしどうしようもなくなったらロスに来て欲しい。君の才能をこのまま埋もれさせたくないから。それに、そろそろ直接会ってお互いを確認してもいいかなと最近思い始めてるんだ。守を心の底から支えてくれた真美に僕は会いたいな。その気になったら、返信をくれるとうれしいよ。気長に待っているから』
こんなメールが月に一度は真美のスマホに届いていた。真美はメールが届くと嬉しくて、ついつい笑みをこぼしながらメールをみるようになり、いつの間にかジョンからのメールを楽しみにするようにもなっていた。その度に、もう一度デザインをしたいという気持ちが昂るのだが、この十年間に起こった出来事を振り返るとなかなか戻る気にはなれなかったのである。まだ多少の蓄えがあるということが、切羽詰まった行動に走らなくてもいい状態だったのかもしれない。
渡口刑事と木下刑事は、青木真美が住んでいるマンションを訪問していた。赤坂守が入院していた時のことを確認するためだ。
渡口刑事がマンションの玄関扉の横にあるプレートで部屋番号を押す。ピンポーン。チャイムがなぜか悲しげな音に聞こえる。真美はインターフォンの画面を覗き込み、オートロックの玄関前にいる男性は見覚えのない顔だと思い、居留守を決め込んだ。しかし、執拗にチャイムは鳴らされ続け、終わることがないのかと思われるほど、連続して音を出していた。渡口は事前にベランダを確認し、人が動く姿を確認していたので、在宅しているのは間違いないと確信していた。最終的には真美の方が根負けして返事をしてしまった。
「はい。どちら様ですか。今、忙しいのでお帰りいただけますか」
「あ、切らないでください。私は、品川警察署の刑事です。これ、警察手帳です」
渡口と木下は、カメラの前に警察手帳を提示して、真美に見せた。見せられた真美の方が驚いてしまった。
「刑事さんが何の用なのでしょうか」
「実は、小早川日向さんのことで少し、お伺いしたいと思いまして、訪ねて来ました。少し、お時間をいただけないでしょうか」
「えっ、日向のこと。分かりました。お入りください」
真美はマンションの玄関のオートロックを解除し、二人をマンション内に招き入れた。真美の部屋の前に来たら、もう一度チャイムを鳴らすだろう。真美は鏡を見て簡単に身なりを整えて渡口たちを待った。真美の部屋の玄関のチャイムが鳴った。真美は一応覗き窓を確認し、先ほどの男性だということを確認してからドアロックをはずした。
「突然訪問してしまい申し訳ありません。少々お時間いただいてもよろしいでしょうか」
「はい。中へどうぞ。女性の刑事さんも一緒にいらっしゃるので私も安心です」
「あ、いや。私一人でも安心ですよ。なにしろ、真面目な警察官ですから」
「申し訳ありません。そんな意味ではなくて、最近、色々と事件も多いので、余計な不安を抱えたくないんです。そんな性格が時々煩わしくもありますけどね。申し訳ありませんが、部屋は狭いのでこちらでお願いします」
部屋に招き入れられて、短い廊下を歩いてダイニングテーブルがある場所に通された。それほど広い部屋ではない。見たところ間取りは2DKかなと渡口は思っていた。ソファを置くスペースは無いので二人用のダイニングテーブルに折りたたみ椅子を奥の部屋から真美は出してきた。マンション自体もオートロックはついているが、それほど新しくはないようだった。小さなテーブルを囲んで三人は座った。渡口刑事が率先して折りたたみ椅子に手をかけて座った。
「あ、その椅子は私が使いますからこちらをどうぞ」
「いやいや、お気遣いなく。座高の高い私が座れば会話もちょうどいい高さでできるでしょう、な、木下」
「はい、私もそう思います、フフ」
「申し訳ありません。訪ねてくる人はほとんどいないので、自分用の家具しかないので。コーヒーでも入れますね。緊張で喉もカラカラなので」
「あ、お気遣いなく。でも、できれば、私は濃いめに入れてもらえると嬉しいです」
「渡口刑事、全く遠慮というものがないですね。申し訳ありません」
「ふふふ、いえ、はっきり言っていただいた方が私も楽ですから。お湯は沸いてますのですぐに入れますね、濃いめのコーヒー」
渡口刑事は、また余計なひと言を言ってしまったかと思い、頭を掻きながら苦笑いしていた。そしてまた余計な一言で会話を始めた。
「青木さんは、売れっ子のデザイナーさんだと聞いていたのですが、割と質素な暮らしなんですね」
「ええ、贅沢は性に合わないもので。私自身、シングルマザーの母親に育てられたこともあり、生活に必要以上のモノは買わないようにしているんです。そのほうが楽ですから。シンプルライフが一番です」
「なるほど。確かにすっきりとして清潔感を感じます。物が少なければ埃も溜まりませんものね。おい、木下、お前も見習えよ」
「私に振らないでください。私の場合は、渡口刑事に引っ張り回されるから掃除する時間がないだけです。好きで汚くしているわけではありませんから。ねぇ、青木さん、ひどいでしょ、この先輩。何かあるごとに私をバカにするんですよ」
「バカになんかしてないよ。育てているんだよ」
「でも、お二人っていい関係なんですね。あ、変な意味じゃなくて。師弟関係というか」
「ありがとうございます。まぁ、そんなところです」
「私も赴任してから、ずっと渡口刑事の下なのですっかり慣れてしまいました」
「いいですね。私の師匠はもうこの世にはいないので、お二人が羨ましいです。はい、熱いうちにコーヒーをどうぞ」
真美は二人の刑事の屈託のないやりとりを見ていて、守と会社を立ち上げていた時のことを思い出していた。少しだけ涙で潤んだ目を木下刑事は見逃さなかった。
「青木さん、辛いことを思い出させてしまいましたか。ごめんなさい。でも、今日は思い出したくないことを質問するかもしれません。先に謝っておきます」
「あ、ごめんなさい。はい、お二人を見ていていいなって思ってたら、涙が勝手に出てしまいました。でも大丈夫です。今日は日向のことでいらっしゃったんですよね」
渡口刑事はコーヒーを味わうように二口ほど飲んで、話し始めた。
「私は、周りくどく言うのは好きではないので、単刀直入に言いますね。実は、小早川日向さんの裁判は判決が出てしまっていますが、小早川さんは犯人では無いのではないかと思っているんです。ただ、青木さん、あなたから地位や名誉を奪い取るために行った行動の根幹にある青木さんに対する小早川さんの恨みが勘違いではないかと私は考えているのです。もし、そうならば事実を小早川さんに伝えてあなたへの憎悪を解消してあげたいと思っているんです」
「何だか、刑事さんじゃなくて弁護士さんのようなことを言われるのですね。それに今更、勘違いだったと分かっても私としては何も変わりません。でも、日向が学生の時のように真っ直ぐに生きてくれるようになるのなら喜んで協力します」
「ありがとうございます。じゃあ、木下刑事、電話のことから確認しようか」
「そうですね。青木さん、実は古い話で辛い思い出だと思いますが、赤坂守さんが亡くなられた時のことをお伺いします。看護師さんから電話を受けて青木さんは病院に直行されましたよね。実はその時、電話をされた看護師さんは二回電話をされたそうなんです。最初の電話はこの番号だったそうですが、これは青木さんの携帯ではありませんか」
「えっ、はい、私の携帯です。そういえば、登録していない番号から着信が入っていたことに、かなり後になって気づきました。でも、そのまま忘れてしまいました」
「やはり、そうでしたか。看護師さんによると青木真美を最初から呼んで欲しいと頼まれていたそうなんです。もし、最初の番号で出なかったらと言うことで小早川さんの携帯の番号も伝えられたそうなんです。何れにしても、最後に会って手紙を渡したいのは青木さん、あなただったのですよね。それを小早川さんは自分の携帯にかかって来た電話を青木さんが黙ってとったことで青木さんを疑い始めたのだと思います。その時、青木さんはなぜ小早川さんの携帯に出てしまったのですか?」
「えーっと、あの時は確か、日向と私はドレスの生地のことで打ち合わせをしていた時だったと思います。日向が生地を取りに倉庫の方に行ったんです。その時、日向は携帯をテーブルの上に置きっぱなしにして行ったんですよ。そしたら、急に携帯に着信が入ったんです。普通なら人の携帯に出ることはないんですが、あの時は胸騒ぎがしたんです。出なければと何かに導かれる感じで。本当です。そしたら、看護師さんからでした。『青木真美さんに赤坂さんの病室に来るように伝えてください』と言われたので咄嗟に、私が青木真美ですと返事したら、『よかった。できるだけ早く来てください。危篤なんです』と言われ、着信履歴だけ消して日向には何も告げずに病院に直行しました。着信履歴を消したのは、日向が誤解するといけないなと思って無意識にやってしまいました。それが余計にいけなかったんですね」
真美もあの時の電話を鮮明に覚えていた。危篤だと言われ全てのことが頭から消え去り、自分のデスクに戻りバッグと携帯とコートをひったくるようにとってタクシーを拾ったのを覚えていたようだった。
「なるほど、看護師さんの証言も同じような内容でした。小早川さんが来てしまうと肝心なことを伝える前に自分の時間が尽きてしまうかもしれないと赤坂さんは心配していたと言うことでした」
「そうだったのですか。守さんは会社の存続が一番気になっていたんですね。自分の恋愛のことは二番目だったんですね。守さんらしいです。最後の力を振り絞って、私に会社を頼むと告げて逝ってしまいました。日向のように無邪気に泣くことができればどんなによかったか。守さんは、最後まで私の気持ちを知ることはなかったのかもしれません」
「私には男女のことはよく分かりませんけど、青木さんはあまりにも頼れる人だったんじゃないですか。男はちょっと弱いところを見せる女性にフラフラッとなるような気がしますけどね。まぁ、私のカミさんは今ではめちゃくちゃ怪獣みたいに強いですけど。あっ、またひと言多かった」
「そうだったのかも知れません。私は守さんの右腕になりたかったし、本当は生活のパートナーにもなりたかったというのが本音なんですけどね。あっ、私も余計なひと言を言ってしまいました。ごめんなさい」
当時のことを思い出し、宙を見つめるような仕草をしている真美に木下刑事が追加の確認をしてきた。
「赤坂守さんが亡くなる少し前、病室で口論みたいなことをされた記憶はありませんか」
「口論ですか。さぁ、特に無かったと思いますが」
「赤坂さんのお母さんも一緒にいらした時のようなんですが。社長交代とかの話題で口論というか大きな声を出したとかはどうですか」
「ああ、大きな声になったことはありました。守さんが私に、自分が亡くなったら株式会社にして社長をやってくれって頼まれたことはありました。その時は横でお母様が泣かれていました。私は、まだ生きている守さんを目の前にしてそんな事はできないと思い、社長代行はやるから元気になってくださいと言ったと思います。あの時は思わず感情が昂って大声になっていましたね。確か亡くなる数週間前だったと思います。その後焦って法人化のための役員決めなどを実施しましたから」
「あー、なるほど。社長交代じゃなくて社長代行だったんですね。なるほど、通りすがりに聞こえたとすれば勘違いしますね」
「えっ、誰かが聞いていたんですか」
「ええ、病室の前をちょうど通った看護師さんが聞いたらしく、ナースステーションでの噂話のネタにされたそうです。それが小早川さんの耳に届いたようです」
「そういえば、日向は叔父さんから教えてもらったようなことを言ってましたね」
「ええ、そおなんですよ。投資コンサルのおじさんがいて、どうやら、その叔父さんのお客様が看護師の中にいたようで、しっかりと聞いたわけじゃなく、噂のまま小早川日向さんに伝えてしまったようなんです。それで誤解をしてしまったんでしょうね。小さい頃から遊んでもらっていた叔父さんだったらしく、全てを信じてしまったのでしょう」
「そうだったんですか。でも、結局はそう受け取られても仕方がない行動を私がしていたってことなんですよね。どこかで守さんと付き合っている日向が羨ましかったし」
「でも誤解だとわかれば、青木さんも元の会社に戻れるのではないですか」
「いいえ、私はもう戻りません。人の心は一度離れてしまうと、取り繕う事はできると思いますけど、完全に元の信頼関係を取り戻すには時間がかかります。その時間は会社にとって最も重要なんです。おそらく私自身がその時間を使ってしまうことになるので、会社はその前に倒産してしまうでしょう。そうなれば、また恨みを買ってしまいます。そんな事はもうイヤですから、戻りません」
「そ、そうですか。ではこれからどうされるのですか」
「ゆっくりと考えたいと思っています。しばらく生活していく分には贅沢さえしなければ蓄えもありますから」
渡口刑事と木下刑事は、青木のしっかりした考え方を聞いて、仕返しのために小早川日向を陥れるようなことをする女性ではないと確信した。小早川日向は家持誠治の毒殺の罪が確定し収監されている。もし、日向が犯人でないとしたら、では誰が小早川日向のマンションに痕跡を残さず侵入することができたのかと言うことが疑問になる。渡口はそれとなく聞いてみた。
「そうですか。青木さんの気持ちと生き方はよく分かりました。私のような俗人には真似できない強い意志を持っておられるようです。もう一つ、今度は家持誠治さん殺害事件のことについて質問させてください。こっちの方も青木さんにとっては辛い経験だっと思いますが」
「ええ、顔から火が出るほど恥ずかしい経験でした。亡くなった家持誠治さんには悪いのですが、話術に優れた男の人の経験は私にはありませんでした。守さんもどちらかといえば口下手の方でしたから。なので、自分の違う面が開花したような錯覚だったんでしょうね。勉強代としてはあまりにも大きな代償でしたけれどね」
「家持誠治さんはチョコレートの中に注入された毒物が原因で死亡されたのですが、そのチョコレートは前日に小早川日向が作ったものでした。毒物も彼女の部屋から見つかっています。私には、そのこと自体が不自然に見えて仕方ないのです。仮説ですが、誰かが部屋の合鍵を持っていて、こっそりと小早川日向の部屋に入ることができたとすれば事情は変わってきます。小早川日向は冤罪だと言うことになるんです。警察としてはわざわざ冤罪を明るみに出すことを嫌うかも知れませんが、間違いなら正さなければなりません。そこで、お伺いしたいのは、合鍵を持っていた可能性がある人物を教えて欲しいということです。どなたか心当たりはありませんか」
にわかに青木真美の顔が曇った。真っ直ぐな性格だけに、すぐに顔に出てしまう。自ら、誰かを陥れることは嫌う真美だった。もし、軽はずみなことを言って仕舞えば迷惑をかけてしまうことになる。今回の自分が置かれている立場と同じになってしまうかも知れないと真美は考えて、即答できずにいた。そのことを見透かしたように渡口刑事はゆっくりと口を開いた。
「青木さん、あなたが思っている人物を口にされたとしても、我々は鵜呑みにするわけではありません。今回もあなたは誤解の末に被害に遭われたのですから、同じことを私たちがする訳にはいきません。ましてや、殺人という罪なのですから。ただ、もし小早川日向さんが罪を犯していないのであれば、なんとかして救出したいのです。そのことをよく考えてみてはくれませんか」
「そうですよね。ただ、私も確信はありません。あくまでも可能性の話です。そのことを踏まえて動いていただけるなら、私の知っていることをお伝えします」
「もちろんです。私もひと言多いくらい先走っちゃう性格ですが、こと仕事の操作に関しては一線を引いていますから」
「分かりました。では、お伝えします。実は、日向はあんな性格なので、守さんのお母様にはかなり嫌われていたんです。ことあるごとにお母様は、守の相手が私だったら良かったのにと愚痴をこぼされていました。最後の方は、日向と付き合ったことが守さんの体を酷使するようになったからガンを発症してしまったんだと本気で思っていらっしゃいました。私も何度も違いますよと言いましたが、お母様は取り憑かれたように『いいえ、あの女のせいで私の大切な一人息子の命は縮められたの、間違いないわ』と私と顔を合わせるたびに言ってらっしゃいました。最後の方は私も怖くなったほどです。でも、守さんが亡くなってから二年が経過し、お母様も忘れてくれたのかしらと思っていた時、突然、お母様から電話があったんです。『電話だと失礼だから、守と付き合っていた時に言えなかったお礼を言いたいので、自宅の住所を教えて欲しい』と言う内容でした。ちょっと悩みましたけれど、教えたんです。そのことは日向にも伝えておきました。でも、結局、お母様は訪問される事はなかったようです」
「もしかして、お母様は息子さんが持っていた合鍵を持っていて、その場所を知りたかったと言う事でしょうか」
「私にもよく分からないんですが、そうだったのかも知れません。でも、いざとなったら訪問する勇気がなかったのでしょうね」
「いや、もし、もしですよ。小早川日向に対する復讐心を持っていて、そのタイミングを狙っていたとしたらどうでしょうか。テレビでは青木さん、好きだったあなたを蹴落として地位を得た小早川日向が新しい男性と結婚宣言をしていた。青木さんまで苦しめたことを知って、復讐心が再燃したとしたら」
「でも、あの優しいお母様に毒薬を入手する事はできないのではないでしょうか」
なんとなく光が見えてきたように感じながらも、守の母親が実際に犯行を行なうには偶然や壁が多すぎると二人の刑事は感じていた。真美のマンションを後にした二人の刑事を、春の強い風が後押しするかのように後ろから吹いていた。
了
下記企画への応募作品です。
先週までの投稿
青写真、チョコレート、梅の花、閏年で始まる書き出し固定小説を、連続小説で
投稿しています。(古い順で掲載)
🌿【照葉の小説】ショートショート集 ← SSマガジンへのリンク
🌿てりはの電子書籍案内はこちら
🔶 🔶 🔶
いつも読んでいただきありがとうございます。
「てりは」のnoteへ初めての方は、こちらのホテルへもお越しください。
🌿サイトマップ-異次元ホテル照葉
よろしければサポートをお願いします。皆さんに提供できるものは「経験」と「創造」のみですが、小説やエッセイにしてあなたにお届けしたいと思っています。
