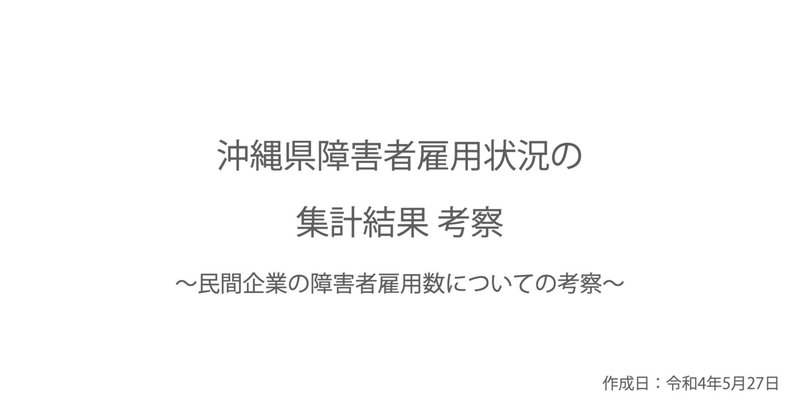
沖縄県障害者雇用状況の集計結果 考察
今回は沖縄県労働局が集計している「令和3年沖縄県内の障害者雇用状況の集計結果」を元に民間企業の障害者雇用数について考察をしてみたいと思います。
沖縄県の障害福祉サービスの現状も鑑みながら考えると様々な方向で考察できるのでいくつかのシリーズ化していたいと思います。
沖縄県の障害者雇用者数・実雇用率について

※実雇用率や法定雇用率ってなんですか?と思う方は以下をご参照ください。
障害者雇用における障害者の定義


沖縄県の実雇用率

規模別(従業員別)の障害者雇用状況


納付金(50,000円/月)の支払い義務の対象になる100.5人以上の企業の方が、100人未満の企業より法定雇用率達成企業割合が高いことがわかる。
(沖縄県は、500人以上企業が少ないため法定雇用率を達していない企業があると、その分達成割合が低くなりやすい。)
令和3年度 障害者雇用0人である企業数

納付金義務の対象とならない100人未満企業のでも、43.5人以上〜100.5人未満の雇用者数がいる企業は1人以上障害者を雇用しなければならないが、0人企業が9割以上となっている。
考察・見解

果たして本当に「ノウハウ不足」という理由で100人未満従業員数の企業の障害者雇用が進まないのだろうかはもう少し調べたい。
②について、各都道府県に、ハローワーク、生活・就業支援センター、地域障害者職業センターがあるので、そこの機能強化を図った方が早いのではないかなと思うが、配置数増やすとか、なんでまた助成金新設になるのだ。よくわからなーい。
企業の雇用率にばかり着目しがちだが、就労系福祉サービスを提供する側の「就労支援」としての取り組みも調べてみたい。もちろん、福祉サービスを提供する事業所それぞれの理念や方針、プログラムがある。ただ、それぞれの事業所がどのような「就労支援」を行い、就労に繋がっているのか興味がある。そしてそのノウハウはどのように構築(組み立て)しているのだろうか。気になる。
今後
沖縄県は公的機関の障害者雇用促進の課題と、実雇用率が高くなるカラクリがあるのではないかと考えているので、そのこともまとめたい。
就労支援については「職業リハビリテーション」という学問に沿って、ある程度の枠組みがあることを共有したい。できれば。
参考資料
厚生労働省 職業安定局 障害者雇用対策課 令和3年 障害者雇用状況の集計結
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23014.html
厚生労働省 令和3年沖縄県内の障害者雇用状況の集計結果https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23014.html
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
