
一億総◯◯社会
今回は 人材育成 に関することについて示します。
興味を惹かれた一冊の本から自身の解釈です。
目次
1.活躍
2.他責
3.称賛
1.活躍
人は誰でも活躍できる。僕は本当にそう信じています。
引退を決意したイチロー選手、A代表に返り咲いた香川選手。スポーツの世界で例にとると、世界を騒がす本当に優秀な選手は一握りかもしれない。
しかし、どんな人にだってスポットライトが当たる時がある。その瞬間を引き寄せるかどうかは、誰のせいでもなく、自分自身の行いただ1つ。
中には、出来るだけ目立たないようにと、ひたすらに縁の下の力持ちになる人がいるが、そういう人はその時点でスポットライトが当たっている。
目には見えないし、誰からも気がつかれることもない。華やかさはできるだけ抑えようとするので、誰も気がつかない。
このような人々は、家庭で家族を支える専業主婦の方々の存在かもしれない。
僕の母親は本当にそうだった。目立つことは一切嫌い。いつも親父を立てていた。頑張って家の中のことを散々してくれてるのに、誰も感謝の気持ちを伝えない。伝え方を知らない。
なぜなら、それが当たり前という空気になっているからだ。
今となってはありがとうと言う感謝の気持ちを形で表せるようになったが、まだまだ足りない。もっと言葉で感謝の気持ちを伝えないといけない。
自分にはまだその勇気が足りない…
一億総活躍社会とは、2015年10月に発足した第3次安倍晋三改造内閣の目玉プラン。安部首相自身が次の3年間を「アベノミクスの第2ステージ」と位置付け、「一億総活躍社会」を目指すと宣言した。少子高齢化に歯止めをかけ、50年後も人口1億人を維持し、家庭・職場・地域で誰もが活躍できる社会を目指すというもの。
まさに家庭の専業主婦の皆さんや控えめに過ごしてきた皆さんが活躍できる世の中。
この動きに乗るチャンスが来たと言える。
何をどこまでどういう風に活躍できる仕組みができるのかは別として、一人一人が本当に世の中に貢献していて、お互いに認め合い、褒め合い、慰め合って生きていける世の中になってほしいと願う。
一億総活躍社会とは、
まずは子供も大人も、一人一人を褒めあえる社会の構築であると思っている。
そうしないと明るい未来は築けないと考える。当たり前のはずだが、これがなかなか難しい。みんなが活躍できて、みんなが平均的に幸せになり、みんなが助け合ったり褒め合ったりできる、そんな社会が待ち遠しい。
それにしても、なぜ人は相手を褒められないのだろうか…
2.他責
人を責めることが多くなっている現代人。すぐに人のことを責めたがる。
以前、私が記したnote、「正しい指摘もいじめの始まり?」の中で、いじめにも理由があり、人を指摘したりすることは、脳科学的にも立証されていると言うことを解説した。
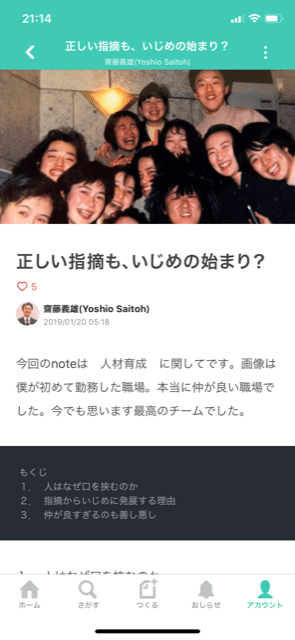
ここに紹介する一冊の本は、二度見、三度見、四度見したほどの本であった。
片田珠美 著 一億総他責社会 イースト新書 2019
表面的な文字面だけを追うと、一億総活躍社会に見える。
でもよく見ると一億総他責社会。
何度もじっくり見たが、やはり◯◯◯他責◯◯と記されている。
完全に購買戦略に負けて早速購入となった。
他責って、他人を責めると言うこと?? 今の時代、みんな活躍しよう!じゃなくて、みんな人のせいにしてるってこと!?
これはまさに衝撃的でした。
でも・・・あ〜〜
なぜか腑に落ちるなあ…と興味深く読んでしまいました。
この本によると、冒頭部分でこのように書かれています。
「不満と怒りの原因を作った本来の相手に対しては、怖くて怒ることができない。だから、無関係の弱い相手に怒りをぶつける。つまり怒りの矛先がずれているわけだが、このずれが日本中の至る所で生じている」
どうだろうか?
僕は率直に激しく同意した。本当にそう思う。
仕事であったり、趣味であったり、人が集まり1つの集団を作るとき、何かしらの問題が生じる。その問題とは、多くの場合、人間関係の問題に集約できると思う。
これは、アドラー心理学では明確にそのことが示されているが、自身の年齢が時を重ねるに連れ、世の中の問題は全て人間関係であると言っても過言ではないと思う。
どうして自分に怒りの矛先が向くのか?
それは管理職だから?マネージャーだから?リーダーだから?コーチだから?父親だから?夫だから?男だから?
確かに諸問題を解決する立ち位置にいる時、周囲の関係者は自身に頼るだろう。現実、何か問題が生じたときは、上司に相談したり、担任の教師、コーチ、とにかく自分より立場が上の人に報告したり相談したりする。
怒りの矛先が自身に向いているのは、1つは頼られる存在であるから。 これは本当にありがたい。しかしもう1つは、無関係の弱い自分であるということがこの本から理解できる。
弱い自分がそこにいる。だから戦いを挑めとは言わない。
重要なのは、弱い人が弱い人に怒りをぶつけるのだから、怒りの矛先が自分に向かっているのなら、相手を受け止める絶好のチャンスであると捉えたい。
そう簡単にはならないものだが・・・
3.称賛
なぜ人は褒められないのだろう。管理職の中でもストレートに褒めることができない人は本当に多い。
嫌味っぽくでしか表現できない人。そうしてくれるだけでありがたいと捉えよう。
一億総称賛社会の実現を!と私は心から願う。
この本によれば、他責する傾向が増加した理由に、「発達障害の増加」と記してある。
これは、製造業種が減少した現代、サービス業界が多くなり、人とコミュニケーションを取る機会が頻繁になった。今までも発達障害の人々の存在はある程度社会の中で確認できていたが、現代ではよりクローズアップされるようになったと解説している。
また更に、発達障害と診断されるケースが増えた一因として、「空気を読め」と風潮が以前よりも増加したのではないか。こう記してある。
発達障害の人は空気を読むことが苦手であり、これを暗黙のうちに要求されると、とてもしんどくなり、精神科受診に至るケースが増えているとのこと。
空気といえば、同様にして以前私がnoteに記した記事でも少し触れている。

空気とは、「絶対的な支配を持つ判断基準」、「臨在感的感情移入」などとし、目には見えないけれども、絶対的な支配と臨在感を併せ持つ魔物のようなものであると私は感じる。
場合によっては発達障害ではない普通の人だって、この空気は統一のものではなく、微妙に違う事もある。だからこそ非常に厄介なのである。
今回紹介している本によれば、
なぜ空気を読むことが以前にも増して要求されるようになったかといえば、世間が壊れてきたからである。と衝撃的に記している。
つまり、昭和の古き良き時代、あのような世間がいわゆる良き空気であったと示している。
では、あのような世間という、世間にもともとあったルールとはなんであろう。いわゆる地域ぐるみでの共同体の感覚であると読み取れる。つまり以下の事柄であると示している。
①贈与・互酬の原則
②長幼の序
③共通の時間意識
・・・これに加え
④差別的で排他的
⑤神秘性
①は、お中元やお歳暮などに代表されるように、贈ったら贈りかえすなどのような「お互い様」の気持ち。
②は、年長者に敬意を払うということ。日本では伝統的に重視されてきた。
③は、同じ世間に所属し、お互い同じ時間を起きているということ。これは日本人は特にそう思う傾向があり、欧米では一人一人の時間で生きているという思想で、「今後ともよろしく」という挨拶はないという。
④は、世間とは「自分と利害関係のある人々と将来利害関係を持つであろう人々全体の総称」とし、同質の人間は共同体であるが、それ故それ以外は差別的で排他的になりやすいとしている。
⑤は、世間という神秘性を我々は感じており、世間の正体を掴みにくいと示している。つまり、世間とは何かと問われて答えられる人はほとんどいないと示し、その正体が分かりにくいからこそ、世間は圧倒的な力を持つ。と示している。
現代社会、以上のようなルールが崩壊され、共同体の再構築は不可能だとも表現している。
この5つのルールは確かに壊れかけている。しかし完全になくなってしまうのか。世間の良きルールを復活させるためにはどうしたら良いのだろうか?
この本の著者、片田氏は以下のように警鐘を鳴らしている。
「みんながより平等になり、お互いが同じ人間であることがわかってくると、その間に残る違いにより敏感になってしまう」
「他責的な考え方に傾くのは、自分自身の問題を否認したいからであり、自己愛の影響による。したがって、新型うつ病は一億総他責社会の象徴であり、時代の病といえよう」
不公平だとか、何かの言い訳をして他人を責めること。これはこの著書の中でも示されているが、自分と他人を比べているに他ならない。
これはアドラー心理学で言うところの「劣等感」である。劣等感は持って良い感情。それをどうやって好転させていくか、いわずもがな、誰のせいでもなく自分自身の行動力であることは誰でも知っているはずである。
「もはや国民の養成機関としての学校には何の価値もない」などと表現している著名人もいるようで、本当にこのようなことを普通に叫ばれる時代であっていいのだろうか。
価値観や思想などが大きく変わりつつある現代。いわゆる過渡期であるこの時代をたくましく生き抜いていくためにはどうしたら良いのだろうか?
それは一定概念を持たない、押し付けない、柔軟性が必要であると考える。
これはこうあるべき!という思い込みが強いと、様々な状況下で、自分の都合良い解釈でしか理解しようとしないので、自分自身を守るために、益々他責傾向が強くなる。
柔軟性、この著書の中では「多様力」と表現しているが、最後に片田氏は以下のように締めくくって本書を終えていることに、多くの人は心から気づき、勇気を持って行動して欲しいと願う。自分自身も…
「ここで忘れてはならないのは、自分自身の不遇を誰かのせいにして幸せになった人はいないということだ」
そして最後に私は言いたい。
人のこと責めるより、もっと褒めようよ!
僕なら絶対責められるより褒められたいから…
そうすれはきっとみんな輝ける。
みんながみんな公平じゃないのは知っているから。
自分が輝いているところをもっとアピールして褒めてもらいませんか?
一億総活躍社会 = 一億総称賛社会 の実現を目指して…
#一億総活躍社会 #他責 #称賛 #もっと褒めようよ #理学療法士 #アドラー心理学 #4コマ漫画 #育児 #写真 #絵本 #インタビュー #ねこ
