
彼らの眼がまさに“夜明け”だった~映画『夜明けのすべて』~
※映画『夜明けのすべて』のネタバレを含みます。ご注意ください。
2024年2月9日(金)、瀬尾まいこさんの原作小説を映画化した『夜明けのすべて』が公開された。
1月11日(木)に開催されたプレミアナイト、2月9日(金)公開初日、そして2月10日(土)の舞台挨拶生中継2回の計4回鑑賞して、本当に本当に素敵な作品で、作品から受け取った温かさがずっと心の中に残っている。
映画『夜明けのすべて』は瀬尾まいこさんの原作本の良さやあたたかみを残した物語でありながら、映像化の醍醐味である画からもそのあたたかみや登場人物の日々の変化がきちんと伝わってくる、とても丁寧に描かれた最高の作品である。
そしてこの作品に関わったすべての人たちがお互いにリスペクトし合い、優しさと温かさを持って、この作品に取り組んでいたことがスクリーンを通して観客にちゃんと伝わってくる。
作品を観た私たちにも何かをお裾分けしてくれるような、そんな映画である。
映画『夜明けのすべて』物語
物語はあらすじに書かれている通り、本当にあらすじに書かれている通り、「月に1回、PMSの影響で激しいイライラを感じてしまう藤沢さんと、藤沢さんと同僚でパニック障害を抱えている山添くんが、互いの事情を知り、職場の人たちの理解に支えられながら、同志のような関係を築き、互いに助け合う」物語である。
本当にそれだけ。
何か事件が起こったり、どんでん返しが起こったりすることはない。
特別なことは起こらない、まるでドキュメンタリーのように二人の日常を切り取った作品である。
でも私たちの日常がそうであるように、特別なことが起こらなくても、心は動き続けていて、不安や苦しみ、孤独を感じることがあるように、山添くんや藤沢さん、そして二人を支える人たちにもある。
そんな不安や苦しみを“乗り越える”という作品はよく見かけるけれど、この作品は共に生きていくこと、付き合っていくことを選んだ人たちの時の流れをそっと覗かせてもらったような作品であった。

映画『夜明けのすべて』の画
映画に触れる前に瀬尾まいこさんの原作も読ませていただいていた。
「この空気感をどんな風に映像化するのだろうか?」とわくわくしていたが、その期待感を遥かに超える画が目の前にあった。
何か特別なことが起こる物語ではないけれど、映像として生み出すにあたり、緻密に寝られた作品であると、観ている中で私は何度も感じた。
印象的だったことの一つに光の使い方がある。
作品の中では陽が出ているシーン、陽が沈んだシーン、どちらも同じくらい出てくるのだが、そのどちらにもちゃんと意味がある。
例えば、山添くんと藤沢さんが支え合うようになる過程、二人の心理的距離が近づいていく過程は夜のシーンが多かったように感じた。
苦しみを抱える二人が人目を気にせず、自分らしくいることができたり、不安を吐露できたりするのは夜だったのかもしれない。
だからか、会社からの帰り道や、退勤後の山添くんの自宅など、夜の暗闇が印象に残った。
そんな二人がお互いのことを理解し、助け合うようになることで、自分自身を受け容れられるようになったのだということを感じたのが、山添くんが自転車に乗って、藤沢さんの自宅に忘れ物を届けに行くシーンである。
それまでたくさんのことを諦め、生きがいも気力も失っていた山添くんが少し生きることに前向きになった様子が彼を照らす、あたたかな陽射しに表れていたように思う。



そんな山添くんを自宅のベランダからそっと見送る藤沢さんもまた同じ。

それまでのシーンは日中でもどこか影を感じる二人で、画としても影を感じていたけれど、互いを理解する時間を重ねることで、不安な夜から、少しだけ楽な夜に、そして感じる余裕すらなかった陽の光を感じられるようになったのではないかと観ていて感じた。
もう一つは無駄なシーンが一つもないということである。
原作から加えられた設定はもちろん、一つ一つのシーンがしっかりと練られ、そこに存在していた。
プラネタリウムの設定が加えられたことについては監督や出演者の方がいろいろな媒体でお話しされているので、割愛することとし、私が素敵だと思ったのは住川さんの息子さんのダンくん率いる放送部の存在だ。
放送部の活動の一つとして、ドキュメンタリーを制作すべく、中学生が栗田科学の面々にインタビューをしていく。
インタビューを通して、内容自体が物語に直接関わりがなくても、栗田科学の雰囲気を感じることができたり、何気ない毎日を覗き見している感覚を観客にもたらしてくれる。
結果として、登場人物をとても近い存在に感じることができたように思う。
またりょうさん演じる藤沢さんのお母さんが警察のお世話になった藤沢さんを迎えに来るシーン。サインをもとめられ、ペンを1回落としてしまうお母さんはその後の未来に繋がる伏線だったのかもしれないと感じてしまったり。
藤沢さんに自宅まで送ってもらい、炭酸やおにぎりといった食糧をもらったはずなのに、自分でコンビニに買いに行ったものを食べている山添くんの机が映し出されると、山添くんと藤沢さんとの心の距離を感じたり、あるいは食べられるものと食べられないものがあるのかな、と山添くんの身体を案じてしまったり。
一方で山添くんが藤沢さんの家に忘れ物を届けるシーンでは、山添くんが栗田科学を出る前に社員たちが小競り合いをしていたり、山添くんが自転車で登ることを諦め、押しながら登っている坂で、子どもを乗せて自転車を漕ぐお母さんが易々と横を通り過ぎていくシーンや、栗田科学おじさん3人衆のインタビュー、ヘルメットを逆にかぶる栗田社長に山添くんがツッコミを入れるシーンなど、クスッと笑ってしまうような、緩んでいく瞬間も散りばめられている。
そして、時折映し出される街並みの風景は時の流れを感じさせてくれ、最後の移動式プラネタリウムのシーンで、回転するプラネタリウムは地球が回り続けていることを想起させる。
その後、ある種の救いとして提示される「どんな一日も科学的な事実によって、必ず終わりを迎えること」にグッと重みをもたせてくれる。
この作品は直接的なことや多くのことが語られる作品ではない。
でもすべての画が意味を持ち、観客である私たちに余白を与えてくれる。
そこを想像せずにはいられないくらいに。
だからずっと心に残り続けているのではないだろうかと思う。
“解け合う”物語
この作品を一言で表すとしたら、“解け合う”という言葉だろうと私は思う。
一見、正反対に存在しているように思える朝と夜、そして光と影。
パニック障害を抱える前の自分と抱えた後の自分。
PMSの影響を受けていない自分と、受けている自分。
正反対に存在しているように感じても、実は隣り合わせの存在であるということを気付かせてくれたように思う。
松村北斗の言葉を借りるなら、「シームレス」な存在なのかもしれない。
それに気付いた登場人物たちが、それぞれが持つ不安や苦しみを受け容れ、互いに補い合い、助け合いながら、“解け合う”様を見せてもらった、そんなような気がする。
きっとよく言う“乗り越える”ことも、まず“受け容れる”ことから始まるんだ、ということも。
加えて、それぞれの役者さんたちと登場人物が解け合い、生きていたのも印象的だった。
プレミアナイトの中でお話しされていた内容でもあるが、松村さんが上白石さんに「その場に馴染む力がある」と、上白石さんが松村さんに「役に溶け込むのが本当に早い」とおっしゃっていた通り、二人ともがあの街で、一人の夜を過ごし、助け合っていることに無理がない。そして嘘もない。そんな時間が映像の中で流れている。
きっと私の近くにも山添くんや藤沢さんがいて、人知れず苦しんでいるかもしれない。
今は「自分だけどうして…」と思っている不安や苦しみも、もしかしたら誰かと分かち合えるかもしれない。
そう思うと、ありきたりな言葉ではあるが、「自分は一人じゃない」とちょっぴり思えた気がする。
松村北斗が演じた“山添くん”
直近の出演作『キリエのうた』でも感じていたし、それ以前の『カムカムエヴリバディ』や『恋なんて、本気でやってどうするの?』、『ライアー×ライアー』などの作品でもずっと感じていたことではあるが、松村北斗は眼の光が印象的な俳優である。
演じる役の状況に応じて、眼の光を操ることができるのだと私は思う。
そして今作でも彼の眼こそが山添くんを山添くんとして存在させたのではないだろうか。
藤沢さんとの交流がまだ無い、物語の前半の山添くんは無気力、虚無感、虚ろな眼、挨拶もしなければ、人と目を合わせることも顔を見ることもない、人と関わることをしない素振りばかりが目立つ存在だった。
これはきっとパニック障害になり、自分にできること・できないことの制約がついたが故に、自分が人と関わってもいいことも無ければ、関係性が発展することもないという諦めに満ちた姿である。
パニック障害になったことで生きることへの希望を失い、気持ちだけが「こんなはずじゃない」と焦り、張り詰めている様子は暗い部屋の中で一人で焦る姿や不安を隠せず、自ら体を震わせる姿からも伝わる。
自分がパニック障害であることを周囲にひた隠しにし、外では飄々をしているけれど、本当は焦っているし、受け容れられていない、そんな山添くんがそこにいる。

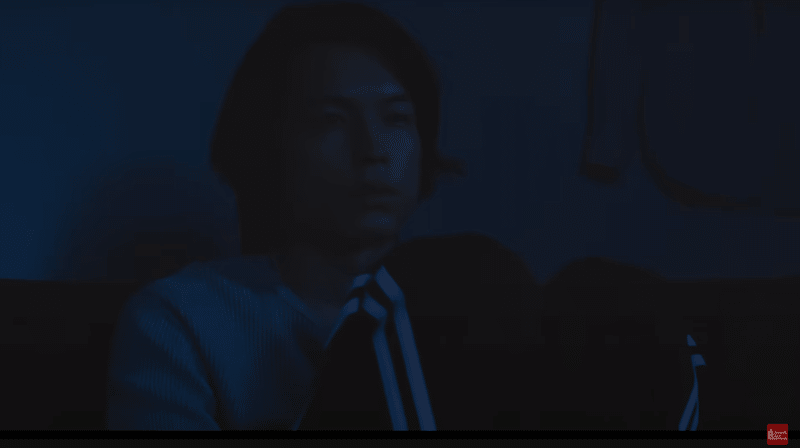
一方、藤沢さんと助け合うようになった物語の後半の山添くんは明らかに他人と心を通わせることに対して、抵抗感がなく、たおやかに身を任せているように見える。パニック障害という生きづらさを抱えている自分だからこそ、パニック障害になる前よりも、人の痛みや苦しみに目を向けることの大切さに気付いた山添くんが他者と交流することで、緩んでいく、肩の荷が下りていく過程を見せてもらったように感じた。順風満帆な時には気付けなかった、人が持つあたたかみや苦しみを知り、“誰かを助ける”という一つの救いを見つけたことが、今の彼を彼自身が受け容れられるようになるきっかけを与えてくれたのではないだろうか。


この変化の表現が本当に素晴らしかった。
「パニック障害になった」という事実によって、眼に光がまったくなく、生きる希望がごっそり抜け落ち、人相までもが変わり果てた山添くんが、他者に一歩ずつ歩み寄り、自分の殻を破りながら、理解し、理解されることを通して、助け合っていくことで、自分にもできることがあると少しずつ希望を感じ、眼の光を取り戻しながら、緩んでいく様が見事であった。
人が変わる時、それは突然パキッと変わるものではなく、たくさんの経験をじんわり、ゆっくり噛み締めることで、徐々に、グラデーションのように変わっていくものである。
自分自身でも変化点がまったくわからないほど、徐々に変わっていくものである。
その姿を演技で表現することの難易度は計り知れない。
それをやってのけた。なんてことだ。
そしてそれがあまりにも自然なのだ。
自然すぎるほどに自然なのだ。
例えば藤沢さんが山添くんに怒りを爆発させてしまったあの日、帰り道で藤沢さんが視界に入っていることに気付きながらも、ギリギリまで気付かない振りをし、サラッと挨拶をして立ち去る絶妙な距離感。「気まずいんだろうなぁ…この二人」が伝わる距離感。

前職の上司、辻本課長とZOOMで話をしている時の生き生きとした姿は、パニック障害になる前の自分を知る相手だから、自分が在りたい姿「本来こうなんだ」と思いたい過去の自分でいられる唯一の相手だからこそのもの。「パニック障害になった自分を受け容れられていないんだろうなぁ…」と感じられる。
このシーンで過去の自分のように振る舞い、現在の勤め先である栗田科学への不満を話している山添くんがいるからこそ、最後に辻本課長に対して、今の自分の気持ちを素直に話せるようになったあのシーンがグッときた。
会社で発作を起こして早退した山添くんと、山添くんを家まで送っていった藤沢さんがアパートの玄関前で会話をするシーンでは決してポジティブなものではないし、拒絶に近いかもしれないけれど、作品の中で初めて山添くんの感情が動いた瞬間だったと感じた。
自分の感情を動かしてくる存在と出会い、髪を切られたことで、山添くんが籠っていた殻が解け出したことがよく伝わった。
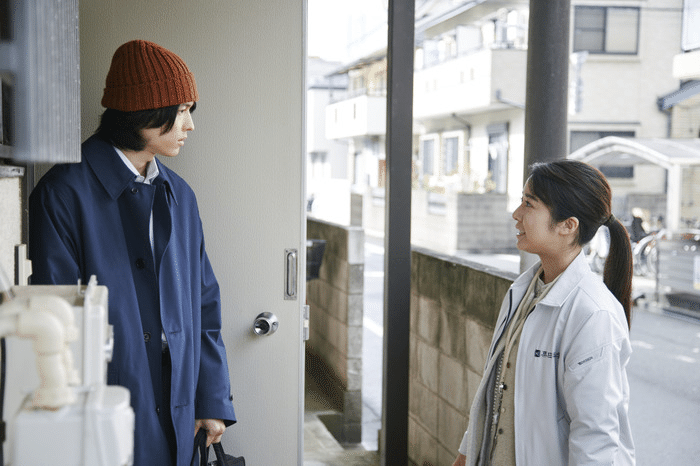

そして、移動式プラネタリウムの中で藤沢さんが話す山添くんと藤沢さんのこれまでのやりとりを振り返る話や「夜についてのメモ」の話を聞く山添くんの表情。少し照れくさいような、でも自分を救ってくれる藤沢さんが話す夜についてのメモに想いを噛み締める様子が自然で、こちらもグッとくるものがあった。

これらすべてがなんとも自然で、「人ってこういう時あるよなぁ…」と思わせてくれるのだ。
まるで街の中で人間観察をしているような気分になる。
実際に松村北斗はインタビューの中で以下の通り答えている。
この作品の面白さって、そういう人間観察の感覚に近いんじゃないかって。ある種、すごく無防備に登場人物たちが存在しているのを、観客のみなさんに観察していただくというか。だから演じる身としても、いかにスクリーン上で無防備に、ありのままで存在しうるか、というのが重要になってくると思いましたし、それがこの作品のすごく素敵な部分でもあると思います。
私は山添くんと藤沢さんのやりとりで大好きなやりとりがある。
二人が会社の帰りに肉まんを食べながら、
山添くん「俺、将来の見通し0ですよ。」
藤沢さん「そんな悲観的にならなくても」
というやりとりがある。
話している内容は一見重く、ネガティブな話に思えるが、とても軽やかに話しているのだ。
確かに事実として、山添くんはパニック障害が良くならない限り、将来の見通しが0かもしれない。
でもこの時の山添くんは本気でそうは思っていない感じがするのだ。
「なんとかなるかもな」という心の軽さが存在することが垣間見える。
そして悲観的にならなくていい、と伝える藤沢さんは山添くんのパニック障害のことをわかりながらも、本気で悲観的にならなくていいと思っていることが伝わってくるのだ。
この何気ないやりとりに、山添くんと藤沢さんの変化を感じ、とっても愛おしくなった。


“夜明け”が表すもの
周りに明るい星がなく、たった一つ、その場所で光を放ち、アラビア語で「孤独なもの」という意味の「アルファルド」と付けられた星が、暗闇によって明るく輝くように、暗闇があるから光を感じられる。
そして暗闇によってもたらされた光が旅人たちの目印として、誰かの役に立っている。
これは私たちにも言えることである。
不安や苦しみがあるから、喜びや幸せを感じられる。
この2つは正反対なものではあるものの、隔たりがあるわけではない。
実は隣り合わせで、隣り合わせだからこそ、互いの存在が引き立てられ、遠い存在のように感じてしまうかもしれない。
でも正反対で隣り合わせだからこそ、互いに互いを感じられ、そして必要としているのではないだろうか。
夜が無ければ、地球の外に目を向けることはなかった。
夜があるから地球の外に目を向け、星に気付くことができるように、自分だけが苦しんでいるように思っても、苦しみを知った上で、周りに目を向けると、周りの人が苦しみを感じていることに気付ける。
そして自分も不安や苦悩を抱え、知っているから、人の痛みに目を向け、労わることができる。
山添くんと藤沢さんが一人で不安や苦しみを抱えながら、ここまで生きてきたから、山添くんは藤沢さんという存在に、藤沢さんは山添くんという存在に気付き、互いに助け合うことができたのではないだろうか。
不安や苦しみを抱えながら生きてきたことは無駄ではない。
その日々があったから、誰かを助けることができ、誰かを頼ることができた。
まさに互いが互いに「アルファルド」のような存在だったのだと思う。
「誰もが生きづらさを感じる今に、生きることが少し楽になる願いを込めた映画です。」
生きていれば、大なり小なり不安や苦しみは一生つきまとう。
でもどんなに喜びに溢れた一日でも、どんなに苦しい一日でも地球が回り続ける限り、朝は来る。
誰にも等しく夜明けが来ることは、科学的事実なのだ。
夜が来たら、朝が来るように、不安や苦しみが喜びや幸せを連れてきてくれることもあるのだということをこの物語の主人公たちが教えてくれた。
ずっと暗いトンネルの中にいると思い込んでばかりいるのではなく、暗いトンネルの中にいる自分自身を受け容れ、一歩ずつ足を踏み出せば、いつか“一人じゃない”と思える時が来る。
そうしたらきっと少しだけ、ほんの少しかもしれない、でも自分が見ている世界が変わるかもしれない。
この物語の主人公たちの眼こそ、まさに“夜明け”だった。
夜の暗闇と朝の陽射しが解け合い、少し明るんだ夜明けの空が訪れるように。
不安や苦しみと喜びや幸せが解け合い、少し前向きになれる。
『夜明けのすべて』はそんな映画でした。
ps.ちょいちょい垣間見える松村北斗の運動神経を感じるシーンに愛おしさが募ったのは言うまでもない。
社員の方と自ら積極的に関わり合う山添くんの変化に胸を打たれるはずのエンディングで、自転車の乗り方の不器用さにクスッと笑ってしまったり、風のせいもあるだろうが、フリスビーをとんでもない方向に投げてしまったり(笑)
とってもとっても愛おしい山添くんでした。
おけい
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
