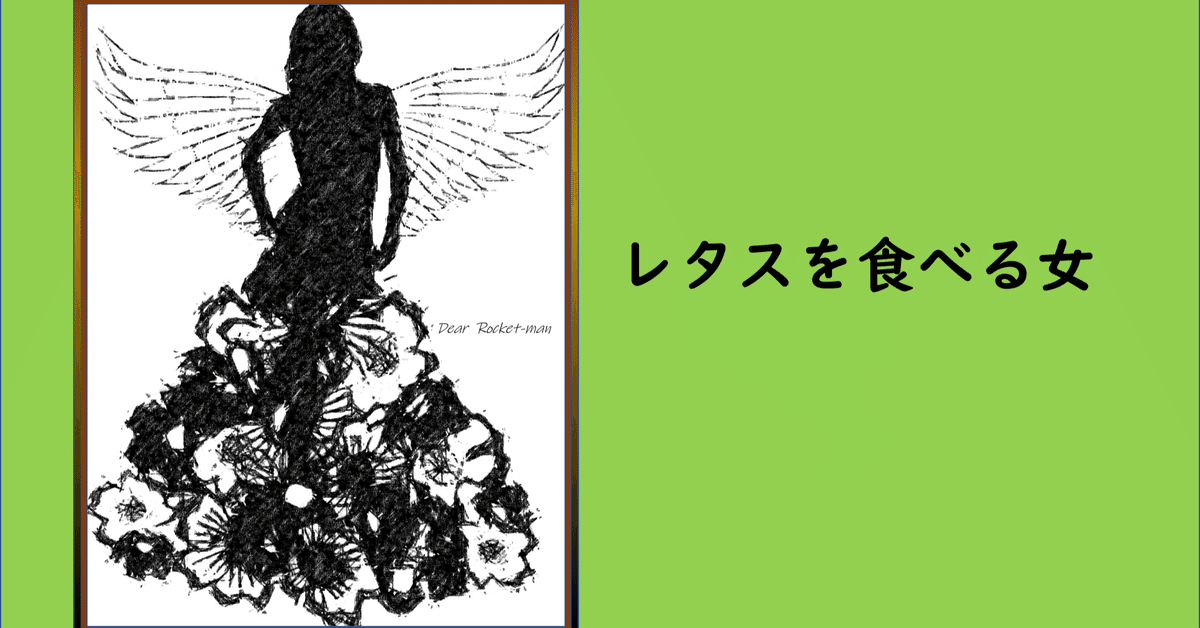
【断片小説】レタスを食べる女
うめき声が聞こえたので台所に向かう。スーツ姿の彼女は、霜のついたジップロックをプラプラと振りながら言った。
「ねぇ、レタス冷凍したでしょ」
「したよ。だってたしかもう3日くらい放置されてたじゃない?」
「いいえ。このレタスは昨日買ったの。ねぇ、レタスは水分を多く含んでいるんだよ。そんなの解凍したときに本来のシャキシャキ感が失われちゃうじゃんか」
いや、そうじゃない。確かに3日前くらいに一緒に買い物に出かけ、オランウータンの頭くらいのレタスを買ったはずだ。朝のサンドイッチに2、3枚使っただけのはずでまだ子ザルの頭くらいは残っていたはずだ。急に小さくなったものだからそれが不思議だったけれど、もしや僕の知らない間に彼女はひとりで別のレタスを買ったというのか?
「それならチャーハンにでもしてしまえばいいじゃないか」
「私は温くて萎びたレタスが嫌いなの。言ってなかった?」
少し記憶を探って、彼女がそのようなことを言ったかどうかを思い出そうとした。しかしうまく思い出せなかった。というか、そもそも、そのレタスは昨日買っただって?
「聞いてないですよ。凍ったレタスもそれはそれで歯ごたえありそうだけど。ねぇ、そんなにこだわることなの?」
彼女は眉間に皺をよせた。
「あのさ、そういうのも了承して一緒に暮らすことに決めたんじゃないの? こんな世間のコロナ騒動じゃ中々会えないからって。離ればなれは嫌ってことで。こういうことは起こりうることでしょ?」
「違う、そうじゃない。そうじゃないよ。そういう、僕ら二人の違いが果たして互いに了承できるものかどうか判断したいから一緒に暮らし始めたんだ。コロナ騒動はきっかけにすぎないよ」つまり、結婚してこの先二人で一生過ごすための練習になるのだ。
「ごはん用意してくれたのも嬉しいけどさ。とにかく野菜は野菜室に、冷凍食品は冷凍室に」彼女は安全点検をする現場監督みたいに冷蔵庫を指差した。
「わかったよ。冷蔵庫はキミの領分だよ。ちなみにプリンは?」プリンはきっと冷蔵庫にしまっておくのでいいよね? という意味だったのだけれど。
「冷凍プリンは美味しそうじゃん」彼女は笑った。「お風呂入ってくるね」
僕はプリンを買いに行く。いくら彼女が長風呂に浸かるのが大好きで1時間は入っているからと言って、そんな時間の短さじゃプリンは固まってくれない。食事をするスピードの遅さを付け加えたとしても、プリンは凍ってくれない。
「気にしないで。冷凍プリンは明日まで楽しみにしておく」と彼女は箸をゴーヤチャンプルーの上で彷徨わせながら言った。苦手でもどうか食べてほしい思いで苦みを抑えたゴーヤをいれた。しばらく迷った後、彼女は、豚肉とゴーヤを一緒に口に入れた。何度か咀嚼し眉根を寄せながらそれを呑み込んでしばらくしてからこう言った。
「あのさ、レタスのことであんなに機嫌悪くしたけれどちゃんと感謝しているんだよ。ただ、仕事で疲れてたから、それで八つ当たりしちゃったんだね。その、とにかくいつも感謝しているんだよ」
それからまた沈黙が流れる。僕は返すべき言葉を舌の上で転がしながらも黙ったままでいた。
「もう一つ謝らなくちゃいけないんだけれど、3日前に買ったレタスはね、2日目には全部私が食べてしまったのよ。だからあなたが冷凍したのは昨日私がこっそり買った新鮮なレタスなの」
「あの子ザルの頭くらいの大きさのレタスが?」
「その子ザルサイズのレタスをわざわざ買って偽装したの」悪びれもせず、サイドメニューの味噌汁をすする。「この前ゾンビ映画見たじゃん? 生きた人間にゾンビが群がって手足を捥いだり、皮膚を噛みちぎったり。かなりキモかった。脳みそをくちゃくちゃ食べる音とか嫌にいつまでも残ってさ、そのあとしばらく焼肉を食べるのも見るのも嫌になっちゃった。」
そこで彼女は一息吸い込んだ。重大な秘密を打ち明けるのにひとつ決心を決めるみたいに。
「でもなんだか不思議なもので、頭のなかでその音が反響していくうちに、なんだかその行為がまっとうでちゃんと正しい行為のように思えてきたの。おかしいでしょ? そう、おかしい。でもこう考えた。あれは理性を失い、生きる力を失い、心までも失ったゾンビがなんとか心だけでも取り戻そうと脳みそを求め食べる、正しい行為なんだって。とは言え、人の脳みそを食べるなんて実際には憚られるじゃない? だからレタスで代用したというわけ。それも新鮮でシャキシャキと音が出るレタスをね。くちゃくちゃなんて音はやっぱり気持ち悪いもの」彼女は困ったような顔をする。
「君がホントに人肉に目覚めたんじゃなくてよかったよ。僕の脳みそは食べられるためにあるんじゃないし…。人肉って、それも脳みそなんてホントは危ないんだよ。感染症を引き起こして、しまいには笑ったまま死んでしまうんだ」
「パプアニューギニアのフォア族みたいに?」
「よくご存じで」
「ウィキペディアで調べたから」
「とにかく、君にとってレタスを食べるというのは、心を求める行為と同義なんだね?」
「そういうことになるわね」そういうと彼女はまた豚肉とゴーヤを一緒くたにして口にほおばった。そしてまた眉根を寄せた。
「ねぇ心は脳にあるのよね。だから私のレタスひと玉丸かじりも仕方ないことよね」僕が枕の高さ調節に苦闘していると、横で彼女は天井を見つめながら呟いた。
僕は彼女が夜中に冷蔵庫を開け、むしゃむしゃとレタスを齧る様子を想像してみる。そのほとんどが水分の植物を無表情で食べる仕草は滑稽でありながら、物寂しかった。
「そういう説もある。けれど、心とは、ホントのところはね、脳と身体と環境の間を絶えずフィードバックし続けるシステムやファンクションそのものなんだよ。環境というのには他人である僕も含めてね」
僕は、そこで彼女の心臓を指差し、それから彼女の広い額に指を置いた。ベッドサイドのランプに下から照らされ、奇妙な陰影を生んでいた。
「心は、心臓でもなく、脳みそでもない。心は、どこにあるかということではなく、どう機能したか、するのかということに対して名付けられるものなんじゃないかな。というわけでさ」そこでランプを消した。それから彼女に触れてみた。
「ロマンチックなのか、あまりにリアリスティックなのかよく分からないわ。ただ―」彼女は僕の手の甲をつねった。
「下品なのはたしかね。ばかじゃないの。その手を、どけなさい。今そういう気分じゃないんだけど」もう一度強くつねられる。あまりに痛いので手を引っ込めることにした。
「あのさ、ゾンビとかのホラー映画からもひとつくらいは実生活に活かせる知識を得られるんだよ。『いいかい、照明を甘く見ちゃいけないよ。下から照らせばホラーだけど、ほら、こうすればロマンスに早変わりさ』なんてね」そう僕はセリフを吐きながら、カーテンを勢いよく開いた。カーテンが開けられると月光が真っ直ぐベッドに降り注ぐ。
最後の演出としてはあまりにも出来すぎだ、と自賛する。あまりにベタすぎて、気障すぎて、とてつもない羞恥心があるものの、だ。でもそれでいい気がした。
「ばかじゃないの」
「ばかじゃないよ。ばかばかしいけれど、真剣そのものなんだよ。これは、スピルバーグが昔そう言っていたんだ。僕らはきっとロマンスの最中にいるんだ。それでいいだろ? 何もかも上手くいく気がする。きっと」
「あなたが『きっと』なんて言う時、私はいつでもそれ相応の覚悟をしなくちゃならないのよ? ちがうかしら」
「違わない」
「それとこれとは別だけれど」彼女は窓の外と僕の手とを交互に指差しながら糾弾するように言った。
「まぁそう言わず、大丈夫だって。空は1つ。月も1つ。星もたくさん瞬いて綺麗じゃないか。君がまたおかしいくらいにレタスを食べたくなったら、迷わず僕に触れるといいさ」
そう言って、彼女の顔を見つめた。月光に顔は青白く。何かに怯えているようにも、それらを受け入れ全てを悟っているようにも見える。黒い瞳に月が映っている。二つの瞳に二つの月。それから彼女の二つの腕は僕の首に回された。
この記事が参加している募集
よろしければお願いします!本や音楽や映画、心を動かしてくれるもののために使います。
