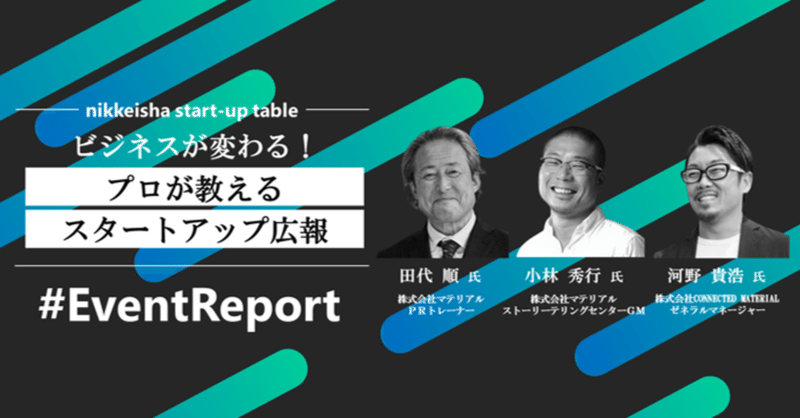
#イベントレポート「ビジネスが変わる!プロが教えるスタートアップ広報」
≪そもそも「広報」で大切なことって、何だっけ?スタートアップにこそ伝えたい、「広報」のポイント≫
「nikkeisha start-up table」では、スタートアップの「1→100」のために、成長期に直面するさまざまな悩みや課題に応えるべく、“社会との対話“の機会を提供しています。
まだ企業や事業の知名度が低いスタートアップにとって、社会への情報発信を効果的に進めていくために、「広報」は必要不可欠なものです。しかし、提供できる広報ネタが無いと困っていたり、メディアが求めているものに合致せずに取り上げられなかったり、といった悩みを抱えている経営者や広報担当者が多いのではないでしょうか。特に、担当者が1人で対応していたり、経営者自身が担当していたりすると、なかなかリソースが割けずに後回しにされてしまいがちです。
先日、「プロが教えるスタートアップ広報」と題して、スタートアップにとっての「広報」の方法や在り方を改めて考えるウェビナーを開催しました。その中で、株式会社マテリアルの田代順さん、小林秀行さん、株式会社CONNECTED MATERIALの河野貴浩さんに語っていただいた“スタートアップが重視すべき広報の考え方と手法“について、少しだけご紹介します。
■メディアへ向けた「広報」で重要なのは読者目線
前半では、田代さんに「広報」で重要なことを解説いただきました。
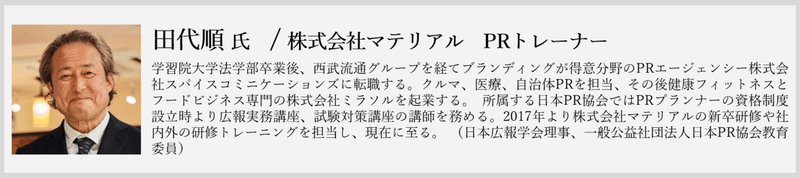
広報をうまく活用しているスタートアップを例にして、何が「広報」にとって大事なのかを解説します。
そのスタートアップでは、自社の製品について記者に聞かれた際、その製品の機能では無く、消費者が体験の先に感じる喜びを語っていました。自分たちが言いたいことを話すのではなく、顧客目線でわかりやすく、読者が知りたいことを先に説明しているのがポイントです。
また、出すキーワードや話し方も含めて、記者が記事にしやすい形の情報として提供していました。伝えたい意味が相手に伝わるように意識をして、言葉を使っていることが印象的でした。つまり、記者と話しているというよりも、記者の向こう側にいる読者に向けて話しているのです。その記事を読んだ人にどう感じさせたいのか、どう態度変容させたいかをイメージして、逆算して情報を提供していくことが大切です。この企業は、こうしてさまざまなメディアでも好んで取り上げられたことで、その後マザーズへの上場も果たしました。
大事なのは、常に読者目線であること。
読者目線を意識するということは、メディアがいち早く読者に伝えたい情報かどうかを意識することです。読者にとって価値のあるニュース性が、「ニュース価値」となります。
皆さんも、自分たちのことをニュースにするために、一生懸命プレスリリースを作成していることと思います。しかし、実際にニュースを作るのは記者です。私たち広報の担当者は、記者に「情報を提供する」ということをシンプルに考えるべきです。
ニュースをつくるのではなく、「ニュース価値」をつくるのです。
「ニュース価値」の視点を磨くためには、日ごろから狙ったメディアに触れて、それぞれのメディアがどのようなニュースを発信しているのか、スタートアップらしい取り上げられ方はどのようなものか、を学ぶことが重要です。
■事業の推進にも重要な「広報」のチカラ
続いて、小林さんからは、「ビジネスが変わる」という観点から、広報の重要性を語っていただきました。
「広報」は、ビジネスが出来た後から始めるものと考える人もいますが、PRはもとより、社内広報・採用広報も含めて、小さなうちこそむしろ重要です、と小林さん。
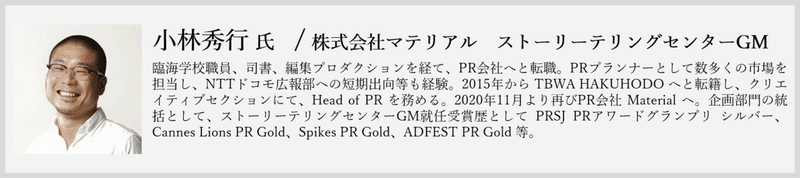
起業とは、社会という池に石を投げ入れる、ということ。
その時、そこに意義や意味がなければ、共感されることはありません。
大事なのは、「なぜ」この会社があるのか、シンプルに伝えられることです。しかし、この「なぜ」を整理できていない企業も多いのが実情です。そうした企業には、是非そこを追求していただきたい。自社が、どのような物語を社会で紡いでいくために存在するんだっけ、という部分をきちんと作れていると、広報業務もやりやすくなるし、SNSでもグッと評判が集めやすくなります。会社として、何のために事業をやっているのか、という一本の軸があると、事業のその後の展開や広報・宣伝活動でも、やるべきこと・やるべきでないことがはっきりと見えてくるはずです。その結果、会社としてのキャラクターも、だんだんはっきりしてくるという好循環が生まれてきます。
また、広報の観点で考えると、これらを整理していく時に、気をつけるべきことがあります。
陥りがちな罠として、自社のマーケット内のみから発想してしまうことがあります。例えば、自社のサービスが競合他社とどう違うのかというバリューばかりを伝えてしまう場合です。ここのみに固執してしまい、必ずしも大衆の関心と合致していないということが多々みられます。
また、戦略顧客=話し相手に設定しがちなことも陥りやすい罠の一つです。
戦略顧客は、その商品を買っていただける方かもしれませんが、必ずしもそのブランドを面白がって話をしてくれる方と合致しない場合があるからです。
メディアの人に話すときにも、私たちの顧客はこんな通な方々なんですよ、と紹介することがあると思います。しかし、その情報は何の驚きもない情報なので、ちっとも面白くないというケースにも陥りがちです。大衆を見据えたメディア、またその大衆からしてみると、自分にとって意味が無かったり関係が無かったりする情報となってしまうことが結構散見されています。
私たちPRプランナーからみて、その時にこういう部分に気をつけた方がいいというポイントをご紹介します。これらに沿って情報を精査していくと、それだけでメディア/ソーシャルメディアに受け入れられる幅が変わってきます。
<ポイント①>
メディアのその先に見ている読者・大衆にとって関係する
あなたゴトに変換しなきゃいけない。
<ポイント②>
業界の中でどうなんだっけという話よりは、もっと広く
世の中のどうなんだっけという話にしなきゃいけない。
例えば、文房具業界で初の文房具と、小学生の学びに
必要不可欠な文房具と伝えるのでは、受け止め方が変わる。
<ポイント③>
数字で利益について語ることに執着するのではなく、
世の中をどう変えていくかという理想を語る。
<ポイント④>
自分の会社紹介のときは、自分の会社がどんな行動をして、
どのような約束をするのかを紹介するとよい。
メディアへの情報提供にせよ、自社のコーポレート的な発信にせよ、自社のことを説明する情報だと価値がありません。業界ごとではなく、ただの自社の紹介でもなく、世の中にとっての何だっけということを翻訳してあげると、幅広く聞いてもらうエクスキューズになります。
最後に、自社の説明の仕方が大丈夫なのかどうかを確かめる方法をお教えします。
それは、一度、自分の会社のことを自分で書いてみるということです。
プレスリリースでもなんでも、一回アウトプットしてみる。そのアウトプットを見直したときに、これってやっぱり業界ごとに留まっていないかとか、これってやっぱり自分の会社の紹介になっていないかということを確認することが大事です。確認するには、ブログやプレスリリースにして配信してみたりすることで、客観的に見直してみるのがおすすめです。
■メディアを知り、自社の情報を整理していくための効果的な方法
田代さんが語る、メディア毎の読者にとっての「ニュース価値」を探ること。小林さんが語る、世の中ゴトとして自社を見つめ直し、整理してアウトプットすること。
それら両方を効率よく進める方法の一つとして、最後に河野さんより「クラウドプレスルーム」を紹介いただきました。
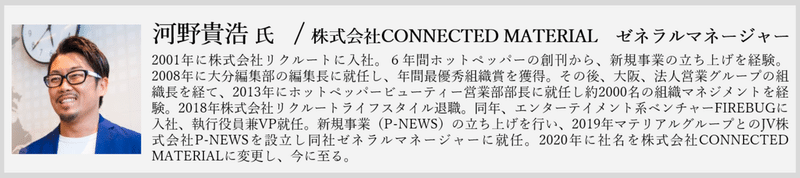
「クラウドプレスルーム」は、企業とメディアを1on1で繋ぐマッチングプラットフォームです。
さまざまな広報の方にヒアリングするなかで、広報業務が型化されておらず、属人的な業務となっている現状があると感じました。それに対してメディア側でも、情報収集の仕方において課題が山積していました。常に最新情報を発信するためには、ネタが足りず、莫大な情報からの検索には時間がかかります。また、企業からのプレスリリースは、メディアが求めるような読者目線の「ニュース価値」がある情報になっていない、等の課題です。
そこで、情報の流通を健全にし、ブランドに関わるすべての人を幸せにするために「クラウドプレスルーム」が出来ました。「クラウドプレスルーム」内には、スタートアップ側が自社の情報を整理してメディアに提示する「PRESS-KIT」と、メディア側が求めるネタ募集に直接コミュニケーションをとれる「CONNECTED」といった機能があります。メディア側がどんな情報をどのタイミングで求めているのかを理解できるうえ、自社がもつ情報がニュース価値のあるものなのかどうか、棚卸しして整理できることが特長です。
ただプレスリリースを一様的に配信するのではなく、メディアの読者にとって「ニュース価値」のある情報として発信していくためのツールになるかと思います。
社会への発信のために、読者目線をもつこと、自社の情報を見直し整理すること。私たちnikkeisha start-up tableは、そうした「広報」を進めるための下支えとして、ウェビナーを始めとして、今後もいろいろな形でサポートさせていただきます。ぜひ、お気軽にご相談ください。
ご相談のお問い合わせはコチラ▼
https://www.nks.co.jp/inquiry/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
