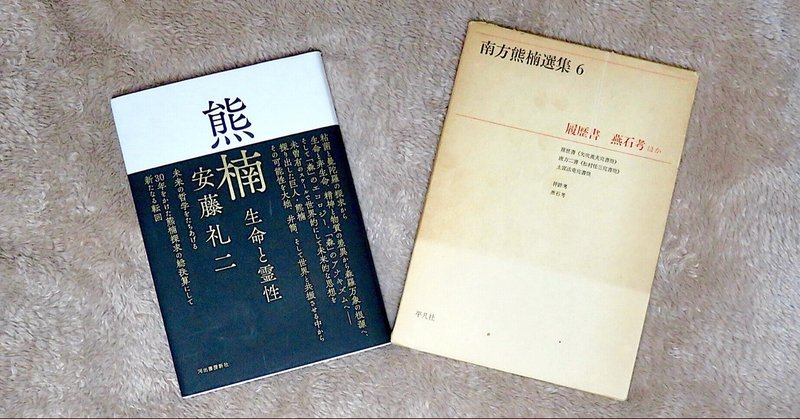
安藤礼二『熊楠 生命と霊性』
☆mediopos2265 2021.1.28
森羅万象は
いったいどこから
生まれてくるのだろう
南方熊楠は
その根源の場を探究しつづけ
非生命と生命
物質と精神の差異を
乗り越えようとし
まず粘菌
そして曼荼羅
最後には
潜在意識の構造的な把握へと向かった
安藤礼二はここで
「熊楠研究」ではなく
「熊楠論」というかたちの論考を提出している
論考というよりは
安藤礼二流の批評的営為といってもいい
資料だけからでは見えてこない
熊楠思想の可能性の中心を見定めるためだ
どんな探究にもいえることだが
残された資料には限界がある
重要なのはその資料をインプットしたうえで
そこからいかに創造的なイマジネーションを展開するかだ
安藤礼二は熊楠の思想の重要な源泉として
次の三冊を挙げている
熊楠は
コープの『最適者の起源』によって
粘菌を見出し
ブラヴァッキーの『ヴェールを剥がされたイシス』によって
曼荼羅を見出し
マイヤーズの『人間の人格とその死後の存在』によって
潜在意識を見出したというのだ
そして最終的に到達した潜在意識の構造的な把握を
最も良く理解させてくれるのが
そこに神話論理の体現されている「燕石考」という論考だという
その論考で見出された曼荼羅状の構造は
人間と自然を通底させるもので
熊楠はその曼荼羅から
森羅万象を生み出し続けている
宇宙の根本原理である大日如来の心の構造を推し量り
心・物・人間・自然・神という理念を再編成したというのだ
森羅万象つまり宇宙におけるあらゆる存在の根源へ
南方熊楠の視線は注がれていた
安藤礼二はそこに熊楠思想の可能性の中心を見ている
そのイマジネーションは深く頷けるものだ
■安藤礼二『熊楠 生命と霊性』(河出書房 2020.12)
■『南方熊楠撰集6/履歴書 燕石考ほか』(平凡社 1985.2)
(安藤礼二『熊楠 生命と霊性』より)
「南方熊楠は、おそらく、その生涯をかけて、一つのヴィジョンを追い求め続けた。それを一言でまとめてしまえば、非生命と生命との差異、物質と精神との差異を乗り越え、森羅万象あらゆるものが発生してくる根源的な場を探究すること、となるであろう。熊楠は、そのような根源的な場を、まずは粘菌に求め、さらにそれが曼荼羅という継承に昇華され、最終的には潜在意識の構造的な把握というかたちに落ち着いた。
私は、そこに熊楠思想の可能性の中心をみる。
私は、私自身が考える熊楠思想の可能性の中心を、熊楠が遺した一次資料にもとづいた「熊楠研究」ではなく、私自身の解釈にもとづいた「熊楠論」として提出する(・・・)。ただし、私的な「解釈」とはいっても、熊楠が残したテクスト(論考、書簡、日記)を無視したり、恣意的にねじまげたりすることはしないつもりだ。熊楠のテクストに忠実に、また、「熊楠研究」の最新の成果も、できうる限り(・・・)十全に活用したいと思う。その上で、一次資料からだけでは明らかにできない、ある種の「解釈」の飛躍にもとづいた、一つの首尾一貫した熊楠の思想体系を抽出することを試みる。私は、南方熊楠という知の巨人を対象として、客観的な研究ではなく、主観的で固有の解釈、すなわち「批評」を実践する。解釈と批評によって生み落とされた最も創造的で最も魅力的な「分身」を提示する。そのために私が依拠するのは、熊楠が確実に読み、現在もその蔵書として保管されている三人の著書が残した、それぞれ膨大な三つの書物(合計五冊)である。(・・・)
第一に、アメリカに生まれた古生物学者、エドワード・ドリンカー・コープの『最適者の起源』。次いで、ロシアに生まれ、近代的な総合宗教でもある神智学を創出したオカルティスト、ヘレナ・ペトロヴナ・ブラヴァッキーの全二冊からなる『ヴェールを剥がされたイシス』。最後に、イギリスに生まれた心霊学者、フレデリック・ウィリアム・マイヤーズの、これもまた全二冊からなる『人間の人格とその死後の存在』である。」
「熊楠が粘菌を見出すためにはコープの『最適者』』が、曼荼羅を見出すためにはブラヴァッキーの『イシス』が、潜在意識を見出すためにはマイヤーズの『人間の人格』が、それぞれ、重要な源泉となったと推定される。あえて断るまでもないが、私は「重要な源泉」と言っているだけであって、「唯一の源泉」などと考えているわけではない。粘菌について、熊楠は、生物学的な研究と実践的な採集を積み重ね、曼荼羅や潜在意識についても、真言宗の僧侶、後にその宗団の頂点(高野山真言宗管長)にまで登り詰める土宜法龍との対話を積み重ねて、独自の生命観、宇宙観にまで高めている。しかし、その起源において、この三人の著書と三つの著作は、熊楠に、決して無視することのできない、大きな影響を与えたと推測される。
それだけではない。古生物学、神智学、心霊学と、一見すると、相互に何の関係ももたないと思われるこの三つの書物は、一つの共通する潮流のなかで形づくられたものだった。それは、一つの特異な進化論である。熊楠が自他ともにそこから受けた甚大な影響を認めているハーバート・スペンサーやチャールズ・ダーウィンに由来はするふが、スペンサーやダーウィンのものとは根本から異なった進化論である。進化のなかに退化を含み、退化のなかに進化を含み、根源的な物質にして根源的な精神(「細胞=魂」cell-soulにして「魂=細胞」soul-cell)から森羅万象あらゆるものの発生にして産出を説く進化論である。」
「最も近しい死者によって発動され、あらわになった潜在意識においては、生者と死者、精神と物質、生命と非生命、動物と植物、その他、ありとあらゆる対立が消滅してしまう。粘菌とは潜在意識によってはじめて見出される、潜在意識そのものを体現したような存在であった。」
「粘菌とは、精神の起源、つまりは「意志」の起源でもあった。熊楠は、法龍に向けて、繰り返し、意志(Will)から森羅万象すべてが生まれ、意志こそが森羅万象すべての基盤になっていると説いていた。」
「熊楠のいう意志は、「夢」に直結し、また「潜在意識」に直結する。」
「熊楠の粘菌の起源には、なによりもまず、ヘッケルの「モネラ」が存在していた。(・・・)ヘッケルが「モネラ」とともに提起した「個体発生は系統発生を繰り返す」というテーゼは、実は、ブラヴァッキーの『イシス』にも、マイヤーズの『人間の人格』にも、密かに貫かれている。曼荼羅をそのなかに含み、潜在意識をそのなかに含む南方熊楠の粘菌は、エルンスト・ヘッケルに端を発し、古生物学者コープ、神智学者ブラヴァッキー、心霊学者マイヤーズに受け継がれた諸主題に、一つの総合を与えるようなものであったはずだ。」
「モネラからプロティスタ(原生生物)、さらには植物と動物へ。そして、魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類へ。生命の系統発生を、母胎のなかの胎児は、一つの生殖細胞から哺乳類にいたるまで、縮約し、反復している。そして人間の個体としての形態が整った段階で、母胎から外へと生み落とされる。個体発生は、系統発生を繰り返している。モネラは、生命の起源であるとともに、個体の起源でもある。モネラとは「器官なき生命体」(ヘッケルの定義)、すなわち「器官なき身体」そのものであり、そのなかに無限の分化可能性を秘めた一つの「卵」(生殖細胞)である。遺伝子が発見され、ゲノムが解読されつつある現在、ヘッケルの「反復説」はもはや成り立たない。しかし、ヘッケルが生命の「発生」を見つめ続けていたことは事実であり、「原型」(胎児にして胚)への志向によって多くの貴重な報告がなされ続けたことも事実である。
南方熊楠の曼荼羅は、そこからはじまる。」
「熊楠が、マイヤーズの『人間の人格』に見出したものとは一体何であったのか。ブラヴァッキーの『イシス』が、曼荼羅の客観的な姿、「粘菌」に体現される、根源からの万物の流出と曼荼羅を示したとするならば、マイヤーズの『人間の人格』には、曼荼羅に主観的に「直入」する方法、粘菌のように変化し続ける「心」を通して曼荼羅と一体化する方法を、熊楠に示したのだといえる。」
「粘菌、曼荼羅、潜在意識。それらは熊楠にとって一つのものであった。その、ただ一つのものだけを、熊楠は、生涯をかけて探究したのである。」
「潜在意識は曼荼羅のように、あるいは粘菌のように構造化されている。
粘菌としての潜在意識、曼荼羅としての潜在意識は「夢」を通してその働きをあらわにする。」
「「夢」は混沌から秩序を生み出す。「もの」たちの重なり合いのなかから無数の論理の束、関係の束を導き出す。熊楠は、その生涯においても思想においても、互いに相容れない二面性を生きぬいた。顕わなものと隠されたもの、過剰に言語化されるものと根底から言語化を阻むもの、人為と自然、等等。熊楠はつねに二つの極のあいだを揺れ動き、二つの極の矛盾と相克のなかから、「夢」を媒介として、特異な神話的思考方法を編み出していった。熊楠の自他共に認める英文論考の代表作「燕石考」は、そのような熊楠的な神話論理の結晶として、図書館と森を舞台に、その二つのきわめて特色のある場所の連続性と断絶性のもとで成立したものである。マイヤーズの助けを借りることで見出された潜在意識のもつ論理的な側面、論理を生成していく側面を最もとくあらわしている論考でもある。粘菌(混沌=自然)とともにこの「燕石考」という論考(秩序=論理)こそ、熊楠が見出した潜在意識の構造を最も良く理解させてくれるものなのだ。」(・・・)熊楠にとって「論理」と「神秘」は表裏一体の関係にあった。」
「人間の論理を超えた「理」の観点から世界を捉え、複雑に絡み合った「事」の束を解きほぐしながら世界の意味を明らかにしてゆく。それが、熊楠が達成を目指そうとしていた「事」の学の全貌である。つまり熊楠の言う事の学とは、あたかも「夢」の謎を解き、「夢」を根底から理解することと等しい。」
「熊楠にとって「神話」とは、このように言葉と物が多極多層的に接合されることを許す、意味の磁場から立ち上がってくるものであった。それは心(内部)と物(外部)が二つに分割され、また一つに結合される場所のことである。(・・・)結局のところ、それは法龍に宛てて出された「曼荼羅書簡」に描き出された「曼荼羅」と別のものではない。」
「「燕石考」に体現された熊楠の神話論理は、心と物、精神と肉体の関係に再考を促すものである。そこに見出された曼荼羅状の構造は、人間と自然を通底させる。曼荼羅はまた、人間の心の構造から、自然の根源にある、森羅万象を生み出し続けている宇宙の根本原理である大日如来の心の構造を推し量る唯一の方法でもある。熊楠は、近代が可能にした新たな「科学」を利用しながら、中世以降の信仰原理(曼荼羅)を読み替え、そのことによって心・物・人間・自然・神という理念を再編成したのである。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
