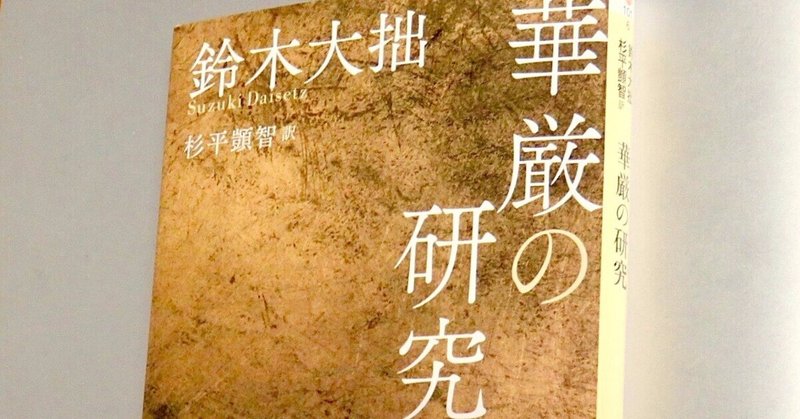
鈴木大拙『華厳の研究』
☆mediopos-2258 2021.1.21
原初の仏教は
自性を認めていないといわれる
自性とは実体であるアートマン
仏教の根本理念には
諸行無常
諸法無我
涅槃寂静
という三法印があるが
そこには自性はなく
関係性そのものが世界となっている
変わらないものはなく
すべては関係性のなかにあり
そのことを悟ることで
安らかな境地に至れるというのだが
であるならば
悟る者も安らぐ者もそこにはいないことになる
悟る者・安らぐ者という
意識がそこにあるとすれば
そこにはなんらかのかたちで
意識する者とその対象が
顕れているということになる
いってみればそれが無明でもあるのだが
しかしその意味では
無明であるがゆえに
世界は現象化しているともいえる
大乗仏教は
仏教ではないともいわれる
鈴木大拙の理解でいえば
究極の実在として
森羅万象のあらゆるものの根源に
「心」を置くからである
いわゆる大乗起信論的な如来蔵である
たしかに関係性だけで成立することを超えたとき
それを仏教と名づける必要もないのかもしれないが
世界には無数の意識が
多様なかたちで存在し現象化している
そしてそれらの意識・存在はすべて
その多様性のままで「空」であり
その空性において
すべてが光明荘厳されているととらえるのが
華厳の基本的な宇宙論ではないかと勝手に理解している
つまりすべての意識・存在は
その関係性において上下の階層はなく
すべてが中心であり
霊的な光に満ちながら無限に重なり合い
互いに鏡のように照らし合い
永遠に光り耀く「法界」が顕現している
解脱とはそのことを悟ることであり
すべては照らし合う存在である以上
自身だけにそれを留めておくことはできない
森羅万象を含むあらゆる存在は
ほんらいその法界にあるにもかかわらず
それに気づけずにいるから
気づきをもたらさずにはいられないというのが
悟った者としての菩薩であるといえる
しかし仏といい菩薩といっても
決して上下に階層化された関係ではありえず
中心と周縁をさえつくらない
すべての存在は中心であり照らし合っている
まさに自由の無限展開ともいえるのだ
そうした華厳の認識は
人と人だけではなく
森羅万象すべての関係性に
ほんらいの霊性をもたらしてくれる
そのことに
すべての存在が気づき
法界そのものが世界へと変容しようとする・・・
それは一なるものがみずからを映す鏡をつくり
みずからの姿を写しだし
みずから識ろうとするプロセスでもあるのかもしれない
その意味で多として顕れる存在に自性としての実体はなく
一なるものそのものが無としての実体であるともいえる
■鈴木大拙(杉平顗智 訳)『華厳の研究』(角川ソフィア文庫 令和2年12月)
「一切の存在をその多様性のままで空とするのは、『般若波羅蜜経』の偉大なる業績である。それはインド心性によってなし遂げられた最大の業績の一つである。自証聖智境界を仏教生活の基底として挙揚することは、禅が解釈する限りでの『楞伽経』の使命である。そしてまたこれを菩提達磨以前のシナ仏教徒が十分に理解し得なかったところである。しかしながら、もし禅匠たちがこれら以外になお何かを有していて、それによってかれらの働きを一層強化することがなかったとしたら、おそらく禅が東洋の諸民族の精神的生活の一般的形成においてあのようなめざましい成功をおさめることはできなかったであろう。壮大なあの直観----その広大さにおいて、その深さにおいて、またその透徹さにおいて、壮大なあの直観----『華厳経』の本質を形造っている壮大なあの直観----は、全世界の人々の霊的生活のためにインド心性が打ち立てた巍然たる記念碑である。かくして禅は必然的に『華厳経』の豪華なる王宮的建築の中にもまたその住処を打ち立てる。すなわち禅は『華厳』の無数の荘厳の一つとなる。他の見地からいえば、禅は発展して法界をかざるところの一切の荘厳となるのである。」
(安藤礼二「解説」より)
「『日本的霊性』の後、やはり華厳を一つの重要な主題とした『仏教の大意』(一九四七年)を経て、一冊の書物全体を費やして華厳のもつ可能性を論じ尽くしたのが本書、『華厳の研究』(一九五五年)であった。」
「大拙にとって禅と華厳に共有されているものとは一体何であったのか。一言でまとめてしまえば、この世界に存在する森羅万象ありとあらゆるものの根源、「究極の実在」である「心」を探究し、その「心」がもつ諸相、その「心」がもつ可能性を明らかにしてくれる方法にして実践であった。しかしながら、きわめて中国的に組織された教えである禅は、ややもすると「文字」による宗教的経験の体系化を軽んじ、ある場合には徹底して拒否してしまう場合もあった。それとは対照的に、きわめてインド的に組織された教えである華厳は、直観によってはじめて到達できる宗教的経験の根底にしてその諸相、「究極の実在」である「心」すなわち「法界」にひろがる風光を見事に、しかも美しく、大拙の言葉を借りれば、その広さにおいても深さにおいても、さらにはその透徹さにおいても、表現することを可能にしてくれた。華厳をあらためて自らのなかに取り込むことで、禅は限りなく豊穣な教えへと変貌することができた。第悦は、こう記している。すなわち禅は『華厳』の無数の荘厳の一つとなる。他の見地からいえば、禅は発展して法界をかざるところの一切の荘厳となるのである。」
それではまたなぜ、善財童子という若き一人の求道者、ごく普通の一人の有限の人間の前に、無限の仏が住まう世界、悟りをひらいた仏陀が生きる「法界」の扉がひらいたのか。大拙は答える。善財は、大乗仏教が理想とする「菩薩」を体現する存在であったからだ。『華厳経』(「入法界品」)は、その全体を通して、菩薩とはどのような存在であり、どのようぬ生きなければならず、その結果として、自らの前にどのような世界がひらかれてくるのかを明らかにしてくれる教えだった。『華厳の研究』の第二篇では、「大乗」の菩薩とはどのような存在であったか「小乗」の声聞と対比されながら論じられ、第四篇「華厳経における発菩提心」では、どのように生きれば菩薩となることができるのか、その条件である「菩提心」を起こすこと、あるいはそこで起こされた「菩提心」とは一体どのようなものであるのか、その詳細が論じられていた。そして第三篇「菩提の住処」では、「菩提心」を起こすことで「菩薩」となった者の前にはじめてひらかれる「法界」の在り方が具体的に論じられている。
菩薩として生きる。それこそが、大拙が理解した意味での仏教の本質、大乗仏教の東方的な展開にして仏教全体(インド、中国、日本)の総合でもある「東方仏教」(極東の仏教)の根幹に据えられたものだった。だからこそ、大拙がその探究の最初に選ぶとともに最後に選び直さなければならなかったのが、菩薩の理想にして理想としての菩薩の姿を描ききった華厳の教え、その教えが過不足なく十全に表現された「入法界品」だったのだ。それでは、菩薩とは一体どのような存在であったのか。大拙は、『華厳の研究』の第二篇のすべてを費やして答えてくれている。大拙は、簡潔にこうまとめている。「菩薩の本質は、有情のみならず非情までも含む一切衆生の正覚と解脱と救済とに関連する」。菩薩は自身だけの悟り(正覚)と救いを願わない。なによりも他者の、しかも人間のみならず草木や国土もそのなかに含めた森羅万象あらゆるものの悟りと救い、「一切衆生を究極の解脱、すなわちこの世界のものでない至福の状態に導くこと」を願う。」
「善財が無限に重なり合う楼閣のなかに見るのは自己の生がもつ無限の可能性だけではない。他者である弥勒の生がもつ無限の可能性をもまた同時に見るのだ。他者を救うことは自己を救うことであり、自己を救うことは他者を救うことであるからだ。自己のもつ可能性を尽くすことが同時に他者の可能性を尽くすことになる。
華厳の認識は、新たな社会関係、人間同士の関係のみならず人間と森羅万象あらゆるものとの関係性を再構築していくための手段とさえなるであろう。華厳の教えを基盤として、「霊性」としての体験を共有した、「霊性」としての社会関係が築き直される。自己の自由、自己の主体性を失うことなく、しかもそうした自己の内へと閉じこもるのではなく、自己を外なる無限の他者へとひらいていくことを可能にする。なぜなら、「光の本質的性質は相互に干渉し合うことなく、相互に妨げ合うことなく、相互に破壊し合うことなく、入り交じり得るところにある」からだ。華厳はそう教えてくれる。現在、われわれが切実にその実現を求めている、物質と精神の立場をはじめとするあらゆる差別にして区別、矛盾にして闘争、つまりは分断を乗り越えていくための社会的ネットワーク、「霊性」の光にもとづいた新たな社会的ネットワーク構築の可能性さえ夢想させてくれる。
しかも華厳を禅とともに考え、禅を華厳とともに考えることで、霊的な光に満ち、現代の集合論さえ先取りするような「毘盧遮那荘厳蔵楼閣」をごく普通の人々が生きる家に、あるいは禅僧の一つの理想である、あらゆる伝統や制度を粉微塵に打ち砕く「大破砕者」、さらには無一文にして無所有となった者が自由に生きる「無住」の場、どこにも「根づけられていない」場に、容易に転換していくことが可能になる。理論と実践が一つに総合される。そこでは、「仏はもはや天上の光に包まれた超越的存在ではない、われわれの中に歩み、われわれと共に語る、われわれと同様な一個の老紳士である、全く近づき易い見なれた存在である」。
そのような、どこにでもあると同時にどこにもない場所にこそ「霊性」としての心、すなわち「本願」としての心、大悲にして大慈の「菩提心」が立ち上がってくる。それが「存在」の故郷となる。すべての主観的な事象(精神)とすべての客観的な事象(物質)の根底にあるとともに両者を生起させる「実在」(大文字のリアリティ、すなわち真に実在する唯一のもの)、永遠に光り耀く仏陀が生きる「法界」が、おのずから顕現してくる。そここそが、鈴木大拙が最後にたどり着こうとした霊性の光満ちあふれる「住処」である。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
