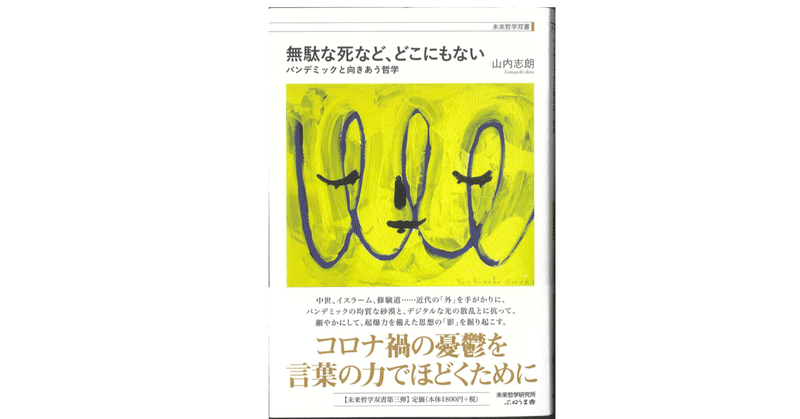
山内志朗 『無駄な死など、どこにもない』
☆mediopos-2424 2021.7.6
哲学は情念やからだが苦手だ
デカルトも情念を語ろうとし
メルロ=ポンティもからだを語ろうとしたが
思考することで成立する哲学は
とくにその思考が主語的であればあるほど
その相容れない矛盾のなかで
どこか迷路のなかに入り込んでしまうことになる
情念をそしてからだを語ろうとしても
それが思考されればされるほど
それは概念や論理にすり替わってしまうのだ
それは情念(受難)を生き
愛を説いたイエスの教えを
政治的な国家権力によって
教会が管理するようになったことにも似ている
アッシジのフランチェスコが
「第二のキリスト」と呼ばれたのも
失われていた聖霊的なありようを
取り戻そうとしたからなのだろう
聖霊の働きは
「教会を介することなく、
神やイエスに至るメディア」となるからだ
ヨハネ福音書にあるように
初めにことば(ロゴス)があった
ことばの内に命があった
ことばは肉となった
はずなのだが
それが知性や理性のもとに
管理されるものとなるとき
聖霊の働きは失われてしまい
ことばから情念(受難)や
肉(からだ)が失われてしまう
知性や理性のもとにあることばは
主語的なものだ
しかし情念やからだをもふくみ
知性や理性もそこから生まれ出ることばは
述語的なありようとしてとらえることで
聖霊的な働きを取り戻すことができる
「花が存在する」のではなく
「存在が花する」ように
ことばを述語的にとらえるとき
存在の根底にあるのは無であり闇だ
その無であり闇であるものが
自覚的に自己限定されることで
光としてのことばは生まれてくるのだが
その光としてのことばを哲学は扱えないでいる
故に哲学が死を語ろうとするとき
死はただ無への闇への帰還としか語り得なくなる
ことばに情念とからだを取りもどし
それを無であり闇であるなかから
産み出される光の創造としていくためには
哲学ではなくポエジーが必要となる
ノヴァーリスが学(科学/学問)は
哲学になったあとにポエジーとなると示唆したのも
哲学という壁を越えるためではなかったか
哲学に聖霊が降りるとき
そのことばこそがポエジーとなれる
知性も理性も
そして情念もからだも
ほんとうのことばとなって
歌うことができますように
■山内志朗
『無駄な死など、どこにもない/パンデミックと向き合う哲学』
(未来哲学研究所 ぷねうま舎 2021.6)
(「はじめに 死とは何か」より)
「いま、私の心を占めているのは、死を生の姉妹(sora nostra morte corporale)と捉えたアッシジのフランチェスコの思いを少し跡付けること、それだけである。」
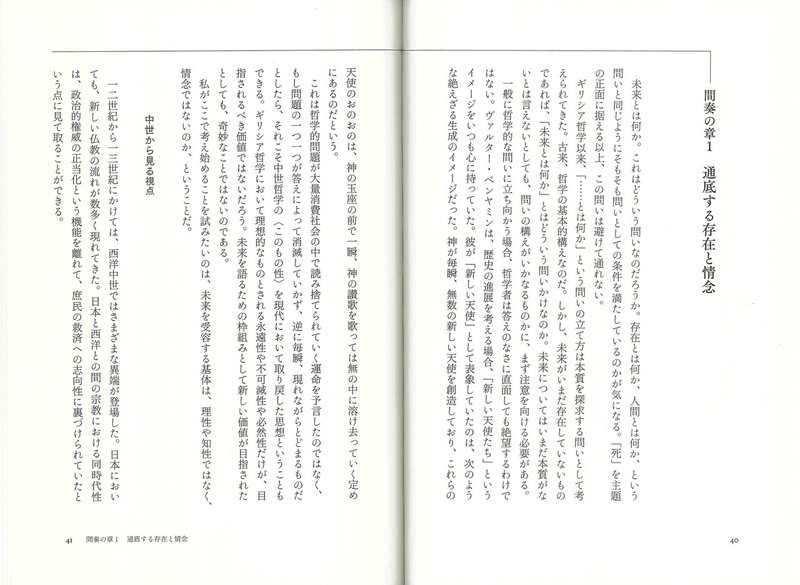
(「間奏の章1 通底する存在と情念」より)
「キリスト教の枠組みでは、情念(受難)は、政治的権威とは対極的なものであった。イエスは、サドカイ派やパリサイ派という体制側に立つユダヤ教の反発し、主流派の救済のみに目を向ける傾向に対立して、民衆に根ざした集団を形成していった。
フランチェスコが一三世紀初頭に「第二のキリスト」と呼ばれたのは、ローマ教皇庁が世俗的権威との関係への配慮に終始していたことへの反発が、イエスの原始キリスト教団への憧れのかたちをとって現れたということなのだろう。つまり、キリスト教は国家権力に対抗するものとしてあったにもかかわらず、キリスト教の国教化によって国家との共生的・相補的関係(協力関係)に巻き込まれてしまったのである。
政治権力との提携は、ローマ教皇や司教が、世俗君主や官僚と同様のものとなってしまうことを意味する。キリスト教が本来目指していた民衆の救済から逸脱してしまうのだ。一二世紀以降、宗教的権威の基盤が強固なものとなり、その権威を高めるにつれて、その傾向は強まった。その結果、一二世紀以降、さまざまな異端運動が現れる。
一二世紀の異端運動の特徴を示すキーワードとしては、リテラシー(識字)、女性、聖霊がある。リテラシーは異端運動を考える場合、特に重要である。聖書こそ、魂の救済、天国へ至る鍵となるものだが、聖書を読解することは、ラテン語を学び、その内容を理解できるだけの教育を受ける必要があった。そのような能力を持つ市民がごく少数であったが、一二世紀以降、経済的に余裕のある市民が聖書を購入し、時間的に余裕のある女性が読解のためのリテラシーを身に着け、教会の聖職者に頼らずに、自分たちで聖書を読む運動を広げていった。これが、一二世紀の異端を支えた基本的構図であった。
その場合、聖霊は教会を介することなく、神やイエスに至るメディアとなった。聖霊主義が無媒介性を重視するのは、媒介や順番を重視すると、既成の組織体制に取り込まれてしまうからである。」
「この聖書主義は、西田幾多郎や井筒俊彦が立脚した「述語主義」的枠組みで考えると理解しやすい。「花が存在する」のではなく、「存在が花する」という言い方が端的にその事態を表現している。実体という個別的で具体的で確定したものが最初にあるのではなく、未規定的で不定で曖昧なものが先にあって、そこから具体性が立ち現れてくるという枠組みである。
聖書主義的な枠組みは、時間論との折り合いがよい。すなわちそこに、不条理は発生しにくい。自然科学的・法則主義的世界観によれば、初期条件が定められると、その後は決定論的に科学法則に従って物事が生起するという枠組みが支配的であった。しかし新型コロナウイルスもそうであるように、予想できなかったことが人間社会では成立し、それがすべてを揺り動かす。東日本大震災もそうであった。」
「経済変動を予測することが、知性の証であると捉える知性モデルは過去のものだ。では、未来は予測不可能であって、ニヒリズムの中で生きなければならないのか。絶望の中で精神的に冬眠しながら生きていくことも有力な方法ではあるのだが。
私はここでふと感じる。未来を予測する器官(センソリウム)は知性や理性だけなのか、と。情念もそうではないか、と私には思われる。認識的であり、同時に情緒的な能力は不可能なのか、非知性主義に陥ることなく、未来を感じることはできないのか。それを考える一つの糸口を中世の聖霊主義に探ってみたいと思う。
情念が未来に臨む枠組みは、聖霊の時間に体知る機能と類似しているように思われるのだ。聖霊はいつも閾を乗り越え、閾の上で方向性を逆転させる機能を持っていた。正確に、述べれば、逆転というよりも、矛盾対立的・同時相互浸透である。人間が他者とのコミュニケーションにおいて、いとも容易に使いこなしている機能である。」
「宗教において重要な機能を有していた聖霊は、その機能をまったく失ってしまったのか。もちろん、その聖霊の復権を主張することは、危険な反知性主義を惹き起こしかねない。聖霊の無媒介性、直接性は危険な側面もあるのだから。」
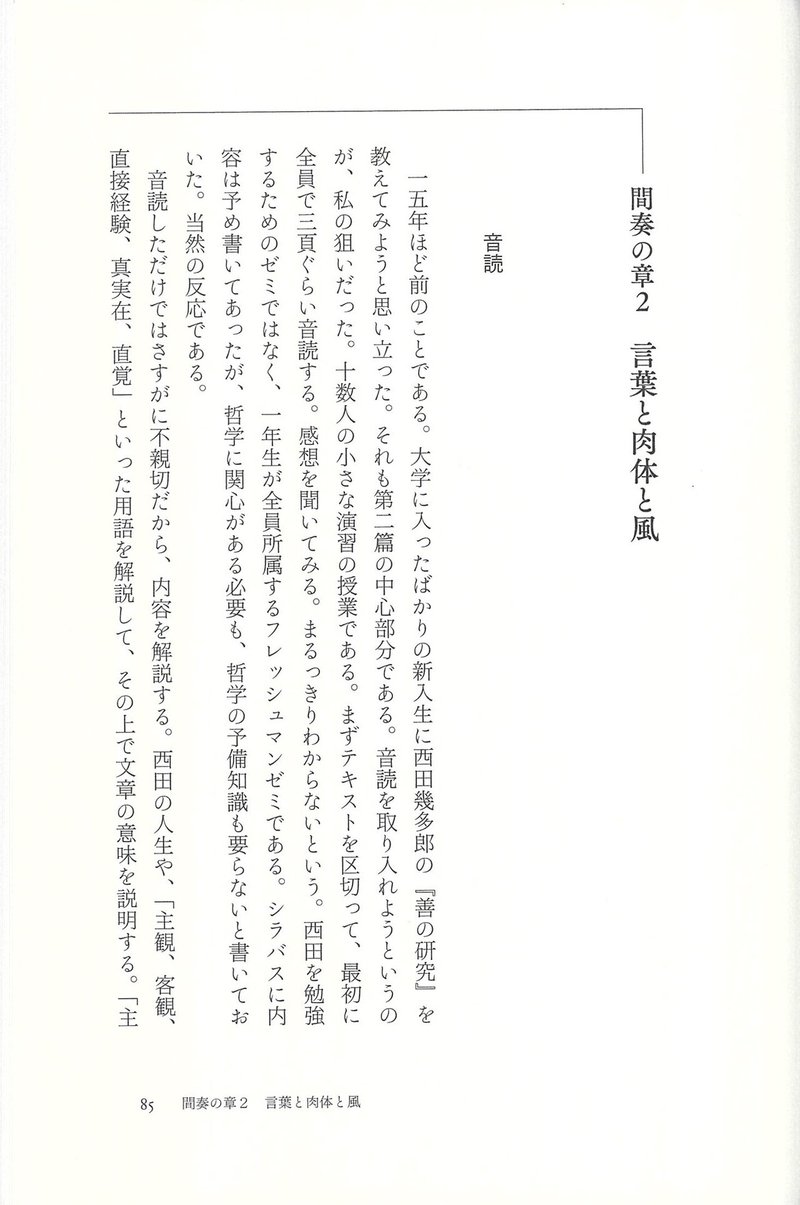
(間奏の章2 言葉と肉体と風」より)
「概念なき哲学は可能なのかどうか。経典や詩篇の読誦や典礼が意味なき呪文としてではなく働くように、言葉も肉体に直接働きかける通路を用意しているのかどうか。哲学を知性を介して理解する前に、体で体験することはできるのではないか。それもまた哲学との出会いのはずだ。私は哲学書を音読することこそ、開かれた出会いにつながると思う。哲学書は音読されるべきもので、そのとき哲学に向き合う肉体は身を開く。
概念が理解されるということは、そこから真なる命題を作れることだと考えられている。哲学の専門家は、難しい概念をつなぎ合わせて、真なる命題から構成される論文をいくつも作り上げることを求められる。
哲学を理解することは論文を作ることではないし、それを求められるわけでもない。暗記して風呂に入りながら、いや砂浜で風に吹かれながら口ずさんでみることもできる。しかし、テキストをそのまま風景が浮かぶまで繰り返し読んでみるのもよい方法だ。いや、風景が浮かばなくてもよい。経典を読むように響きを楽しむだけでもよい。中世のスコラ哲学の浩瀚なテキストを目に、読み方に難渋し、あまりに時間不足の中で絶法しているとき、音読することは一服の涼を得るに等しい。音読によってスコラ哲学が直接声として体に染み込んでくるような感じがする。その時、声は声の風ではない。肉を持っている。
直接、言葉が体に入り込んでくる。この感覚は、どこかほかのところでも味わった気がする。例えば、光明真言。(・・・)光明真言を唱えるとき、何かが体に入り込み、刻みつけられ、沁み込んでくる。もちろん、それはただの思い込みであって、青空の下にさわやかな風が吹いているだけだ。おどろおどろしく感じるだけかもしれない。だが、この具体的な肉体の感じは何か。」
「<存在>は言葉によって語られるのか。いや、言葉は<存在>を語ることができるのか。そう問いたくなるのは、<存在>こそ語ることの可能性の条件のように見えるからだ。言葉が<存在>を語るということは、何に似ているのか。私たちが父母を産み出すこと、それどころか地球や宇宙を産み出すことと似ているのかもしれない。それは途方もないことではない。ライプニッツのモナドは無限の宇宙を表現し、そういった無限のモナドによって構成される宇宙を一つひとつのモナドが表現することで、モナドの中には、幾重にも重なる無限性の層ができているのだ。モナドの表現とは、関数的な対応関係というよりも、肉体が肉体を貫くこととも言えるのではないのか。<私>とは、光源ではなく、奈落、根底、暗闇、深淵などだ。底を見ると、コギトも自己もなく、闇だけが広がっている。自己が自己に語りかけるとき、深淵が深淵に呟きを投げかける。そして、呟きだけは暗い谷底に響き渡る。
言葉が<存在>を語ってしまうことは途方もないことだ。形而上学は、存在である限りの存在を探求する。これは宇宙を支える亀が自分の足元を見ようとすることに似ているのではないか。<存在>は己を求めるあまり、自分自身の中にめり込んでいこうとする。
この絶望的な努力の中では、<存在>が稀薄なものであり続けるのではなく、粗い網でありながら、そこに膜が張り、硬化して、いつのまにか織り地となり、ついには壁になっていく。そして、言葉はその堅い壁に消えない傷を残す。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
