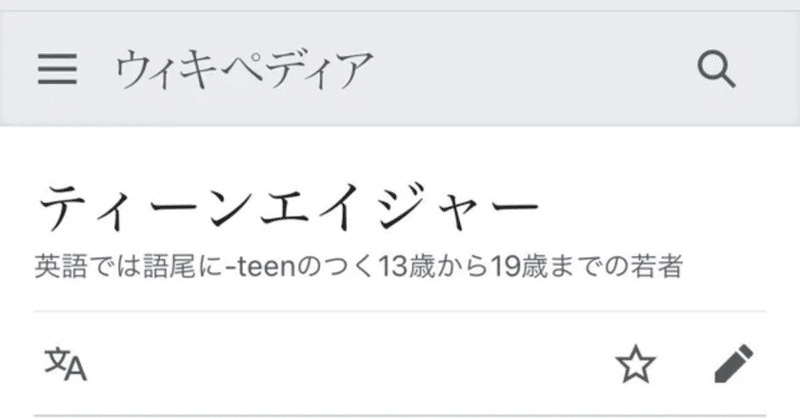
短編小説 『ティーンエイジャーの憂鬱』(五)
※前回
五
「若いねえ」
大人になっても絶対に言いたくないと思っていた言葉が当たり前に出るようになったのはいつからだろう。
少なくとも雲行きが怪しくなったからといって喫茶店で時間を潰して外の天気を窺うなんて守りの姿勢ではなかったとは思う。
店に入って三十分程経った頃か。背後の席で何やら騒動が起こっているらしかった。沸々とこみ上がる"おばちゃん魂"はやはり私が年相応に老けたという事なのかもしれない。こうなれば恥は無い。いざ。
振り返ると一組のカップルに若い男が乱入しているシーンであった。会話は途切れ途切れで確認は難しい。
「――!」
声にならない大声を最後に、乱入した男は座っている女の子の手を掴むとズンズンと店の外に出ていってしまった。
残された男はやや伏し目がちに頭を垂らせ、カップの中身を啜っていた。
「若いねえ」
思わず口にこぼれてしまった。伊達に女性という性を数十年過ごしてきたわけではない。腕を取られた彼女の顔はまんざらではなかった様に見えた。いや、きっとそうだ。そうなのだ。
甘酸っぱい青春の風が心を撫でる。しかし、風はだんだんと雲を集め、雨を降らせ、果てには暴風雨に発展し、私のこれからの所業を苛んだ。
左手の薬指の指輪をさする。
「若いなあ……」
誰に対してだったのか。受け取ってほしい相手がいる気がした。しかしそれは、これから会う男性ではきっとないのであろう。それだけはわかった。
先程の一件で騒がしかった店内はすっかり元通りのなりにおさまっていた。ふと背後の取り残された彼を見ようと振り返るがそこに姿はなかった。
結局こうだ。野次馬根性と縁がないわけないじゃないか。今日に始まった事ではない。いつだって平凡な風景や日常に刺激がほしくて、求めて、行動している自分がいたのだ。しかし、刺激を求めるために私が差し出せていたものはただの若さでしかなく、また無限でないことを知ったのが差し出せるものが無くなってからだというのはありきたりな話なんだろう。
その証拠であり結果が薬指におさまっていつでも私を見ている。
"視線"も最初は慈愛に満ちたものであった、いや今でもそうだ。しかし、私という人間はどうしようもなく我儘で、贅沢で、愚かだった。幸せは風化していくものだと思い込み、その先に求めるものは結局その幸せの破壊である。私はもう求めるものと釣り合うだけの対価は持たない。なら、幸せを差し出すことしかできない。
店内の時計に目をやるといい頃合いだった。
席を立ってレジへ向かう。扉から連なって入ってくる客たちが酷く濡れており、どうやら天気は暴風雨に変わったことを知った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
