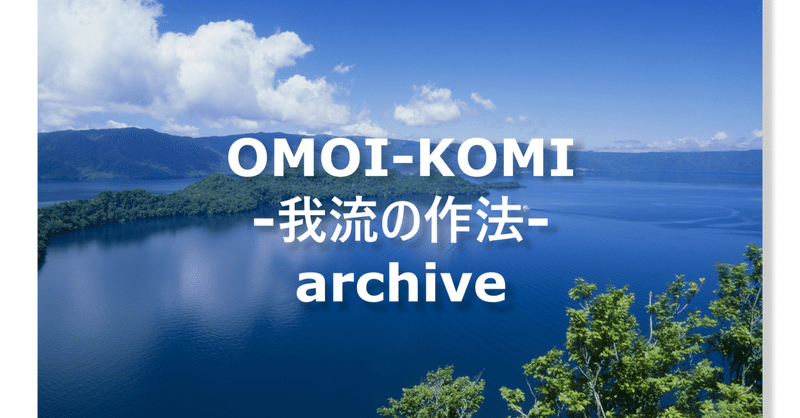
人は意外に合理的 新しい経済学で日常生活を読み解く (ティム・ハーフォード)
同じ著者の本として、以前「まっとうな経済学」を読んでいます。本書はその「拡大版」とのことです。
著者は、昨今の行動経済学の研究内容を理解しつつも、それに反論しています。多くの行動経済学の実験は、通常の生活環境ももとでなされたものではなく、いつもとは異なる不慣れな環境下で判断を強いられていて、その結果にはバイアスがかかっているとの考えです。
すなわち、人々は通常の環境下においては、ほとんどの場合「合理的な判断」をしているとの主張です。
著者は、本書における「合理性」を以下のように定義しています。
(p23より引用) 合理的な人はインセンティブに反応する。あることをするコストが上昇すると、人はそれをしなくなる。・・・選択肢を比較検討する際には、合理的な人々は全体的な制約を念頭に置いて評価する。つまり、どれか一つの選択肢のコストと便益だけではなく、予算全体を考えるということだ。そして、現在の選択肢が将来もたらす結果も考慮する。
本書では、いくつもの社会的な課題を取り上げて、課題を産み出してしまう個々人の行動の「合理性」を解説していきます。
そのうち、「都市」への経済の集中・地域格差の拡大を取り上げた章の中で、「通信技術」の位置づけを論じた箇所がありました。通信技術の進歩は、地域間の情報格差を解消し都市への集中を無用化するものか否かとの論点です。
(p263より引用) 経済学用語でいえば、デジタル・コミュニケーションはおそらく対面での会合の代替財であるのとまったく同じように、その補完財でもあるのかもしれない。そして、デジタル技術が対面での会合の補完財であるなら、対面で会うことを容易にする都市の補完財でもある。
著者は、偶然性も含めた密なコミュニケーション空間としての都市の役割を重視しています。
巨大都市は、リアル・バーチャル双方のコミュニケーションの深化・拡大により、ますますイノベーションの発信地となるとの考えです。
(p270より引用) 因果関係の連鎖の方向は、生産性から多様性ではなく、むしろ多様性から生産性へと向かっているようであり、文化の多様性はともかくも都市の生産性を高めるというのがいちばんそれらしい説明になる。
このところ「行動経済学」関係の本を何冊か読んでいるので、本書の論旨は、それらとの対比という意味で有効でした。
「経済は感情で動く」とか「予想どおりに不合理」といった本で紹介されている「非合理性」は、神経経済学的アプローチも採り入れており「個々人ベース」の行動例が多いように感じます。
他方、本書で解説されている「合理性」の主体は、「集団」が主になっています。ただ、それらの説明に使われている例示が、欧米社会の在り様を前提としているので、正直なところちょっと腹に落ちにくい印象を持ちました。
その点では、同じ著者(ティム・ハーフォード)の前作(まっとうな経済学)の方が取っつきやすいですね。
最後に、本旨とは全く異なるのですが、本書を読んで気になった言葉をご紹介します。
(p91より引用) 2005年にノーベル賞を受賞したとき・・・、シェリングは受賞記念講演の冒頭でこう語りかけている。「この半世紀のあいだに見られた最も劇的な出来事は、起こらなかった出来事です。私たちは、核兵器が怒りにまかせて爆発することなく、60年という歳月を過ごすことができました」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
