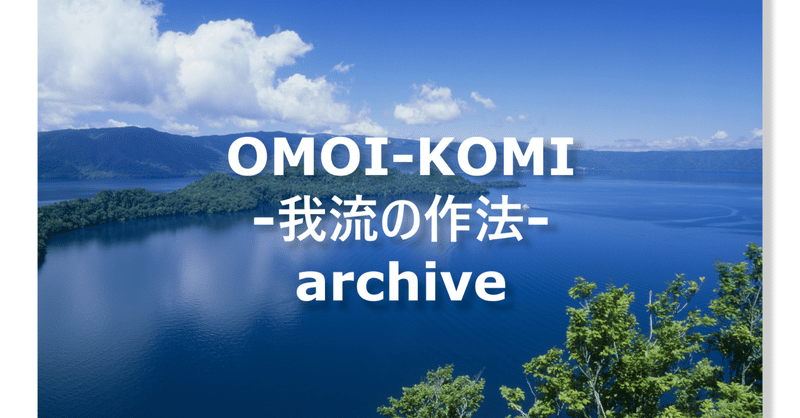
雪 (中谷 宇吉郎)
ずっと気になっていて、いつか読んでみようと思いながら今に至った本です。
専門的な研究内容の説明は最小限にとどめつつ、一科学者としての、科学に取り組む純朴な姿勢、そこに住む人々へ科学をもって貢献したいとの真剣な想いが丁寧に書き込まれた著作です。寺田寅彦氏に師事したとの経歴も頷けます。
著作の中心は「雪の結晶」の研究の紹介で、雪の分類・雪の人工生成に関するくだりは大変興味深く読めました。
たとえば、こういった記述です。
(p104より引用) (観測の)結果を整理して見てはつきりと分つたことであるが、殆どすべての降雪は各種の結晶の混合から成つて居るのである。・・・
かういふ現象は、上空の気象状態が非常に複雑だといふことを示すのである。即ち上空の各層の気象状態が夫々異り、各々の層で別の形の結晶が出来、地表に近い所で出来た結晶はその儘に近い形で地表に達し、上層で出来たものは落下途中で更に色々な成長をなして地上に達する。所が結晶の形によつて落下速度が異る為に、落下の途中で前後が生じ、色々の形の結晶が入り乱れて同時に地上に達するものと思はれる。それに上昇気流や下向気流が加はるので問題は一層複雑になるのであらう。
その他、地道な研究に愚直に取り組む学究の想いが垣間見られるフレーズをいくつかご紹介します。
まずは、「日本に根ざした研究へのプライド」を示すコメントです。
(p14より引用) アメリカで立派に役立つからと言つて、そのまゝそれが雪質の全然違ふ日本で立派に役立つなどと考へるのが既に最初の錯誤であらう。アメリカへ支払ふラッセル車一台の購入費を投げ出して、日本に降る雪の性質を根本的に研究したならば、日本のために真に役立つ除雪車は必ず出来るに違ひない。鉄道のみに限らず、あらゆる部門でかゝる哀しむべき事実が数多く行はれてゐることであらう。
もうひとつ、「顕微鏡写真の弊害」について。
(p32より引用) この点で顕微鏡写真の発達はかへつて、一時科学的な雪の結晶の研究を阻礙したとも言ひ得るのである。・・・つまり一口に言へば、顕微鏡を覗いて見て、美しくないものは写真に撮らない。模様的に美しく、しかも平面的なもののみを撮る傾向がある為に、一般の人々に雪の結晶がさういふものだと思ひ込ませるやうになつたのである。
確かに、私も「雪の結晶といえば、この形」といった固定観念を持っていました。本書で紹介されている結晶の分類についての解説で、その多種多様な姿を知った次第です。
さて、本書ですが、ひとつの研究に対し一途に真正面から取り組んできた科学者の、静かではありますが熱い気概がしっかりと感じられる佳作でした。
(p149より引用) 研究といふものは、このやうに何度でもぐるぐる廻りをして居る中に少し宛進歩して行くもので、丁度ねぢの運行のやうなものなのである。
「附記」でもこう語っています。
(p160より引用) 或る主の仕事は、何年やつてもその効果が蓄積しないものであるが、科学的の研究は、本当の事柄を一度知つて置けば、その後の研究はそれから発達することが出来るのであるから、さういふ意味で決して迂遠な道ではなく、寧ろ最も正確な近路を歩いてゐることになると少くとも科学者はさういふ風に思つてゐるのである。
著者は、謙遜して以下のように書かれていますが、科学の説明に止まらず雪国の生活をも思いやった素晴らしい内容だと思います。
(p158より引用) それで極めて平凡な一人の学徒の平凡な研究の話も一部の読者には興味があるかも知れないと思つたのがこの本を作つた主旨である。もし料理屋の立派な御馳走を喰べ馴れて居る人に、茶漬のやうな味を味はつて貰へたら望外の喜びである。
第1版は昭和13年の岩波新書。いかにも旧仮名遣いが似合う作品です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
