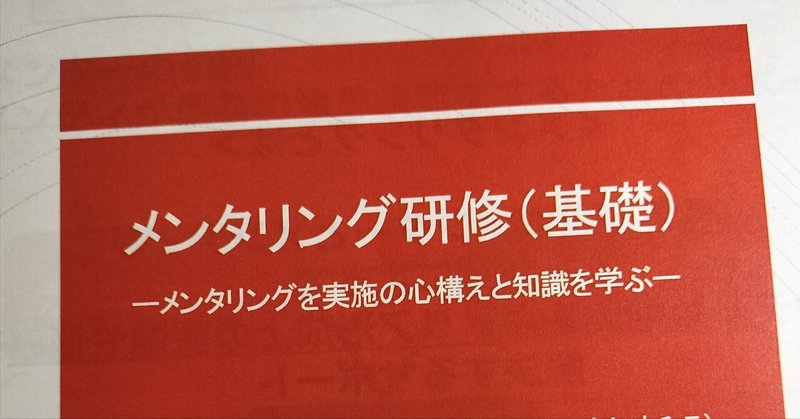
「メンタリング研修(基礎)」を受講してきた!
『毎日note365』16日目。
昨日、メンタリング研修を受講してきました。
今、ふくい女性財団に「社外メンター」として登録していて、昨日はその登録社外メンター向けの研修でした。
ふくい女性財団は今年度、「社外メンター導入制度」という事業をスタートさせていて、私たちは希望のあった各企業に派遣される社外メンターになります。
事業開始にあたり、メンターとしての基礎を学び直す目的で実施されたのが今回の研修。
登録社外メンター全員が、福井県が主催する女性リーダー養成講座を修了していて、その講座のプログラムの中で一度、メンタリングの基礎的なものを座学で学びます。
なので、座学的な内容はそこそこに、研修の半分以上はロープレでした。「15分ロープレ+10分振り返り」×3セットという、もりもりのロープレ。(キャリコン養成講座を思い出す)
前置きが長くなりましたが、今日のnoteは、研修の簡単なおさらい(アウトプット)と、研修後に議論された「女性活躍推進」についての話を書きます。
メンタリングとは
メンタリングについて、まずは研修資料のフレーズを拝借。
<メンタリングとは>
経験豊富なメンターとメンティが、対話によってメンティの抱えるキャリア形成上の課題や悩みを解決するサポート
少し自分でも調べてみましたが、アメリカの自己開発方法として知られているんですね。
こんな説明もありました。
POINT1 ~自由な対話であること
職場での対話というと、仕事にフォーカスしてしまいそうですが、プライベートなことも含めて、感じたこと、思ったことを何でも話し合えることがポイントです。
POINT2 ~楽しめること
何でも話し合えるためには、お互いに楽しめる時間であることが必要です。メンタリングを続けることで深まります。続けるためにも、楽しめる時間にしたいものです。
POINT3 ~共に成長すること
メンタリングは、メンティーのためだけのものではありません。メンターの成長も目的となっています。むしろ、「メンターの成長の方に効果があった」とするアンケート結果もあるほどです。
改めて調べてみると、「メンタリング」に対する定義や意味づけは、少し曖昧なんですね。おそらく場面によって求められるものも得られる効果も異なるから、そういう自由度の高さや柔軟性も含めてメンタリングの良さ、と言ったところでしょうか。
メンターの役割(3つの要素)
今回の研修で、一番納得感が強かったのがここです。
メンターの役割についての説明。
メンターの役割は「メンティが最善の意思決定をするためのサポート」をすることで、それは3つの要素に分解されます。
要素1:カウンセラー
カウンセラーは「整える」人。
必要なのは「承認」と「傾聴」。
メンティが語れるように関わることがポイント。
メンティは課題や悩みを抱えているので、気持ちを落ち着かせたり、一緒に状況を整理したりする役割がこれです。
要素2:コーチ
コーチは「サポートする」人。
必要なのは「思考を拡げ、思い込みを外す問いかけ」。
「仮に〜〜だったら?」「もし私(メンター)だったらどうすると思う?」といった質問をきっかけに、メンティが自分で気づくような関わりをする役割がこれです。
要素3:コンサルタント
コンサルタントは「知識や情報を提供する」人。
必要なのは「押し付けではない、情報提供」。
求められていないアドバイスは不要なので、自分語りをしないよう要注意。自分の実体験も貴重な情報なので、調べればわかる情報よりも、その人が体験してきたリアルな知識や情報を、メンティのニーズに合わせて提供することが大事だそうです。
メンタリングの流れ
これは備忘録的に。
事前合意(その場の目的、意義の共有)
役割の共有(メンティが主役)
自己紹介(安心感の醸成)
テーマの問いかけ(メンティ話したいことを聞く)
テーマの背景(なぜそのテーマなのか、背景やきっかけを知る)
今日の方向性(何をどのようにしたいか、メンティのゴールを確認)
※目の前の課題を解決したくなりがちだけど、そこではなくて「中長期的な視点でのサポート」を忘れないことが重要。
ロープレの感想
「15分ロープレ+10分振り返り」×3セット、みたいなロープレはキャリコン養成講座以来だったけど、不思議なことに養成講座の時みたいな緊張がなくて、純粋にとても楽しかったです。
ただ、「アドバイスをする」というところは、本当に難しいなと思いました。「アドバイスをしない」という縛りがあった方が、断然やりやすい気がする。
「アドバイスをする」という意識を持つと、すぐに自分語りをしてしまいそうになるし、自分の経験と重ならない悩みの場合は何が言えるのか考えるのに時間がかかってしまいました。これは場数を踏むしかなさそう。
講師の方が言うには、メンティの悩みと自分の経験が重ならない場合、その悩みの抽象度を上げて、自分の経験値が生きる部分を探して、そこからアドバイスをする…という感じらしいけど、その思考を回せるようになるには練習が必要だと感じます。
別にメンタリングの場でなくとも、普段子どもたちと話している中で練習できそうだから、実生活で「頭の回し方」を意識しようと思いました。
女性活躍推進は何のため?誰のため?
研修後、社外メンターの交流会がおこなわれたのですが、そこでは「女性活躍推進」についての話がめちゃくちゃ盛り上がりまして。
・「女性活躍推進企業」への登録がパフォーマンス化しているのでは
・変化した女性が職場に理解されず閉塞感を抱いてしまう課題
・本音と建前(女性が下に見られている現実はまだまだある)
・「女性」にフォーカスしすぎかも
・特別扱いされる「女性」の肩身の狭さ
・男性が感じているであろう置いてけぼり感にも目を向けたい
・「女性活躍」を掲げることで逆に妨げられる多様化
・「女性活躍」と言っていること自体が古いのでは
要点だけ挙げるとザッとこんな感じですが、議事録を取ればよかったと思うくらいの内容でした。
「社外メンター」という、ある種の同質性のおかげか、「そう!そうだよね!」「やっぱりそこだよね〜」という共感ポイントがたくさんあり、どなたの話も刺さる。自分の課題意識もさらに明確になり、とても有意義な時間でした。
私が考えていることについては、また改めて書こうと思います。
今日は研修の記録なので、ここまで。
ではまた明日。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
