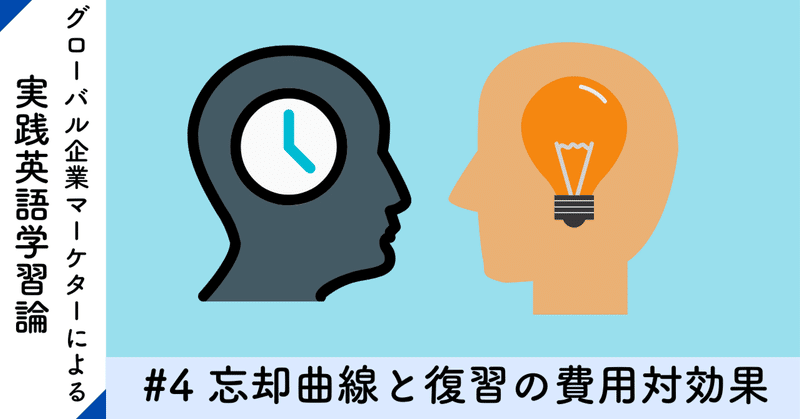
”#4 忘却曲線と復習の費用対効果 ” 「グローバル企業マーケターによる実践英語学習論」
忘却曲線とは
英語学習の中でも、単語、熟語、文法の習得には、いかに効率的に記憶に定着させるかがポイントになります。
学習内容と記憶についての研究結果で、エビングハウスの忘却曲線というものがあります。(出典:代々木進学ゼミナールのページのグラフ)

私は高校生で受験勉強をしているときにこの忘却曲線の存在を知り、「復習をしなければもったいない」と思うようになり、復習にしっかり取り組むようになりました。
復習の効果
また、カナダのウォータールー大学の記事によれば、復習は回を重ねるごとに効率的になっていくことが示されています。

Day 1 で新たな知識を講義によって学習した時を100%として、復習を全くせずにDay 2以降にどれくらいその内容を覚えているかを示したのが黒の線です。Day 30では2%~3%くらいしか覚えていないという結果になるようです。
一方で、復習をすれば短い時間で記憶を100%に戻せるということを示したのが、オレンジの線です。Day 2に10分だけ復習をすると記憶が100%に戻り、同様にDay 7に5分、Day 30では2-4分復習するだけで記憶が100%に戻り、長期記憶として定着するとのことです。
復習の費用対効果
上記の研究をもとに学習の費用対効果について考察してみようと思います。
計算式としては下記を用います。計算結果の数字が大きいほど、費用対効果が高い(=少ない時間で効果的に学習できる)ということになります。
<学習の費用対効果の計算式>
学習の費用対効果=100 (100%の記憶がある状態)÷ 記憶が100%になるために費やした学習時間(分)
初めての学習では北米の大学の一般的な講義の時間である60分を学習時間と設定し、復習にかかる時間は上記グラフに記載の時間をもとにします。すると費用対効果は下記のように算出されます。(小数点第一位四捨五入)
初めての学習(Day 1):1.7
一回目の復習(Day 2):10
二回目の復習(Day 7):20
三回目の復習(Day 30):25~50
三回目の復習の際の最大値50は初めての学習の際の1.7の約30倍です。つまり、復習は、初めての学習に比べて、最大約30倍の費用対効果があるということになります。
こんな費用対効果の高い復習を疎かにしていては、大損ですね。
私の復習サイクル
最後に私が学生時代に実践していた復習サイクルについて説明します。
私は単語帳や文法の参考書に関して、下記のサイクルで回していました。
初めての学習:Day 1
一回目の復習:Day 1の翌日 (Day 2)
二回目の復習:Day 2の一週間後 (Day 8)
三回目の復習:Day 8の二週間後 (Day 21)
四回目の復習:Day 21の1ヶ月後 (Day 50)
五回目の復習:Day 50の2ヶ月後(Day 110)
上記サイクルで回すために、単語帳はこれ、文法書はこの本、というように特定の本を決めて、学習した日の日付を各ページの肩の部分に記載して復習履歴の見える化もしていました。
上記サイクルは勉強が本業の学生だからこそできたサイクルだと思うので、社会人の生活サイクルで上記をこなすのは少し厳しい気もします。仕事をしている今の自分がサイクルと回すとしたら、上述のウォータールー大学の記事も参考に、下記くらいが現実的かと思います。
一回目の復習:Day 1の翌日 (Day 2)
二回目の復習:Day 1の一週間後 (Day 7)
三回目の復習:Day 1の1ヶ月後 (Day 30)
一般論としては、復習の大切さを理解した上で、具体的なサイクルに関しては、自分にあったものを試しながら見つけるのが大事かと思います。
また、復習は上述の通りかかるコスト(学習時間)が圧縮できるので、「机でしない英語学習」にて紹介したように、日々の習慣の中で復習すると継続できるかと思います。
今回も読み進めていただきありがとうございました。
よければ下記の記事・マガジンもご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
