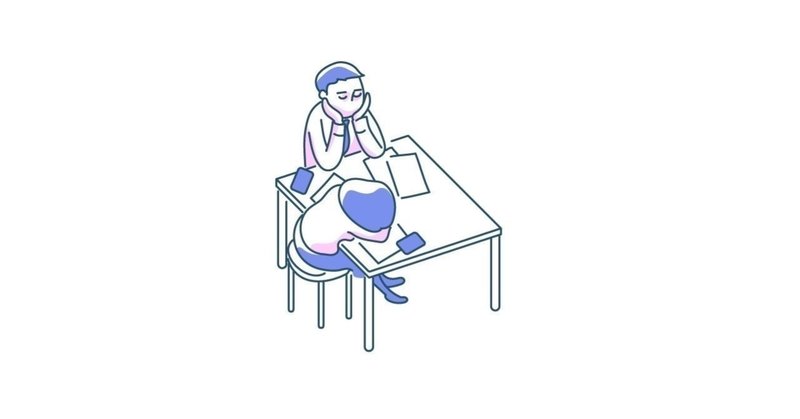
「仲間や家族をつくる」ということについて。
こんな記事を読みました。
タイトルにもあるように、「やってあげている」という気持ちで取り組むと、どうしても見返りを求めてしまい、それが「やってもらっているつもりがない」相手を呪うことに繋がるわけです。「やってあげる」くらいだから、本来幸せを祈っていた相手のはずですよね。にもかかわらず、「やってあげる」ことによって、むしろその相手を呪うという真逆の結末に意図せず至ってしまうわけです。
この現象は、まちづくりの現場でもしばしば見られることであり、それゆえまちづくりを頑張る人ほど「疲れてしまう」ということが起こります。このことについて、拙著『モテるまちづくり』で、そのメカニズムと処方箋を記しました。
さて、以前も書きましたが、僕らは生きる上で、自然界の富の消費をしなければなりません。しかし、その富の配分は、常に多い少ないが偏ります。そうすると多いところは余らせて腐らせるし、足りないところには飢餓と貧困が生まれます。この自然界の富の偏在を、人の手で移動して均すことを「経済」と呼ぶわけです。
人間集団は、みんなで生き延びていくために、経済を回すことが必要なんですね。この経済の回し方には大きく2つあって、贈与と交換です。
そのうち贈与というのは、「一方的に贈り与える」ということです。シンプルですね。この贈与で経済を回すプレイスタイルを「贈与経済」といいます。贈与って言うと、なんだか特殊なことに聞こえますが、今だったら例えばプレゼントとか、ボランティアとかいうものがそれです。
一方、何かをしてもらったら等価のお返しをせねばならない。そういう交換原則で富を移動するプレイスタイルを「交換経済」といいます。「やってあげたんだから、相応の対価を支払うべきだ」という信念は、交換経済の考え方です。
私達が暮らす社会は交換経済が支配的です。だから交換スタイルが身に染み付いています。が、贈与経済のプレイスタイルは実はあんまりなれていないっぽいんですよね。
贈与と交換には、それぞれ強みと弱みがあります。贈与の強みは、一方的に贈ればいいわけですから、富の移動にあたって媒介となるものが要らないってことです。交換だと、等価でかつ相手がほしいと思っているものをお互いが持っているという条件がないと成り立ちませんよね。これを「欲望の二重一致の困難」といいます。それを解決するには等価交換を「ツケにする」のがよくて、ツケましたよ、という証明書、すなわち借用証明を代用品として交換します。これが通貨、つまりお金の原点であるという説があります。交換で経済を回そうとするとそういう媒介を用意する手間が発生するので、その点、贈与は贈りつけるだけでいいので、富を移動することだけに関していえば、コスパいいです。
一方で、この贈与ていうやつ、実は厄介な性質もありまして。それは「贈与の二重の不確定性」と呼ばれるものです。さっきから二重、二重いってますが。この「贈与の二重の不確定性」ってのは、贈る側がどういう意図で贈っているのか、ということと、受け取る側がその贈り物をどう評価するのか、ということが、事前に確定しないっていう性質のことです。例えば、友達にプレゼントを贈ろうとするとき、相手が喜んでくれるか迷惑に感じるか、事前にわからない。あるいは友達が贈り物をくれたんだけど、これが好意からきたものかあるいはなんらか別の意図があってのことかわからない。このように、贈り手と受け手との間で二重に確定しないという性質があります。これが二重の不確定性です。この不確定性があるがゆえに、贈与のつもりが相手を嫌がらせたり傷つけたりしてしまったり、逆に善意の贈与を装うことで相手に負債を負わせたりといったような濫用ができてしまうんですね。この二重の不確定性がもたらすリスクっていうのが、贈与の弱みです。
その点、交換は便利で、贈る側がなんのつもりでやっているのか、受け取った側が喜んだかどうか、確定することができます。だって贈る側は対価が欲しくてやるんだし、受け取る側は、嬉しくなければ対価を支払わないということで贈り手から自己防衛ができるんですよね。これが交換の強みです。
ところで、以下、ちょっと長めの余談ですが、せっかくまちづくりで飯を食っているっていうポジションにいるので、その立場から付け加えて語っておくとですね。良いか悪いかは別として、まちづくりはなんだかんだ地域住民のボランタリーな参加に依存している営みです。では、まちづくりの現場では、純粋贈与の消耗戦性や、二重の不確定性リスクはどのように回避されているのでしょうか?
この点について僕は、「無意識的結合生産プロセス」という概念を提示しました。これは、人々が行為によって得られる結果に自己充足する(コンサマトリーである)ことで、他者からの返礼をせずとも消耗戦にならないで済むという理論で、一見自己犠牲的消耗戦ボランティアが成り立つかのように見える状況を説明しました。
しかし、このような無意識的結合生産は、一見自己犠牲的消耗戦ボランティア活動が成り立つかのように見える現象を説明しましたが、これはあくまでも自己充足的に行われるものであり、他者への貢献は約束されていません。だから、自己充足を前面に出して「やりたいことをやりましょう」と呼びかけるボランティアの普及戦略のデメリットとして、他者貢献をもたらさない矮小な自己満足に陥るリスクがあるわけです。しかし、他者貢献をうかつに事前に約束しようとすれば、交換原則に基づくビジネスへ接近してしまうのでした。
なので、最近僕は「やりたいことをやる」よりも「やりたくないことはやらない」、そして「特に積極的にやりたいわけではないが、やってみてもいいと思えることをやる」という言い回しの置き換えを提案していたりします。余談ですが。
さて、余談にそれてしまいましたが、ここまでの話を踏まえた上で冒頭の記事の話に戻すと、そもそも、経済を回すプレイスタイルとして、贈与と交換という2つのプレイスタイルっていうのがあって、それぞれ強みと弱みがあるってことなんですよね。そして、それぞれ状況に応じて向き不向きがある。
で、じゃあそれぞれどんな状況に向いているのかっていうと、贈与は、相手の意図や評価が事前にわかっている間柄においては、二重の不確定性が弱まってデメリットが減るので向いています。だから付き合いが長く、気心が知れた家族や仲間といった間柄では、あんまりお金で富の移動をしないのが一般的なようです。
一方で、贈与は相手の意図や評価が事前にわからない間柄においては二重の不確定性リスクが無視できない程度に大きくなります。例えば、見知らぬおっさんから通りすがりにもらったおにぎりは怖くて食べれませんね。その点、コンビニや飲食店で出される食べ物を、僕らがなんだかんだ無邪気に口に入れるのは、「この人は対価が欲しくてやっているんであって、おかしなものを食わせれば私から対価が得られなくなるんだから、そんなことはしないだろう」という交換の思考が働くからですね。
逆に言えば、富の移動に交換というプレイスタイルを持ち込むっていうことは、「相手の思考や意図に対する不信の表明」になっちゃうわけです。だから親しい間柄に交換スタイルを持ち込むのが「なんか変な感じ」になるんですね。
つまり、本来、贈与でやりとりすべき場面と、交換でやりとりすべき場面ていうのがあって。そのどっちかに偏るのが変だったということなんですよね。そこをわからないまま、本来贈与で回すべき、例えば家族や仲間内の経済に、金と損得勘定の交換を持ち込む人を、宮台真司なんかはトンマだと言い切ったりしています。
まあ宮台さんはそうはいうものの、一方で、「この間柄は、どっちのプレイスタイルでいくべきなのか」という判断は案外難しいものです。
例えば一昔前なら日本の企業の雇用慣行には終身雇用っていう仕組みがあって、企業共同体は家族みたいなものだといわれていました。そこでは社員は会社に滅私奉公をするもんだと信じられていたりしたんですってね。これは贈与の考え方ですね。だから給与も、滅私奉公への対価という感じではなく、贈与っぽいニュアンスで理解されていたんちゃうかな。逆に、これだけ働いてあげたんだから、相応の対価が欲しい、と言い出す社員は煙たがられていたりしたかもしれないですね。
しかし、いまはそうでもなくて、そもそも終身雇用はオワコン化しましたし、プロジェクト単位で契約ベースで働く人も増えてきました。クローズドな人間関係の中で完結できず、流動的な人間関係が増えてきます。そうすると、中には相手をだまくらかしてくるような、悪いやつも混じってくるでしょうし、そういうやつとも付き合っていかないといけません。そこで、かつてのような家族的な贈与ベースの付き合いを迂闊に持ち込むと、相手を騙して搾取されてしまうかもしれない。そういう不安が強まってきます。そうすると、残業するんだったら、してあげるから、ちゃんと残業代をくださいねと、対価を要求せなあきませんよね。相手がどういう考えの者かわからない。そういう不信に基づく緊張感で結びついた間柄では、贈与ではなく、交換のプレイスタイルが選ばれがちです。
一方で、家族や仲間といった、長期的な関係に基づく感覚の一致と信頼でなりたっている間柄に、交換スタイルを持ち込むと、おかしくなります。これだけのことをしてあげたんだから、その分見返りをちょうだいね、と。先述の通り、そもそもそういう投げかけが出る程度に相手の振る舞いを信用できていない時点で相手を信じれてないってことなんですよね。
しかし、家族や仲間といわれるカテゴリに入っているからといって、相手が信用できる人だとは限らないのが難しいところで。毒親とかダメンズとかいうたりしますが、相手からの信任を悪用して、不当に相手に損をさせる輩もいるわけです。だから、家族や仲間と呼ばれる間柄だからといって、なかなか贈与スタイルに踏み切れないっていうか、この辺、「家族や仲間だから贈与、職場だから交換」というカテゴリ分けでシンプルに考えたい人にとってはどっちのスタイルでいくか不安になって迷うってこともあるんでしょうけど。
要は富を移動する相手の性質や考えと、自分の幸福との調和を信じるかどうかってことなんですよね。信じるなら贈与でいいし、信じないなら交換でいいってことかと。てことは、相手の性質や考えと自分の幸福が調和するかどうか、確かめるコストが必要ってことです。一緒に喋ったり、遊んだり、お出かけしたり、悩んだり、ケンカしたりして、だんだんわかってくる。あるいは、お互いに相手との共通経験を経て価値観が変化したりして、最初は調和していなかったお互いの感覚が調和するようになっていく。いわば楽器のチューニングみたいなもので。
そういう膨大な過去の経験の蓄積から調和が可能になっていくのだとすると、家族や仲間がいかにかけがえがないものかってことがわかります。簡単に作れないんですよ。時間も労力も、自分自身の変化も、すげー必要だし、取替不可能なものだってことになります。それは、実際に一緒に住んでいる血縁家族かどうか、籍を入れているかどうか、みたいなことではなく、チューニングができているかどうかですから、それさえできているなら、たとえ血の繋がりや法律上のつながりはなくとも、職場のチームでも地域ボランティア団体でもカップルでも、家族や仲間だってことです。ていうか、そういうかけがえのない取替不可能なくらい調和した間柄こそ、家族や仲間という定義に当たるんでしょうね。そして、その間柄では、相手の幸せはもはや自分の幸せとさえなるでしょう。自己充足的に相手に尽くすことができるようになるかもしれません。そこまで至れば、相手を信じて、贈与で富を移動することを、僕らはいとわないでしょう。
冒頭の記事の場合、作家さんには、「夫と十分な調和をしてなかったことに気づきがあった」わけですね。洗濯物は事後的に整えればいいと相手は思っていたんだけど、その相手の考えわかっていなかったと。その程度には相手のことを知らなくて、結果、自他の調和が成立しておらず、自己充足できる状態になっていなかった。そこで相手との富の移動に交換のプレイスタイルを無意識のうちに持ち込んで「やってあげたんだから見返りがほしい」と思ってしまい、それが得られないことに憤ってしまった。家族だから調和ができるわけではないってことはこういうことですね。でもここでこの作家さんは対話を経て相手のことを知り、目からうろこ的自己変容を経験します。こういう経験の積み重ねなのかもしれないっすね、家族になっていくって。知らんけど。
なんか、そういうの、面白いなと。十分な知識や経験の共有をして、自他の幸福の調和を信じられる間柄なら、贈与の二重の不確定性はもはやなく、確信を持って贈与できるでしょうし、僕は贈与で相手が喜ぶことを通じて自己充足できるでしょう。もうその時点においてはもはや相手からの見返りを必要としない域に達しているでしょう。すげー。おもしれー。って感じです。
サポートされると小躍りするくらい嬉しいです。

