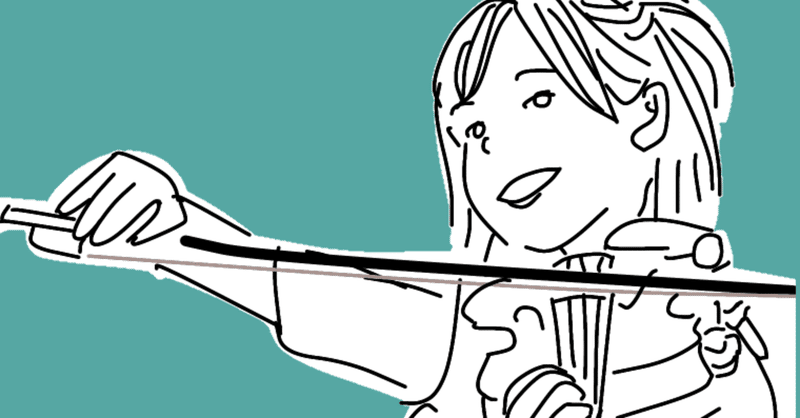
「加入するメリットがない」んでなくて「非加入でいることにデメリットがない」んだよな
よく、住民参加のまちづくりでは町内会の役割が重要だっていうんですね。でも一方で町内会の加入率低下っていうのが近年問題になっていて、それに伴う担い手不足、高齢化、アイデアの枯渇、利用者へのアクセス不全など、組織維持が難しい状況があると言われています。
加入率の低下については以前こちらにも書きました。
ここでも書いたんですけど、加入率低下っていうのは長年に渡って全国的に起きている問題というよりは、ここ20年に主に都市部で起きている問題だって言うことが示唆されていて。80年代に政治色を脱色され、90年代に阪神大震災が起きて近隣互助の必要性が高まると、むしろ町内会への参加度は高まってきたんですね。それが2005年に最高裁で町内会の任意加入性を認める判決が出たことがおそらくはトリガーとなって、これまで「特に意思を示さなければ参加しているものとみなす」ことができたものが「特に意思を示さなければ不参加とみなす」ように、デフォルト設定が変わったわけです。その結果、町内会は加入の意思確認をしないとけなくなり、その結果、町内会不参加者からは「参加してなんのメリットがあるんですか」と聞かれるようになったわけです。
それを受けて、少なくない町内会が、加入のメリットを示す情報発信をしていますし、自治体もそういう動きをサポートしています。しかし、それが加入率の向上に大きく寄与したって話は殆ど聞かないんですね。じゃあ、それはなんでだっていうと、「加入のメリットをはなにか、と聞いている」からといって「加入のメリットが示されれば参加する、とは言っていない」ってことだからで。そこがポイントなんですね。
例えばあなたが恋している相手から「あなたと付き合ってなんのメリットがあるの?」と聞かれていると想像してくださいよ。けっこうクルものがあるでしょ。そこで「ぼ、ぼくと付き合ってくれたらこんなメリットがあるよ!」とか言っているわけです。うーんこれ、スジがあるように思えないですよね。まあ、そういう関係なわけですよ。いま町内会が置かれているのは。
もっといえば、「加入するメリットがない」こと以上に、「非加入でいることにデメリットがない」んすよね。繰り返し書いているように、まちづくりとは、非排除的な財を提供するっていう、親切な活動です。で、町内会が提供するサービスの多くはこの非排除性を帯びる財です。なので、町内会の会員であろうがなかろうが、町内会が生み出す利益を享受できるわけです。にもかかわらず、加入すれば、金銭的、労力的な負担が生じるわけですから、加入には明確なデメリットがある。とすると、簡単な算数の計算で、そりゃ非加入のほうが合理的だって判断になるわけです。
これ、そもそも町内会が地域の公共財の提供をする組織である以上、「交換原則的な民間事業の理屈」でやろうとすることにそもそも無理があると思うんですよね。かといって、「全員強制加入」に回帰することは少なくとも2005年の最高裁判例が覆らない限り、極めて難しいだろうなと思うんですね。
じゃあどうしたらいいんだっていうと、町内会が地域の公共財の提供をする組織であるならば、やっぱり「再配分と贈与の理屈」で回ってると理解する方がより実態に適していて。つまり、「持てる者が持てる者の高貴な義務として」町内会運営の負担を背負う、っていうことです。
サポートされると小躍りするくらい嬉しいです。

