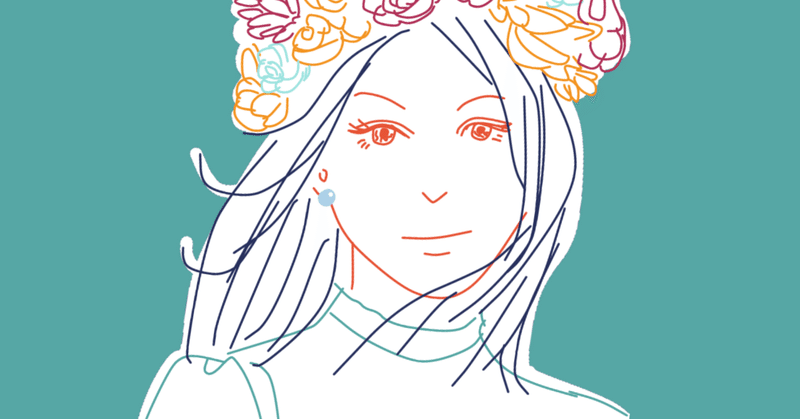
「つながり」を一発で作って孤独を解消すれば色々問題が解決できるはず、という夢を打ち砕く。
話題の『社会的処方: 孤立という病を地域のつながりで治す方法』を読みまして。
本書で、海外にはリンクワーカーという職があるということを知りました。例えば、孤立している人にヒアリングをして、「ああ、この人は歌が好きなんだな」とわかったら、地域の聖歌隊グループにつなげる、みたいなことをして孤立を解消していく仕事で、孤立している人を社会に包摂することで病気や犯罪などに対処する方法を社会的処方という。私達もまちづくりの現場でしばしばやる仕事だけど、それ自体を職名として担う専門家がいるっていうんですね。
ところで、もう10年以上前のことだけど、大学院で博士論文を書いていた時に、コミュニティの再定義を行ったんですね。当時の私はコミュニティを「資源の最適組み合わせで価値を生む機能」であると説明しました。この説明は今も一定の説得力があると思っていて。
で、リンクワーカーという職は、放っておけば分断しがちな人々を最適に組み合わせている。まさにコミュニティの機能の一端を担うお仕事だなと読みながら思ったんです。
この社会的処方、著者によれば日本でも研究されているらしいけど、そういう専門職は身近にあまり見ない。というか、まだ珍しいから本で広める価値があった情報だったんだと思う。だから本書では「日本ではみんながリンクワーカーになろう」と提案する一幕もあるけれど、みんなってことは、無償ボランティア化するということで、リンクワーカーをボランタリーにやっていくことの限界もまた見えてしまう。
一方で、じゃあ日本で同じ仕組みが成り立つのか、ということを考えながら、『コミュニティの幸福論 ――助け合うことの社会学』読みました。
本書では、人から親切にされることに伴う「居心地の悪さ」、すなわち「心理的負債」について述べられていて。なぜ負債感があるかっていうと、人間には贈与には必ず返礼がセットである、という返報性原理が備わっているからだというわけです。
で、日本人にアンケートをとると、見知らぬ人に助けてもらうことへの負債感がひどく大きく、困ったときに助けてもらうのは家族だっていう回答がすごく高いんだそうで。
サポートされると小躍りするくらい嬉しいです。

