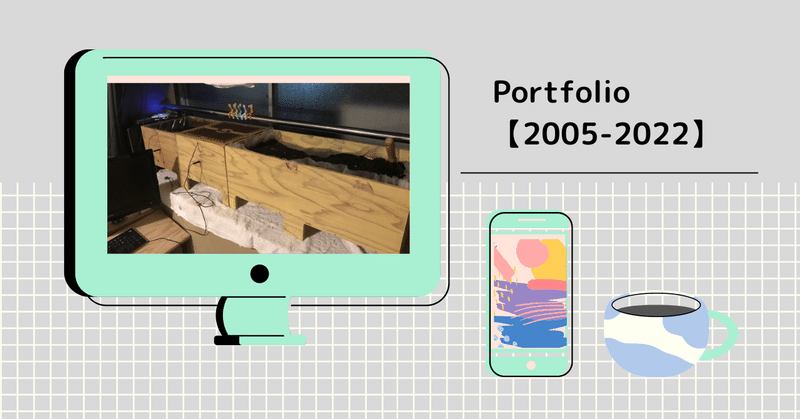
【2019-2020】コンポストBOX・プランター【#コンポスト #DIY】
【Caution!!!】
今から話す内容は、私がやったからといって気軽にマネをしないでください。実行に移す際は、近隣の迷惑にならないか、よく確認してください。
迷惑行為に発展したとしても、私鹿音のんは一切責任を取れません。

なぜ、コンポストなのか?
逆に聞きたい。
じゃあ何で、生ごみを「燃えるゴミ」の日に捨てるんですか?
「燃えるゴミ」にしちゃって、もったいないと思いませんか?
さして自慢にならないかもしれないが、2020年に今のアパート暮らしになって以降3年間、今に至るまでずっと、燃えるゴミの日に生ごみを出したことなんか、全くといっていいほどない。しかも、アパート暮らしにも関わらず。これは私の誇りである。
このすごさは、なかなか一人暮らしで自炊をしたことがある人か、一家の中で家事を一手に担ったことのあるか、それくらいの人にしか分からないすごさかもしれない。なぜなら自炊している以上生ごみは大量に出るし、かさばるわゴミ箱は臭くなるわで皆が処分に苦労しているからである。でも、そんな中私だけは「生ゴミをごみ捨て場に捨てたことがない」記録の更新が今でもずっと続いている。玉ねぎの皮一枚、にんじんを剥いた皮一枚たりとも、捨てたことがない。
なぜ、そうまでして頑なに燃えるゴミの日に生ごみを出さないか?
土に還るからである。
土に還ればいい肥やしになるものを、もったいなくて私は捨てることができない。
かつてお寺暮らしをしていたとき、境内には生ごみ処理用のコンポストがあった。こういうやつだ↓
ちなみに、紹介のためやむなくAmazonのリンクを貼ったが、こういうタイプのコンポストははっきり言って「買うな!」と強く言っておく。
生ごみが嫌気発酵して、匂っただだけで吐き気を催すほど内部が物凄く臭くなるからである。おまけに、うじ虫も湧く。
お寺の境内に設置されていたものに至っては、こいつの蓋を開けた瞬間蛇と至近距離でコンニチワしたことまである。ヘビである。🐍。
私は巳年生まれだがヘビが大の苦手で、この時ばかりはヘビーメタルのボーカルも出せないような金切り声を上げて絶叫してしまった。
だが、そういうHeavyな恐怖体験を幾度となく強いてきたアイリスオーヤマのコンポスターも、今の私の人生にとって欠かせない大事な教えをもたらしてくれた。
それは、生ごみは土に還る、というシンプルな事実である。
だからこそ、さまざまな事情で寺から追い出されて、生活保護でアパート暮らしを続けるようになった今でも、コンポストをやって、生活で出た生ごみは全て土に還し続けようと決めた。
問題は、このアパート暮らしにおいて、生ごみをどう土に還すか、ということであった。
目標・価値・実現方法
目標
アパート暮らしでも邪魔にならない、コンパクトなコンポストをつくる
生ごみを土に還す生活を続ける
コンポストの土で野菜を育ててみる
提供したい価値
生ごみを捨てる行為からフリーになることで、「ゴミ捨て場に行く」という面倒な作業の頻度が減る
ゴミ捨て場に行く頻度が減るだけでなく、ごみの削減にもなる。これってエコじゃない?
生ごみを還した土を活用して野菜を育てるという「循環型の暮らし」をアパート暮らしであっても実現できる
実現方法
アパート暮らしを始めた2019年4月当初は、生ごみを冷凍庫で凍らせて保管しておいて、いずれどこかで土に埋めて捨てよう、くらいに考えていた。
ところが、日々溜まっていく生ごみが冷凍庫の中を逼迫していくにつれて、これは何とかしなければ、と必死にネットでいい方法がないか検索した。
その時に出会ったのが「ダンボールコンポスト」だった。
ご覧いただいて分かるとおり、「ダンボールコンポスト」で検索すると結構な数の自治体のホームページで紹介されているのが分かる。行政自ら推奨しているやり方だということか。
本にもなっている。私は図書館で借りて読んだ。
ダンボールならスーパー等でタダで手に入るし、置き場所もダンボールを置ける程度のスペースさえあれば手軽に始められるし、コンポストの土の素になる材料はホームセンターで揃う。
コンパクト、かつ、ローコスト。みんながお薦めしている。トラブルシューティングのネット記事も豊富。
となれば、やってみないわけにはいくまい。
早速、私はホーマックに行って、人生で初めてホームセンターで土を買うという経験をした。「ピートモス」「くんたん」「赤玉土」。私のコンポスト生活はここからスタートした。時に2019年8月のことだった。
制作プロセス

最初のコンポストの土のレシピは、
赤玉土
くんたん
腐葉土
だった。写真には写っていないが追加で後に
ピートモス
米ぬか
も加わる。これを図のようにダンボールに敷き詰める。

こうすることで、生ごみに含まれる水分を吸収しつつ、腐葉土に含まれる微生物によって分解が促進されるというわけだ。
ちなみに、腐葉土の部分に米ぬかを混ぜると、微生物が活性化してコンポストの立ち上がりが早くなる。

分解が促進されるように、生ごみは入れる都度、細かくミキサーで粉砕してみた。
果たして、生ごみが分解されるのか。最初はまだ、半信半疑だった。
ところが、生ごみを入れた翌々日になって土をかき回してみると、見事に土と同化しているではないか!
この時の感動が、思えば初めて微生物たちと出会った瞬間だった。私のアパート暮らしに、微生物というペットができたことは、「ごみを減らす」ことで私のQOLを上げてくれただけでなく、微生物が作り出す発酵という豊穣な世界に私を導くことにつながった。
その後毎日のように、私は微生物と苦楽を共にすることになる。
ダンボールコンポストは、結局1年続けた。続けてみると課題が多かった。
臭いが気になったり、コバエが湧くようになってきたのである。
冒頭の【Caution】でお伝えしたように、ダンボールコンポストは下手にやると近所迷惑になる。最大の近所迷惑要因は臭いとコバエである。

それを防止するために、私はえひめAI-2(えひめあいに)という有用微生物とハッカ油スプレーを作った。特に、えひめAI-2は撒いた瞬間から日本酒に似た爽やかな発酵臭が辺りに広がるくらい、臭い対策に効果てきめんだった。ハッカ油スプレーも、それなりに虫除けに効果を示した。
だが、ダンボールコンポストの最大の弱点は、水分にめっぽう弱く、速攻で底に穴が空いたり、土の重さに耐えきれずに潰れてしまうことであった。とりわけ、スーパーにタダで置いているようなものは薄い段ボールが多く、水にちょっと濡れただけでもすぐに形が崩れてしまいやすい。
その対策のためにダンボールを二重にした上に不織布を敷くということをやっていたが、不織布の底は抜けなかったものの、ダンボールは相変わらず簡単に底が抜けてしまう。
そこで作ったのが、コンポストBOXだった。


要するに、木だったらそう簡単に底が抜けないだろう、しかも天然素材だし、ということで作ってみたのである。
せっかくなら、ベランダといえない程度の欄干のついた窓際に置いてみようということで置いてみた。

奥二つがコンポストBOX、手前がプランターである。
ダンボールコンポストも1年経つと、それなりにコンポストの土が育ってきてくれる。
そう、コンポストの土で野菜が育つか、いよいよ実験してみたくなった。
最初はパクチーで試した。

失敗だった。これくらいまで育った段階で、軒並みしおしおと枯れていったのだ。この時、100%コンポストの土でやったのがどうやら失敗の原因かもしれないと思い、友人からにんにくの種を譲っていただき、今度は土の配合にも若干こだわってみた上で、先ほど作ったプランターに撒いてみた。
これも、芽は出た。
pHも測ってみると5.5。まぁまぁ酸性寄りだが、悪い土じゃない、はずだった。

ところがである、プランターに秋に蒔いて春を迎えようかという手前で、

枯れてしまった。
よく「作物を枯らす天才」というものが世の中には存在するというが、それが自分のことだと思いたくなければ、そもそも何かが間違っており、原因を徹底的に探すしかない。
そして、行き着いた原因が、2つあった。
そもそも私は、野菜がどう育つのかについて、全く知識がないこと
そもそもダンボールコンポストでは、植物が育つ土は作れないこと
このことに気づいた時、私は盛大な勘違いをこれまでしてきたことが判明したのだった。それは、総括に書こう。
私がダンボールコンポスト作りを通して、そしてコンポストBOX作りを通して経験したことと反省したことをまとめると、次のようになる。
経験したこと
生ごみを土に還す仕組みをアパート暮らしの中で小さく作ることには、成功した
生ごみを土に還す仕組みを作る中で、私は人生で初めて微生物と親しくなった
コンポストBOXを作る過程で、かなりDIYが自分でもできるようになってきた
反省したこと
植物のこと、土のことに全く無知なまま、勢いでパクチーとニンニクを育ててしまった
「育たない」と判明してしまった結果、「生ごみ」というごみの代わりにただ「コンポストの土」というゴミが発生してしまう結果になった。このゴミはこのゴミでかなり厄介
そして、その失敗作の土をどうするかまで頭を回さないまま、コンポストを作ってしまった
成果
目標達成率
アパート暮らしでも邪魔にならない、コンパクトなコンポストをつくる(100%)
生ごみを土に還す生活を続ける(100%)
コンポストの土で野菜を育ててみる(100%)
総括
当初の目標は、達成した。
しかし、何もかもが失敗だった。
とことんやって、一通りやってはみたけどダメだった、というやつだ。
なぜダメだったのか?
そもそも、ニンニク作りに失敗した2年目にしてはたと気づくまで、私のやっていたことがある種の「有機堆肥づくり」だという自覚がなかったのである。
土づくりとして、「農」の世界で研究され尽くしている豊穣な世界に片足を突っ込んでいる自覚もないまま、栄養豊富であれば育つだろうという単純な考えでパクチーとニンニクを育ててしまって失敗した。栄養豊富なだけでは作物は育たなかった。
作物が育つには、室内に置けるプランターなんてチャチなもんじゃなくて、日当たりのしっかりした、栄養分と微生物豊富な露地の畑が必要だった。露地の畑や自然界に存在する微妙なバランスが保たれた環境でこそ野菜は育つのであって、私が必死に生み出していたコンポストの土はいわば「偏った土」だった。偏った土で、野菜が育つわけがない。
こう書いてみると至極当たり前のことなのだが、コンポストの失敗を通してまざまざと痛感してみると、どれも耳が痛く感じる。
「循環型の暮らし」は、甘くなかった。土づくりの知識がなく、アパート暮らしで畑を持たず、農家でもない私ができることではなかった。
本気で生ごみを土に還すことによって「循環型の暮らし」を真剣に構築するためには、私は農家から直々に土づくりを学び、野菜づくりも学び、
生ごみから「質の良い堆肥」を生み出すにはどうすればいいか
そもそも「質の良い堆肥」とは何なのか
を考え続けなければいけない。
そして、私は「質の良い生ごみ堆肥作り」を、2021年から本気で学び、考え、実行に移すことになる。
今後の展望
現在、私はめでたくダンボールコンポストを卒業して、やっていないのはもちろん、人に勧めないようにもしている。ダンボールコンポストは必ず失敗するからである。
なぜなら、そこでやっているのは生ごみの「発酵」ではなく「腐敗」であり、「生ごみ処理」であって「堆肥作り」ではないからである。だから、次がないし、循環しない。結局、コンポストの土は私が陥ったように「土」というゴミを生み出すだけであって、どこかに埋めるか、ゴミの日に廃棄するしか道がない。だったら、最初っから生ごみはそこらへんの土と混ぜて埋めてしまえばいいことになる。それではあまり意味がない。
現在学んで、実践している「生ごみ堆肥作り」は、生ごみから作物が吸収しやすい栄養素と、作物の生育を助ける微生物が豊富な、質の良い完熟堆肥を目指している。その模様は、以下の記事で紹介しよう。
(note記事)
それとは別に、こんな実験もしていた。

土壌温度計・水分量計の自作である。これも、現在のプロジェクトではそこまで重要ではないためあまり進んではいないが、これをやることによって生ごみを発酵させるときに微生物が生み出す生物燃焼を記録することができるようになる。これも、個人的にワクワクしているプロジェクトなので随時進めていく予定である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
