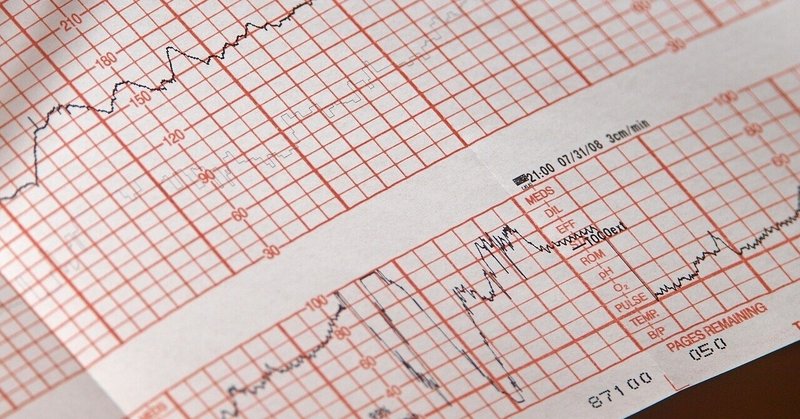
週刊レキデンス ~第5回~不整脈治療の歴史
第1回から第4回までは、麻薬などの乱用に関わる薬と歴史の話をしてきました。第5回からは、心臓疾患を交えた歴史+エビデンスのお話をしてみます。 今回調べを進めると、アミオダロンという薬が最近推しの話題がキャッチ出来ました。何故アミオダロンが推しなのだろうか。その経緯を綴ってみました。
不整脈の治療はいつから?
皆様、「不整脈」というものを聞いたことがありますか?
不整脈とは、正常な心臓は規則正しく協調的に拍動するが,これは固有の電気的特性を有する筋細胞によって電気パルスが生成・伝達され,それにより一連の組織化された心筋収縮が誘発されることによって生じる。不整脈と伝導障害は,そうした電気パルスの生成,伝導,またはその両方の異常により引き起こされる。
とされています、なんだか難しいです。少し簡単にすると、「心臓は電気信号の伝導」で動いており、「伝導に異常」が起こった結果脈が早くなったり遅くなったりすることでしょうか。
ジギタリスから始まった
そんな不整脈の治療は一体いつから始まったのでしょうか?
不整脈治療の歴史を辿ってみると、遡る事230年以上前、ある民間療法師の老女が重症浮腫の患者に対して、数種類のハーブを混ぜて飲ませていました。すると、浮腫症状の改善がみられたことに William Withering(1741年3月17日 - 1799年10月6日)は、驚きました。彼は調べた結果、浮腫が改善した主な原因は、ジギタリスの利尿作用だということを発見し、1785年に報告しました。(1)(2)そして、ジギタリスを不整脈に初めて使用したという報告が1909年の Lewis らによってなされ(3)、更に心房細動を伴う心不全に対して、ジギタリスが使用できる事を1991年 Mackenzie らが報告しました(4)。その後もジギタリスの不整脈に対する研究は続けられて、次第に心房細動の有無に関わらずジギタリスが洞調律達成に使用できると発表されました(5)。
この様に不整脈薬の古い記述を調べていると、ジギタリスの歴史が一番古いこともあり、1970年代まではジギタリスを中心に不整脈治療が行われていました。
因みにここで登場している William Withering は Vaughan William 分類を作った William(1918年8月8日– 2016年8月31日) とは別の人物です。偶然にも名前が似ていることで、同一人物かと勘違いしてしまい、混乱してしまいました。
その他の不整脈薬
その他のジギタリス以外の歴史ある不整脈薬については、キニーネについての記述もありました。1912年、オランダの解剖学者 Karel Frederik Wenckebach(1864年3月24日-1940年11月11日)の患者さんで、マラリアの治療のためにキニーネを飲んでいた方が自らの不整脈が静止していることを医師に報告しました。報告を受けた、 Wenckebach 医師は心電図を取ってみると確かに彼には心房細動の不整脈があり、そしてキニーネの服用によって不整脈が静止している事を確認(6)。しかし、その後 Wenckebach 医師は他の患者にもキニーネを使用してみたが、効果は表れませんでした(7)。これが後にキニーネのエナンチオマー(鏡像異性体)であるキニジンが不整脈に使用することに繋がります。
不整脈は治療しなきゃいけないの?
ここで1つ確認したいことがあります。何故不整脈を治療していく必要があるでしょうか?不整脈を放置すると何か良くないことがあるのでしょうか?
調べてみると不整脈は、心筋梗塞後の無症候や軽度PVC(心室性期外収縮)、VT(心室頻拍)が起こると予後が悪く(8)、死亡に繋がる事が知られています。(HR:3.63(95%CI:2.59-5.09))(9)。
なるほど!だから不整脈を治療する必要があるのですね。そのために不整脈が原因になる死亡を減らそうと、新しく抗不整脈薬が開発されて使われるようになってきたのですね。
ここである臨床試験が行われました。
新しく開発され使われていく、その抗不整脈薬の効果を確認しようと、心筋梗塞後の不整脈を停止をさせることで死亡率が下がるのか証明しようと Cardiac Arrhythmia Suppression Trial(CAST 試験)(10)というものが行われました。しかし、結果は期待と裏腹に「不整脈は減りました」が、「死亡率が増えて」しまい、早期に試験中止になりました。この結果を鑑みて、ボーンウィルアム分類のⅠ群に当てはまる薬を連用や、積極的な使用は控えていくことになりました。代わりにⅢ群のアミオダロン等が使用されていきます。
そんなアミオダロンですが、CAST 試験(10)前のアミオダロン錠の評価は、致死的不整脈に有効性を示す一方で、重篤な間質性肺炎や肺線維症、甲状腺機能障害などの安全性面で懸念がありした。そのため、抗不整脈の中では、最終選択の位置づけとして使用されていました。
しかし、CAST 試験の後では、Ⅰ群の積極的な使用が減った影響やBASIS 試験(11)CASCADE 試験(12)、EMIAT 試験(13)、CAMIAT 試験(14)などにおいてアミオダロンの死亡率低下などの有効性が示されたことで、現在では積極的な使用が推進されています。(15)
アミオダロンについて、もう1つ。この薬は現在、注射剤:劇薬、経口剤:毒薬という分類になっています。元々は、どちらも毒薬でしたが、分類が異なるように変更されました。
そのきっかけは、アミオダロンの適応にあります。2013年に病院におけるアミオダロン注の使用について、適応拡大「「電気的除細動抵抗性の心室細動あるいは無脈性心室頻拍による心停止」の効能又は効果が承認」がありました。それによりアミオダロンが毒薬であると管理が厳重であるため、緊急時の対応が遅れる事を鑑みて、注射剤のみ劇薬指定へと変更されました。(16)(17)
【どうして注射薬が毒薬に?】
それでは、なぜ添付文書が改訂されるほどに、救急時の使用が重要なのでしょうか?それには、「院外心停止(以下、OHCA:out-of-hospital cardiac arrest)」が関わっています。OHCA とは、病院以外で心停止が起こることを示します。OHCA は、心筋梗塞のうち、ST 波上昇心筋梗塞(STEMI)の合併症として起こります。また、OHCA うち、死亡に繋がりやすい、VT(心室頻拍)/VF(心室細動)の波形を示す人が多いのが特徴的です。更に OHCA は
救急搬送後の院内死亡率の増加に関与しているとの報告があります。(18)その VT/VF に有効とされている薬の1つがアミオダロンになります。
ただ近年では、VT/VFを起こした人が投薬ではなく、緊急 PCI を受けることで院内死亡率を下げることが出来ることも報告されています。(18)しかし、全ての救急を受け入れた病院でPCIが出来るとは限りません。その場合に、薬物投与が選択肢に挙げられるのではないでしょうか。その時にアミオダロンを厳しい管理から外すことで、素早く救命対応に使用することが出来たら、蘇生率は上がるのかもしれません。
では、実際の報告を見てみましょう。緊急搬送の時に使用したリドカインとの比較した試験があります。それよるとリドカインと比較したアミオダロンの入院までの生存率は、オッズ比2.17(95%CI,1.21-3.83)P=0.009 (19)と高くなっていました。
これらの報告の様に薬剤の使用やPCIなどと救命に繋がる選択の幅が少しでも広がることは、死亡という重要なアウトカムを回避出来る、手札が1つ増えることに繋がるのではないでしょうか。
【参考文献】
1)William B. Bean,Arch Intern Med. 1963;112(1):143-144.
2)野上昭彦,心室不整脈に対するハイブリッド療法 JPN.J.ELECTROCARDIOLOGY Vol.29 No.3 2009
3)Lewis, T : Paroxysmal tachycardia. Heart, 1: 43, 1909.
4)Mackenzie J : Digitalis. Heart 2 : 273, 1911.
5)Christian HA: Digitalis therapy. Satisfactory effect in cardiac cases with regular-pulse rate. Amer J Med Sci 157: 593, 1919.
6)Wenckebach K. Cinchona derivatives in the treatment of heart disorders. JAMA 1923;81:472 –474.
7)Davies MK, Heart. 2002 Aug;88(2):118. PMID:12117827
8)Henkel DM,et al. Am Heart J.2006 Apr;151(4):806-12.PMID:16569539
9)Mehta RH,et al.JAMA. 2009 May 6;301(17):1779-89.PMID:19417195
10)Echt DS,et al.N Engl J Med. 1991 Mar 21;324(12):781-8.PMID:1900101
11)Burkart F,et al.J Am Coll Cardiol. 1990 Dec;16(7):1711-8. PMID:2254558
12)Am J Cardiol. 1993 Aug 1;72(3):280-7. PMID:8342505
13)Julian DG, et al.Lancet. 1997 Mar 8;349(9053):667-74. PMID:9078197
14)Cairns JA,et al.Lancet. 1997 Mar 8;349(9053):675-82. PMID:9078198
15)https://www.pmda.go.jp/drugs/2007/P200700007/78006900_21900AMX00049_B101_2.pdf
16)https://www.j-circ.or.jp/old/topics/ancaron201305.pdf
17)アンカロン注 インタビューフォーム
18)Liu HW,et al.Chin Med J (Engl). 2012 Apr;125(8):1405-9.PMID:22613643
19)Dorian P, et al. N Engl J Med. 2002 Mar 21;346(12):884-90. PMID:11907287
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
