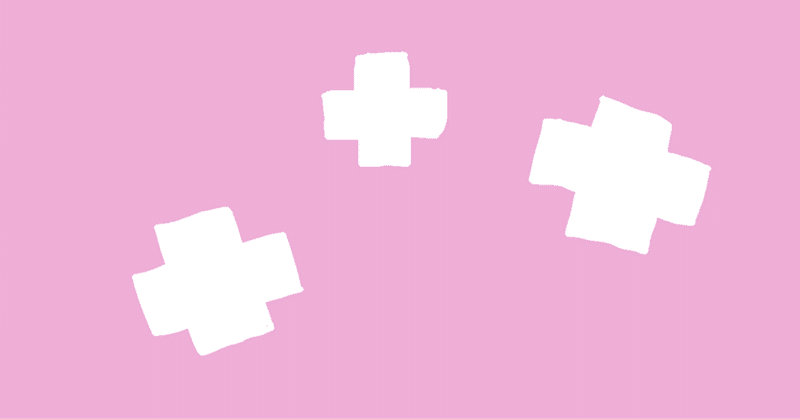
傷の手当て
はる様の素敵なイラストを使わせて頂きます。ありがとうございます。
:
終電まで残り2分。
久しぶりに駅内をダッシュしてホームに向かった。
こんなに全力で走ったのはいつぶりだろうか。
毎日ランニングをしてるとはいえ、全力は久しぶりだった。
改札口まで残り50メートル。
重心が崩れ、スローモーションのような感覚で崩れ落ちた。
膝には擦り傷。
普通に痛い。。
電車に間に合ったものはいいものの、とりあえず手で押さえて何とか防ぐ。
そんな昨日の経験を振り返ると、以前傷の手当てについて書かれていた本を読んだ。
傷の手当てをしたのはいつからか。という内容が書かれあり、その内容がとても興味深かった。
それは六〇〇万年ほど前、現在の中央アフリカのサバンナに一人の猿人が暮らしていた時。
彼は何か食べ物になりそうなものを見つけて走りだしたが、急いだあまり足を滑らせて脛を何かにぶつけて切ってしまったらしい。
痛いし血が出ている。
そこで彼は誰に教わったわけでもなく咄嗟に手でケガをした場所を押さえた。
すると不思議なことに手で押さえると血は止まり、痛みも和らいできた。
これが人類史上最初の「手当て」であり、最初の医療行為として現在に伝えられている……というのは「見てきたような噓」であるが、このようなことは当然あったはずだ。
ケガをすれば痛いし血が出てくる。
血が出るのも困るが、止めたいと思うのは当然である。
これが動物ならどうするか。
舌が届く範囲なら傷を舐めるだろう。
舌で舐めれば痛みが止まることを本能的に知っているからだ。
なぜ舐めると痛みが止まるかといえば、「傷は乾くと痛くなり、空気に触れないようにすると痛みが和らぐ」からだ。
だから原初の猿人も最初は傷を舐めようとしたはずだ。
ところが幸か不幸か、ヒトが自分の舌で舐められる範囲は広くない。
よほど体が柔らかくなければ自分の足の指を舐めることさえ難しい。
しかし、手なら自分の体のどこにでも届く。
このような理由から、人類では傷の「手当て」が始まったのだろう。
手当ては非常に有効な治療法だが、困ったことがある。足の傷を押さえたままでは走れないことだ。
しかしうずくまったままでは自分が猛獣の餌になってしまう。
だから手の代用品が必要になる。
そこでそこらに生えている葉っぱや木の葉をむしりとって傷に当ててみる。
ツルか何かで縛れば手で押さえなくていいことに気がつく。
これが最初のドレッシング材(創傷の被覆材料)であり、包帯の誕生だそうだ。
要するに「手当てに使う手の代用品」である。
そのうち、傷に貼ると血が止まる葉っぱや、痛みを抑える葉っぱ、あるいは傷が早く治る葉っぱが見つかる。
最初の傷の治療薬だ。
やがてヒトは、植物以外のものでも傷の治療に効果があるものがあるのではないかと考えるようになり、色々なものが試されるようになる。
記録に残っているもので一番古いのが、紀元前二五世紀のハチミツと樹脂であり、紀元前一七世紀のエジプトではカエルの皮膚が使われ、古代メソポタミアでは粘土を利用したことが書き記されている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
