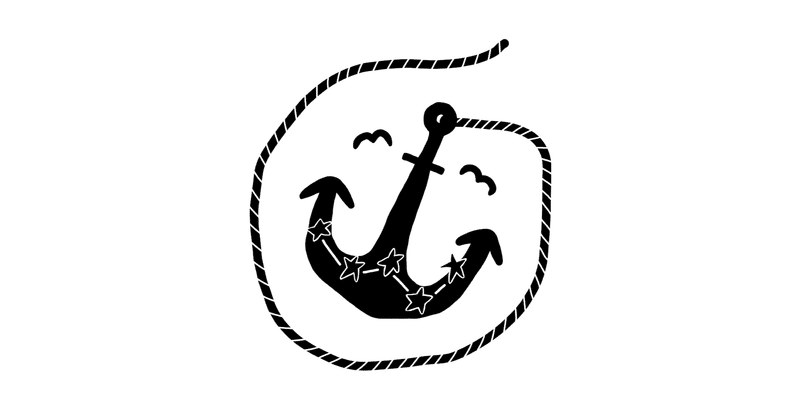
「アンカーリング。」/ショートストーリー
目覚めたとき、部屋がとても暖かくて気分が良かった。
でなければ、12月に入ったと言うのに散歩などする気も起きなかっただろう。
もともと、自宅に引き籠るタイプで外出など用事がなければしない。
散歩なんてね。健康には良いんだろうけれどと思いつつ、積極的に散歩しようなどとは思わないのがわたし。
そんなわたしが珍しく散歩しようと思い立った。
近くにはわりと大きな公園がある。
そこへ行ってみようと思った。
暖かいとは思ったが、念のため少しだけ厚着をするのは忘れなかった。
「散歩へ公園まで行ってくるわね。」
ずっとパソコンに向かっている夫に一言だけ言って家をでた。
夫は、いつもどおりに返事はしなかった。
やはり、暖かい。
昨日なんかはとんでもなく寒くて、早めにベットに潜り込んだと言うのに。
公園には売店もあって、そこで珈琲を買った。
ベンチがいくつもあることは知っていたから、散歩の途中で飲もうと思ったのだ。
「どうです。当店自慢の揚げパンも?」
揚げパンか。子供の頃、給食に出る日は楽しみだった。
あの頃はなんでも楽しくて理由がなくても大きな笑い声で過ごす毎日だった。
ベンチに座って、珈琲と揚げパン。
わたしの今日の朝食だ。
夫は朝食をとらないので、その辺は心配しなくても良い。
それにしても、公園でゆったりとしているとあらためて季節を感じる。
木々の葉は黄色や赤に染まっている。
この辺はめったに雪はふらないけれど、雪が降ったらさぞかし風情がありそうだ。
あまりに気持ちが良くて、こうして長い間ベンチに座っていてもあきない。
ほんとにわたしとしては珍しい。
遠くでは子供と親御さんと思われるひとがキャッチボールをしている。
こういうのをある意味、完璧な朝と呼んでもいいのではないか。
珈琲は飲んでしまい、揚げパンか半分残っている。
どうしようかと思っていたら、いつの間にか白い綺麗な犬がそばでじっと食べたそうにパンを見ている。
あらあら、ご主人さまはどちらかしらと周りを見てみたのだが、そのようなひとはだれもいなかった。
「あなた。どうしたの?迷ったの?」
目がくりくりとしたその犬は、しっぽを振っていた。
「これが食べたいの?」
犬にパンを与えても良いのかと一瞬迷ったがわたしはパンを差し出した。
白い犬がパンを美味しそうに食べるのを見たら、なんだか嬉しかった。
気がつけば、頬を涙が一筋伝わることにわたしは驚いた。
白い犬は、わたしが座っているベンチのそばに座り、大人しくしている。
その犬が首輪をしているのに気がついた。
やはり、誰かの飼い犬なのだということが何故かわたしのこころに淋しい風がふかせた。
「あなた。どこの誰ちゃんなのかしらね。わかるといいけど。」
わたしはそっと首輪を外してみた。
その時も白い犬は大人しかった。
きっと、頭の良い子なんだと感じた。
その首輪の裏に書いてある犬の名前と連絡先を見たとき、わたしは心臓の鼓動が耳元で聞こえてきた。
首輪にはオオカミという名前とわたしの携帯番号が書かれていたからである。
そんな馬鹿なとわたしは何度も確認してみたが、見間違いではなかった。
間違いなく、わたしの携帯番号だった。
「オオカミ。」と白い犬に向かって呼んでみた。
白い犬は、いつもそうしているがごとく、わたしのひざに頭を乗せた。
オオカミはわたしの犬なのだ。
誰が何と言うと。
たとえ、それが奇妙でも。不思議でも。
わたしはオオカミと家に帰ることにした。
帰るつもりのなかった家に。
今日の朝、目覚めたとき思ったのだ。
一体なにがわたしをこの世にひきとめているのだろうかと。
考えても何一つ浮かんでこなかった。
理由がないのに、これから先も生きていかなきゃならないかと。
本当に。本当に、生きていかなきゃいけないのかしら。
子供はいなくて、夫は定年間近だった。
いつの間にか、わたしたちの間には溝ができていた。
溝ができていたけれど、だからどうのこうというほどでもない。
離婚するほどのエネルギーがなかった。
家を出たとき、寒い寒い地方へ行ってしまおう。
そのまま、雪に埋もれてしまおうと決めていた。
それなのに。
神様の使いなのだろう、きっと。
オオカミがわたしをこの世に引きとめるために遣わされた。
アンカーリングとして。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
