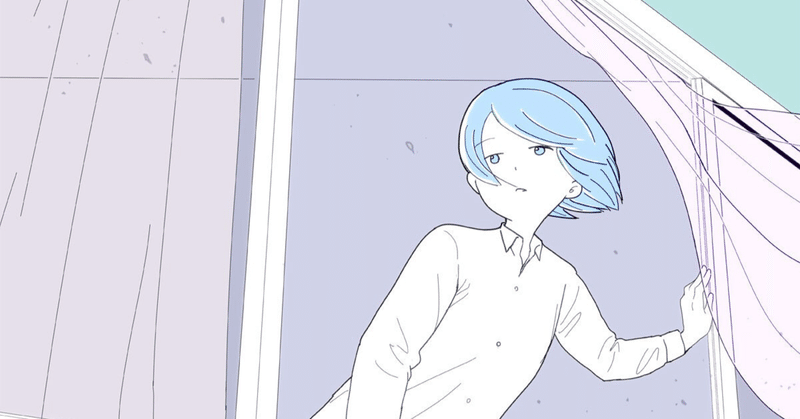
最後の聖女【掌編小説】
※2,851字数。
本作はフィクションです。
愛娘の結婚は、時として父性の感情機能を激しく揺さぶることがある。特に、正博のようにシングルファーザーとして一人娘を育ててきた場合は尚更だ。長年来、娘の為に注がれたあらゆる情念は鼓動そのものが永久に奪われるかもしれない。
【パパ、おはよう。
さっき、賢太朗君からプロポーズされた。】
明け方の4時に夏菜子は父へLINEをした。父はトイレの便座に腰掛けた直後にLINEを既読状態にした。モノクロ調の思い出が走馬灯の如く、脳裏を駆け抜けた。娘からの活字をまるで無関心で読んだのは、これが初めてかもしれない。嬉しいでも淋しいでもないー、単なる虚無感だった。気がつけば、目の前で娘が見知らぬ男から連れ去られる父親に自らを置き換えていた。
お相手である佐藤賢太朗は、コンビニ経営5年目の25歳である。ほとんどの時間を店内で過ごすことが多い。夏菜子はそこでアルバイト店員として出逢った。プロポーズが明朝に決行するしかないほど、忙殺されているのだろうか。それとも朝方にプロポーズすることは今流行りなのだろうか。そもそも、面と向かってプロポーズを受けたのか。まさか、オンラインでプロポーズを受けたわけではないだろうな。正博は、色んな意味で愛娘を案じ憐れんだ。
【お義父さんおはようございます。賢太朗です。夏菜子さんへ先ほど気持ちを伝えさせて頂きました。】
元々、正博の会社の部下だった賢太朗は律儀にもLINEを送ってきた。正博は慌てて内容を確認した。義父の感情を逆撫でする、かもしれないが良いではないか。生涯一度のおめでたいタイミングでLINEをする義息がいても。ただ、二度目の報告は困るが。正博は、目を真っ赤に充血させてトイレを出た。「良かった」と正博は呟き、自らを神となぞらえて人を赦すぐらいの寛大な心でいようと決めた。夜明けを告げるトイレからの斜光に背中を焼かれながら、彼は寝室へ戻った。結婚式はいつなのだろう。今年の6月だろうか。目を充血させるどころか、眼球ごと外れるぐらい涕泣するタキシード姿を正博は想像した。最近、50歳を超えて俄然涙脆くなりまして、とでも言い訳をしようか。いや、こちら片家のスピーチはそもそもないか。頭の中での妄想は突如、覚醒したように蠢いた。
正博が寝室でしばらく茫然自失としていると、夏菜子から着信があった。
「パパ、おはよう。さっき賢太朗から電話あった?」
正博は、怪訝に思いながらも「おめでとう」と一言だけ返した。妻が生きていたならどう切り返すのだろう、戸籍上、独りになるから素直に喜べないのだろうか。とにかく何かにすがりたいと、彼は激しい寂寥感に襲われた。
「賢太朗君に宜しくな」
必死に言葉を探した。たった一言に全てを託すかのように夏菜子に伝えるのが精一杯だった。もう、父親としての威厳などなくても構わないとさえ思った。
「お父さん、今日実家に一人で帰省していい?」夏菜子は声のトーンを落として語りかけるように、話す。
正博は(もちろん)と言わんばかりに、心底嬉しく思った。
「いいよ。でも、仕事は大丈夫? お店は忙しくないの?」
「賢太朗も今日一日は大丈夫だって」
正博は急に賢太朗が善人に映った。いい奴じゃん、と正博は心中で思いつつ、少しだけ気持ちが楽になった。先ほどトイレで抱いた天涯孤独のような気分が薄らいだ。急に夏菜子が仏様に見えた。地獄で遭うあっちの仏に。本当は現実の娘なのに。
夏菜子は、その数時間後に正博の住む神奈川の実家に来た。
「パパ。来たよ」
夏菜子は、玄関先で東京下町の和菓子を片手に立ち尽くしていた。少し雨に濡れていた。先ほどまでは関東全域は終日快晴の予報だったはず。妻の千鶴がそうさせたのか。
「お母さんにも報告しよう。居間の仏壇に」
「うん。ママ、東京下町まんじゅう大好きだったね」
「賢太朗君はお店?」
「いや、学生アルバイトの子たちが新しく入ってきた」
居間に入るなり、自分達以外を慮る会話を始めた。他愛のない会話なんて夏菜子とずっとしていなかった。夏菜子の隣に千鶴が座っているように見えた。
早いもので、時計は午前11時半を指していた。夏菜子の濡れた髪は綺麗に乾き、21歳のきめの細かい肌は何かを弾くような柔軟さを持ち合わせていた。今が一番高揚していて、幸福感に満ち溢れているのだろう。少しばかり見ない間に化粧が似合う女性になっていた。亡き妻と初めてデートをした日がプレイバックされた。
「何か、作るけど。お昼食べる?」
正博はためらいながらも、本日は精一杯のおもてなしをするつもりだった。
「パパ。料理するようになったの? ウーバーイーツとか、出前でいいよ」
夏菜子はおもてなしの受け取りを拒否する、というよりも、正博を極度に気遣っていた。遠避けられていたはずが、思っていたよりも親子の距離は近かったような気がした。
「昔の写真」と一言だけ言うなり、夏菜子は携帯電話の画面から家族写真を見せてきた。
まだ千鶴の癌が影も形もない時、家族3人でよく旅行に行った。亡き妻は夏菜子と仲が良かった。正博は仲間外れにされることもあったが、何かある毎に家族3人は結束し、乗り越えてきた。
「3人で北海道に行った時、楽しかったなあ」
「パパ、車でよく色んなところ連れて行ってくれたよね」
「夏菜子は女の子なのに車とか飛行機とか船が好きな子だった」
「そうなの? あんまり覚えていない」夏菜子は無邪気に笑った。両手を口に当てて、笑う癖はずっと変わっていない。3月初旬なのに初夏のような暑さだった。正博はエアコンのリモコンを手に取り、作動させた。
しばらく沈黙した後にどちらからともなく「涼しいね」と、口をついた。
正博は夏菜子のほうを見た。夏菜子は正博の淋しげな視線に気付くと、ゆっくりと大きな瞳を向けた。机に置いたホットコーヒーを一口飲んで夏菜子に話した。
「賢太朗さんと、ずっと、仲良くな」
生活費のこと、まだまだ二人は若いこと、付き合い始めて3ヶ月と日が浅いこと・・・etc。 眉をひそめて、親として言いたいことは沢山あった。
「ありがとう。パパ」
夏菜子は満面の笑みを向けた。数年前まで高校生だった子供のような無邪気さそのものだった。娘は父親が将来を悲観していることなど知る由もない。親の傷心は、自分が親になって一方的な愛を注いでみないと気がつかない。
正博は手前味噌ではあったが、冷蔵庫にあった野菜と豚ばら肉を使って焼きそばを調理し始めた。
「これお父さんの得意料理」と威勢良く言うなり、素早く完成させた。台所から香ばしい匂いのそれとともにリビングに戻ってきた。
「わあ、美味しそう!」
夏菜子は子供のように嬉々とした。伊藤夏菜子として、父の焼きそばを食べるのはこれが最後になるかもしれない、と一人娘は思った。これを完食したら、また賢太朗の元に戻らなくてはならない。今さらになって、明朝にプロポーズを受けたことに悔悟の念を抱いていた。
【了】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
