
『カムカムエヴリバディ』チーフ演出が最後に語るとっておきのカムカム制作秘話
はじめに
連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』、最後までご覧くださって本当にありがとうございました。
チーフ演出を担当しました安達もじりです。note二度目の投稿です。
前回もほんとにたくさんの方にお読みいだたき、感謝の言葉しかありません。多くの方に支えていただいた『カムカムエヴリバディ』最後の記事です。
4月11日から連続テレビ小説『ちむどんどん』が始まり、“朝ドラ”の舞台は沖縄へと移りました。
『カムカムエヴリバディ』の放送が終わって1か月近く経とうとしていますが、個人的には、終わった、という実感がまだありません。やり遂げた!という実感もまったくありません。
“不思議な気分”――というのが一番しっくりくる言い方です。
今回、総集編という形で再び皆さまに『カムカムエヴリバディ』をお届けできる機会を得ました。本来は最終回の放送直後にnote記事をアップする、という予定でおりました。
ですが、筆が止まるというのはこういうことを言うのでしょうか、何を皆さまにお伝えするべきなのかが、自分の中でまったく見えなくなってしまってしまい、(社会人としては失格ですが)約束した原稿を先延ばしにし続けてしまいました。
もう『カムカムエヴリバディ』は完全に私の手から離れました。巣立った子どもを育てた日々を思い返すくらいしかできません。でも……今しか書けないことがある、今しかお伝えできないことがある、そう信じて書いていきます!
プロジェクトが始まった2019年4月から足かけ3年、一番の試練と言えば、なんといっても「コロナ禍」でした。ありとあらゆることを根本から見つめ直さないといけないことになりました。今、この時代にドラマを作って皆さんにお届けするということはどういうことか。この制作期間中、ずっと考え続けてきました。
放送中、ほんとに皆さんからたくさんの反響をいただきました。「ドラマの考察」という言葉も身近に聞いたのは今回が初めてでした。
これまでは、「作家が生み、キャスト・スタッフが育てた作品を、ご覧いただく皆さんにお届けする」というイメージでドラマ作りをしてきましたが、今回、少し違う感覚に陥りました。
「作家が生み、キャスト・スタッフが育てようとした作品を、ご覧いただく皆さんがしっかり最後に育てて見届けてくださる」、そんな感覚です。
今回は、この『カムカムエヴリバディ』という作品作りを通して、「演出」という立場で、私自身が何を経験し、何を思い、何を考えたか、お話ししていきたいと思います。お気軽にお付き合いいただけたら幸いです。
最初の志――記憶に残るドラマを作りたい
3年前、私はちょうど『まんぷく』という“朝ドラ”を終えたばかりでした。
撮影中に尿管結石を患い、打ち上げでもお酒を飲めず、その後即入院、手術をしました。じっと病室でやることもなく、弱った体でこの先のことを考えていました。秋に一作品、土曜ドラマという番組を担当することは決まっていました。
ふとその先のことを考えているうちに、3年先の“朝ドラ”のことなんて誰もまだ考えてないから、今のうちに手を挙げれば、もしかしたら初めて“朝ドラチーフ演出”をやらせて貰えるんじゃないか、そんな甘い思いが芽生えてきまして……
退院後、まずは作家の藤本有紀さんを訪ねました。
以前ご一緒した『夫婦善哉』というドラマ以来、時々お会いしては、こんなのやりたいですね、あんなのやりたいですね、と夢を酒の肴に話してきていたので、その流れで、朝ドラこんなんやってみたいですね、という話をたくさんしました。
「朝ドラやってみたいですか?」
「もう一度書いてみたい」
そうおっしゃったので、藤本さんもやりたい!とおっしゃっていると息巻いて、上司に訴えました。
すると、なんと「藤本さんで朝ドラ」ということまで全く同じ思いを抱いていた人物が一人いました。制作統括の堀之内礼二郎です。じゃあ、二人で企画を立ち上げろ、とトントン拍子に話が進みさっそくプロジェクトが立ち上がりました。
最初は藤本さんも別の仕事をされていましたし、堀之内を筆頭に初期メンバー5人も、土曜ドラマ『心の傷を癒すということ』という作品を作っていました。そんな中で、少しずつ企画を温めていきました。
どういうドラマにしていくか。最初の1年は自由に語り合える時間がまだまだありました。初期メンバーで40回以上のミーティングを重ねました。
ドラマの企画内容ももちろんですが、ドラマの「作り方」の指針、このプロジェクトにおいて何を大事にするかということも議論を重ねました。
どうなればこのプロジェクトは成功なのか?
元々NHKの放送は視聴率をとることを第一義にしていないところはありましたが、それでもやはり視聴率は気になるところ。しかし、(時はまだコロナ禍前でしたが)ネット配信の映像文化が勢いよく登場し、テレビの視聴習慣が徐々に変わり始めていました。視聴率という価値基準も揺らぎ始めていました。
そんな時代の中で、何をもって「成功」とするのかは、非常に悩ましいポイントでした。
当時ノートに走り書きしていたメモを見返すとこんなことを書いています。
「記憶に残るドラマにしたい」
テレビは、再放送はあれど基本的には一度きりの放送が勝負のメディアです。その一度きりしかない「生の体験」を、いかに多くの人に届けることができるかを求めて戦ってきました。
ただ本音で言うと、精魂込めて作った番組を一度しか見てもらえない、というのはとても悲しいことです。せめて「記憶に残るものを」というのが当時の私の切なる願いだったのかもしれません。
しかも、テレビは基本的にご覧いただく方の顔が見えません。乱暴な言い方をすると、作ってしまえばそれで終わってしまうのです。
ほんとにそれでいいのか?
諸先輩方からは「誰に見て欲しいか?身近な人でいいから、その人の顔を思い浮かべて作れ」と昔から言われてきました。
私事ですが、数年前に亡くなった親友がいました。同世代の小道具担当として、下っ端の時から現場で苦楽を共にし忌憚なく物を言い合える仲間でした。彼の出身地が岡山でした。
今回、物語の舞台の一つが岡山になり、彼のことを思い浮かべました。ケンタはこのドラマを見てどう思うか、常に自分に問い続けながら『カムカムエヴリバディ』を作っていこうとこっそり心に決めました。
ノートのメモには続けてこんなことを書いています。
「では、どうすれば記憶に残るのか。人の心を動かす、つまり、感情的であること。これをつきつめていくこと」
恥ずかしながらこれが私の最初の青臭い志でした。
常に感情的であること、これは実はとても難しいことです。例えばグループショット(少し引いた画角から複数人を写すカット)を撮っても、どこに誰がいてどういう状況で誰と話しているということを“説明する”だけのカットにはせず、その場にいる人物それぞれの心情が見えるカットにする。
どの1カット切り取ってもそこに誰かの心情が表現されている映像にする。
そんな映像を紡ぎ続ければきっと人の心を動かすものができるに違いない、漠然とそんなことをイメージしていました。
「作り方」すら根本から揺らぐ経験
準備を進めていく中で、思いも寄らぬ事態が起きました。「コロナ禍」です。
2020年4月、最初の緊急事態宣言が出て、作家の藤本さんとの打ち合わせも中断せざるを得ない状況になりました。しばらく自宅に籠もる生活に入りました。「ドラマは不要不急か否か」という議論が巻き起こっていました。
「リモートドラマ」なるものを作るぞ!という声も聞こえてきて、結構激しく動揺した覚えがあります。“朝ドラ”もどうなるか分からない状況でした。
ステイホームの中、ネット配信の映像を見る機会が増えました。テレビの役割は?と考えさせられることも多々ありました。
今こそ何か出来ることを、と猛烈に動き始めた制作者たちが発信する数々の「リモートドラマ」を半ば悔しい思いで見ながら、いやいや今自分は『カムカムエヴリバディ』の準備に専念すべき時と言い聞かせたりしたものの、完全に思考が停止してしまいました。
一回頭の中を整理しないと……そんな気持ちに駆られて、自分がドラマを作るにあたって大事にしたいことは何か、もう一度考え直しました。まず3つの項目を挙げてみました。
内容:
企画内容、ドラマのストーリー、その他すべてを含むドラマ本編の仕上がり自体のこと。
作り方:
その「内容」をどういうアプローチ、方法で作っていくか。
届け方:
できあがったものをどういう形、方法で皆さんに見ていただくか。
何を大事にしていくか見極めるにあたって、この3つを混同するとややこしくなる、そう思いました。
「リモートドラマ」はある種「作り方」に価値を置いたもののように当時の私は感じました。失礼ながら「内容」が物足りないと感じてしまうものも多々あったからです。ただ、圧倒的に今を捉えている。今しか作れない「内容」だし、今リアルタイムで「届ける」ことに意味がある。
……などなど、3つの項目を元に整理していくと、いろんなことが明確になってきました。
そして気づいたのは、やはり「内容」がちゃんとしていないと面白くない、という当たり前のことでした。テレビドラマである以上、最終的には、面白いか、見応えがあるかどうか、共感できるかどうか……今まで言われてきた判断基準で考えるしかないのだ、そう思えた瞬間に、初心に戻ろうと思いました。
――今できることを、奇をてらわず、誠心誠意やる。
結局は精神論なんですが、そんな気持ちにたどり着きました。必要なことは常に基本に立ち返ること。まずは「内容」をちゃんと作ること。その意味をあらためて考え直せたことは、今から振り返るととても大事なステップでした。
※この時期に、作品の内容について何を考え準備していたかは、前回投稿したnoteに詳しく書いています。初期の番組構想についてもデザイナーの瀨木が詳しく書いています。よろしければご覧下さい。
コロナ禍でのヒロインオーディション
心は決まったものの、やはり「作り方」の面でいろんな試練が訪れました。その一つがキャスティング。まだ撮影の1年近く前ですが、キャスティングも動き始めなければなりません。
しかし、このコロナ禍の状況はいつもとまったく違う様相を呈していました。
いろんな俳優事務所のマネージャーと話してみても、「今年やる予定だったドラマが来年になりそうなんですが、まだいつになるか決まっていなくて……」「映画の話はあるんですが、いつやるかまったく分からず……」など、先々の予定が見えない役者さんがあまりにも多い状況でした。
舞台もかなり中止や延期になり、何より映画が大変なことになっているらしいという話を聞きました。
映画・ドラマ・演劇業界全体が先行き不透明な状態の中、オーディションを開催するかどうかの議論になりました。
“朝ドラ”と言えばヒロインオーディション、そんなイメージを持たれている方もたくさんいらっしゃると思います。
オーディションの良さはなんといっても新しい出会いや可能性にあふれていること。
その価値は、オーディション開催にかかる手間や時間を差し引いてもあまりあるほどです。3人もヒロインを迎えられるチャンスを得たからこそ、ぜひオーディションを開催したい!そう私は強く願っていました。
初代ヒロイン・安子は10代~20代、2代目ヒロイン・るいは10代~80歳近くまで、3代目ヒロイン・ひなたは10代~60歳近くまでを描く、という構想は、三世代を描くという骨格ができた時点で見えてきていました。
安子とひなたは、ぜひオーディションで選びたい。通常“朝ドラ”のオーディションの場合、書類審査を経て数回の面談審査によってヒロインを決めていきます。
応募人数が数千人におよぶ一大プロジェクトですので、コロナ禍の状況においてはおおごとです。開催するには知恵と工夫が必要でした。
英語指導をお願いし、取材もさせていただいたキャスティングディレクターの奈良橋陽子さんとお話していたときのこと。アメリカでは「セルフ動画審査」というシステムがある、というのをお聞きしました。
役者さんに自分で自己紹介や演技などの動画を撮って送ってもらう、という方法です。日本よりも相当広いアメリカにおいて、例えば東海岸在住の俳優が西海岸でオーディションを受ける場合その移動だけでものすごい負担になるから、と編み出されてきた方法だそうです。
なるべく感染リスクを減らす一つのアイデアとして、書類審査後の最初の面談審査にその「セルフ動画審査」を取り入れてみることにしました。
しかし、いざ準備を始めてみると、どんな動画を撮って送って下さいという案内文一つ作るのにも一苦労。お願いしたいことはシンプルなのに、それを正確に伝えるのが難しい。
直接会話で伝えることができたらどんなに楽か、いきなりそんな愚痴ばかりが口をついて出てしまう状態でした。
ですが、きっと事務所の皆さん、俳優の皆さんがいろいろと試行錯誤してくださったのでしょう、送られてきた動画はどれも見応えたっぷり。数百名分、およそ30時間の映像が集まり、そのすべてを拝見しましたが、見飽きることはありませんでした。
動画審査は、やってみると良い面もたくさんありました。
まず感じたのは、応募してくださる方が、基本的には自分の納得のいく形で送ってくださるということでした。対面でのオーディションの場合、その場の空気に緊張して100%の力を発揮できない、ということもたくさんあると思います。
あとから聞いた話だと、動画を撮るのに10テイク以上も重ねて撮りました!とか、潔く1テイクです!とか、いろんなパターンの方がいらっしゃいました。撮影者がご家族という場合もあり、公の場ではない、素の表情も見ることができたように感じました。
そして何より、映像で届ける作品を作る以上、映像でどう写るか、という基本的な情報を得ることができました。
オーディションの終盤は、面談を重ねていきます。直接お会いすることになるので、感染対策には気を配りました。
と書くと簡単ですが、まだ「感染対策」とはなんぞや?という状態でしたので、何を準備すればいいのか、席はどの程度離すべきか、お芝居は距離が近づかない形でやるべきか、などなどすべてが試行錯誤でした。
参加者の皆さんにはフェイスシールドをしていただき、間にはアクリル板を立て……そんな、ものものしい形での対面審査となりました。
やはり直接お会いしたら、動画以上に見えてくるものはたくさんあります。今回は3人一組になって一つのお芝居を作る、ということをやりました。「演出」はこの段階になってくると、審査の側にいる、というよりは、とにかくこの場に来て下さっている役者さんたちの、一番いいものを引き出すという仕事を課せられています。必死です。
冷静な判断はプロデューサー陣に任せて、とにかくお芝居を作り続ける、これまたある意味贅沢な時間でした。
今回は、「安子」風の人物と「ひなた」風の人物の二人芝居をやってもらいました。なんと「ひなた」が「安子」の時代にタイムスリップして対面する、という内容のお芝居です。
いろんな方が演じる「安子」と「ひなた」を拝見してチームで議論を重ねたことで、「安子」と「ひなた」のキャラクターをより具体的にイメージしていくことができました。この過程がオーディションの醍醐味でもあります。とても大事な時間でした。
最終的に、「カメラテスト」と呼ばれる、ふん装をしてもらってセットで本番同様に撮影する最終選考を経て、『カムカムエヴリバディ』のヒロインは、安子=上白石萌音さん、ひなた=川栄李奈さんに演じていただくことに決めました。
書類審査と動画審査と対面審査。新しい経験であり挑戦でした。今まで以上に多角的に、参加して下さった方のことを知ることができたように感じています。踏ん張ってオーディションをやってよかった。強くそう思っています。
困難を極めた撮影スケジュール組み
コロナ禍の影響を一番大きく受けたのが、撮影スケジュールです。
『カムカムエヴリバディ』では、松岡一史と深川貴志という二人のディレクターが、スケジュール組みを行う、通称「スケジューラー」を担当しました。二人ともドラマの演出経験をもち、キャリアも腕も確かなディレクターです。
実際、松岡は第10・12・19週、深川は第22週で演出を担当しました。
このスケジューラーという仕事はものすごく高度な演出力が必要です。ドラマ作りの生命線とも言えるスケジュール調整の役割を、信頼する演出家の二人に今回は託すことにしました。
スケジューラーは、全部署の事情を調整しながら、どういう順にシーンを撮っていくべきかを考え抜き、スケジュールを組んでいきます。
もちろん出演者の皆さんのスケジュールの調整も必要です。仮に1回分の放送で15シーンあったとして、単純計算で112回の放送で全1680シーン。実際はもう少し多くのシーンがあります。それをいつ、どの順で撮っていくかを決めていく、気が遠くなるような仕事です。
しかし、ただ機械的にパズルをしていくだけでは、絶対にいいお芝居・映像は撮れません。台本の頭から最後まで順番に撮っていけるに越したことはありませんが、そうもいかないことが多々あります。
例えば、撮影スタジオは商店街と竹村クリーニング店とジャズ喫茶のセットを一度に同時に建てられるほど広くはありません。一つのセットのシーンをまとめて撮影しては、セットを建て替え、また別のセットのシーンをまとめて撮影する、その繰り返しです。
るいと錠一郎が「クリーニング店」で初めて出会うシーンを先に撮るのか、るいが「ジャズ喫茶」で錠一郎のトランペットを聞くシーンを先に撮るのか……
セットの都合やロケ地の事情、出演者のスケジュール、天候など、針に糸を通すような細かい交渉と確認を経て、なんとかできるだけ台本の流れ通りに撮っていけるように調整していきます。
そうすることで、役者さんのベストのお芝居を引き出し、作品がよりよい仕上がりになることを目指すのです。
ただでさえ難しいスケジュール組みに追い打ちをかけたのがコロナ禍でした。奇跡的に、出演者が新型コロナウィルスに罹患して、撮影に大きな影響が出るということはありませんでした。
『カムカムエヴリバディ』の撮影が順調でも、役者さんが出演している他のドラマの現場が止まり、先々のスケジュールが読めなくなることも多々ありました。緊急事態宣言が出たことで、ロケ予定を延期せざるを得なかったことも何度かありました。松岡と深川は、万が一撮影できなくなった場合の対応策を常に考えて用意していました。
私自身もかつて“朝ドラ”でスケジューラーを担当したことがあります。でもほんとに今の、何が起きるか分からない、この状況の中でスケジュールを組むことを自分ができるかと言えば、まったくもって自信がありません。
台本が全部できてスケジュールのめどがたったあと、深川は最終週前の第22週の演出を担当しました。自分が作ったスケジュールで撮る、まさにプレイングマネジャー、獅子奮迅の働きでした。
出演者のマネージャーの皆さんにもほんとにお世話になりました。たくさん無理を言ったと思います。無事撮り切れたことが何よりの勲章。あらためて御礼申し上げたいと思います。
問われる現場のコミュニケーション力
『カムカムエヴリバディ』の撮影は2021年3月10日から2022年2月26日まで、およそ1年間にわたって行いました。
一時期の状況を考えると、無事クランクインできる、ということだけで涙が出そうなほどでした。撮影時の「感染対策」は、大阪局制作の前作『おちょやん』でノウハウを作り上げていたので、それを引き継ぐ形で(もちろん試行錯誤はありましたが)割とスムーズに行うことができました。
最初の話に戻りますが、撮影はいよいよ本格的に「内容」を突き詰めていく局面です。ご覧いただく方に「届ける」ことを常に念頭に置いて、「作り方」を試行錯誤しながら「内容」を突き詰めていく。
前回のnote記事にも書きましたが、今どんな気分でこのドラマを見ていただきたいか。
「あたたかくて 優しくて 愛おしい」
そんなキーワードを掲げて撮影を始めました。
撮影が始まって、ささいなことですが、戸惑ったことが一つありました。
これまでの場合、私は割とスタッフや出演者とお食事に行ったりして(有り体に言うと飲みに行って)コミュニケーションをとった上で、撮影に挑むということが多かったのですが、それが一切できない!という事態に直面したのです。
大阪局の場合、東京から来る出演者は泊まりで来ていただくことが多いので、リハーサル後とかに自然と一杯行きます?といった流れになる……そんなある種の「合宿状態」になるのが、大阪制作の一つの良さだと捉えていました。
しかし今回は、結局一年を通してほぼ飲みに行く、ということができない状況のまま終わりを迎えてしまいました。『まんぷく』の時に尿管結石を患って飲めなかったのとは訳が違います。
“ノミニケーション”に頼らない仕事の仕方、ものの作り方、今更ながら恥ずかしながらそんなことに向き合わねばならぬ日々でした。
基本的に口下手なのですが、スタッフ・キャストの皆さんと現場で目を合わせると、なるべく一言でもいいから何かを話しかける、そんな努力もしました。
感染対策の中には、撮影現場にはほんとの必要最低限の人員しか立ち入らない、というものもありました。“朝ドラ”のような長い作品の場合、脚本開発と撮影と仕上げの作業を同時並行でしかもノンストップで進めていくので、どの部署もメンバーのローテーションを組んで対応していきます。
演出の場合、普段だと自分の演出回ではないシーンを撮っている時も時間さえあれば現場で芝居を見たりするものなのですが、今回、この感染対策のためにそれがかないませんでした。できあがった映像を見ないと何を撮っていたのかが分からない、という事態が起きたのです。
コミュニケーションによる「連携」しか術がない。とにかくちゃんと引き継ぐ、議論するといったことが一層求められました。
そんな状況でしたが、撮影はほんとに刺激的でした。必死でしたし、夢中になりました。
今何をご覧いただく方に届けるか。現実世界であまりにも過酷なことが起きている今、届けるものは「あたたかく 優しく 愛おしく」共感できるようなものでありたい。
撮影の仕方は、とにかくいろんな意味で「無理をしないこと」を心がけていたように思います。「ドラマチックであるからこそドラマである、クライマックスには外連味が欲しい!」そんなことも今までよく言われてきましたが、今回は、なるべく“作り物”感を排除したいという気分にどんどんなっていったような気がします。
ご覧いただく方の隣にそっと寄り添って自然と存在しているような世界を作り出したい。それが今突き詰めるべき「内容」だと、撮影を進めるうちに感じていきました。
そう感じさせてくれたのは、他でもない、ヒロインのお三方でした。
上白石萌音さん、深津絵里さん、川栄李奈さん。作り上げた世界の中で、「愚直に」という言葉が一番しっくりくるほど、見事に役を生き抜いて下さいました。
お三方を撮っていると、何も小細工は必要ないといいますか、とにかくそこに生きる「安子」「るい」「ひなた」を撮りたいという気分になってくるのです。
そのまま届けたい。彼女たちが生きている世界は自分たちのすぐそばに「あたたかく 優しく 愛おしく」存在している、そう思わせてくれるヒロインでした。お三方と共に作品を作れたことはかけがえのない経験でした。
お三方から学んだことは数知れません。その集中力、愛情、技術、努力……何をとっても見習いたいことばかりでした。
一つ象徴的なエピソードとして、るいの髪型の話をしておきます。
年代を追うごとに髪型が変わっていったことにお気づきの方も多いと思います。るいの髪型については、深津絵里さんと何度も相談しながらプランしていきました。ウィッグを使うこともなくすべてご本人の髪で、年代を追うごとに徐々にカットしながら撮影しました。
ドラマの終盤でるいと安子の再会を描くことが元々プロット段階で想定されていました。
「るいが額の傷から精神的に解き放たれた状態で安子と再会することで、贖罪の思いを抱え続けた安子自身が救われる」という表現にしたいと思っていたので、最後はショートヘアで額の傷も隠していない、というヘアスタイルにしようと決めました。
クランクイン時点のロングヘアーから最後へ向けて徐々に短くしていく中で、時代や年齢の表現もしていこう、と相談してプランしていきました。
長い年代を描くにあたって、一つの“エンターテイメント”としていろんな姿をお見せしていきたい――深津さんの中にそんな思いがあることも知りました。
何かを表現するためにとことんやりきる、そのほんとにプロフェッショナルなお姿には学ぶことしかありませんでした。
和菓子作り・ダンス・野球・トランペット・ピアノ・クリーニング・そろばん・殺陣・方言・英語・歌唱……挙げればきりがありません。
深津さん、上白石さん、川栄さん、そして他のキャストの皆さんには、お芝居はもちろんのこと、やってくれと無茶をお願いしたことは多々ありましたが、まったく平然とした顔をしながら、ものすごい努力をして、自然とそこにいて当たり前にやる、という表現をしてくださいました。
そんな現場の原動力となったのは、何と言っても藤本有紀さんの圧倒的な力を持った脚本です。
元々「プロット」という形で最後までの大きな構想はありましたが、台本をいただくたび、すべてにおいて新鮮な驚きがあり、ワクワクしながら撮り続けてきました。
物語を動かすために登場人物を無理に動かす、ということが一切なく、登場人物が生きて交差していくことで物語が動いていく、という手法で書かれた藤本さんの脚本の凄みを毎回感じていました。
ご覧いただいている方とほとんど同じ驚きと感動を抱いて脚本を読んでいた気がします。
キャストの皆さんの中にも藤本さんの脚本への絶大なる信頼がありました。脚本に身をゆだね、登場人物の気持ちでこの劇中の「今」を生きる――私はただ、そんな登場人物の姿を真摯に撮り続けたという感覚でした。
脚本の力と出演者の皆さんの表現力に感服し続けた日々でした。
※制作現場の奮闘の模様は、美術部・麻生と照明部・天野がnoteに詳しく書いています。これも合わせてご覧いただければ!
三世代100年を描いたからこそ見えてきたもの
撮影が終わると映像の編集をします。撮った映像を15分の放送枠にはまるよう、映像を切り貼りしながらつないでいくのです。
この作業はとにかく繊細なものです。撮ったカット1つ、その長さが少し変わるだけで、全体の印象が180度変わることすらあります。
ドラマはもちろん作り手が意思を持って作り、ご覧いただく方に届けるものです。ですが、「これ感動するでしょ!」とか「笑えるよね!」みたいな作り手側の(あえて言うなら)「ドヤ顔」が見えた瞬間に冷めるもの。このさじ加減がほんとに難しいです。
『カムカムエヴリバディ』の編集作業は、佐藤秀城というスタッフが全編通して担当しました。佐藤と演出担当が基本的に二人で作業し、プロデューサーや他の演出らを交えた試写を経て、議論を交わして最終的に放送に出す形に仕上げていきます。
第1週の編集をしている時に、佐藤と相当議論を重ねました。そもそもこのドラマはどう見せていくべきものか。藤本さんが生み出すこの世界をどう伝えていくべきか。
二人で出した結論、指針は「演出が姿を消す」というものでした。作為的なことをなるべく排除し、登場人物の感情を軸に、とにかく小細工なしでオーソドックスに物語を紡いでいく、そんなイメージでした。
編集作業をすればするほど、「三世代100年を描く」ということの、事の大きさに直面していきました。ドラマは冒頭から時間を追っていくものだとすると、その時間をどう積み重ねていくかということに正解はありません。
佐藤は数々の大河ドラマや“朝ドラ”の編集を手がけてきた編集スタッフです。
このことを伝えたいならこういう手がある、ああいう手がある、と次から次へとアイデアが出てくる、あまりにも引き出しの多いベテランスタッフです。その佐藤ですら、回を追うごとに頭を抱えることが多くなりました。
これだけの長い100年におよぶ物語です。時間を積み重ねることによって描き出せることは山ほどあり、表現の選択肢もたくさんありました。
藤本さんの脚本を敬愛してやまない佐藤の口癖は「もっとよくなる。もっと豊かになる」。
脚本の世界を立体化するにあたって、とことんいろんな可能性を追求してくれました。まさに100年を共に生きたような感覚。積み重ねた時間の重さに圧倒されながら、悩んで悩んで編集作業を進めていきました。
もちろん撮影時点から仕掛けたことも多々あります。
例えば、かつて空襲で焼けた岡山の商店街と現代の岡山の商店街。あの場所が半世紀の時を経て、こうなった、と感じられることも100年という時間を描く醍醐味でした。意識的に同じカット割り、カメラポジションにこだわって撮ったりもしました。
あの焼け野原、金太が号泣していたあの場所をひなたが走っている……そう思うだけで涙が出てきそうになりました。
放送終盤には世界で大きな出来事が起き始めていました。この日本で、この100年間に生きた市井の人々の経験を、フィクションとは言え積み重ねて描いてきた意味をあらためて考えざるを得ませんでした。
※仕上げの奮闘は編集作業だけではありません。映像、音の効果もこだわりの塊でした。そのあたりのことを、映像技術・今村と音響効果・伊東がnoteに書いています。こちらもぜひご覧下さい!
今の時代の「届け方」
『カムカムエヴリバディ』の終盤、アニー・ヒラカワという人物が登場しました。
そこで思わぬことが起きました。なんと最終週に入ってもなお、アニーは安子かどうか?と、ご覧いただいている方々の中で考察が繰り広げられている!
まったく予想していなかったことでした。
実は、我々としては、登場して割と早い段階で、アニー=安子である、ということをはっきり分かるように組み立てて作ったつもりだったのです。
小出しに「匂わせ演出」をやっていた気はまったくなかったのです……。
最初の方に書きましたが、『カムカムエヴリバディ』を作るにあたって「届け方」についてもいろいろと考えてきたつもりでした。作って投げっぱなし、ではやはりとても無責任な話だと、昨今のいろんな状況を見ても思うようになりました。
早くから広報展開チームを立ち上げ、『カムカムエヴリバディ』をどんな工夫とともに届けるか、いろいろと試行錯誤し続けました。
最初にイメージしたのは、近所にある気楽に行ける遊園地のような場所でした。
関西某所に100年以上の歴史を持つ有名な遊園地があります。肩肘はらずに行って楽しい場所。広報展開を含めたプロジェクト全体がそんな感じになったらいいねえと語り合っていました。
ホームページやSNSを遊園地の入り口として、ドラマ本編自体がその遊園地のメインアトラクション、他にもちょっと楽しいイベントがあるようなイメージです。
語学班に持ちかけて『ラジオで!カムカムエヴリバディ』というラジオ番組を立ち上げたのもその一つでした。
テレビで決まった時間に放送するドラマ本編を楽しんでいただくのはもちろんのこと、SNSやラジオなどテレビ以外の媒体を通して、また異なる方法でこの作品世界を楽しんでもらえるような仕掛け作りにもトライしてきたつもりです。
何より励みになったのは、皆さまからいただくほんとにたくさんの反響でした。最初に書きましたように「育てようとした作品を最後に育てて見届けてくださる」、そんな感覚でした。
アニーの考察も予想はしていませんでしたが、一緒になって楽しんでもらえたことがほんとにうれしかったです。
『カムカムエヴリバディ』を通して気づきました。
“皆さんと一緒に作るドラマ”――それこそが、今の時代のテレビドラマの理想型なのかもしれないと。ともに楽しみ、共感し、いろいろ語り合える、そんな人と人とがつながるきっかけになれるもの。
テレビは決まった時間に放送をする一方通行のものであり、この形が変わらない以上「届け方」に制限はたくさんありますが、「内容」「作り方」「届け方」に工夫をこらし、皆さんに寄り添い、皆さんと共にあるドラマをしっかりと作り続けないといけない。そう痛感しました。
さいごに
ものすごい長文になってしまいました。ここまで拙文お読みいただき、ほんとにありがとうございました。
スタッフ・キャスト皆が必死になってあたためて最後まで愛情を込めた作品を皆さまにお届けすることができ、そして皆さんにかわいがっていただけたことが何より何よりうれしいことです。
この記事の中で触れることはできなかったスタッフ・キャスト・指導考証の先生方・撮影でお世話になった皆さま、そしてそして、ご覧いただいた皆さま……ほんとに大勢の方のお力なくしてはここまでたどり着くことができませんでした。
この場を借りて御礼申し上げます。ほんとにありがとうございました!
コロナ禍の影響で打ち上げもできませんでした。撮影最終日、スタジオに集まって記念写真だけ撮りました。声を出さずにマスクを外して写真を撮りました。
できあがった写真を見て……
この1年の間に出会ったスタッフはマスクをとった顔を見たことがない!という衝撃。誰だか分からないのです……なんと切ない!
いろんな試練がありました。これからもたくさん試練が続くと思います。
でも虚無蔵の言葉にあるように、まさに「日々鍛錬」。
長らく大阪でドラマを制作してきましたが、関西にはほんとにすばらしいロケ地もたくさんあります。少し移動するだけで、時代劇の風景から、大都会の景色まで広がっています。
かつて「日本のハリウッド」と呼ばれた京都太秦を中心に関西だからこそできることを大事にしながら、これからも皆さまに楽しんでいただけるコンテンツを作り続けたいと思います。
最後の最後に、一つエピソードをご紹介しておきます。
磯村吟役の浜村淳さんの最後の声録音を行った日のこと。お見送りした時に、浜村さんがこうおっしゃいました――「勉強になりました」と。
この世界で半世紀以上トップランナーとして走り続けてこられたスーパーレジェンド、浜村淳さんのお言葉です。
このドラマの企画段階の時、100年に及ぶ年表を作りました。るい編で描いた1960年代の大阪のジャズの世界も調べ尽くしました。
その際に、真っ先に目にしたお名前が「浜村淳」でした。
浜村さんは当時大阪や京都の「ジャズ喫茶」と呼ばれたライブハウスで司会業をされていました。劇中の「サマーフェスティバル」やトランペットコンテストにも司会者が登場しましたが、まさにあのようなお仕事です。
時代の証言者、という意味合いも含めて、何らかの形でこのドラマにご出演していただきたい!そういう思いを強く抱きました。
その後しばらくして、旧知のトランペッター、MITCHさん(トランペット指導をお願いしました!)という方から連絡をもらいました。
「もじりさん、浜村さんがラジオで今度の朝ドラの話をしてましたよ!」「え!?」みたいなやりとりがあって、よくよく聞いてみると、ちょうどこのドラマの制作発表をした直後に、浜村さんの名物ラジオ番組で、「カムカムエヴリバディ」という平川唯一さんのラジオ英語講座にまつわる思い出や、戦後のジャズについて語っていらっしゃったとのことでした。
願ったりかなったり、その後、意を決して浜村さんにご出演のお願いをした次第です。
(結果的にはありがたいことに、“時代の証言者”として、浜村さんだけでなく、佐川満男さん、北村英治さん、渡辺貞夫さん、大塚善章さんら、たくさんのレジェンドに番組に参加していただくことができました)
そんな憧れのレジェンドの口から「勉強になりました」と!!!
いえいえ、それはこちらの台詞です。
学びでしかありませんでした!
格好いい。すごい。ああ、こんな大人に私もなりたい!!!
連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』、最後の最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました!
また皆さんにお目にかかれることを願って、精進し続けます!
演出 安達もじり

ドラマ番組ディレクター。主な演出作品は、連続テレビ小説「カーネーション」「花子とアン」「べっぴんさん」「まんぷく」、大河ドラマ「花燃ゆ」、土曜ドラマ「夫婦善哉」「心の傷を癒すということ」(第46回放送文化基金賞最優秀賞受賞)、ドラマスペシャル「大阪ラブ&ソウル この国で生きること」(第10回放送人グランプリ受賞)など。
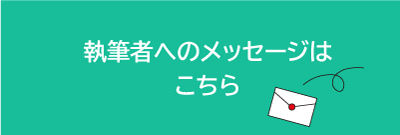
▶▶公式Twitterはこちら!◀◀
▶▶公式Instagramはこちら!◀◀
