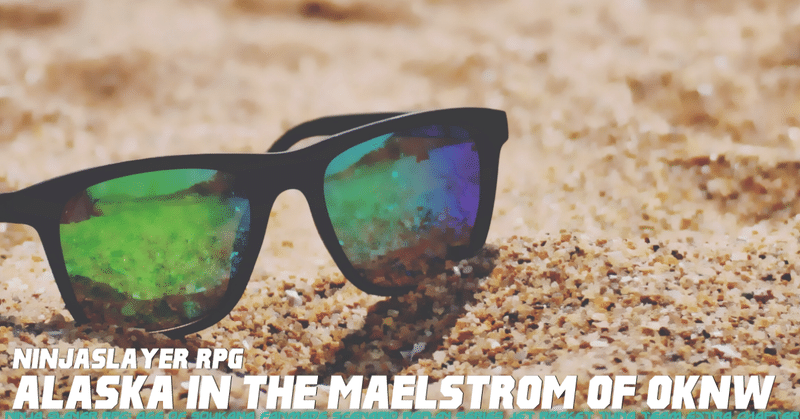
【NJRPG】アラスカ・イン・ザ・メイルシュトローム・オブ・オキナワ#2
アラスカデストラクターはかつてからのネオサイタマにおける情報収集、現地での入念な調査により、オキナワには秘匿されたレシピが現存し、それを受け継ぐ人々が実在していることを突き止めた。そしてそのレシピを秘匿する神聖なドージョーが、ここトカラ・セクションに存在することも!
この記事はDiscordのプライベートサーバーにてプレイした(かもしれない)「ニンジャスレイヤーTRPG」のリプレイ風小説風リプレイです。
実卓リプレイである「ア・ヒキャク・レイド・オン・ニンジャズ・ハウス」の後、登場人物のひとりであるアラスカデストラクターは余暇をどのように過ごしたのか?をテーマにシナリオ(もとい創作小説)を書きながら、気分でダイスを振ったり振らなかったりして展開を決めてゆくという奇妙な進行方式を採用しています。
TRPGには多様性があり、こういう遊び方をしてもいい。わかったか。
インデックス:◇1 ◇2 ◇3 ◇4
◆登場人物
◆アラスカデストラクター(種別:ニンジャ)
カラテ 6 体力 6
ニューロン 5 精神力 5
ワザマエ 3 脚力 4
ジツ 1
◆装備や特記事項
◇カナシバリ・ジツ
◇サイバネ:▶生体LAN端子、▶▶ヒキャク+
◆◆◆
「この我のもとにドージョー破りとは、良い度胸だ」「教えてもらうぞ、オキナワにまつわる秘密のすべてを……!」カテドラルに差し込む太陽光を受け、アラスカの右手に握られた刃が鋭い輝きを放った。
獅子めいたメンポのニンジャ、シンハー。一見して観光客にしか見えないニンジャ、アラスカデストラクター。二者はここトカラ・セクションのバイオ樹林に囲まれた、古い建造物内で油断ならないカラテを構え対峙していた。
◆シンハー(種別:ニンジャ)
カラテ 5 体力 5
ニューロン 5 精神力 6
ワザマエ 7 脚力 4
ジツ 1 回避D 8
◆装備や特記事項
◇エンハンスメント・ジツ、タツジン(トンファー・ジツ)、連射2、疾走
◇装備:パーソナルメンポ、トンファー(二刀流)
『エンハンスメント・ジツ』:手番開始時【精神力】を2消費し、難易度:HARDのジツ判定で発動する。
発動すると左スロットの『近接武器』によるダメージ全て(カウンターカラテも含む)が+1される。
その武器が"木製"の場合、更にターン開始時に入手する回避ダイス+2の効果を得る。
装備する武器を切り替える、あるいは戦闘が終了したとき、このジツの効果は失われる。
『タツジン(トンファー・ジツ)』:『トンファー』(二刀流含む)装備時に限り、次の効果を得る。
『カウンターカラテ』発生時、即座に追加の回避ダイスを+1獲得する。
また4つの戦闘スタイルの効果が以下のように置き換わる。
・『強烈なイアイドー斬撃』:回避ダイスを任意の数消費する。
消費した回避ダイス数+1だけ、この近接攻撃の判定にボーナスダイスが与えられる。
・『マシンめいた精密攻撃』:この近接攻撃を【カラテ】ではなく【ワザマエ】で判定する。
また自身が持つ素の『●連射』スキル値を『●連続攻撃』スキル値の代わりに使用してもよい。
この近接攻撃の判定難易度と回避難易度はそれぞれ+1されるが、『サツバツ!』は発生しない。
・『油断ならぬ防御的イアイドー』:即座に回避ダイスが+3される。
そのターンにまだ攻撃をしていない場合、敵から攻撃を受けたタイミングでこのスタンスを選択できる。
・『フェイント斬撃』:判定難易度が+1される代わりに、隣接する敵1人に対し
回避不能の「攻撃判定難易度+1」デバフを与える。このデバフは対象の次の手番の間まで持続する。
その様子を審判めいて見守るのは、両手にケジメ痕を持つひとりの老婆だ。「では、ハジメ」その一言が、無慈悲なるイクサの幕開けとなった。
「イヤーッ!」シンハーはトンファーの代わりに二本のサーモンナイフを振るい、恐るべき速度でまな板の上のオーガニック魚肉ブロックをスライスしてゆく。その切断速度にも関わらず、弾き出されるスライス魚肉のサイズは均一。何たるニンジャ器用性か!
一方のアラスカデストラクターの得物は平凡な洋出刃が一丁。シンハーは彼女の様子を慎重に伺う。カラテでは圧倒的に優勢。だがしかし、彼は対峙する敵から油断ならぬ何かを感じ取っていた。
シンハーの包丁捌きを確認すると、アラスカデストラクターはまな板へとおもむろにチョップを繰り出す!一体彼女は何をしようと言うのか!?
「イヤーッ!」カゥン!チョップ衝撃音と共に、まな板に並べられたオーガニック魚肉ブロックが30センチほど宙に飛び上がる。包丁を持つアラスカデストラクターの腕が霞んだ。ハヤイ!シンハーは驚愕の表情を浮かべた。
宙を舞ったオーガニック魚肉ブロックは、再びまな板へ何事も無かったかのように着地する。「……何だい?」老婆は訝しむ。シンハーは目にしたワザマエに驚きの声を上げた「バカナーッ!?」。
彼のニンジャ動体視力は、アラスカデストラクターの包丁が一瞬のうちに何巡にも走り、宙を舞うオーガニック魚肉ブロックを適切にスライスする瞬間を捉えていた。そしてスシネタサイズにスライスされたオーガニック魚肉ブロックは、まだその事実に気がついてすらいない。
あまりにも精密な包丁捌きに、間違いなくスライスされているにも関わらず、まるでまだ細胞が結合しているかのように振る舞っているのである!
ハナイタ・マスタリー:調理を始めとする家事全般において、あらゆる判定の難易度を-1する。
その際、判定用ダイスの算出に【ワザマエ】の基礎値を5倍として扱う。
当然ながらアラスカデストラクターは普段からこうした曲芸めいた調理法を実践しているわけではない。ただ、この苛烈なイクサで精神的優位に立つため、明確なパフォーマンスを見せる必要があると判断しただけのことだ。
コツン。アラスカがまな板を軽く指先でたたくと、オーガニック魚肉ブロックは思い出したかのようにほどけ、適切なサイズのスシネタになった。「ヌウーッ……!」シンハーは悔しそうに唸る。
◆◆◆
獅子めいたメンポのニンジャ、シンハー。一見して観光客にしか見えないニンジャ、アラスカデストラクター。二者はここトカラ・セクションのバイオ樹林に囲まれた、古い建造物内で油断ならないカラテを構え対峙していた。
その様子を審判めいて見守るのは、両手にケジメ痕を持つひとりの老婆だ。「では、ハジメ」その一言が、無慈悲なるイクサの幕開けとなった。
「イヤーッ!」シンハーは恐るべき指さばきで、7色のオリガミからあっという間に虹色の鶴を折り上げる。オリガミには繊細なタッチで奥ゆかしい曲線が与えられており、並大抵ではないワザマエが見て取れる。
一方のアラスカデストラクターはヘイキンテキを保ちながら、ゆっくりとしたペースで淡々と一枚のオリガミを折る。一見してただ折り目をつけているだけにしか見えないが、シンハーは彼女の意図を瞬時に察した「まさかそれは……フェニックスか!」
◆◆◆
正座して並ぶ2人のニンジャが条幅用筆をショドー紙に振るう。四方をショージ戸に囲まれた閉鎖空間に、常人であれば即座に失禁しかねない激しいアトモスフィアが満ち溢れる!その様子を審判めいて整然と見守るのは、両手にケジメ痕を持つひとりの老婆だ。
「フン!」先に筆を止めたのは獅子めいたメンポのニンジャ、シンハーであった。彼のショドーには、その苛烈なカラテからは想像もできない奥ゆかしい字体で「オキナワ」「最期の楽園です」などと書かれている。
「フーッ……」続けて筆を止めたアラスカデストラクターのショドーには、ただ「飛脚狂人」「不退転傾向」とだけ書かれている。「ヌウッ……やりおる!」シンハーはその短い語句に込められた、動的なイメージを想起させるパワを見逃さなかった。
シンハーのショドーが奥ゆかしく情熱そのものを文字に表した作品だとすれば、アラスカデストラクターのショドーは今にも爆発しかねない危うさを短い語句に閉じ込めた作品であると言えた。対象的だが、しかし両者譲らぬワザマエ!
◆◆◆
獅子めいたメンポのニンジャ、シンハー。一見して観光客にしか見えないニンジャ、アラスカデストラクター。二者はここトカラ・セクションのバイオ樹林に囲まれた、古い建造物内で睨み合っていた。
その様子を審判めいて見守るのは、両手にケジメ痕を持つひとりの老婆だ。彼女がこのイクサの幕開けを宣言してから、既に数時間が経過していた。
二者の前にはそれぞれ煮立つ大鍋が鎮座しており、互いに無言のまま真剣な表情でそこから目を離さない。香ばしいショーユ香りがたつ大鍋の中身は、大きな塊の皮付きの三枚肉(バラ肉)である。油断ならない2人のニンジャは大鍋を前に、ラフテーと呼ばれるオキナワ料理を作っていた。
ラフテーとはいわゆる豚の角煮めいた料理で、ショーユや砂糖、アワモリなどで甘辛く濃く味付けされる。箸で切れるほど柔らかく煮込まれるため、ある程度の塊のままの形を残し、単体の料理として提供されるのが特徴だ。
バイオ・オキナワ料理の氾濫により、現代においてラフテーは特別に品種改良されたショーユ味のバイオ豚肉を煮込んだ手軽な料理として認知されている。しかし読者の皆さんが今ご覧のように、本来のラフテーはじっくりと時間を掛けて脂を抜きながら柔らかく煮込む、手間暇の掛かる料理である。
彼らは何らかの手段で本来のレシピを知る所となり、今まさにその腕前を競わんとしていた。
「ここで決着を付ける」「臨むところだ」非凡なるニンジャ観察力でラフテーの仕上がりを見極めた二者は同時に動く。派手なパフォーマンスは一切ない。ただ張り詰めた静寂の中、ふつふつと煮立つ鍋の音に、調理器具のぶつかる小さな音だけが響く。
2人は静かにラフテーを鍋から引き上げ、包丁を入れる。切り出されたブロックはそれぞれ2人前。このイクサの勝敗は審判ではなく、調理をしたニンジャたち当人の判断に委ねられていた。互いにワザマエと公正さを併せ持つ相手だと認めたからこその判定方式である。
アラスカデストラクターはまず自身の調理したラフテーを口に運ぶ。若干香りが薄い気もするが、美味しい。適度に柔らかく、十分に脂を落とした三枚肉はしつこくない味わいで、黒砂糖とアワモリが生み出す特有のコクに良く調和している。表情にこそ出さないが、アラスカは内心うまく仕上がった喜びをかみしめた。
シンハーは荒々しくメンポをかなぐり捨て、青年の顔を露わにする。両者ともに自身の料理の味は確かめた。であれば次は、決着を着けるときが来た!相対する2人のニンジャは視線で互いを牽制しながら、ゆっくりと、別の皿からラフテーを口に運ぶ。
再びの静寂。そして。
「バカな!」シンハーはがくりと膝をついた「何故俺のラフテーより美味い……お前は、初めて知ったレシピのはず……」。
アラスカデストラクターは無言のまま、シンハーの調理したラフテーを食べ終えた。「美味しいよ」「何?」「美味しい」「バカを言うな。お前のラフテーのほうが明らかに出来が良い。良く知る料理だと慢心した……俺の負けだ」
「料理は、味で競うものじゃあないよ」「……なに?」シンハーは訝しげに顔を起こした。「私は料理が好き。子供のころからね。今だって、皆にワザマエで作った料理を食べてほしいだけなんだ」
「それは……」青年は何らかのアトモスフィアを感じ、続く言葉を飲み込む。「味なんて結局は好みの問題だと思わない?じゃあ何で良し悪しを比べるかって、それは気持ちの話で……」アラスカは考えを整理しようと頭をひねる。
「誰かに美味しいものを食べてほしいとか、そういう気持ちでは誰にも引けを取るつもりはない、だけど……」
「君の料理にもそれがあった。つまり、ラブが……」シンハーの訝しげな表情が強まった。「気持ちの優劣は比較できない。だから、この勝負は……この私が預かっておいてやろう」アラスカデストラクターは視線を逸らした。
「ハハハ!シンハー=サン、これはあんたの負けだね?なかなか愉快な子じゃないか」老婆は楽しげに笑う。「変なやつ……別に、みっともなく弁明をするつもりは端からない。俺の負けだ」
アラスカデストラクターは、事が穏便に済んだことにこっそりと安堵の溜め息をついた。「では、これでレシピを全部教えて貰えますよね?」
「バカ言っちゃいけないよ。これはただのテストさ」「それでは話が違う」アラスカの声音が鋭くなり、剣呑なアトモスフィアが混ざる。「アイエッ!?早まりなさんな。まだ……まだ話は途中だよ」老婆は一歩下がりながら話を続けた「あんたが中々できる女ということは良く分かった。つまり、そういう人間に頼みたい仕事があったのさ」。
「……」アラスカデストラクターは無言のまま、老婆とシンハーを交互に見た。ニンジャ精神力で敗北から立ち直りカラテ警戒するシンハーとアラスカの眼光が交差する。実力行使は、少しばかり分が悪いか。
しばしの沈黙の後、アラスカは言葉を発する「……いいだろう。話を聞く。だが、私は契約不履行を許さん」。油断ならぬニンジャの言葉に、カテドラルには張り詰めたアトモスフィアが漂い始めた。「そんな不義理はしないさね」老婆は冷や汗をかき、本題を切り出した「頼みたいのは、単純な仕事でね……」。
◆◆◆
「ふわぁ……」気の抜けた声を出しながら、アラスカデストラクターの顔は心地よい湯の中へと沈んでゆく。熱帯の気候と温泉。意外な組み合わせと思われるかもしれないが、実はオキナワには天然の温泉が湧くスポットは幾つもある。一仕事を終えた彼女が体を休める宿もまた、そうした場所のひとつであった。
(まさか、オキナワに天然温泉があるとは……)思い返せば、オキナワ料理については散々に調べたものの、オキナワについてはまるで何も知らない。これではまるで仕事だと、アラスカは苦笑する。
慌ただしい旅程のなか、ビーチには足を踏み入れてすらおらず、リゾートらしいカクテル酒は一滴も口にしていない。当然、そこには自分ひとりが旅行を楽しんで良いのだろうかという後ろめたさがあったことも否定できない。
一方で、土産話のひとつもなければ、どうして楽しんでこなかったのかと周囲から咎められてしまうに違いない。(どうしたものか……)アラスカはより深く顔を沈め、生来の小心さで頭を悩ませる。
カラテ強者であるシンハー、そしてセンセイと呼ばれる老婆の存在。その依頼は非常に簡潔に伝えられたが、アラスカデストラクターには彼らが何かを隠しているという確証があった。しかし、それが何故なのかまでは推測の域を出ない。いずれにせよ、今回の件は一筋縄ではいかないだろう。
必要な道具を調達し、移動手段を確保する。そして手早く仕事を片付け、レシピを伝授してもらう。全てはそれからの話だ。
(明日は頑張ろう……)
もうもうとたつ湯気に、やがてその顔は見えなくなった。
◆◆◆
トカラ・セクション、第5セクター。主要なオキナワ・リゾート圏から外れた区画において、唯一リゾート地としての体裁を整えているのが、洋上ユニットの南西端に位置するこのエリアである。
退廃的な町並み、そこに迫るコンクリート造の建造物群。そして穏やかな波打ち際が演出された白砂のビーチ……と思わしき砂浜。外界から隔絶されてはおらず、天頂にデミ太陽球も輝いてはいない。ホテルのテラスから見渡せるのは、そうしたリゾート地に似つかわしくない光景が全てだ。
もっとも、そんなオキナワの原風景を求めてここを訪れる観光客も少なくはない。彼らはそれが少なからず人工物であると知らずしてか、そこに在りし日のオキナワを見出そうとするのである。そして皮肉なことに、そうした空虚な試みが生み出すマネーこそ、このリゾートホテルと第5セクターの観光地水準を保つ重要な資金源となっていた。
ナンシーはテラス席に座り、陽の沈みゆく水平線に鋭い視線を投げかける。オキナワ海上警備保障のビーコン端末を使った調査はいずれも不発に終わった。現存するグロブスターから同一周波数帯のビーコン反応は確認できず、一部については酷い腐臭のため既に海に還されるなどしており、調査を試みることすら不可能だった。
この時点で既に、ナンシーの提唱した『グロブスターを生み出すUMA生物が人々を襲って食べている』という恐ろしい仮説は揺らぎつつあった。海上警備員の装備の他に犠牲者の残留品が出てきてもおかしくはなかったが、ビーコンどころかそうした残留品のたぐいは一切発見できなかったからである。
あれはただ偶然、誤ってビーコンを飲み込んでしまった、哀れなバイオクジラの腐乱死体に過ぎなかったのだろうか?しかし、ジャーナリストとしての勘から、未だナンシーは失踪事件にグロブスターが関与しているという疑いを捨てきれずにいた。
「あれ……」不意に背後から声が飛び、難しい顔で考え込んでいたナンシーはビクリとして振り返る。ユカタ姿のコーカソイド女性が、しまったという表情で口元を手で抑えていた。
ナンシーは戸惑うが、すぐにその正体に思い当たる「あなたは……飛行機で一緒だった?」。鎖国下の日本では、コーカソイドの特徴を持つ人間は非常に珍しい。相手がサングラスを外していたため一瞬判断に迷ったが、ナンシーはオキナワ行の機内で会釈を交わした相手の外見を確かに記憶していた。
女は恐縮しているのか、やや強張った表情でコクコクと頷く。「ナンシー・リーです。ネオサイタマ新聞社の。こんな所で、偶然ね」「記者さん?ドーモ、アラ……アリシアです。スミマセン、急に声を掛けたりして」
「気にしないで。それに……そうね、少し話を聞かせてもらってもいいかしら?何か冷たいものでも飲みながら」温泉ですっかりのぼせた様子のアリシアを気遣い、ナンシーは席を勧めた。無論、好意からだけではない。
調査の次段階として、観光客へのインタビューも予定していたナンシーにとって、この出会いは願ってもない機会だった。謎の失踪事件、腐臭を放つ恐ろしい漂流物、そうしたネガティブなキーワードは、娯楽を求めてオキナワを訪れる観光客の大半には忌避されるものだ。
だが、良い第一印象を与えられたこの相手であれば、多少踏み込んだ内容でも回答を期待できそうだとナンシーは目算を立てたのである。
「つまり、インタビュー?ええと、私オキナワは……いや、リゾート自体初めてで」ナンシーより幾分か若い女は照れくさそうに目を伏せる。「そんな堅苦しいものじゃないから、リラックスして」ナンシーは手を挙げてボーイを呼び、カクテルを注文した。「初めてのオキナワでトカラ・セクションを選ぶなんて、野心的ね」
自身を料理研究家と紹介したアリシアは、オキナワ料理のレシピを探しているのだと、トカラ・セクションを訪れた理由を語る。「つまり、こういう場所のほうが、古い情報は手に入りやすいんです。完全なリゾートなら、こう上手くはいきませんよ」やや熱っぽい口調で、女は一息に話し終えた。「とは言っても、今の所ほとんど歩き詰めですけどね」
相手がカクテルで口を休めた隙を狙い、ナンシーは話を切り出す「この辺りを歩き回って聴き込み調査していたわけね。何か、変わった話は聞かなかった?」。失踪事件はその特性上、目撃者が存在しない。当然、住民へのインタビューもナンシーの調査プランに含まれていたが、その優先度は物証たるグロブスターの調査より低く、未だ着手できていないのが現状だった。
これは渡りに船、ナンシーは了承を取りレコーダーのスイッチを入れる。
レコーダーの点滅するLEDランプを見つめながら、アリシアは難しい顔で話し始める。「変わった話……第4セクターがここ数ヶ月間、ほとんど魚が捕れていない。とか?」「つまり、トカラ・セクション周辺海域で?」「ええ。巨大バイオクジラが迷い込みでもして、魚が軒並み逃げ出したんじゃないか、なんて聞きました。でも肝心のクジラは誰も見ていないんだとか」
ナンシーはしばし考えにふける。グロブスターの漂着が頻発しているのは、六分割されたトカラ・セクションのうち、隣接した第2から第4セクターが主だったエリアだ。そして失踪事件が起こっているのもこれらが中心。
単なる偶然と捉えることもできるが、しかし、状況証拠からしてそこに何らかの意味がある可能性も否定できない。
「第2、第3セクターについてはどう?」ナンシーは慎重に話を進める。「他の場所はよく……いや、第2セクターは多分大丈夫なんだと思います。第2の漁場を借りられたら……という話もあったので」アリシアは一旦言葉を切る「ただ、正直……」。
「どうにも海に出ることを躊躇っているような、そんな印象を受けました」話を吟味してから、ナンシーは本題を持ち出すことを決めた。「……第2から第4セクターで最近、海上の失踪事件が起こっていることは知ってる?」「失踪事件?」「皆が口を閉ざすのも無理ないわ……」
「ここ数ヶ月、トカラ・セクション周辺海域で、船を残して海上で人だけが姿を消す事件が頻発しているの」「ナンシー=サンはその取材に?」「そう。こちらもほとんど歩き詰め」ナンシーは冗談めかして言う。
「でも手掛かりは断片的で、調査は行き詰まっていた。だから……良い話を聞かせてもらったわ。ありがとう」
「そんな大した話は……え、でもそれって」アリシアはナンシーの言葉を繋ぎ合わせ、ようやくその意味に気がついた。「失踪事件の原因は海中にいるかもってこと」ナンシーはシリアスな表情で続ける「アリシア=サン、くれぐれもトカラ・セクションでは海に出ないで。少なくとも、この旅行の間は」。見知らぬ相手に手の内を明かし過ぎるとも思ったが、彼女は善意から警告を与えることに決めた。
大きな目的のために小を犠牲にする。それこそ彼女たちが忌むべき暗黒メガコーポの思考だったからだ。多少自分たちがリスクを負ったとしても、これ以上犠牲者を増やすわけにはいかない。それはナンシーの決意だった。
「え……ええ。そこまで言うなら、分かりました」女はやや残念そうな表情で応える。ナンシーは密かに安堵した。
「ごめんなさいね。折角の旅行なのに、暗い話をしてしまって」「いえ、そんな……上司に旅行券を貰ったから来た、程度の軽い旅行なので」「へえ、ネオサイタマらしくない良い上司じゃない」
「じゃあ口直しに、あなたの話を聞かせて。ほらオキナワ料理とか……」
◆◆◆
名を偽り、ニンジャ存在感を巧妙に隠匿してナンシーと会話するアラスカデストラクターは、内心冷静な思考を巡らせていた。(ナンシー=サンが追っている事件……私の受けた依頼。その全てがこのセクションの特定セクターに収束している。第4セクターの不漁も何か関係が?あの老婆、一体何を隠している)
日が沈み、つかの間の暗闇が訪れる。微かな光を反射し、アラスカデストラクターの碧い目だけが妙に浮かび上がって見えた。彼女は既に、全容の見えない混沌の渦に巻き込まれてしまったらしいことを理解していた。
(ありがとう、ナンシー=サン。貴女の忠告は確かに善意からの言葉だ。でも……)ユカタの下でサイバネティクスが微かに駆動音を響かせる。(私は目的を果たすため、その好意を無下にしなければならない)遠慮がちにテラスの照明が灯り、彼女の目に宿った危険な輝きをかき消した。
【#3に続く】
![]()
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
