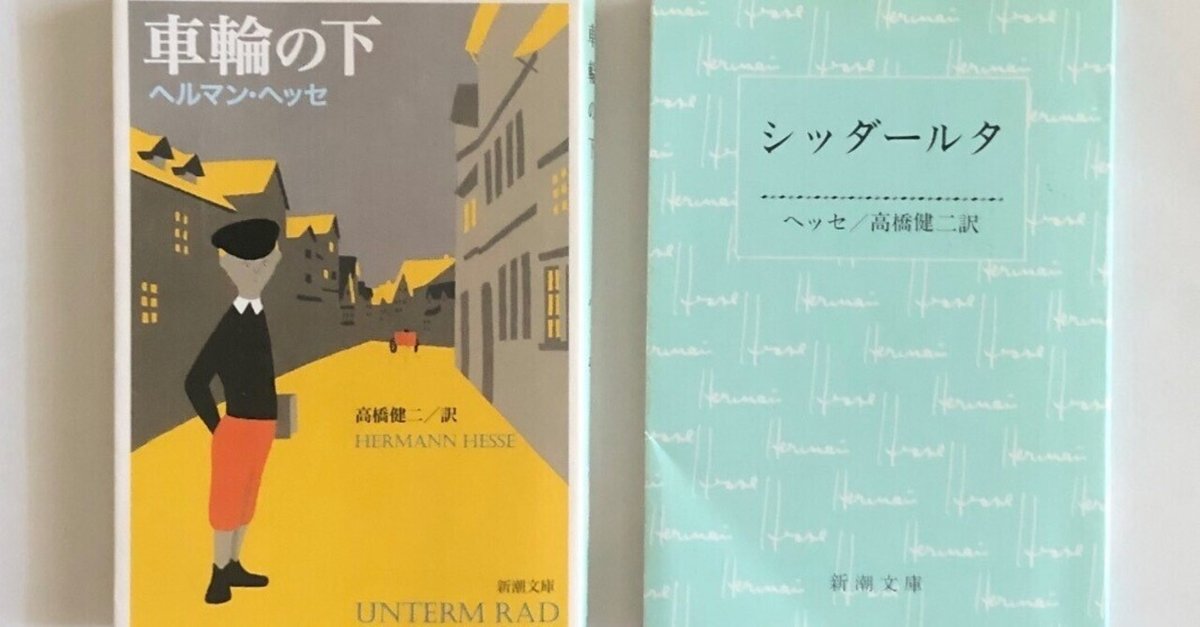
『車輪の下』から『シッダールタ』へ
ヘッセの『シッダールタ』を読みながら、しきりと同じヘッセの『車輪の下』が頭をよぎった。数年前に読んで、記憶もだいぶ薄れかかっていたのに。
二つの小説のあいだには16年間の開きがある。『車輪の下』が1906年で、『シッダールタ』が1922年。
この16年の月日のあいだに、ヘッセ自身のなかで変わらなかったなにかと、変わったなにかとを、感じとったのかもしれないとふと思った。
その考えが正しいとして、それはいったい何なのか。『シッダールタ』を読んでいるあいだ、こんなに『車輪の下』のことを考えてしまっていた理由。それを考えるのがこのページの目的だ。
その試みは同時に、ヘッセ自身の考えを自分の言葉で説明しようという試みでもある。
もちろん、今から書かれることはすでに誰かが言っていることかもしれないとも思う。それに自分はヘッセについてはこのふたつの作品しか知らない。おそらく、自分では気づいていない巨大な光の下にあるのかもしれない。このページは正しいことを言おうとしているのではなく、あくまで「思ったこと」でしかないので、どうか大目に見てほしい。
川と口づけという共通のモチーフ
まず目につくのは、『車輪の下』と『シッダールタ』のあいだには、いくつか共通モチーフがあるということ。
けれども、『車輪の下』ではひたすら暗いイメージにつながっていたそれらのモチーフは、『シッダールタ』においてはむしろ明るい展望にむかって開かれている。
川
『車輪の下』にも『シッダールタ』にも「川」が登場する。この「川」は死と通じている。
『車輪の下』の主人公、ハンスは、学校を中退し、恋にも破れ、最後には「川」で溺れ死ぬ。
そのころ、そんなに脅かされていたハンスは、もう冷たく静かにゆっくりと暗い川の中を下手に流れていた。吐き気も恥も悩みも彼から取り去られた。暗やみを流れて行く彼の虚弱なからだを、冷たい青みがかった秋の夜が見おろしていた。彼の手や髪や青ざめたくちびるを黒い水がもてあそんだ。[…]どうして彼が水の中に落ちこんだか、だれも知らなかった。たぶん道をまちがえて、けわしい場所で足をすべらしたのだろう。あるいは、水を飲もうとして、平衡を失ったのかもしれない。あるいは、美しい水を見て引き寄せられ、その上にかがんだのかもしれない。そして、平和と深い休息とに満ちた夜と月の青白い光が彼のほうをじっと見たので、彼は疲労と不安のためずるずると死の影に引き込まれたのかもしれない。
他方で、『シッダールタ』の主人公、シッダールタは、俗世に倦みつかれ、川で自殺を試みる。以下はその場面の引用だ。
顔をゆがめて彼[シッダールタ]は水中を見つめた。自分の顔が映っているのを見て、それにつばを吐きかけた。ぐったりと疲れて彼は腕を木の幹から放し、少しからだをねじって、これを最後に水中に没するため、まっすぐ身を沈めようとした。彼は目を閉じて、死に向かって沈んだ。
だが、シッダールタは死なない。注目したいのは、それが古い自分が死に、新たな自分に生まれ変わることによってであること。
こんなふうに考え、微笑しながら自分の胃に耳を澄まし、感謝の念をもってミツバチのつぶやきに聞き入った。流れる川を朗らかに見つめた。水がこれほど快く思われたことはなかった。移り行く水の声と比喩をこれほど強く美しく聞いたことはかつてなかった。川は何か特別なことを、彼のまだ知らない何かを、まだ彼を待っている何かを、彼に語っているように思われた。この川でシッダールタはおぼれ死のうと思った。その中で古い疲れた絶望したシッダールタはきょうおぼれ死んだ。新しいシッダールタはこの流れる水に深い愛を感じ、すぐにはここを離れまいと、心ひそかに決めた。
ここでは、『車輪の下』で死を導いた「川」との対面が、新たな再生の契機へと転じられているように見える。『車輪の下』ではただ死へと通じていた川のモチーフが、『シッダールタ』では、新たに死からの再生というイメージを得る。ここには同一モチーフがありながら、以前の絶望を乗り越えようとする転換が見られる。
口づけ
もうひとつ共通点として取り上げたいのは、主人公と他の人物のあいだに「口づけ」が起こる場面だ。これもまた、「口づけ」というイベントが、両作品において別の方向へ向かって開かれている。
『車輪の下』の「口づけ」は、その二人の心が通い合うことよりも、むしろ二人のあいだにある壁を感じさせるように思う。ここでは主人公ハンスと、詩人肌の問題児ハイルナーのキスが描かれる。
おもむろにヘルマン・ハイルナーは腕を伸ばして、ハンスの肩をつかまえ、たがいの顔がまぢかになるまで、ハンスを引きよせた。それからハンスは突然、相手のくちびるが自分の口に触れるのを感じて、なんともいえず驚いた。
彼の心臓は、ついぞ感じたことのない胸苦しさに鼓動した。こうして暗い寝室にいっしょにいることと、とつぜんキスされたことは、なにか冒険的な、新奇な、またおそらくは危険なことだった。この現場をつかまったら、どんなに恐ろしいことだろうと、彼は気づいた。
ハンスは突然キスされたことに驚く。そしてその理由がまったくわからない。こののちにもハンスはハイルナーに惹かれていくけれども、その理由がハンス自身にはどうもはっきりしないように見える。口づけは、二人の分かり合えなさを乗り越えようとして、むしろはっきりとした隔たりの証となってしまうのだ。
たいして、『シッダールタ』における「口づけ」はどうだろうか。それは物語の結末近くに置かれている。
ここではゴーヴィンダというシッダールタの友人の視点から、物語が語られる。ゴーヴィンダとシッダールタは、若いころに別の道に進むことになった。ゴーヴィンダは仏陀のもとで修業し、シッダールタは仏陀の教えに感銘をうけつつも、自分自身の悟りを得るために俗世に入っていった。シッダールタはその人生のなかで自分自身の悟りを得、ある境地に至った人物として、ゴーヴィンダと対面する。ゴーヴィンダはそこで、シッダールタに口づけをするようお願いされる。
「私の方にかがんで!」と彼はそっとゴーヴィンダの耳にささやいた。「私の方にかがんで! そう、もっと近く! ずっと近く! 私の額に口づけしておくれ、ゴーヴィンダ!」
ゴーヴィンダはいぶかしげに、しかし大きな愛と予感に引きつけられて、彼のことばに従い、ぐっと彼の方にかがんで、額にくちびるをつけると、彼にとって何か尋常でないことが起きた。彼の考えがまだシッダールタの不思議なことばにこだわっている間に、時間を頭の中で滅却し、涅槃と輪廻を同一のものと考えようと、逆らいながらむなしく努力している間に、友のことばに対する一種のけいべつが彼の心中で大きな愛と畏敬とを相手に戦っている間に、次のようなことが起った。
[…]
時間が存在するかどうかを知らず、この観察の続いたのが一秒であったか、百年であったか知らず、シッダールタなるもの、ゴータマなるものが存在するのかどうか、我となんじが存在するのかどうかも知らず、心の奥深くに神々しい矢で甘い味のする傷を負わされ、心の奥深くを魅了され、溶かされて、ゴーヴィンダはなおしばし、口づけしたばかりのシッダールタの静かな顔の上にかがんでいた。
[…]
深くゴーヴィンダは頭をさげた。なんとも知れない涙が老いた顔に流れた。無上に深い愛と、無上につつましい尊敬の感情が心の中で火のように燃えた。身動きもせずにすわっている人の前に、彼は深く地面まで頭を下げた。その人の微笑が彼に、彼が生涯の間にいつか愛したことのあるいっさいのものを、彼にとっていつか生涯の間に貴重で神聖であったいっさいのものを思い出させた。
この口づけは、たしかに、悟りを得たシッダールタと、いまだ迷いの中にあるゴーヴィンダの対照と隔たりを示唆している。シッダールタの考えはついに、ゴーヴィンダには理解できない。ゴーヴィンダが感じとるのは、自分自身のなかで湧く愛と、尊敬の念、そして自分自身のこれまでのことだ。この口づけを通して、ゴーヴィンダが(あるいはシッダールタが)、自分自身の外に出ることは叶わない。
とはいえ、シッダールタの額に口づけすることによって、ゴーヴィンダはなにかをつかんでもいるのもたしかだ。そしてそれは、自分の奥深くにあるなにかだ。口づけを通じてこのなにかに触れた瞬間を、『シッダールタ』ははっきりと描いている。
これを描いていることが、『車輪の下』の「口づけ」との違いであり、「口づけ」の隔たりを乗り越えるための契機に思える。
以上、「川」と「口づけ」という点に注目して『車輪の下』と『シッダールタ』を見てみた。『シッダールタ』はある意味、『車輪の下』において描かれた暗いイメージを反復していると思う。川と死の結びつきと、口づけにおける隔たりは、たしかに完全に消え去ってはいない。けれどもそこには同時に、絶望を希望に転じようとする動きが見られるのだ。
このような乗り越えについては、ヘッセと仏教との関係から考えることができそうに思う。この展開の原因に、ヘッセにおける仏教の影響があるのは明らかだからだ。けれども、ヘッセはただ仏教を受容するだけで、『車輪の下』の絶望を乗り越えたわけではない。次の項ではそのことについて考えてみたい。
仏教とヘッセの共鳴
ヘッセの『シッダールタ』は、仏陀をその始祖とする仏教さらにはインドの思想を下敷きにしている。その点で、着眼点1で示したような『車輪の下』から『シッダールタ』への展開において、仏教が重要な役割を果たしているのはまちがいない。
けれどもだからといってヘッセは、ただ仏教のみによって『車輪の下』の絶望を乗り越えたわけではないように思う。
むしろ彼は、そういったインドの思想との「出会い」によって、自分の内側に潜んでいた、それと呼応するなにかを感じとった、というほうが近いのではないだろうか。
『シッダールタ』にはヘッセのそのような思いも書き込まれているように思うのだ。シッダールタは仏陀に出会い、その言葉に感銘をうけつつも、彼とは別の道を歩もうとする。
あなたは死からの解脱を見いだしました。それはあなた自身の追究から、あなた自身の道において、思想によって、沈潜によって、認識によって、悟りによって、得られました。教えによって得られたのではありません! それで、私もそう考えるのです。おお覚者よ――何びとにも解脱は教えによっては得られないと! 悟りを開かれたときあなたの心に起ったことを、あなたはことばや教えによって何びとにも伝えたり言ったりすることはできないでしょう! 悟りを開いた仏陀の教えは多くのことを含んでおり、多くの人に、正しく生き、悪を避けることを教えます。しかし、かくも明らかで尊い教えもひとつのことを含んでおりません。つまり、覚者自身が、幾十万人の中で彼ひとりが体験したことの秘密を含んでいないのです。私が教えを聞いたとき、考え認識したのはそのことです。そのためにこそ私は遍歴を続けるのです。
この場面で、たしかにシッダールタは、仏陀の「言葉」には真実が含まれていないと、すくなくとも肝心な秘密が言葉には欠けていること語っている。
けれども他方で、仏陀の言葉を通して、シッダールタ(=ヘッセ)がなにかを感じとったのもたしかだ。
そのなにかは、決してシッダールタの外側にあるものではなく、いわば彼の内側にある「秘密」だ。それに彼は自分自身の力でたどりつこうと決意する。
ここにはひとつの示唆がある。つまり、誰かの心のこもった言葉はたしかに私たちの心を動かしはする。けれども、それだけでは不十分なのだ。私たちはその言葉が触発したであろう自分自身の「秘密」にむかって、遍歴していかなければならない。
実際にシッダールタは仏陀から自分自身の感じとったものを、自分自身で見極めるために遍歴する。
やがて、その「秘密」は言葉の上では違っていても、仏陀が感じとった真実と同一のものであったことを、シッダールタは語る。その直感は「愛」についての語りにおいてあらわれる。
愛についての私のことばがゴータマのことばと矛盾していること、一見矛盾していることを、私は否定できない。だからこそ私はことばをひどく疑うのだ。この矛盾は錯覚であることを、私は知っているからだ。私はゴータマと一致していることを知っている。ゴータマがどうして愛を知らないことがあろう! いっさいの人間存在をその無常において認識しながら、しかも人間をあつく愛し、辛苦に満ちた長い生涯をひたすら、人間を助け、教えることにささげたゴータマがどうして、愛を知らないことがあろう! あの人、おん身の偉大な師の場合でも、私にとって物はことばより好ましい。彼の行為と生活は彼の説教より重要だ。彼の手ぶりは意見より重要だ。説教や思索にではなく、行為や生活の中にだけ、私は彼の偉大さを知る。
けれどもこれは、決してシッダールタ一人で辿りつけた境地ではない。仏陀との出会いがあったからこそ、可能になった境地だ。いわばそれは仏陀と共鳴することによって、シッダールタに開かれた場所なのだ。
これはそのままヘッセの実感なのではないかと思う。ヘッセは仏教だけで危機を乗り越えたのではないのだ。仏教と自分の詩情の共鳴が、そしてそこから生まれた真実が、ヘッセをこの作品を書けるような境地へと導いたのだ。
同じことは私たち自身についても言えることだろう。
誰か、あるいはなにかとの出会いによって、感銘をうけたときのことを思い浮かべてみよう。
私たちはつい、その言葉のほうに気を取られてしまう。けれど、実はその感銘は、言葉そのものだけではなくて、私たちの内側にあるなにかが、その言葉に触発され、共鳴しているからこそ、起こっているのではないだろうか。
もしそうなら、私たちは言葉そのものだけではなく、この「共鳴」のほうにも心を凝らさないといけないのだろう。ヘッセが、シッダールタが、そうしたように。
とはいえ、ここにはヘッセが作家であるがゆえの矛盾と葛藤も見られるように思う。つまり、言葉は真実を語れない。それなのに作家は言葉を通じてでないと、この真理を伝えることができないのだ。
この矛盾とそれにたいする葛藤は、『車輪の下』でも『シッダールタ』でも、ほのめかされているように思う。
このことを考えるために、次の項に移ろう。
矛盾と葛藤の乗り越え
実は、『車輪の下』と『シッダールタ』にはもうひとつ共通点がある。それは、『シッダールタ』のなかに、暗い影、一抹の無力感をのぞかせている。
その共通点とは、物語の結末で、それまで克明に描かれていた主人公の内面が、突然隠されてしまうことだ。
『車輪の下』を見てみよう。主人公ハンスは落伍者としての自分を認識したためなのか、理由は定かではないが、川に身を投げる。
そのころ、そんなに脅かされていたハンスは、もう冷たく静かにゆっくりと暗い川の中を下手に流れていた。吐き気も恥も悩みも彼から取り去られた。暗やみを流れて行く彼の虚弱なからだを、冷たい青みがかった秋の夜が見おろしていた。彼の手や髪や青ざめたくちびるを黒い水がもてあそんだ。[…]どうして彼が水の中に落ちこんだか、だれも知らなかった。たぶん道をまちがえて、けわしい場所で足をすべらしたのだろう。あるいは、水を飲もうとして、平衡を失ったのかもしれない。あるいは、美しい水を見て引き寄せられ、その上にかがんだのかもしれない。そして、平和と深い休息とに満ちた夜と月の青白い光が彼のほうをじっと見たので、彼は疲労と不安のためずるずると死の影に引き込まれたのかもしれない。
ここでは、ハンスの死は、自殺なのかどうかも、はっきりしないのだ。彼が最後の瞬間になにを感じとったのかも、作品は語らない。そこにはあきらかに、ハンス自身にとっての「真実」があったにもかかわらず。というよりも、そこにハンスだけの「真実」があったからこそ、作品は、それを言葉にできないのかもしれない。
これと似て、『シッダールタ』の最後の章は、ゴーヴィンダの視点に文章の焦点が切り替わる。そして、ゴーヴィンダの目から、悟りの境地に至ったシッダールタが描かれる。
もちろんシッダールタは、言葉を駆使してゴーヴィンダに自分の真実を伝えようとしている。その点では『車輪の下』とは違っているように見える。けれども、ここでははっきりと「言葉の無力さ」が語られてもいるのだ。このことは着眼2で行った引用にあらわれている。加えて、そもそもシッダールタが出会った「真実」は、ゴーヴィンダと彼と視線を共有する私たちには隠されたままだ。
このように、二つの作品には、主人公の内面が経験した「真実」が描かれないという共通点がある。ハンスがどのような絶望を経たのか。シッダールタはどのような真理に至りついたのか。それ自体は謎のままにしておかれるのだ。
言葉によっては真実を語ることができないという、同一の葛藤がここには通底している。それなのに、作家としてヘッセは言葉を駆使しなければならないという矛盾も同様だろう。
だが、この矛盾と葛藤を乗り越えるための道を、『車輪の下』では乗り越えられなかった壁を乗り越える契機を、『シッダールタ』はたしかに描き込んでいる。
すなわちそれが、先ほど書かれたような「共鳴」なのだ。
もう一度、着眼1で見たゴーヴィンダの口づけの場面を引こう。ここでは、『車輪の下』のハンスとハイルナーの口づけとは別の事態が起こっている。
深くゴーヴィンダは頭をさげた。なんとも知れない涙が老いた顔に流れた。無上に深い愛と、無上につつましい尊敬の感情が心の中で火のように燃えた。身動きもせずにすわっている人の前に、彼は深く地面まで頭を下げた。その人の微笑が彼に、彼が生涯の間にいつか愛したことのあるいっさいのものを、彼にとっていつか生涯の間に貴重で神聖であったいっさいのものを思い出させた。
私たちは、他人の「真実」を知ることはできない。けれども、他者の真実に共鳴する自分の「真実」を触れることはできる。
それを通じてなら、他者と同じ「真実」に触れることはできるかもしれない。シッダールタと仏陀がそうであったようにだ。この場面では、ゴーヴィンダもまた、たしかにその契機をつかんでいるように思える。まだ道半ばではあるけれども。そしてこの道半ばだという点で、ゴーヴィンダは私たちと同じでもある。
この「共鳴」を通じてなら、『車輪の下』では解決をみなかった矛盾を解決する希望を見いだせる。ヘッセはそう思ったのではないだろうか。
おわりに
もちろん、ここに書かれたのはあくまでひとつの考えだ。それに特に新しい考えでもないだろう。冒頭で言った通り、すでにどこかで考えられていたことを、別の言葉で言い換えただけという可能性も十分にある。むしろそうでないとおかしいという気もする。
ひとまず言えるのは、『シッダールタ』が『車輪の下』と同じモチーフを繰り返していること。けれどもそうやって繰り返しつつも、かつて『車輪の下』にあった絶望を乗り越えようとしているように見えることだ。そして最後に、その契機として、他者のなにかに感銘をうけることから起こる自分自身の「共鳴」を、ヘッセは見出したのではないか。
なにかに心を動かされたとき、私たちの注意はその対象に向かいがちだ。けれどもそのような感動は、私たちのなかのなにかが、その対象と共鳴してはじめて起こる。外側だけでなく、私たちの内側にも、触発されることによって、高められていくなにかがあるはずなのだ。そのなにかに思いを馳せることも、心を動かされることそれ自体と同じくらいすばらしいことのように思える。
